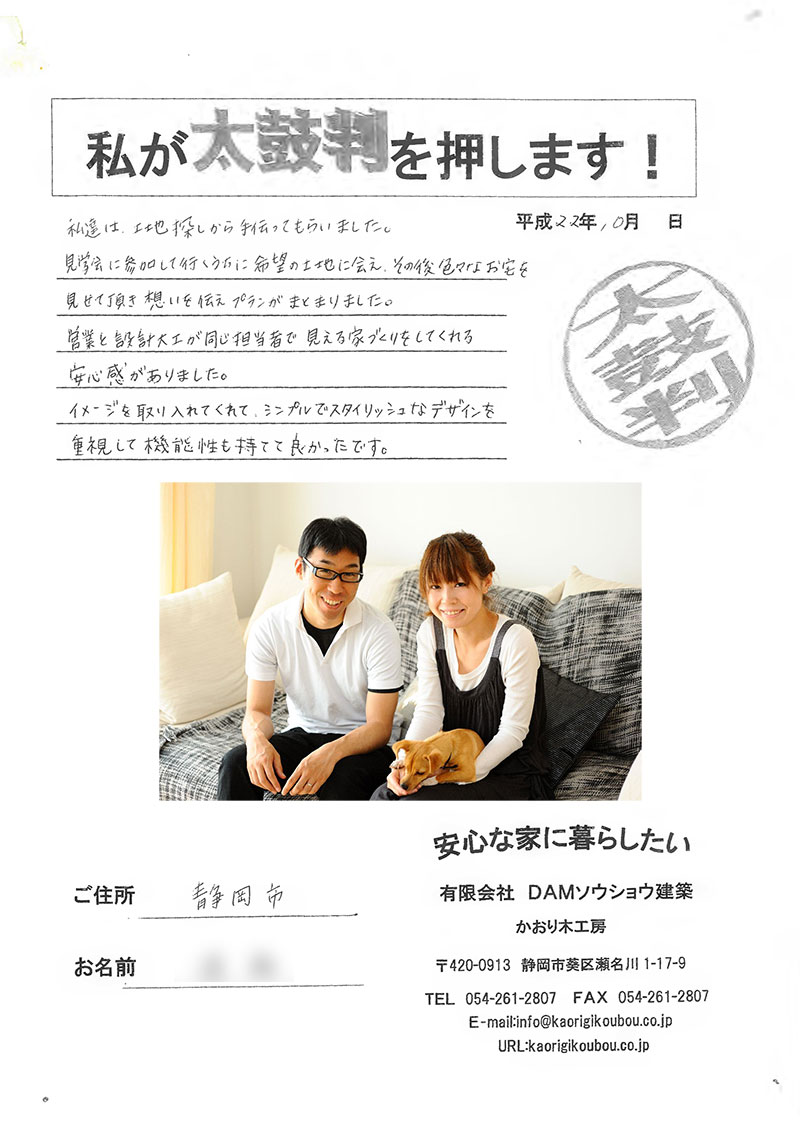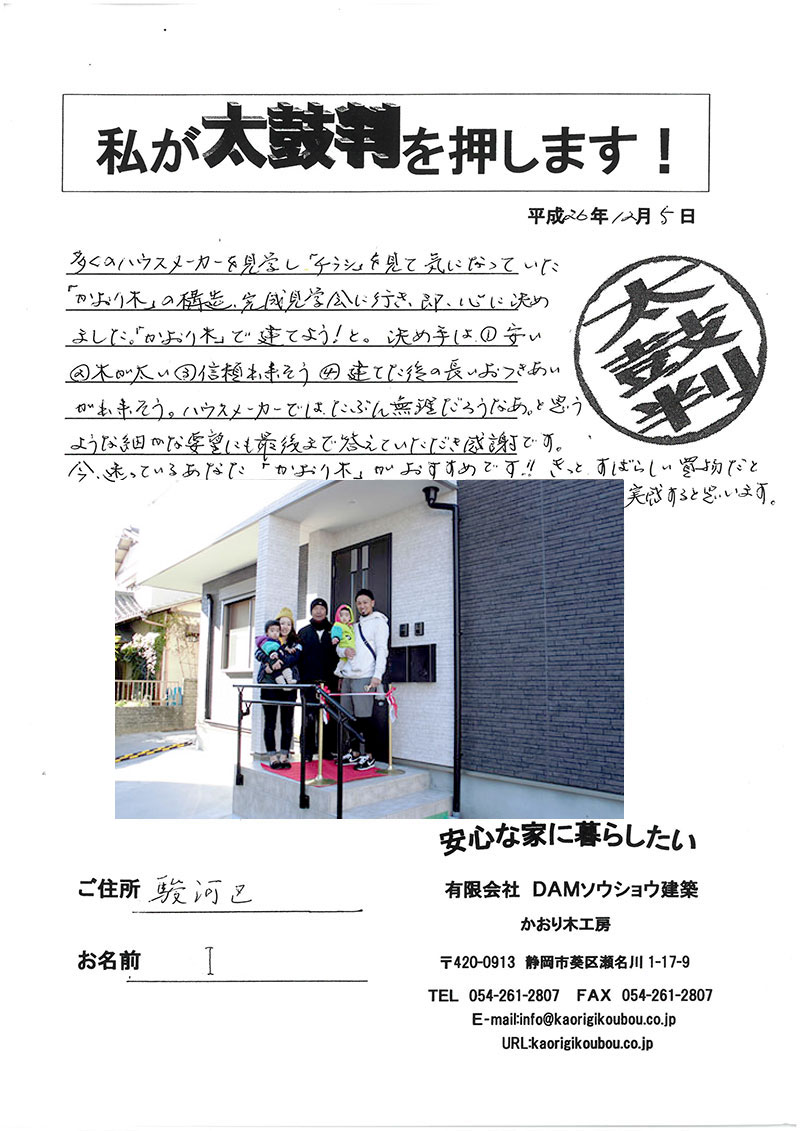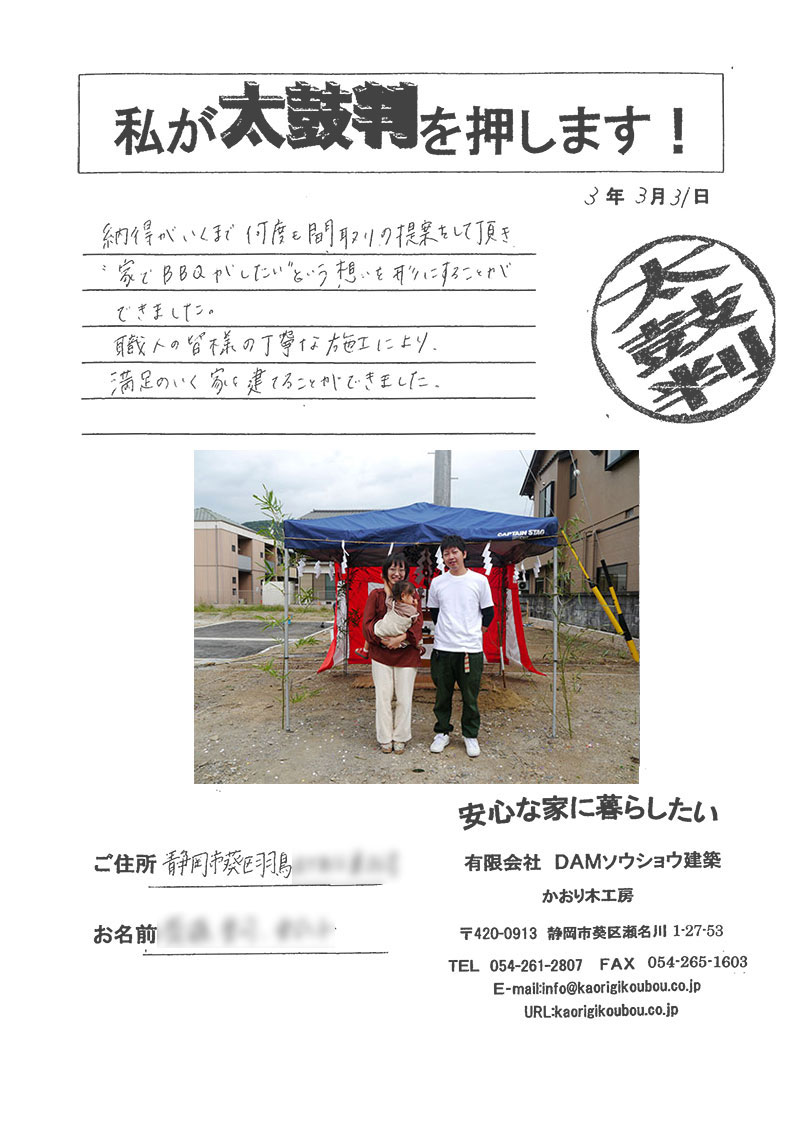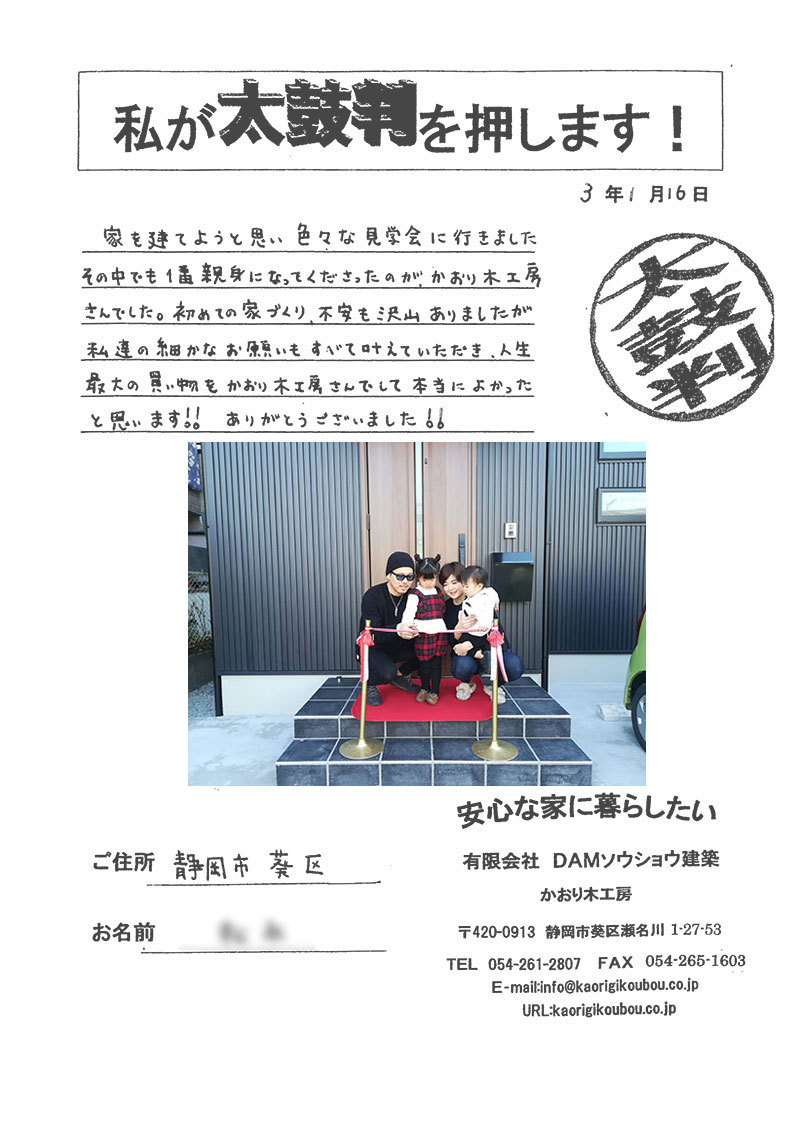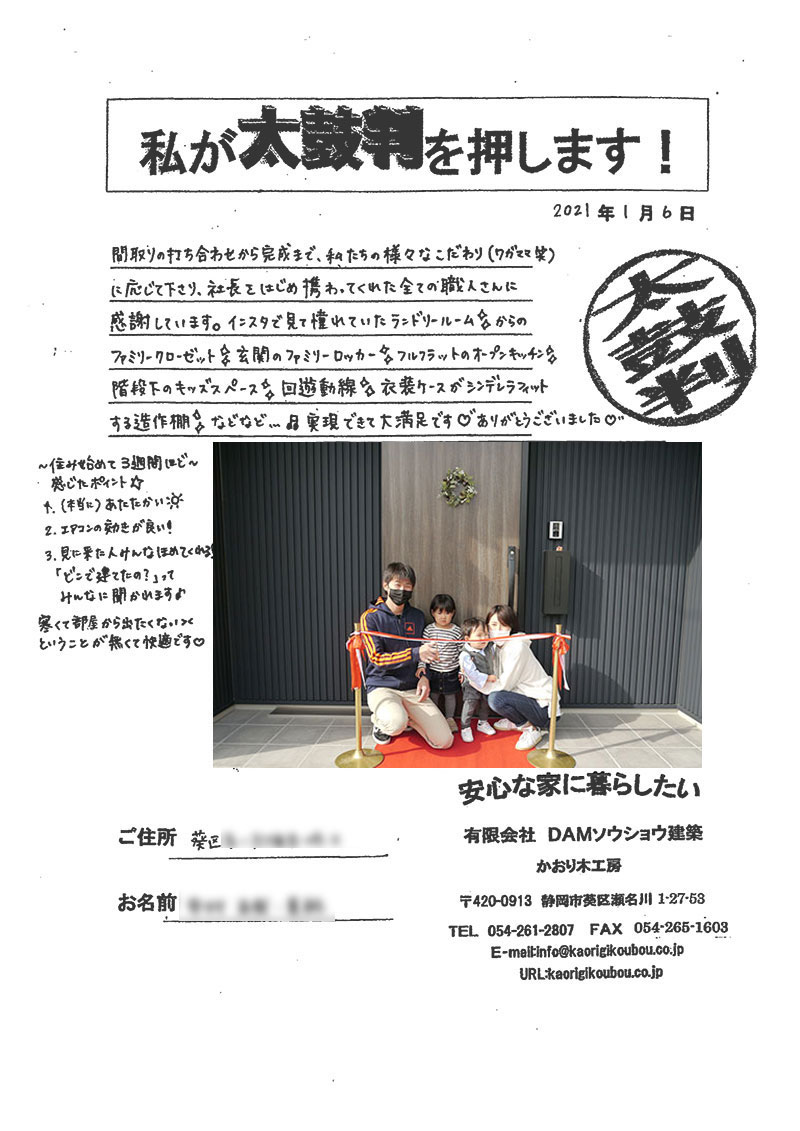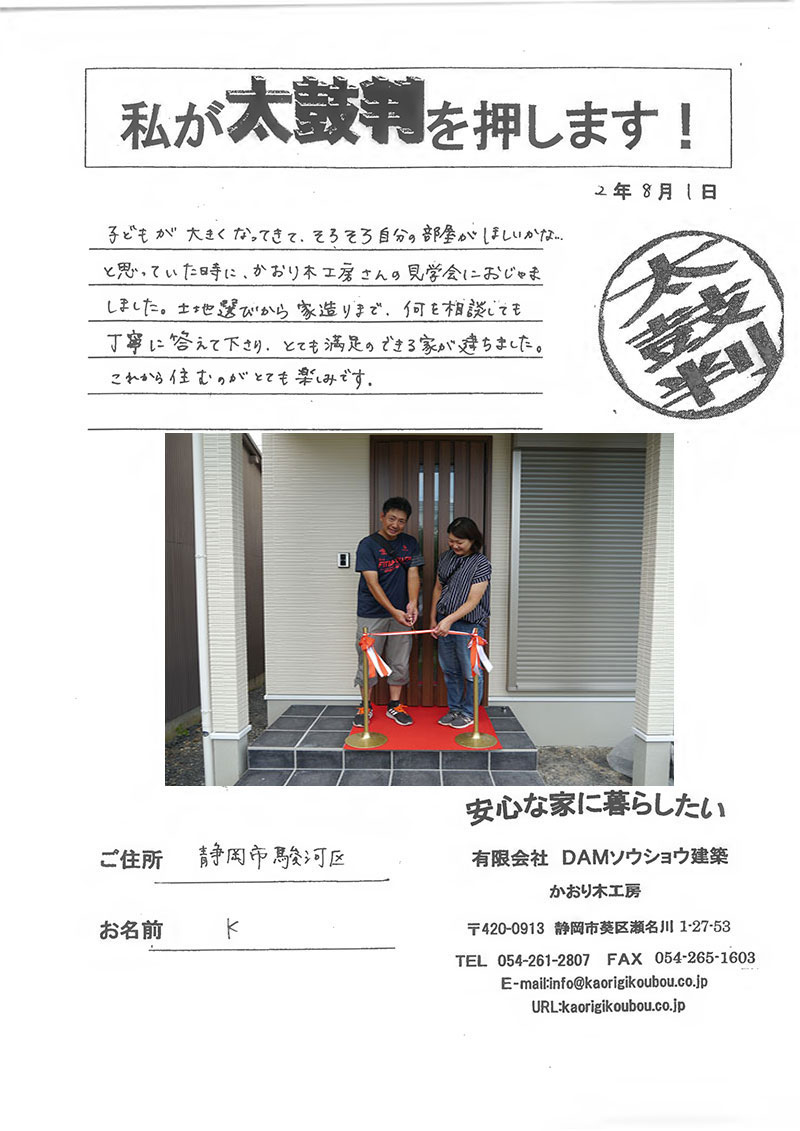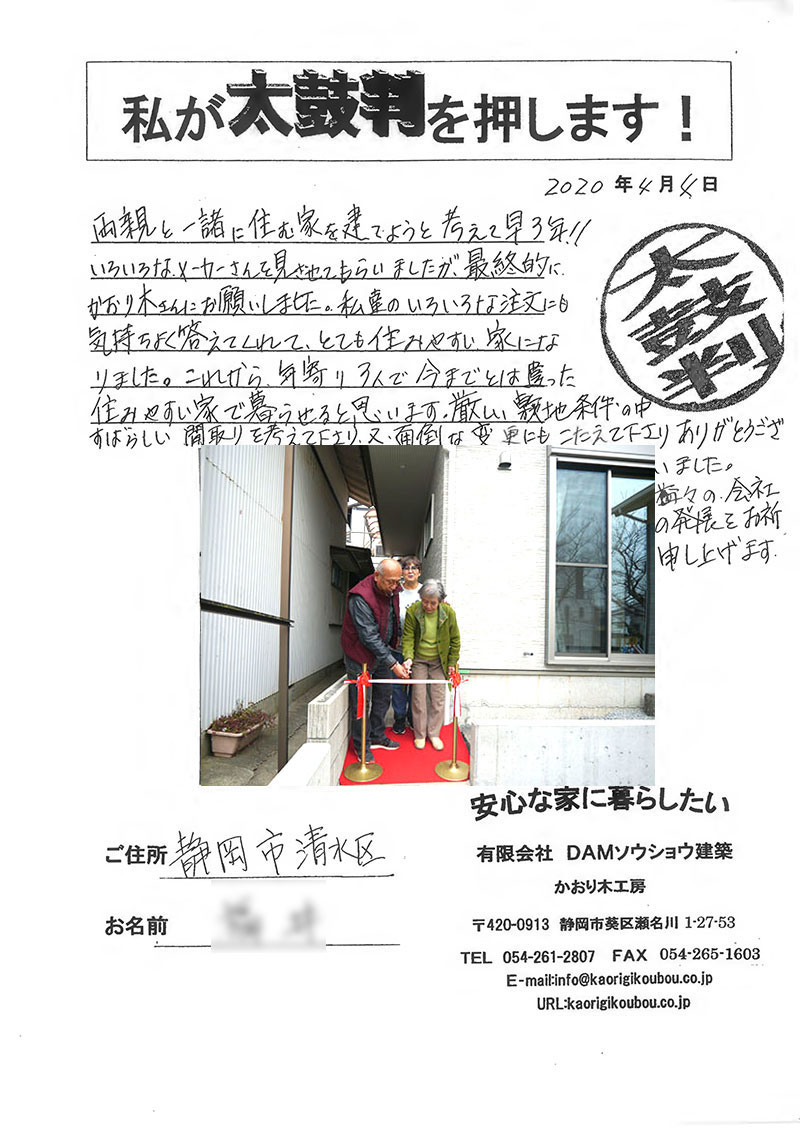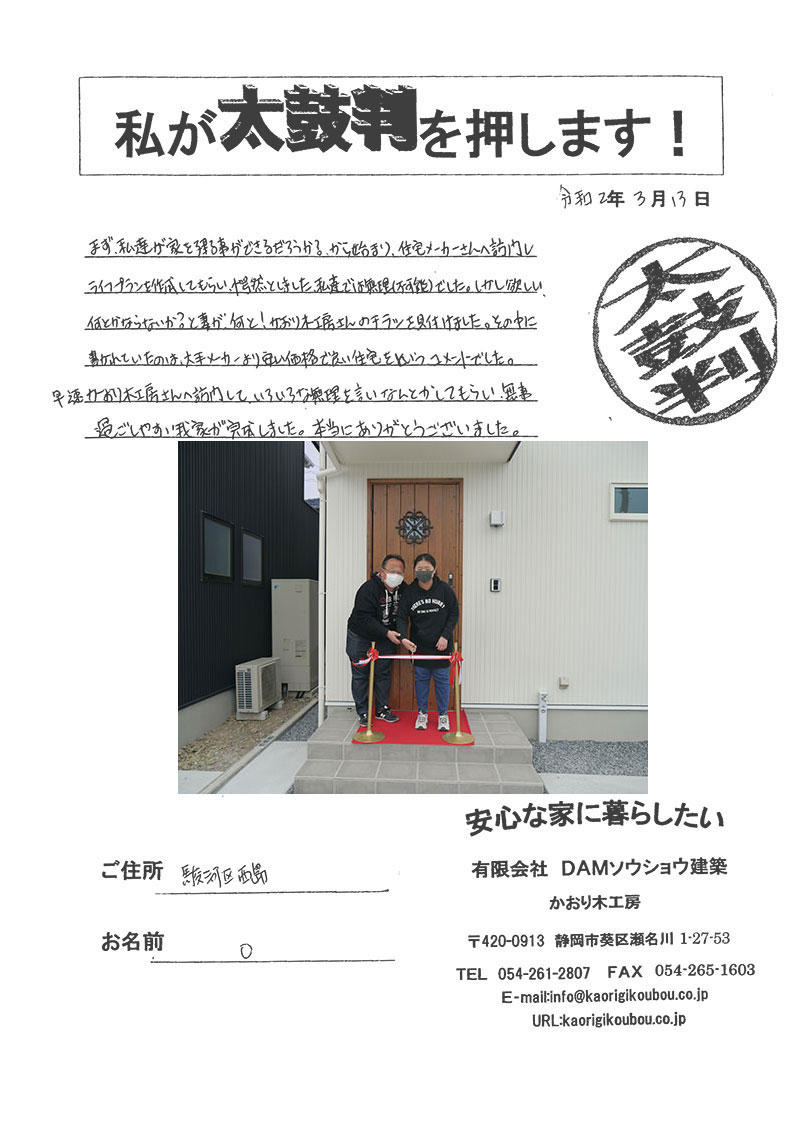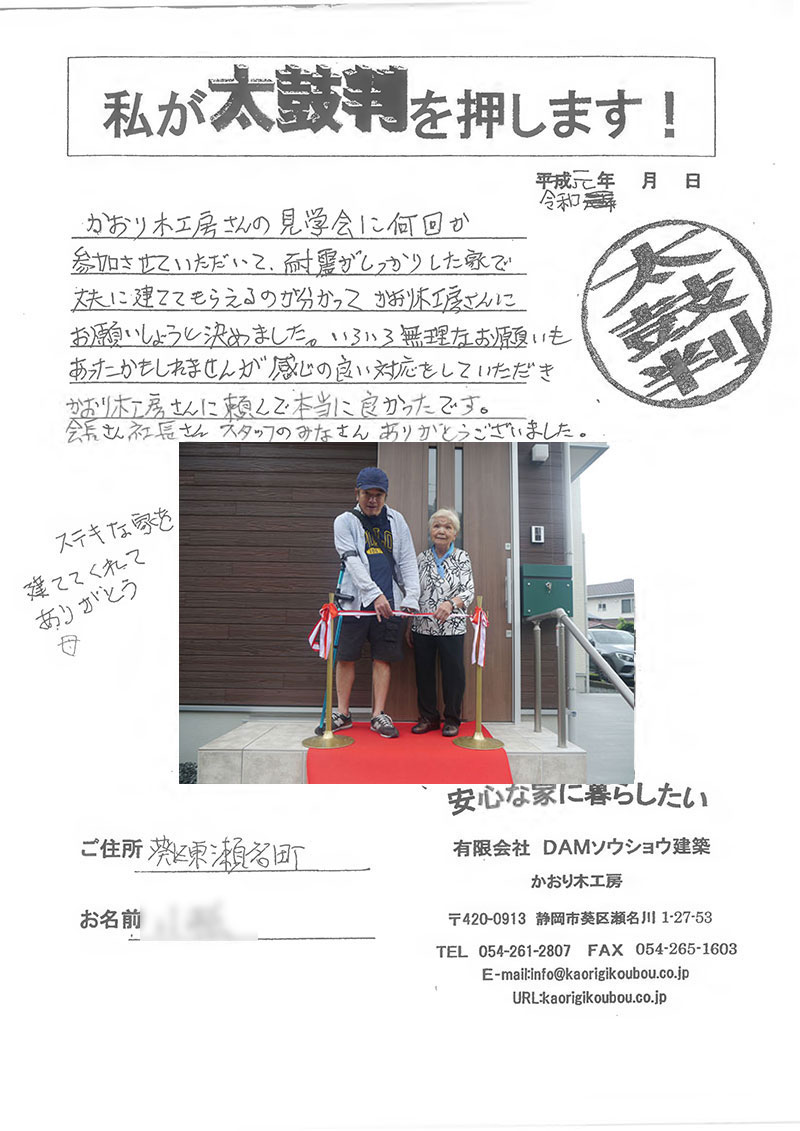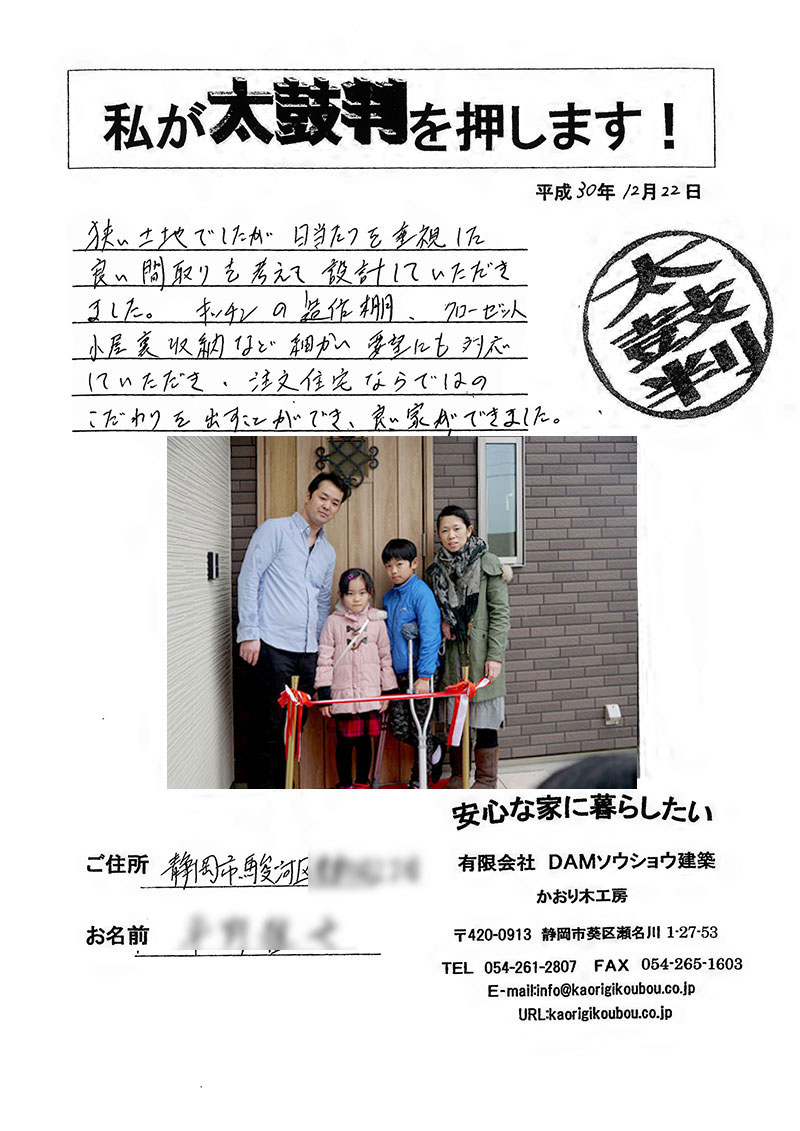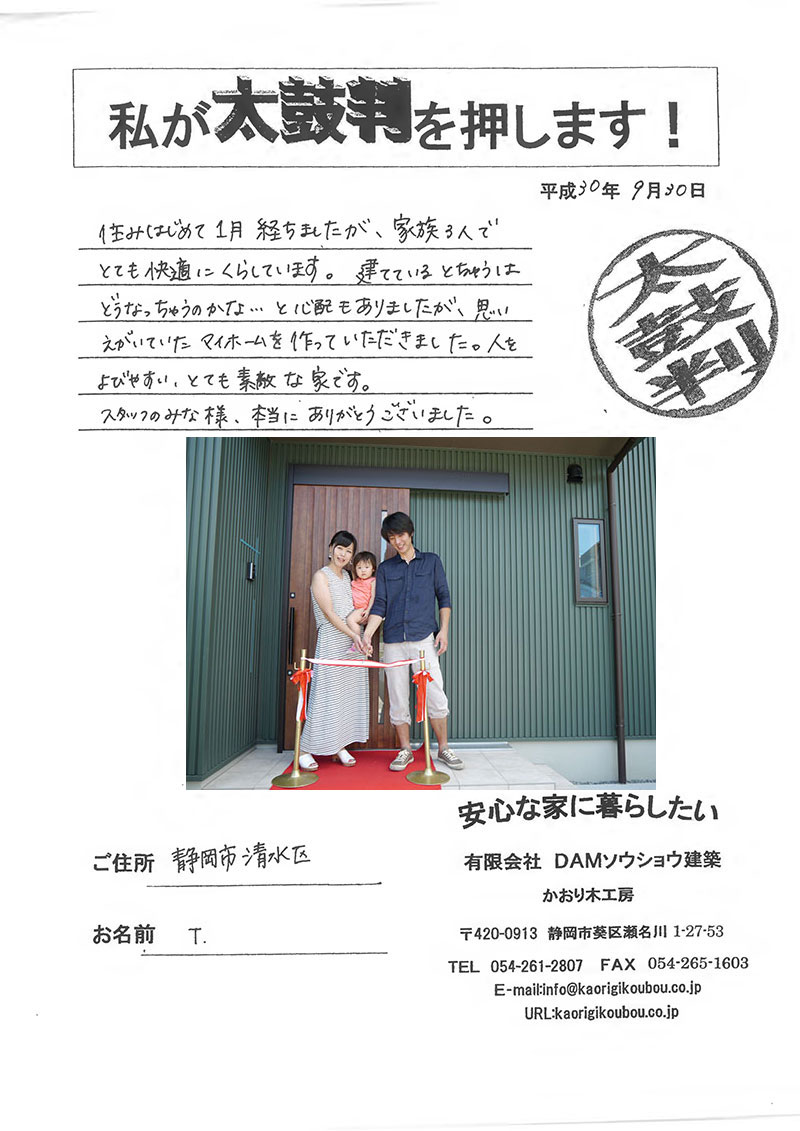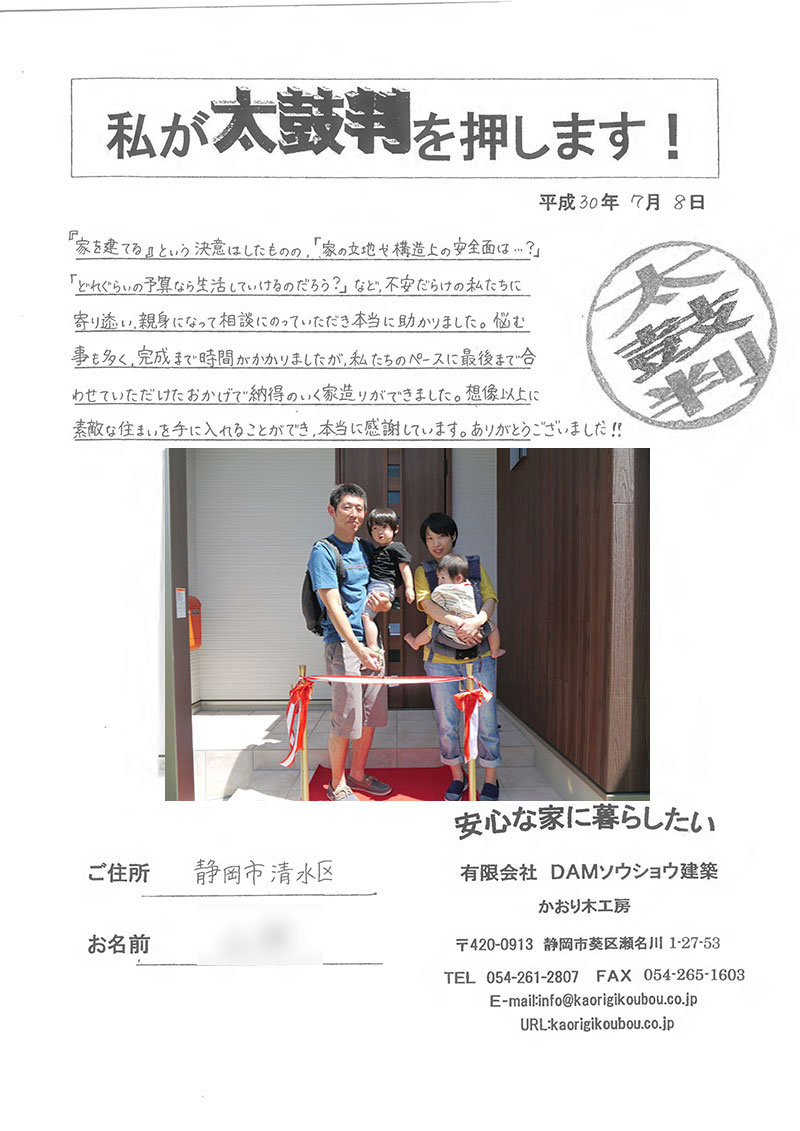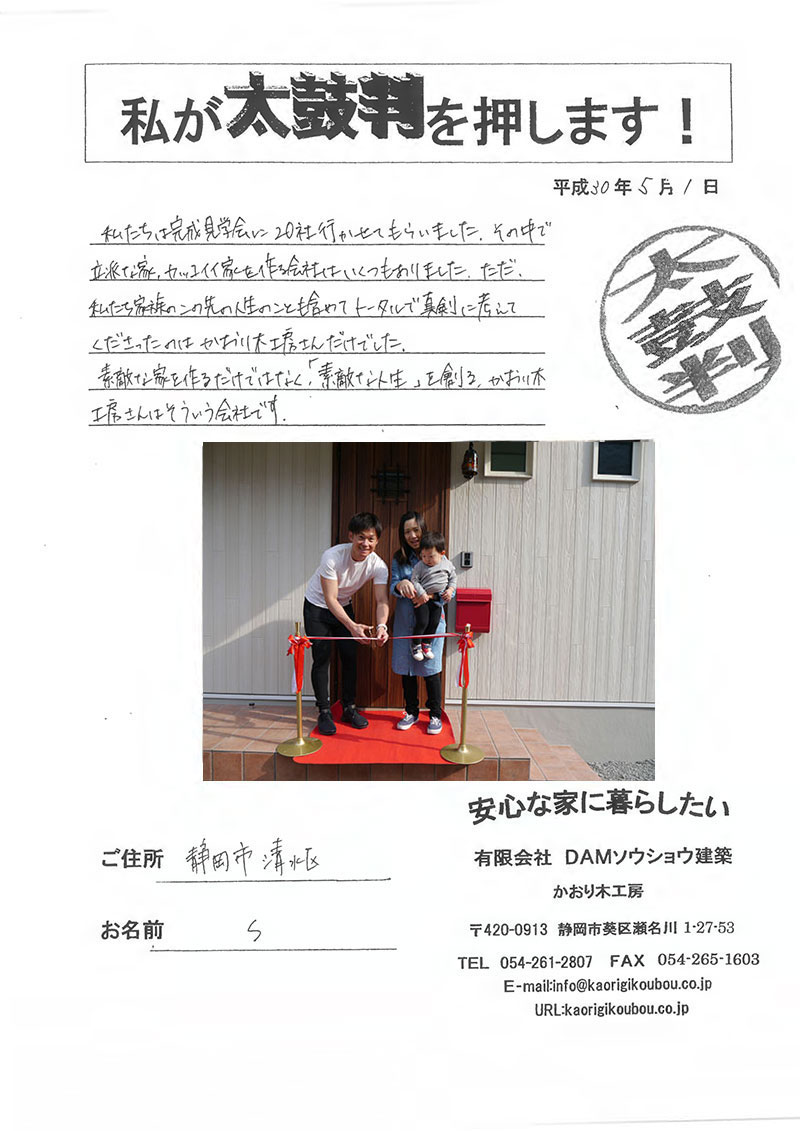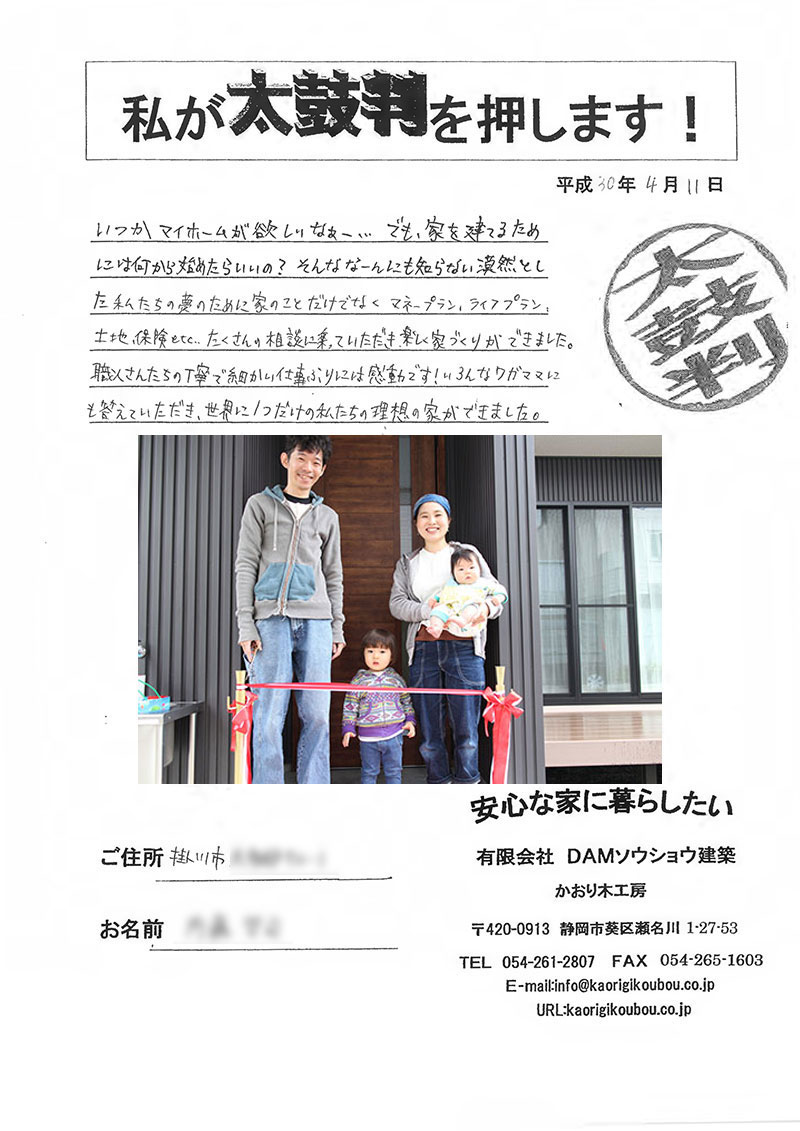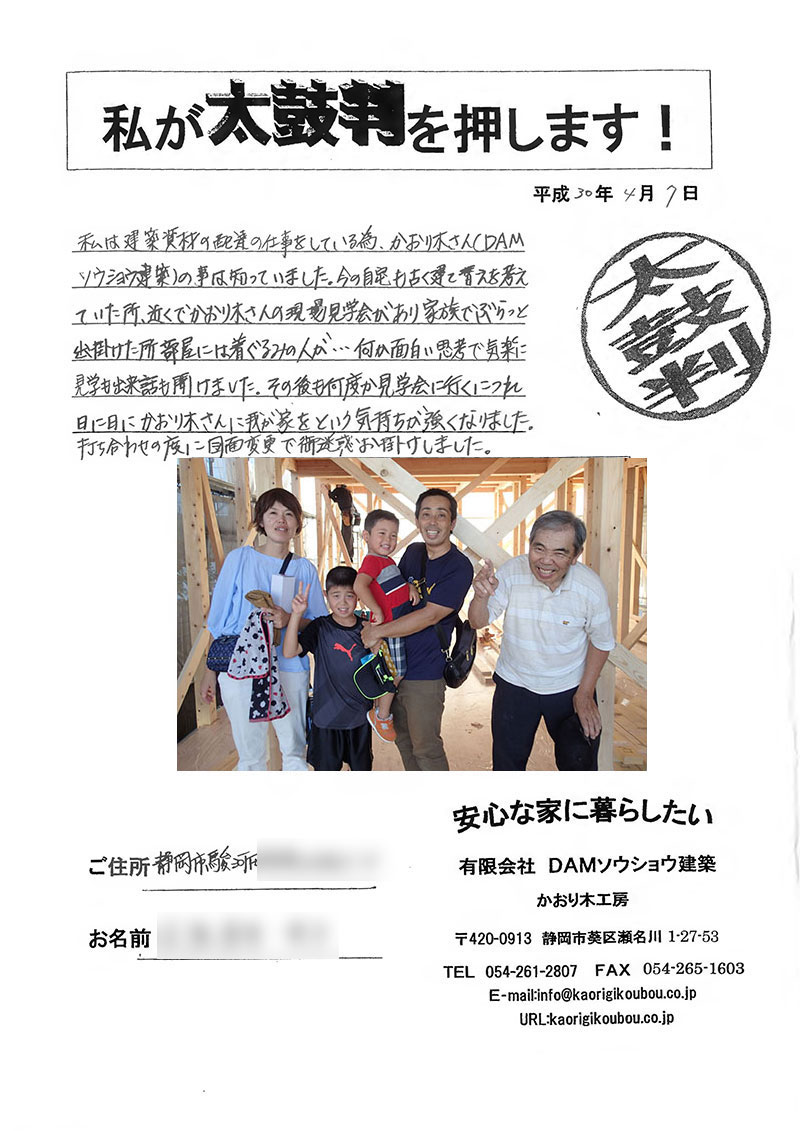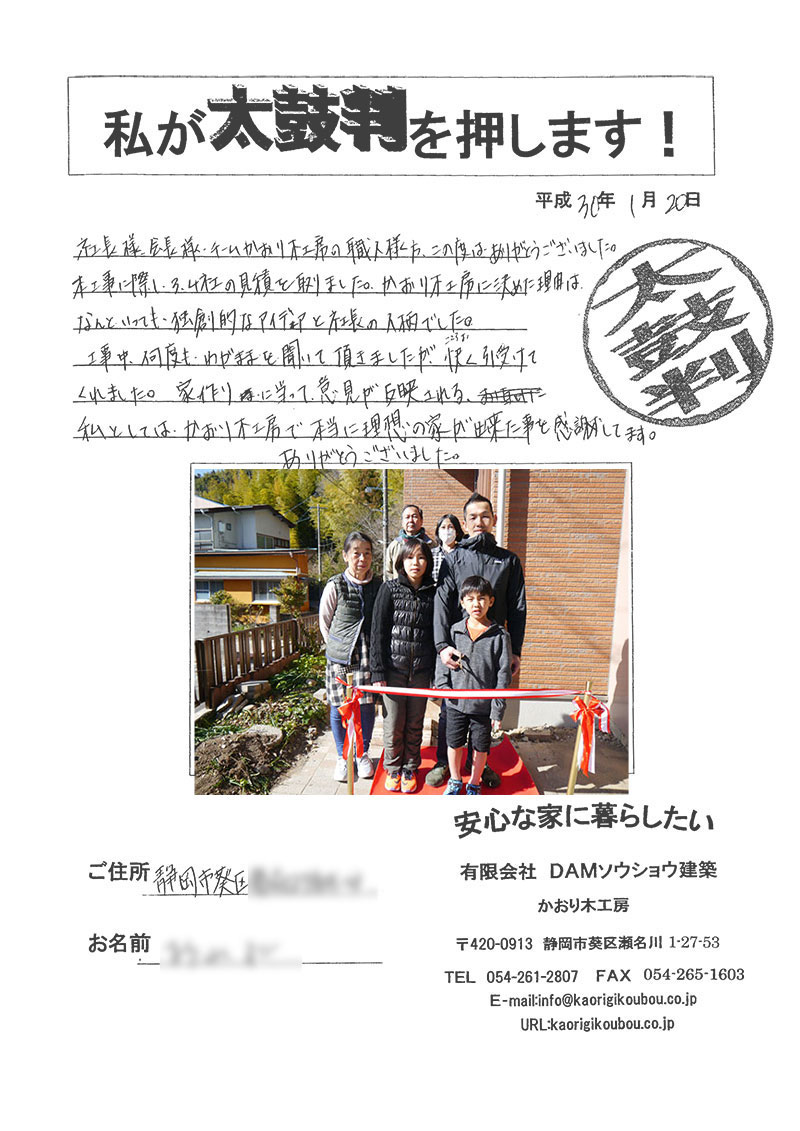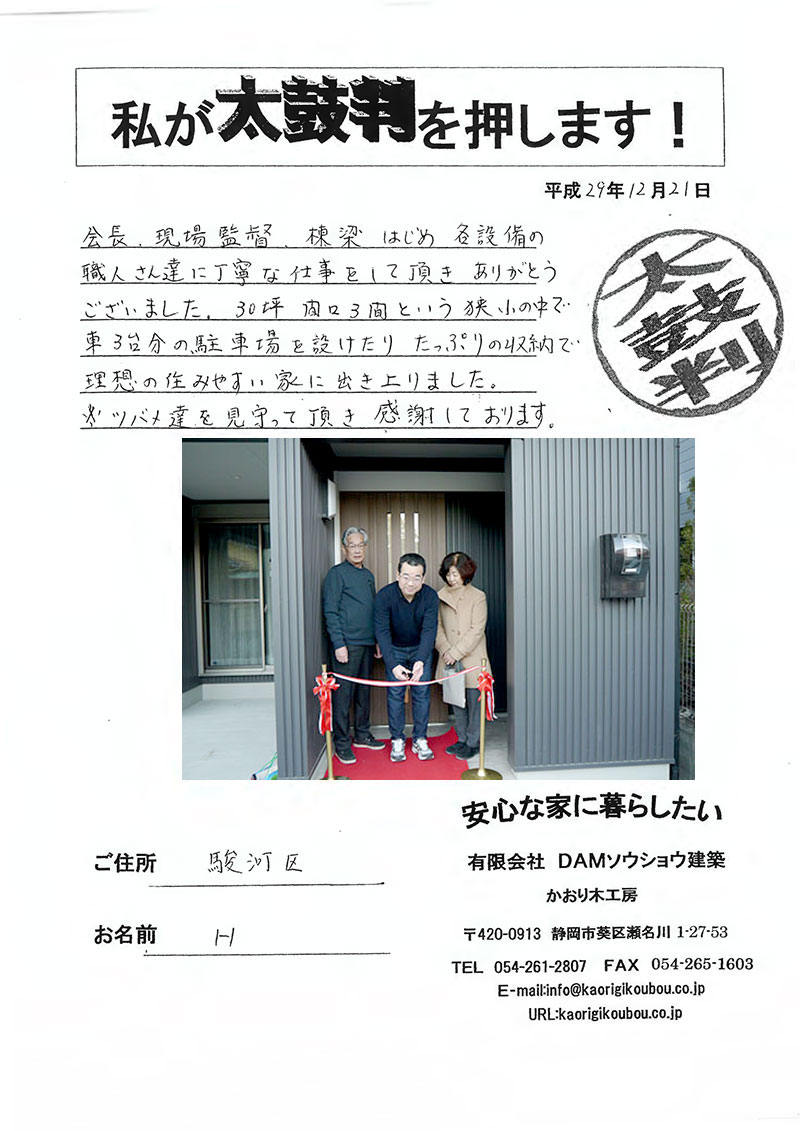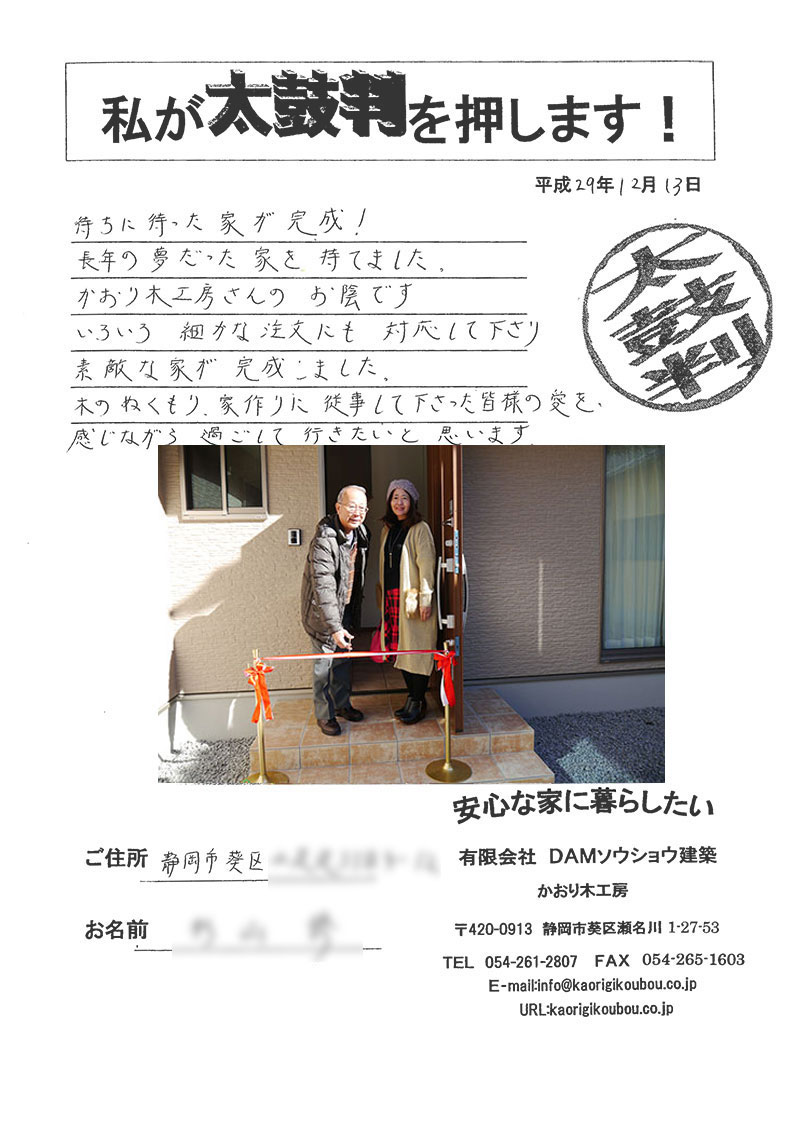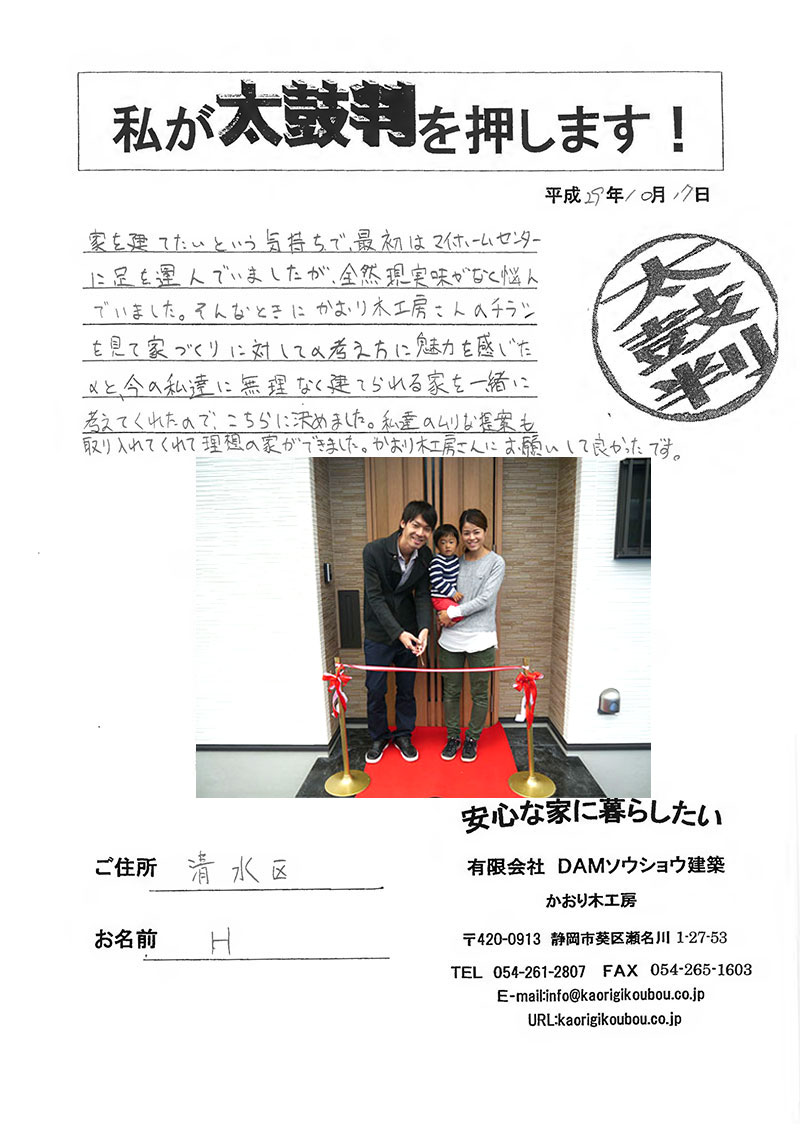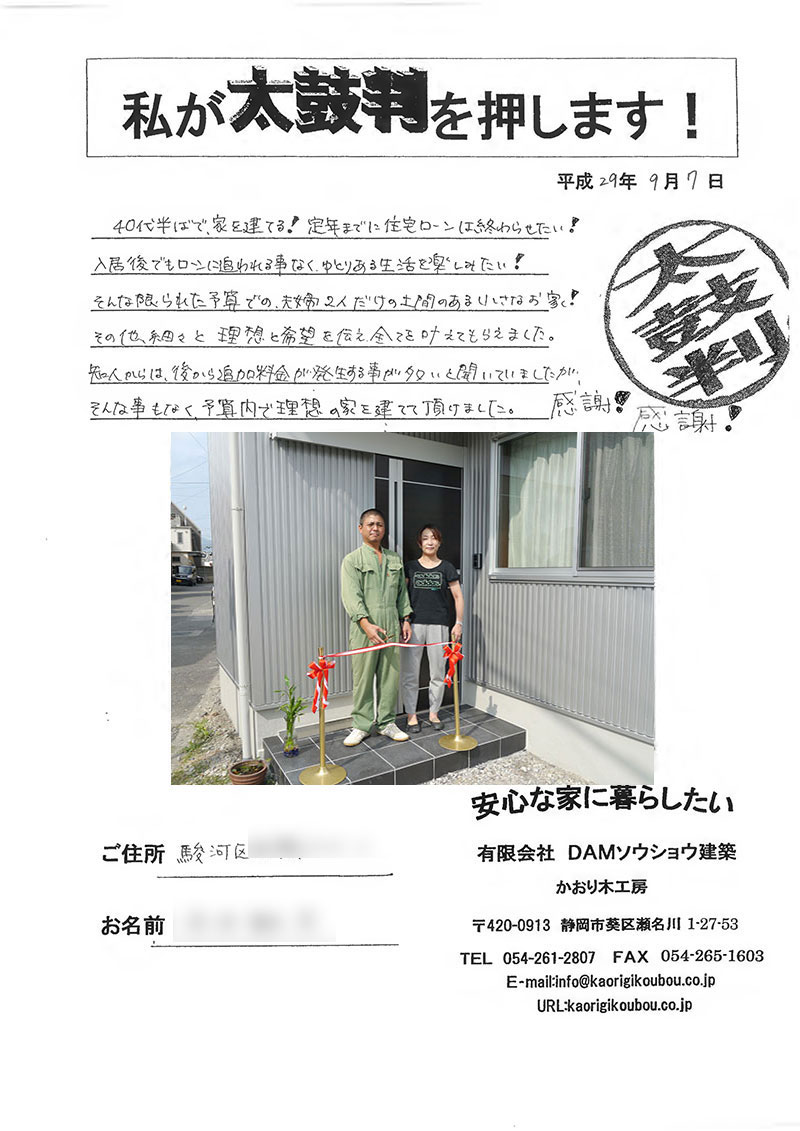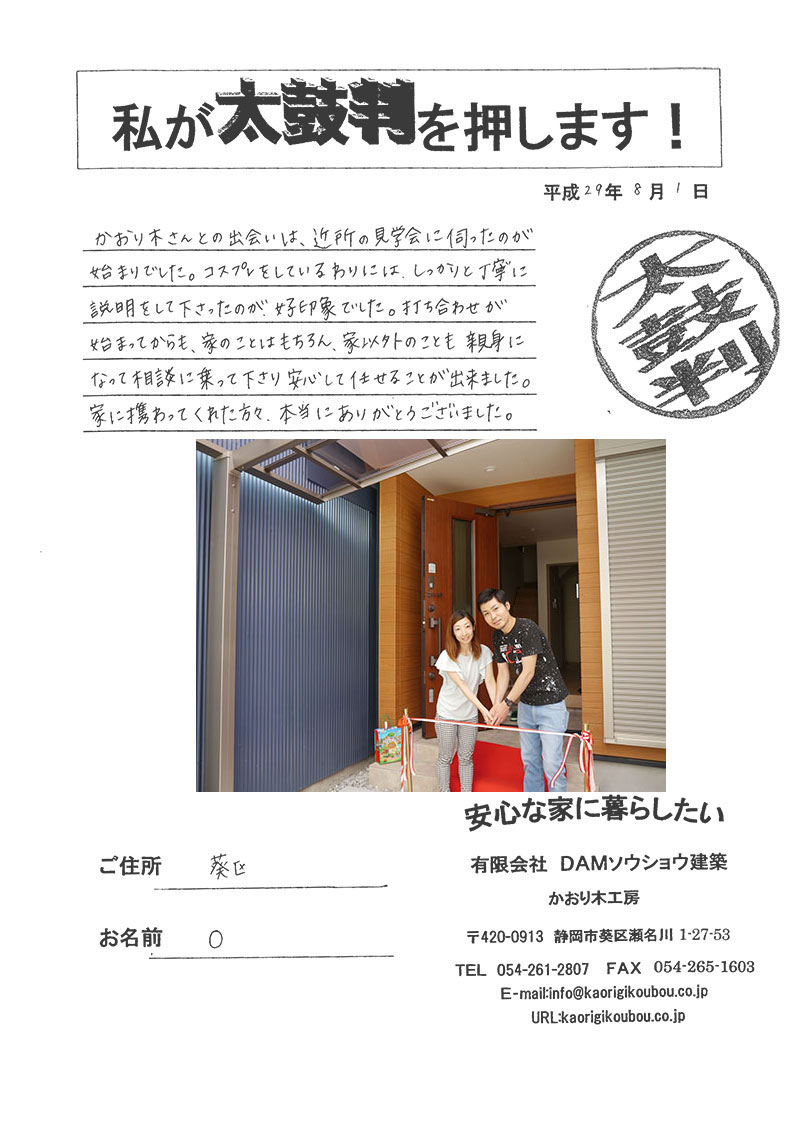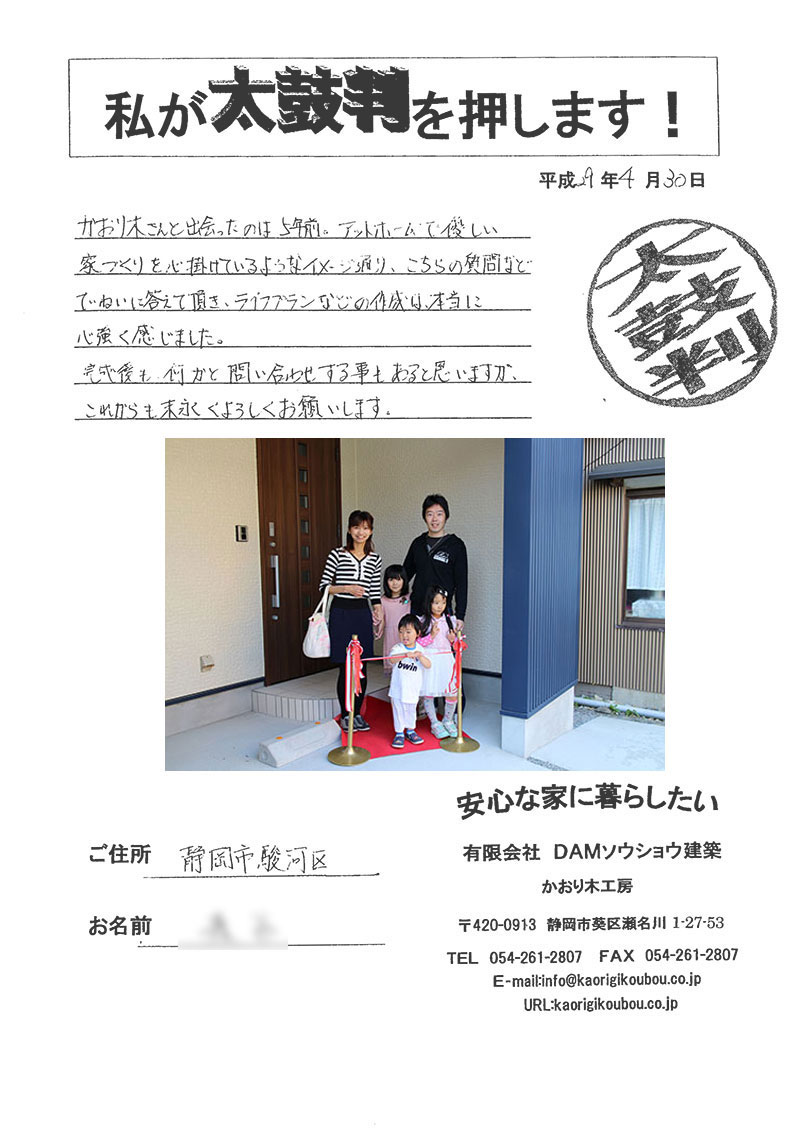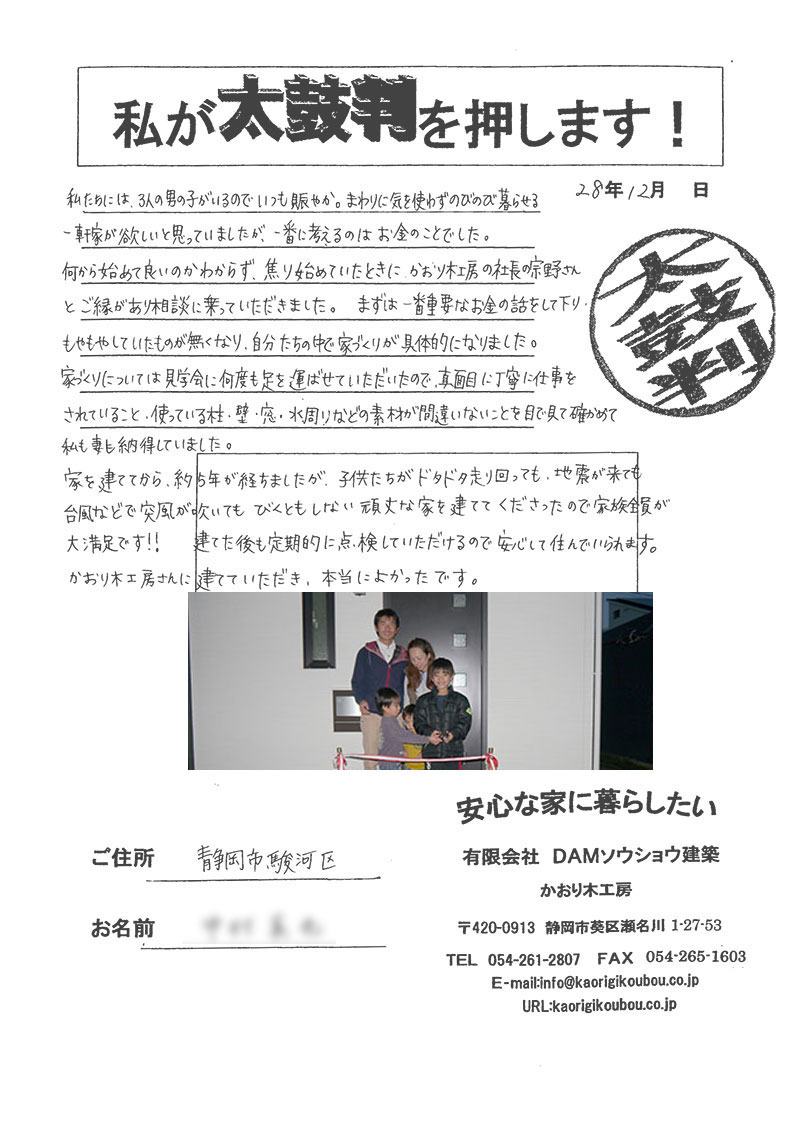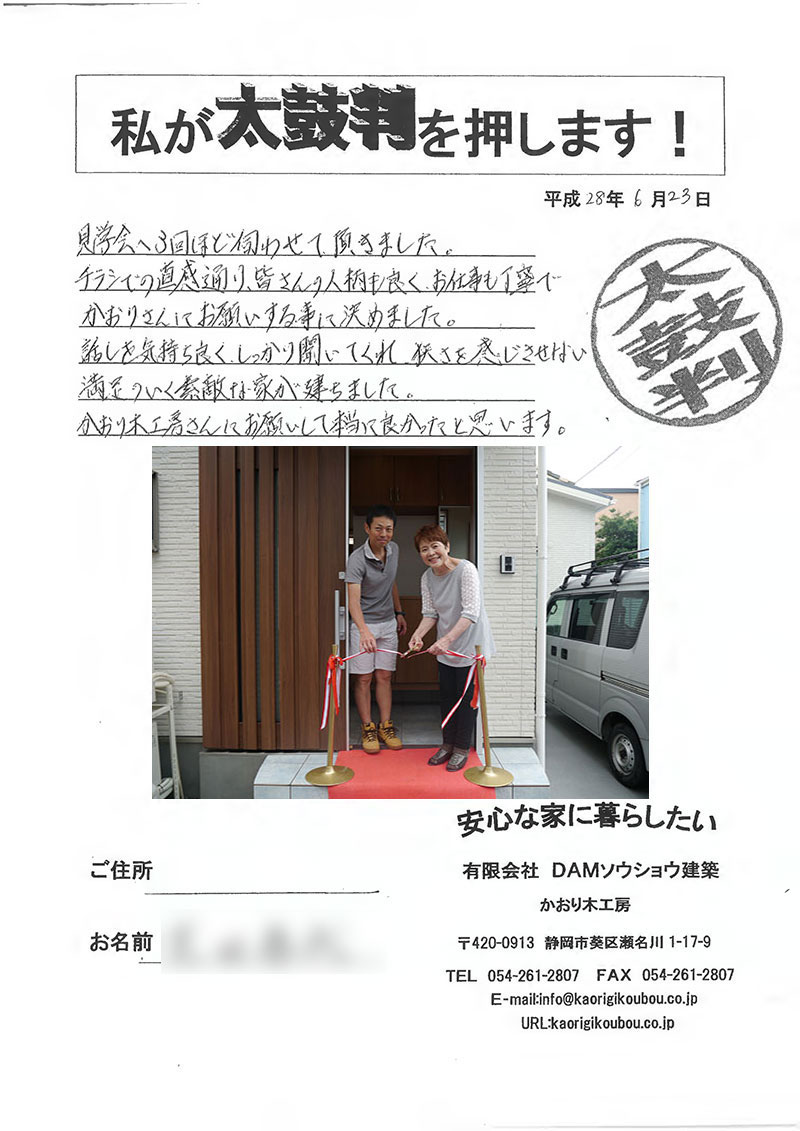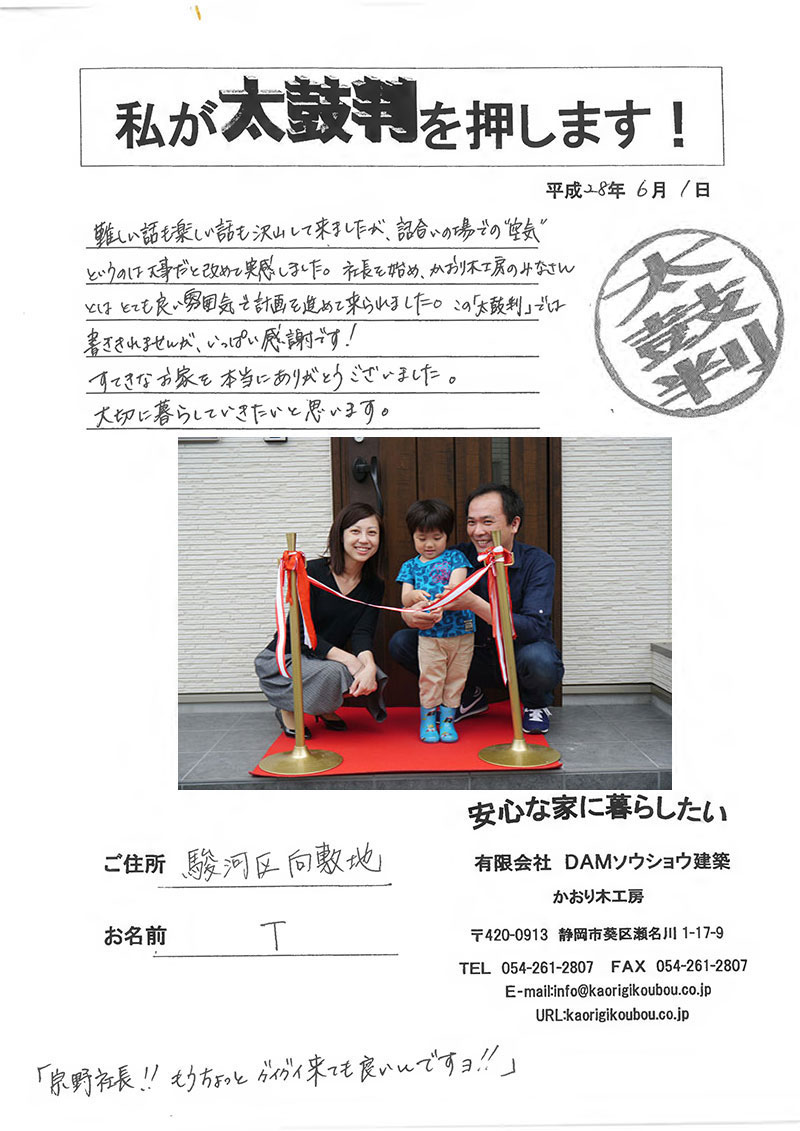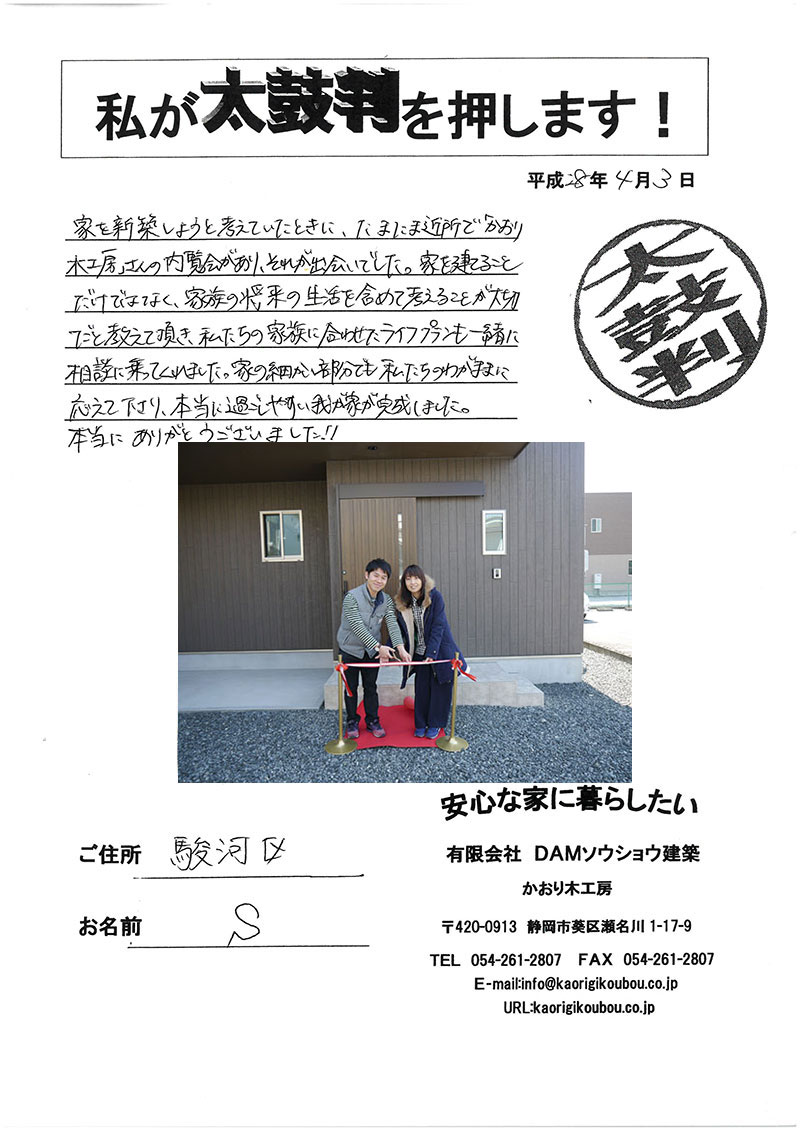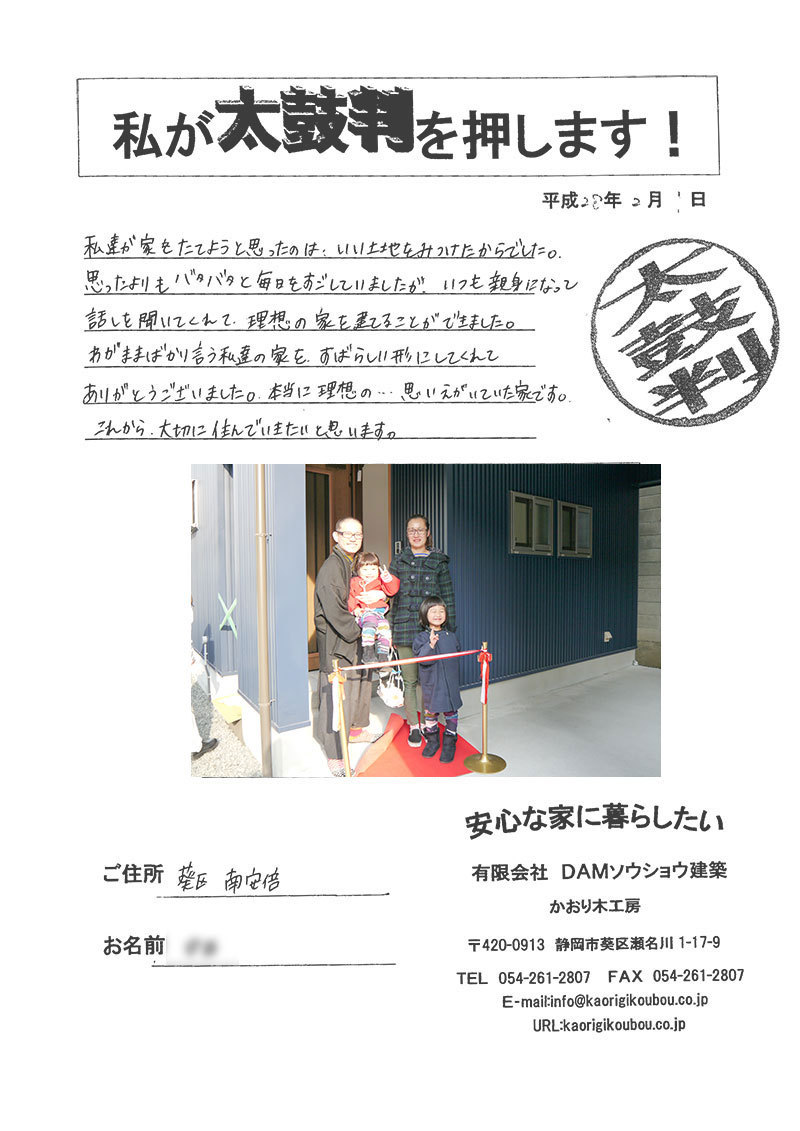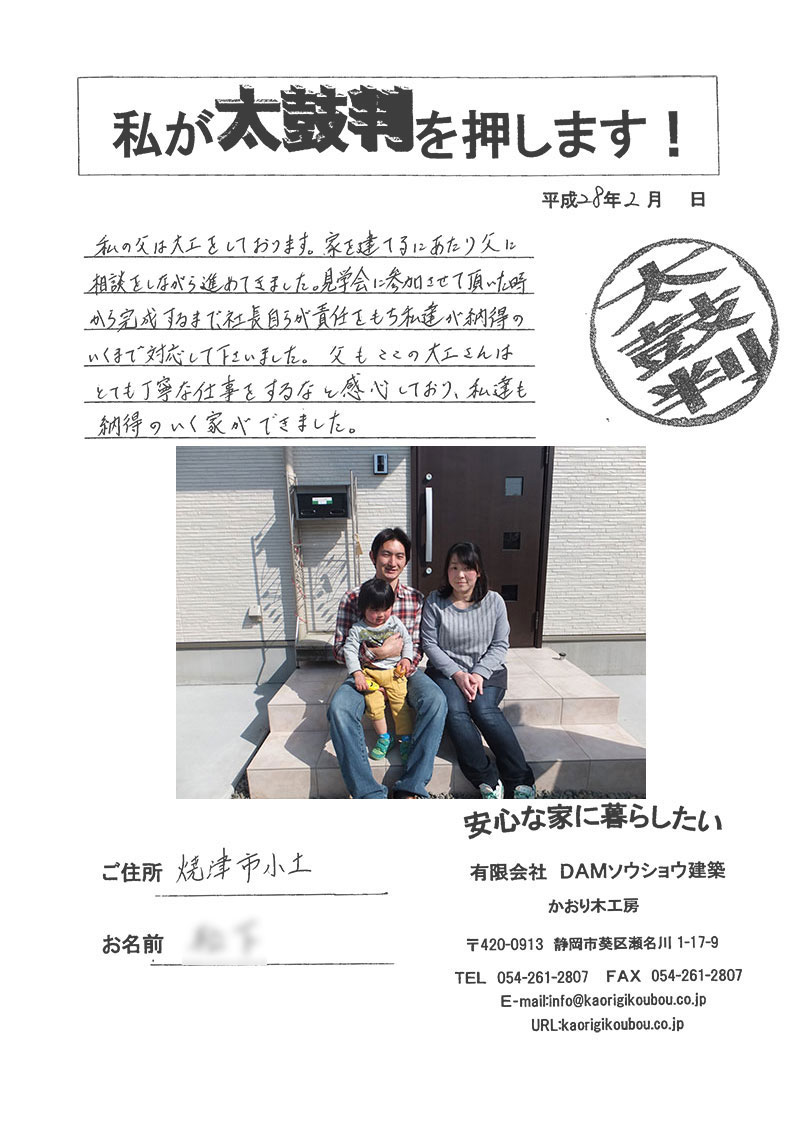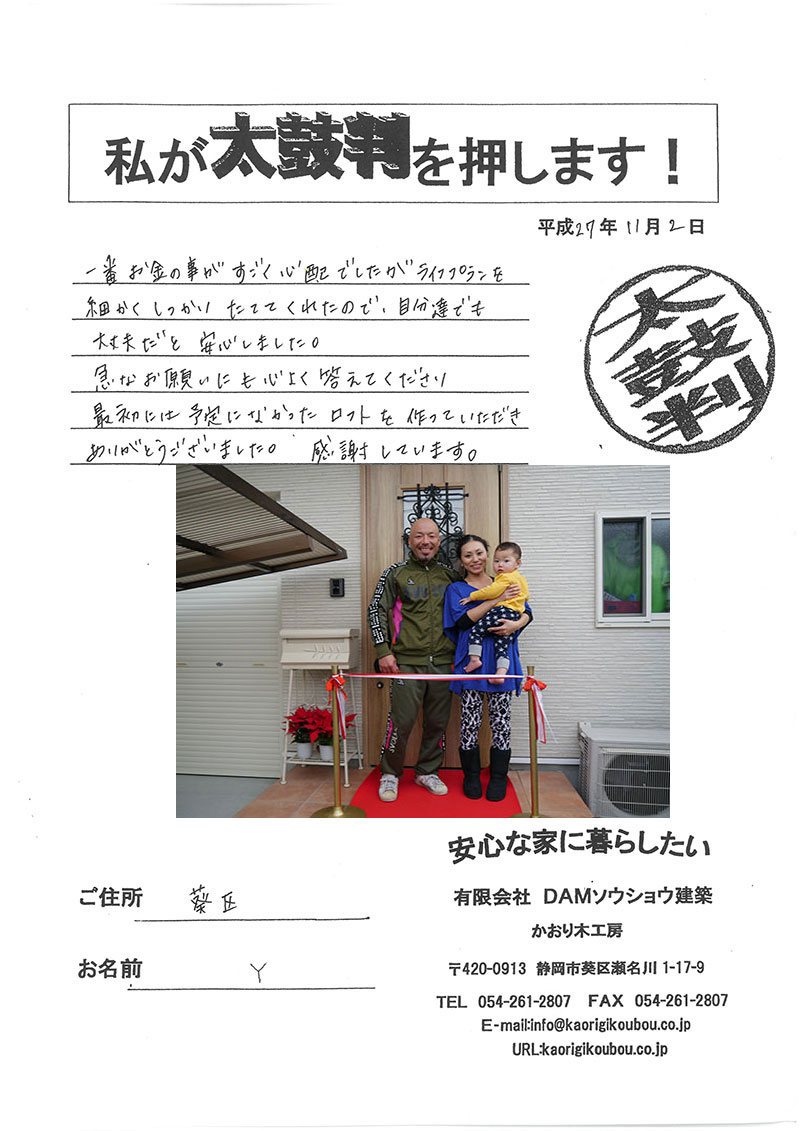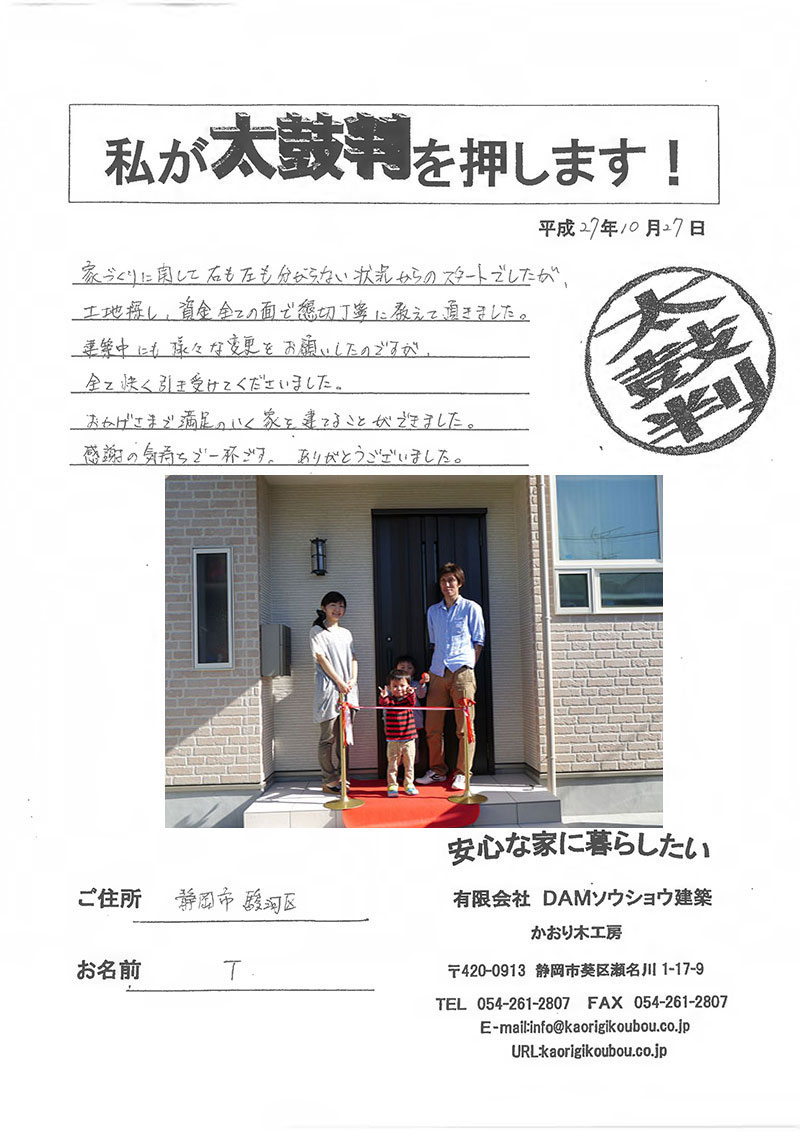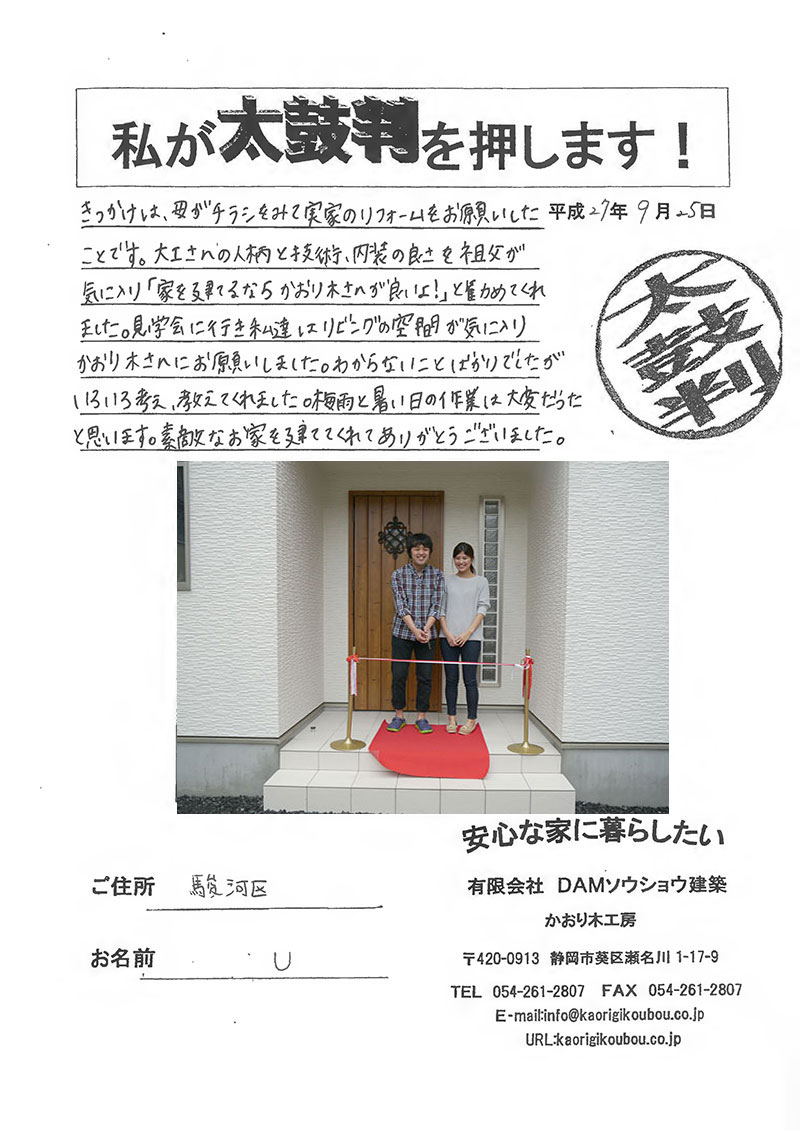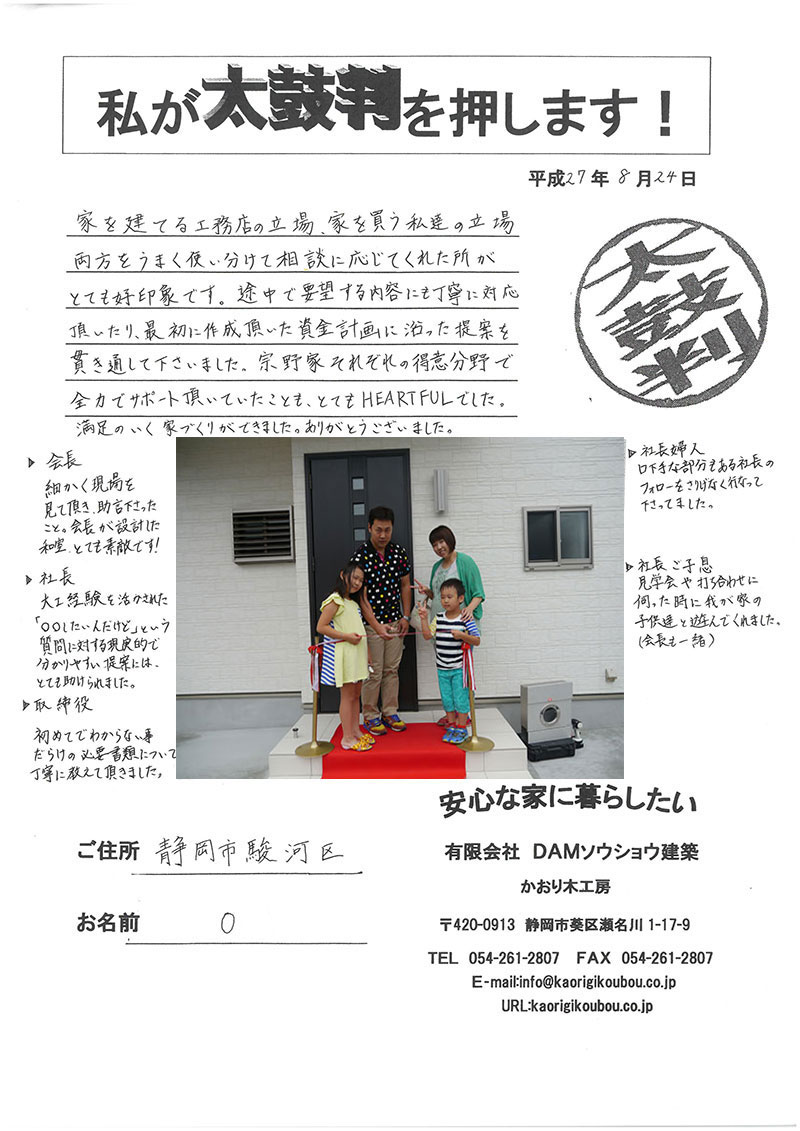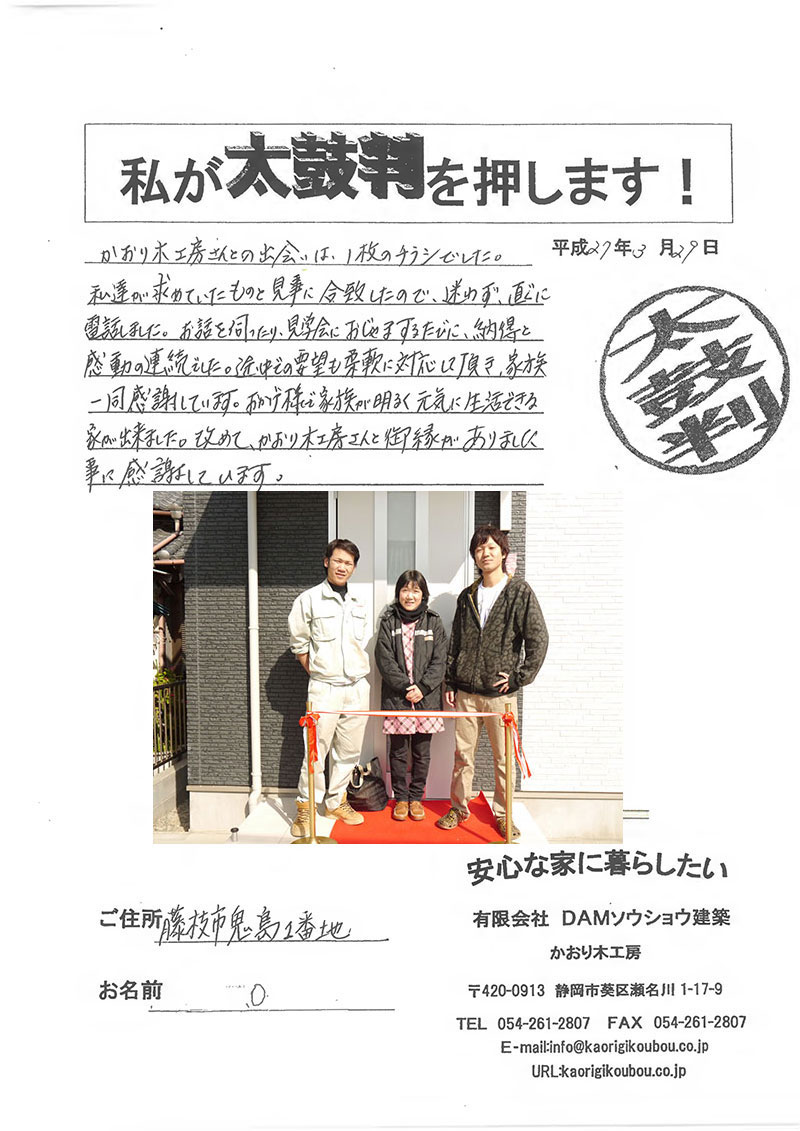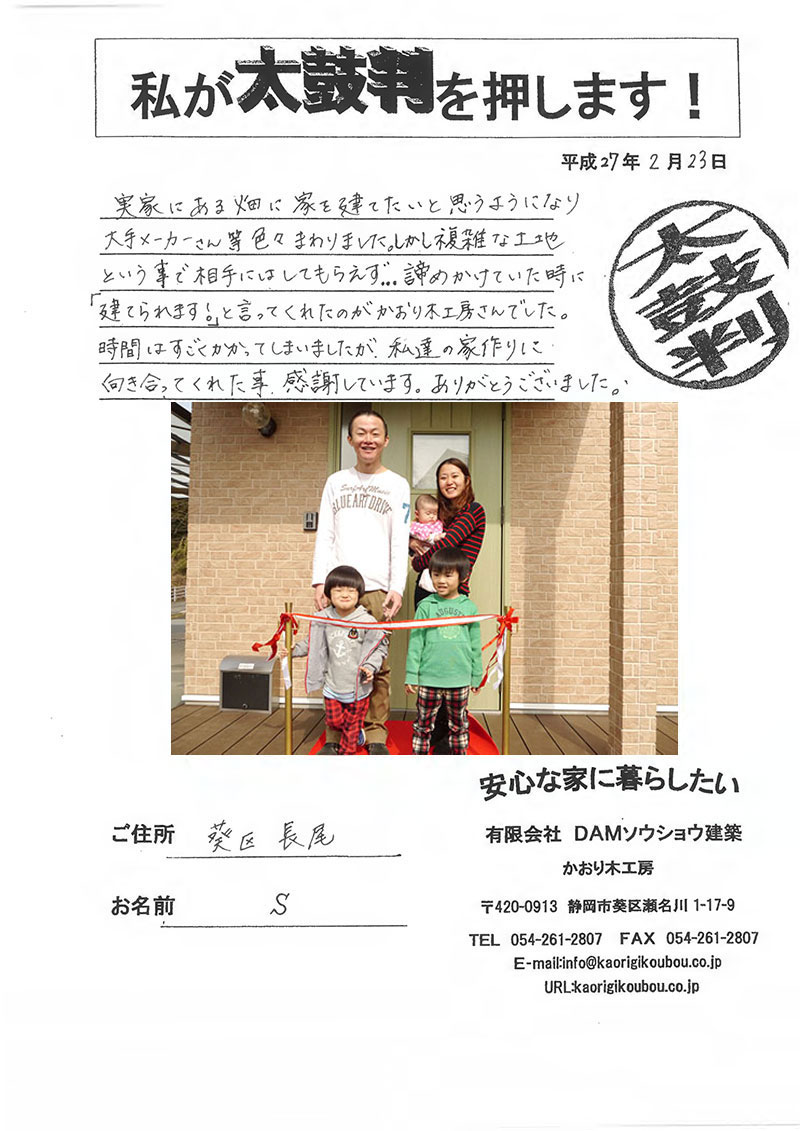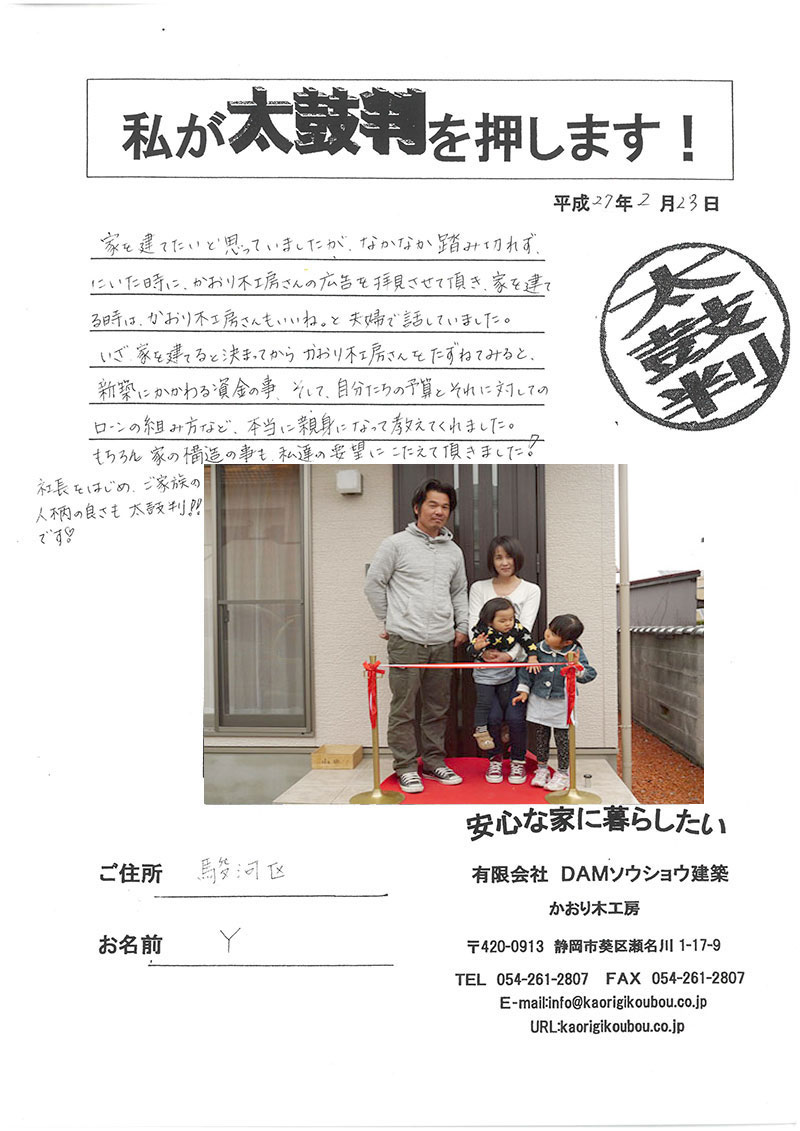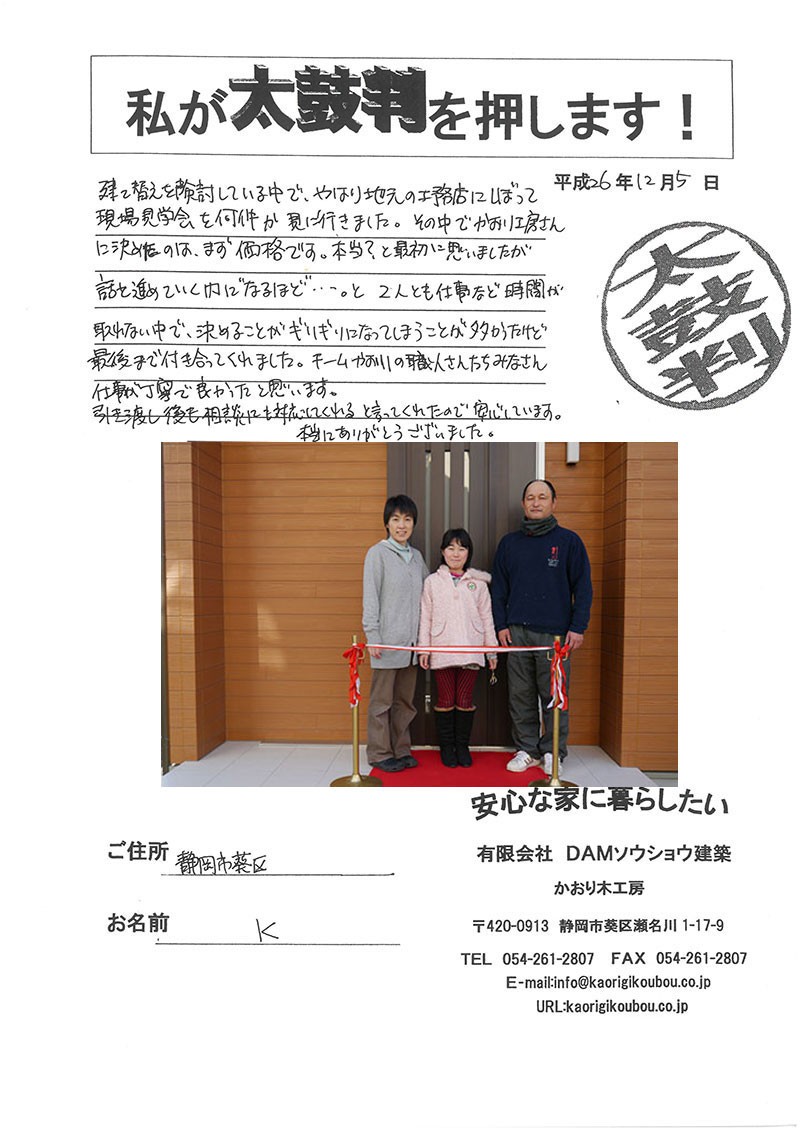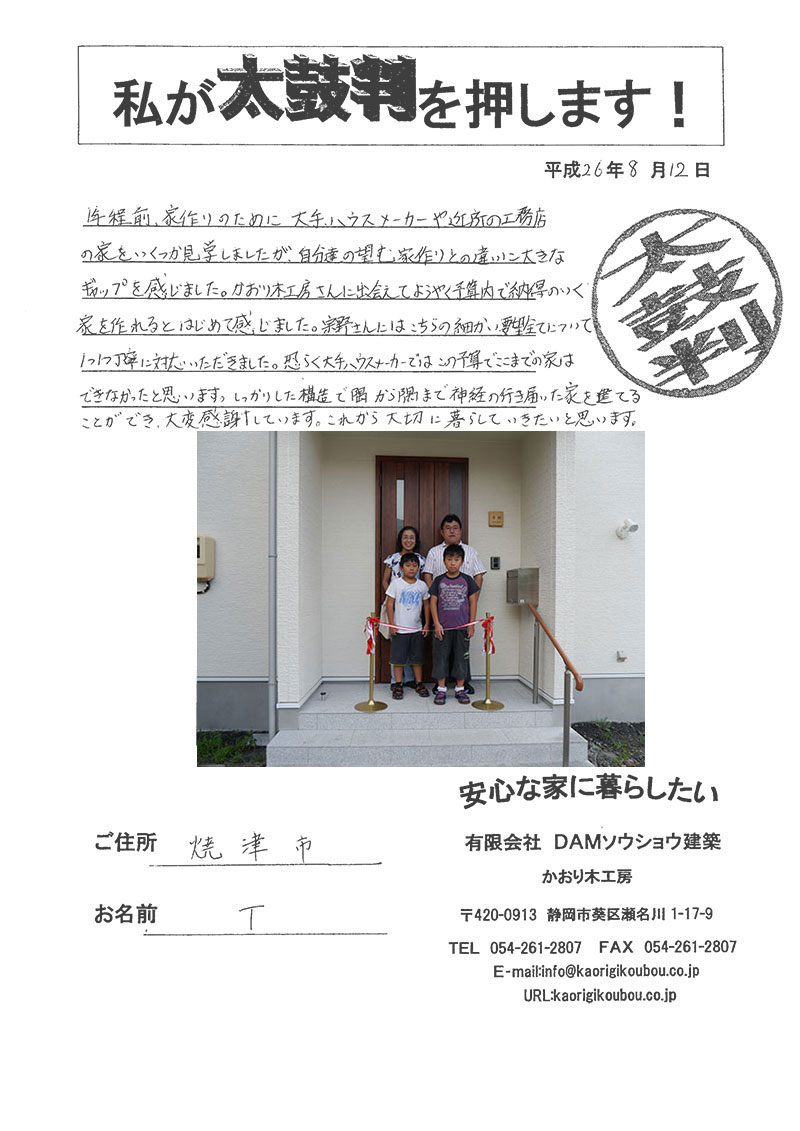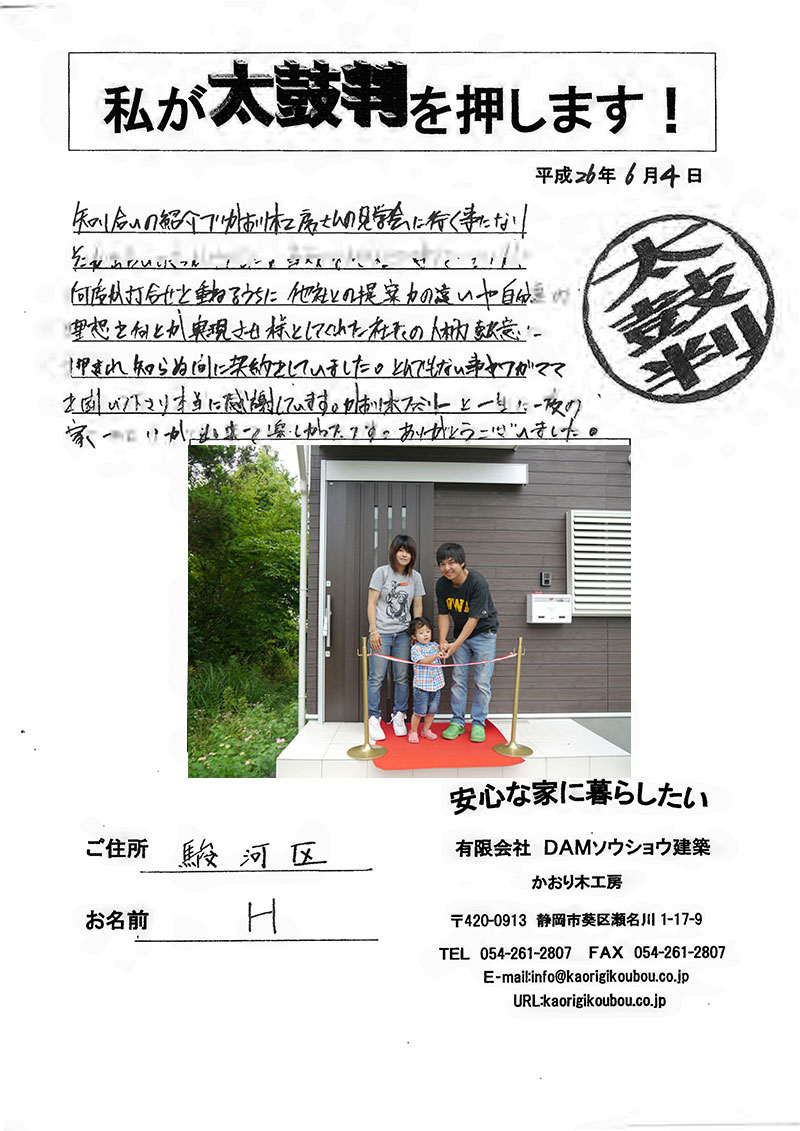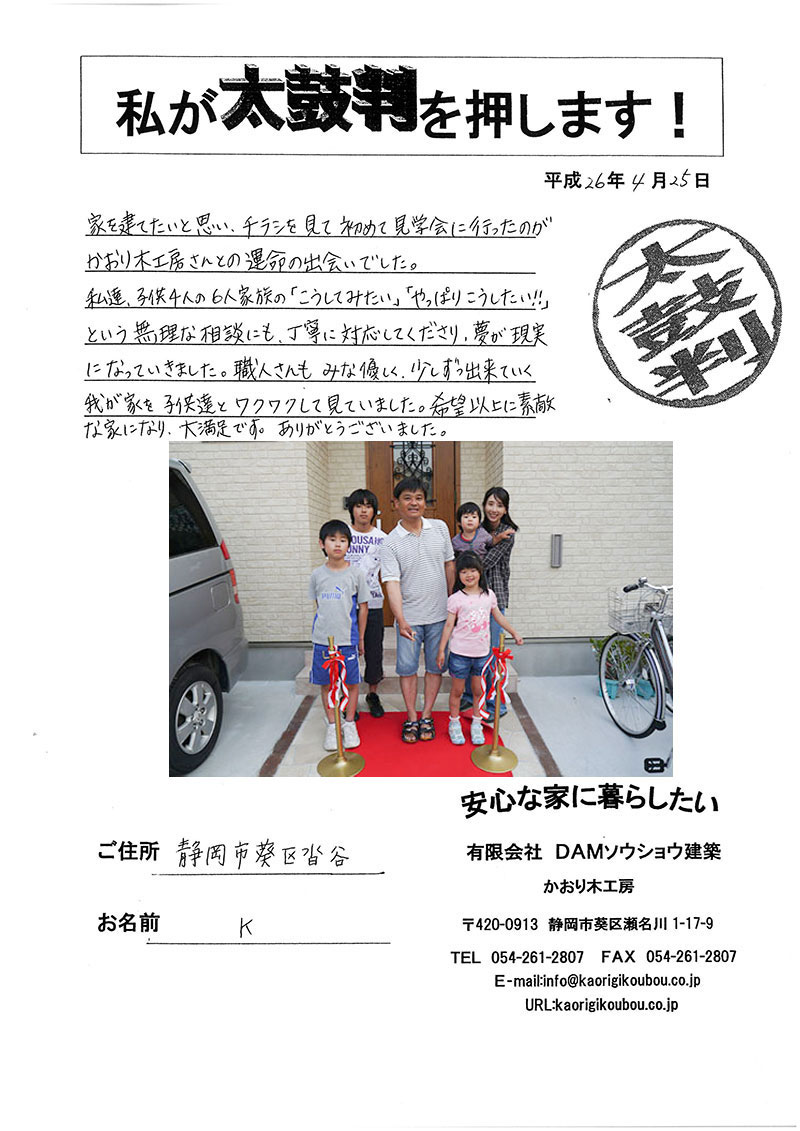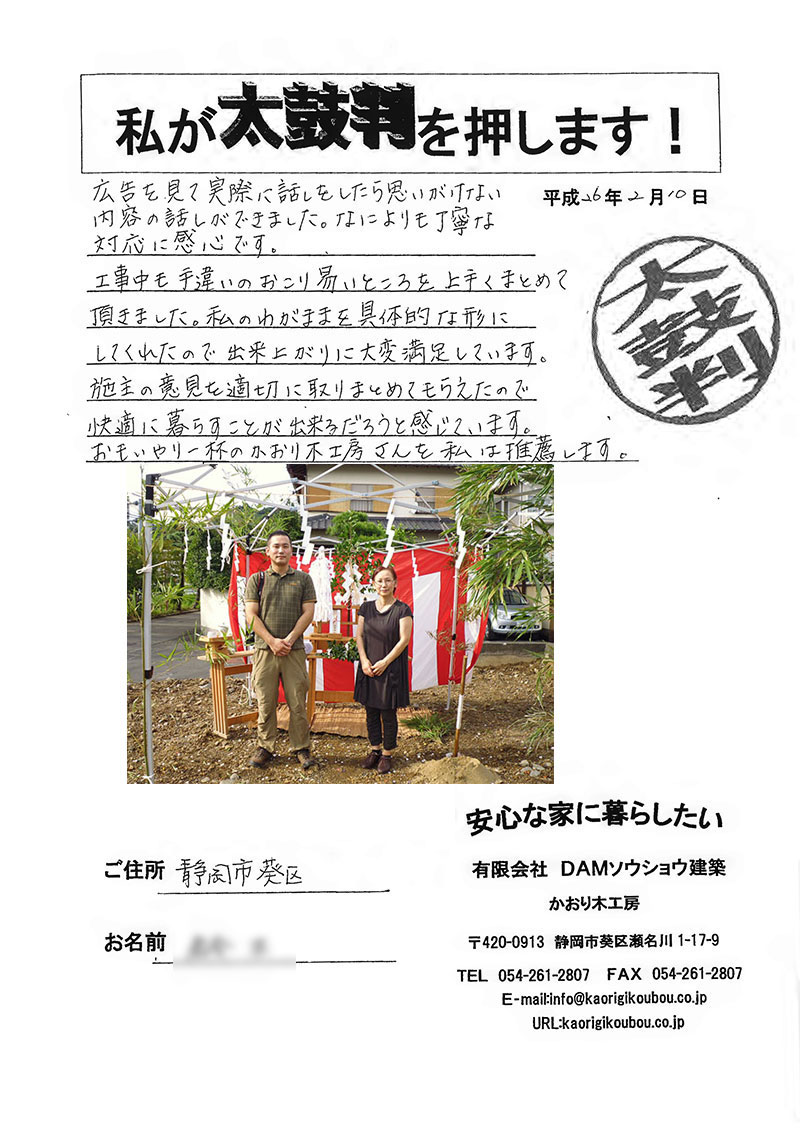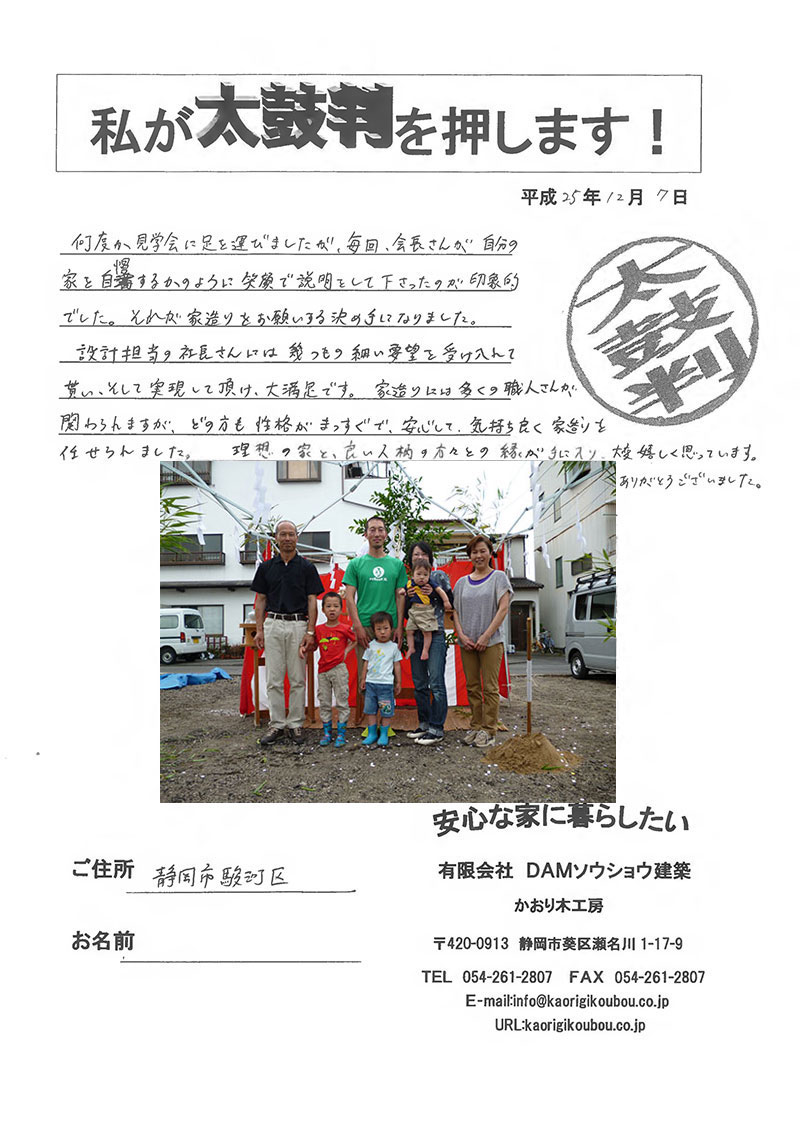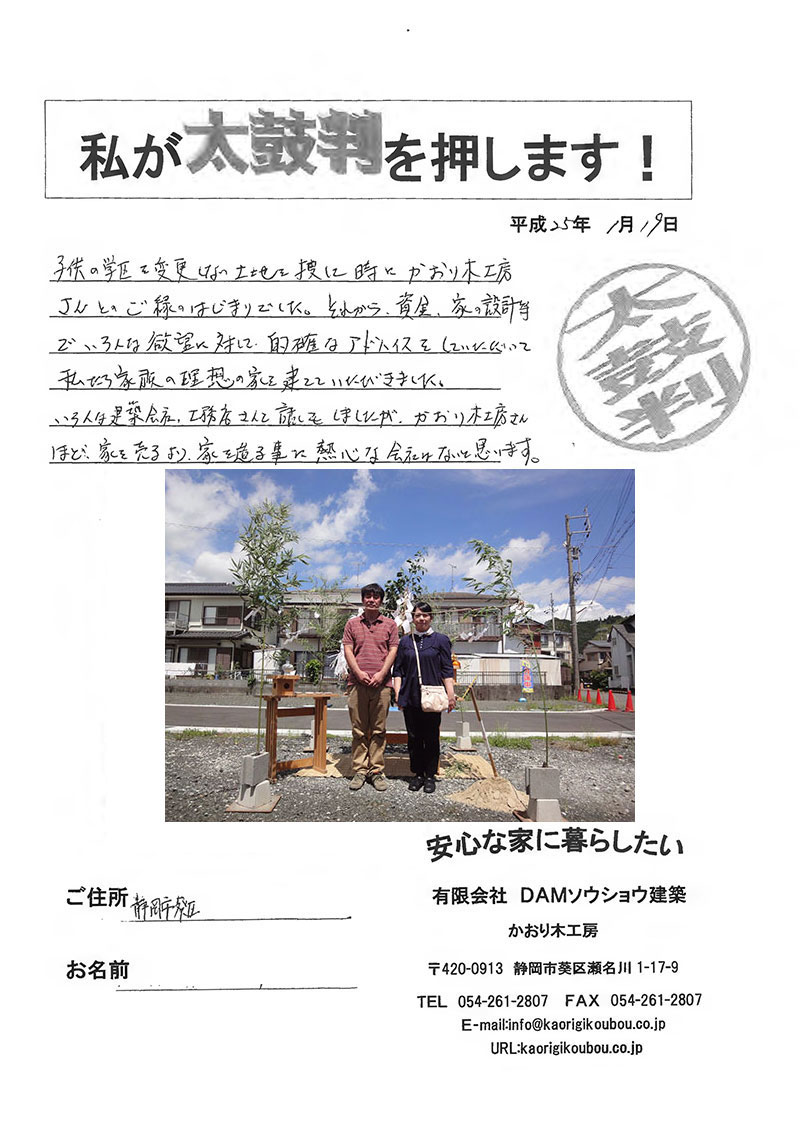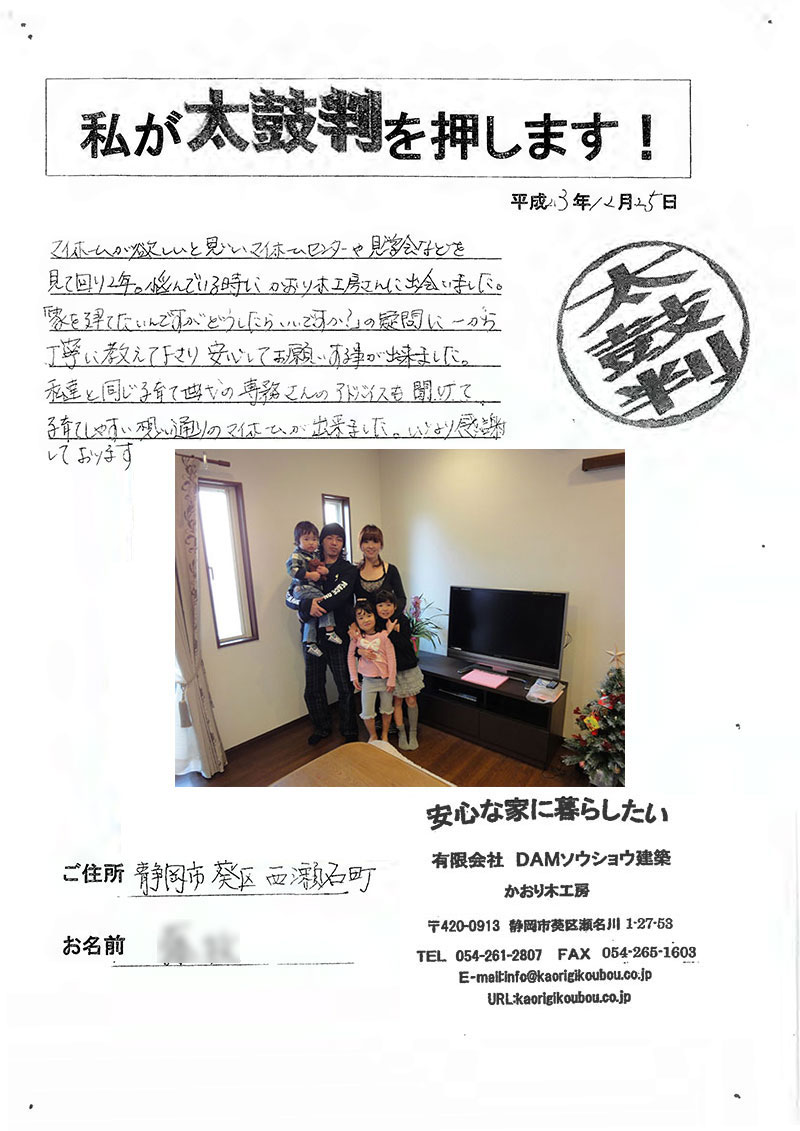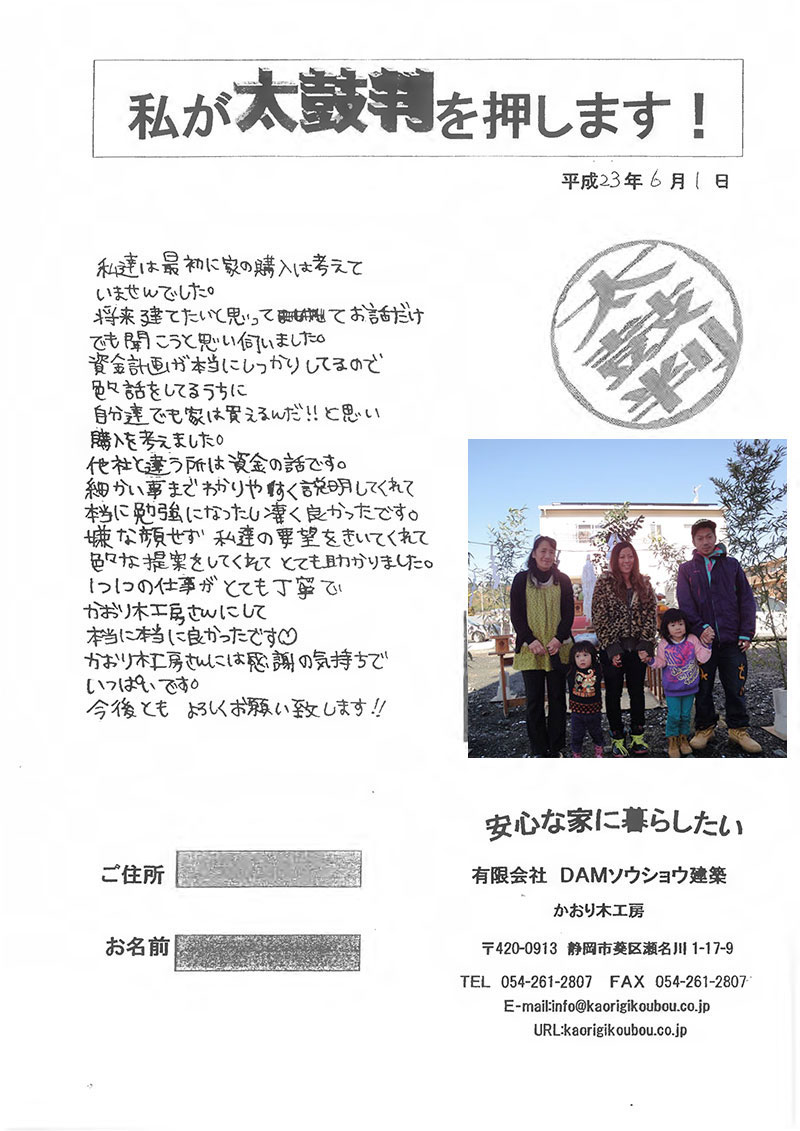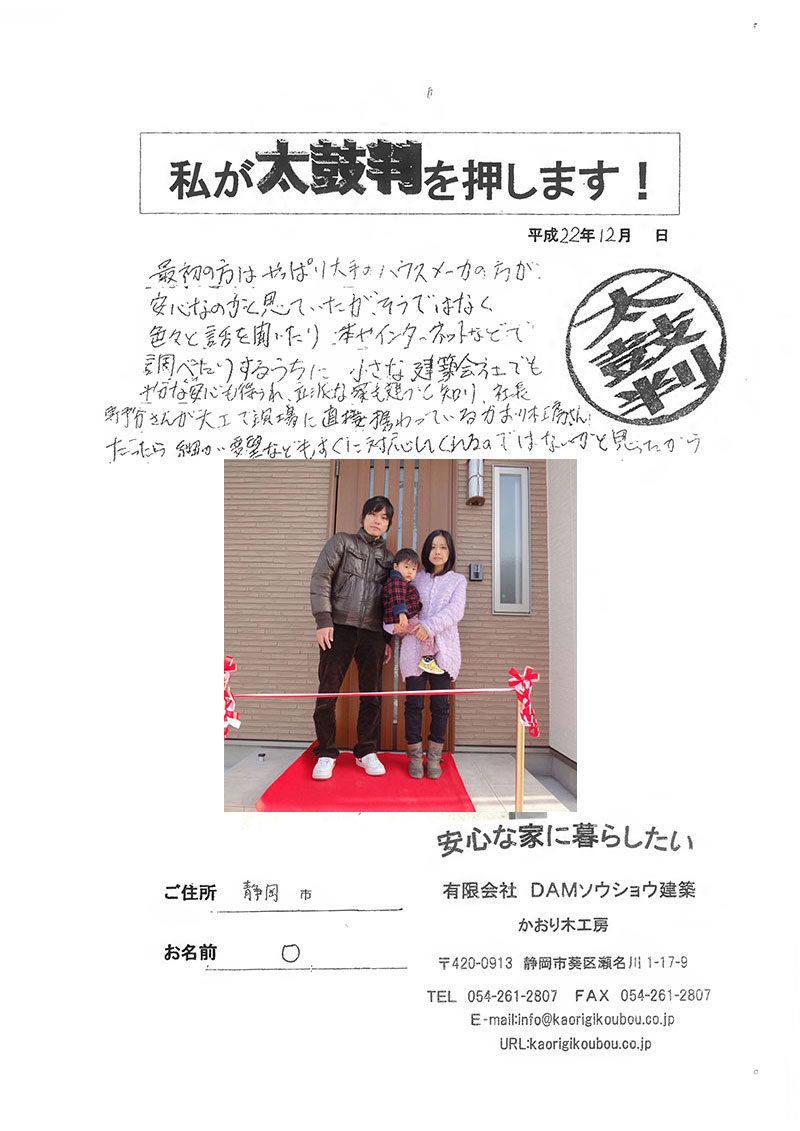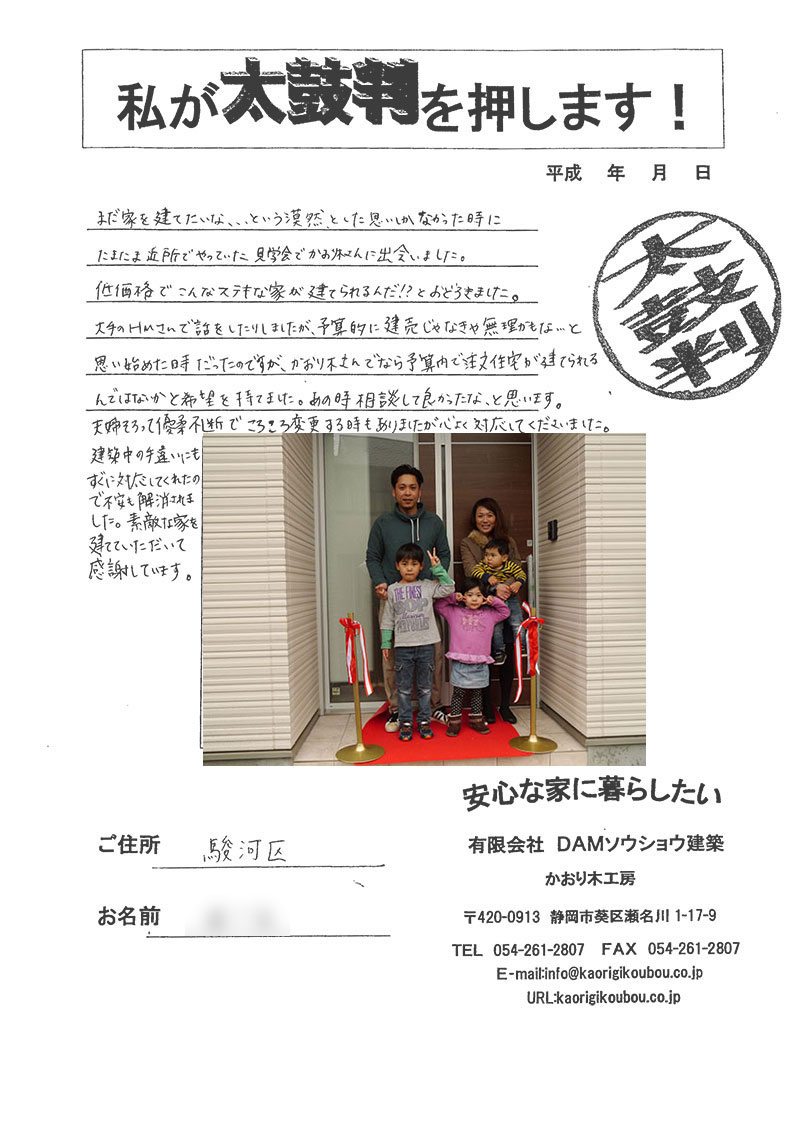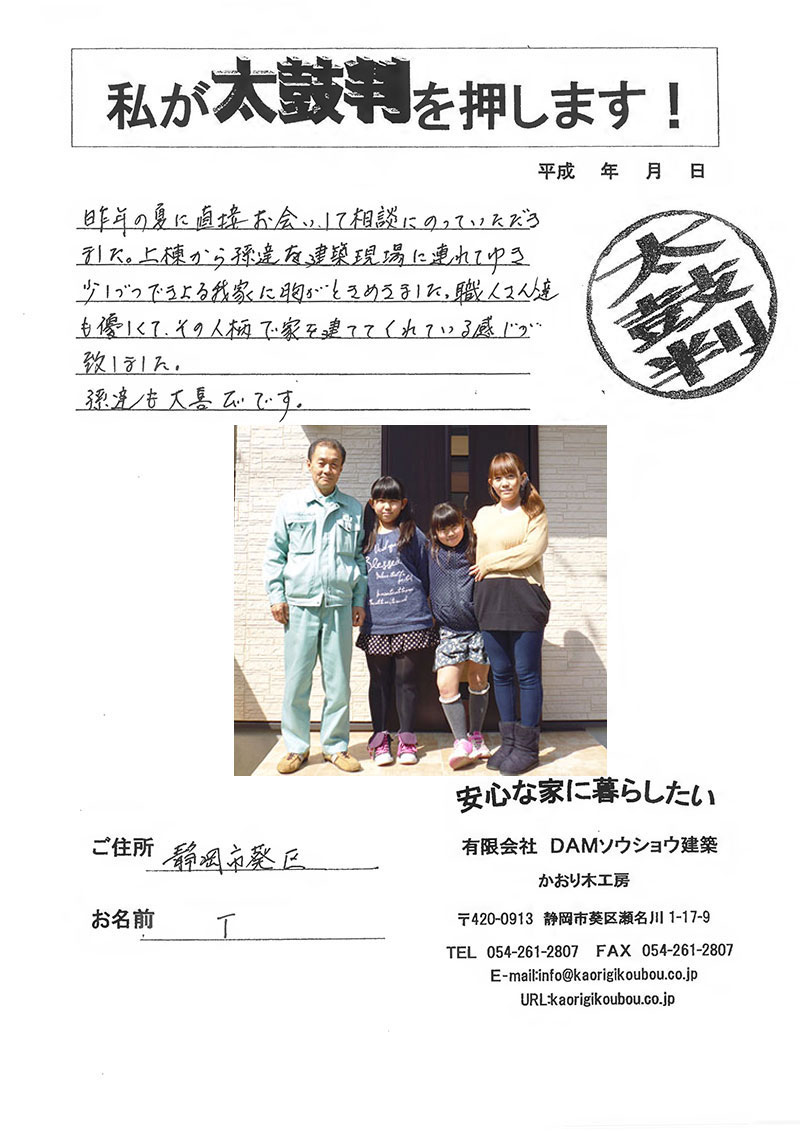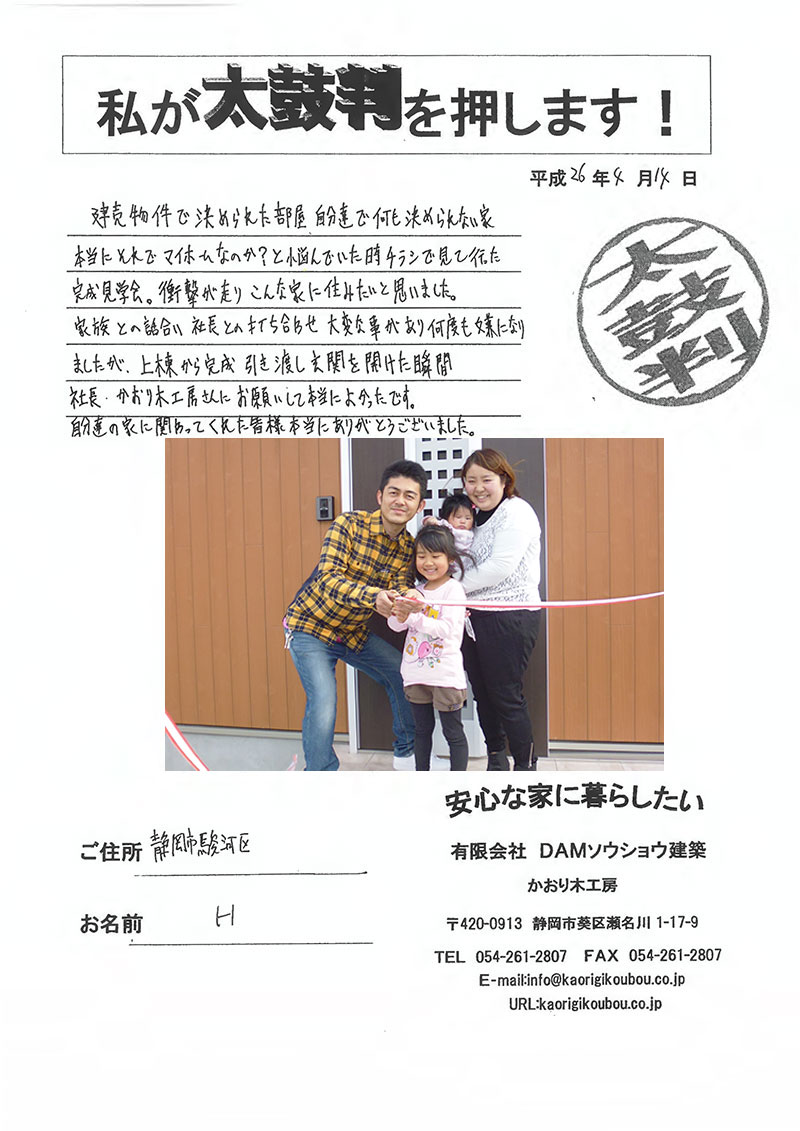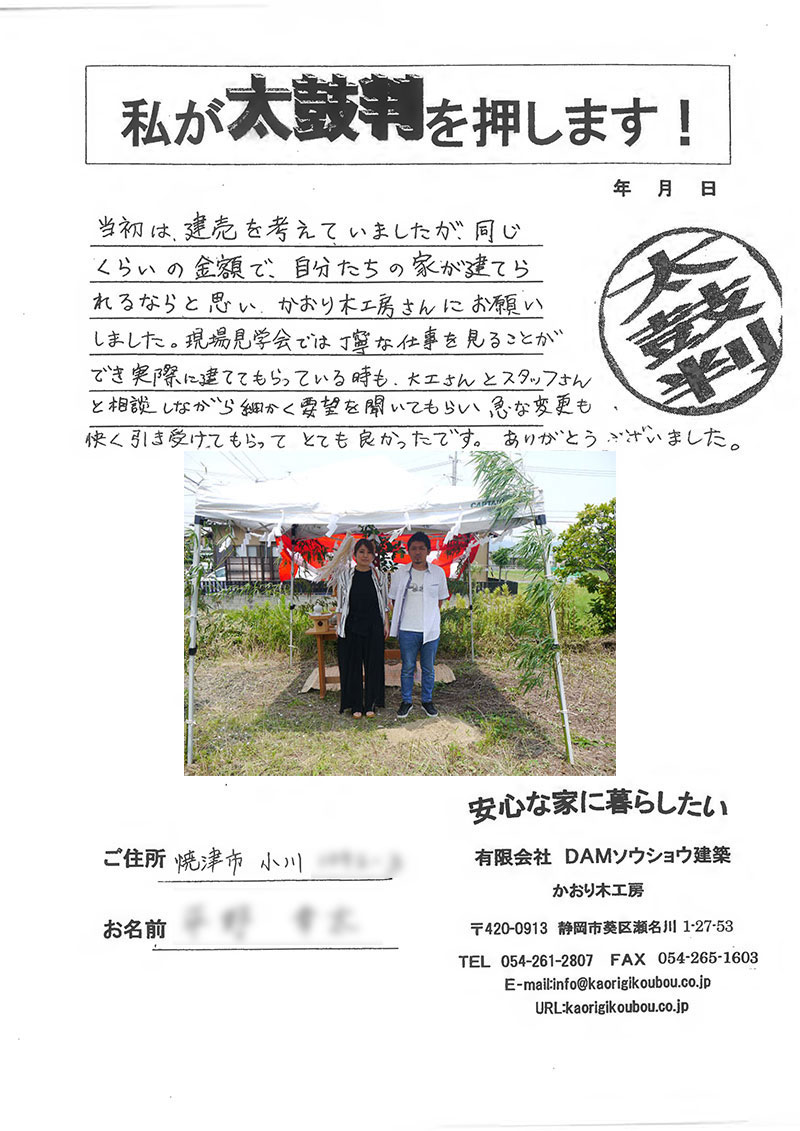加湿と結露の境界線、冬の窓に起きる“見えない危険”
今日のテーマは前回の続編として、
「加湿と結露の境界線──冬の窓に起きる“見えない危険”」
について詳しくお話しします。
こんばんは、かおり木工房のそうのです。
今日の静岡は朝の気温は18℃前後。
朝晩はひんやりと冷えて、秋特有の一日の温度差が大きくなってきました。
こういう季節の変わり目は、家の「湿度コントロール力」が本当に問われる時期です。
この時期、お客様からよく聞かれる質問があります。
「冬は乾燥するから加湿したいけど、結露が心配なんです」
実はこの質問、とても良い感覚なんです。
なぜなら、“快適な湿度を保ちながら結露を防ぐ”というのは、
家づくりの中でもっとも難しいテーマのひとつだからです。
今日はその“加湿と結露のちょうどいい境界線”を、
数字と構造の両面から分かりやすく解説します。
1. 結露とは「湿度が冷たい面で限界を超える現象」
まず基本から。
結露は、空気中の水分が冷たい面に触れて水滴になる現象です。
たとえば、
室内20℃・湿度60%の空気を冷やすと、
12℃以下で水分が空気中にいられなくなり結露します。
これを“露点温度”といいます。
結露を防ぐには、
「空気を乾かす」か「壁や窓を冷やさない」かのどちらかしかありません。
でも、乾燥しすぎると喉が痛くなる。
冷気を完全に防ぐのも難しい。
──だから、この2つのバランスが重要なんです。
2. 「加湿=結露の原因」ではない
よくある誤解が、
「加湿をすると結露する」という考え方。
確かに、湿度が上がると露点温度も上がりますが、
結露が起きるかどうかは“表面温度”との関係次第です。
同じ湿度60%でも、
- 窓の表面温度が15℃なら → 結露しない
- 表面温度が10℃なら → 結露する
つまり、「加湿しても窓が冷えなければ問題なし」。
これが、断熱等級6〜7クラスの家では結露しない理由なんです。
3. 結露が発生する場所は「温度差が集中する部分」
結露が起きやすいのは、家の中でも温度が低い場所。
- 窓ガラス
- サッシ枠(特にアルミ)
- 北側の壁
- 階段下・押し入れの奥
これらは冷えやすく、空気が動かないため結露が発生しやすい。
一方で、家全体が温度一定の全館空調住宅では、
壁・床・天井の温度差が小さいため、
空気が滞らず結露が起きにくくなります。
ポイントは「温度差をなくす設計」。
断熱材の性能だけでなく、空気の流れ方(動線)が重要です。
4. サッシとガラスの選び方で結露リスクは激減する
窓まわりの結露は、ガラスの種類とサッシ素材でほぼ決まります。
| 部位 | 一般的な仕様 | 高性能仕様 | 結露リスク |
|---|---|---|---|
| ガラス | 複層ガラス(ペア) | トリプルガラス | 約50%減 |
| サッシ | アルミ | 樹脂 or 樹脂複合 | 約80%減 |
かおり木工房では、樹脂サッシ+トリプルガラス(アルゴンガス入り)を標準採用。
冬場のガラス表面温度は平均18〜19℃を保ち、
湿度55%でも結露しません。
5. “結露ゼロ”を実現する3つの条件
- 断熱性能:UA値0.26以下(等級7相当)
→ 壁・天井・床の表面温度差を最小化。 - 気密性能:C値0.3以下
→ 隙間風による冷気侵入を防止。 - 換気性能:一種換気(全熱交換)
→ 湿度を一定に保ち、空気のよどみを防ぐ。
この3つが揃うと、
「加湿しても結露しない家」が実現します。
7. まとめ|“結露しない家”は“加湿できる家”
昔の家は、「加湿したら結露する」でした。
これからの家は、「加湿しても結露しない」が常識になります。
- 窓が冷えない
- 空気が動いている
- 湿度が一定
この3つが揃えば、
“快適で健康に暮らせる冬”を迎えられます。
静岡のような温暖地こそ、
気密・断熱・換気を正しく設計すれば、
「乾燥にも結露にも負けない家」がつくれます。
それでは、また。
朝晩の冷え込みが強くなってきました。
どうぞ温かくしてお過ごしください。
賢い夫婦がやっぱり選んだ注文住宅専門工務店「かおり木工房」
住所:静岡市葵区瀬名川1-27-53
電話:054-261-2807(10時〜17時)
社長直通:090-6587-4713(「HP見た」とお伝えください)
施工エリア:静岡市・焼津市・藤枝市
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCV2CLl-P_j80GPTuVRLMXpQ
Instagram:https://www.instagram.com/kaorigikoubou/
LINE:https://page.line.me/107aufgi?openQrModal=true
TikTok:https://www.tiktok.com/@kaorigikoubou