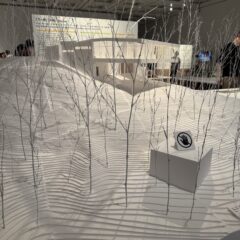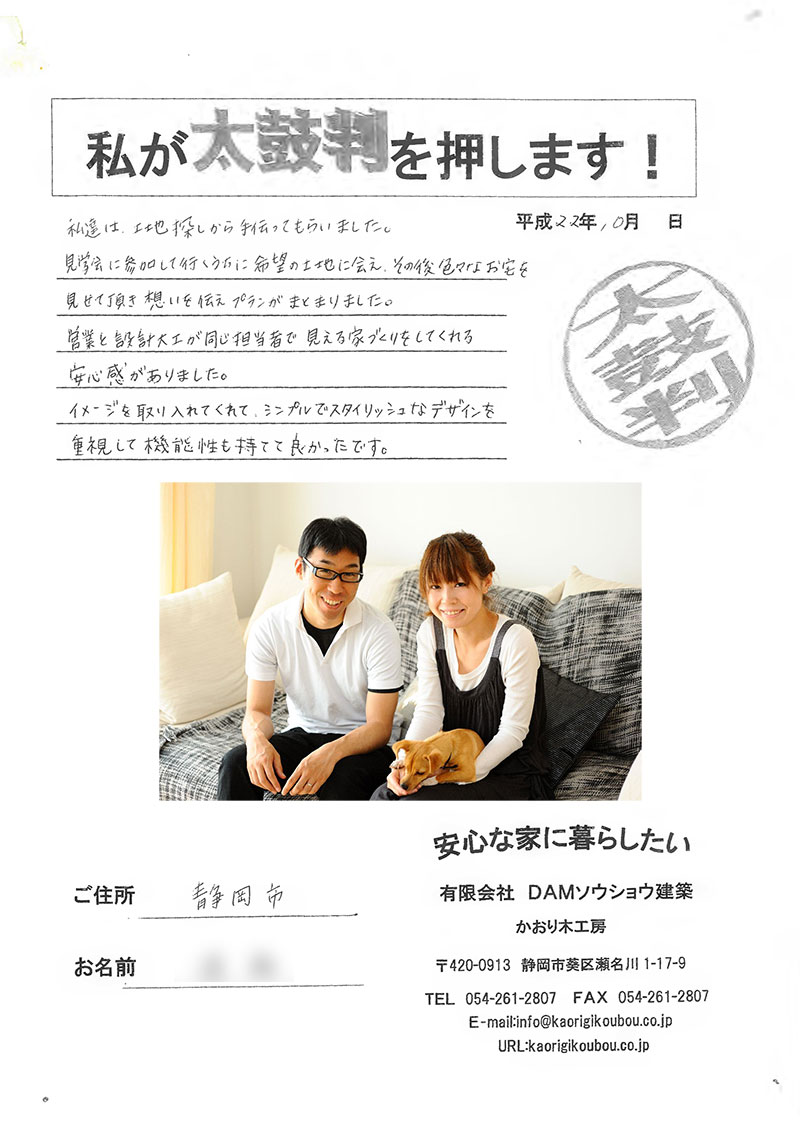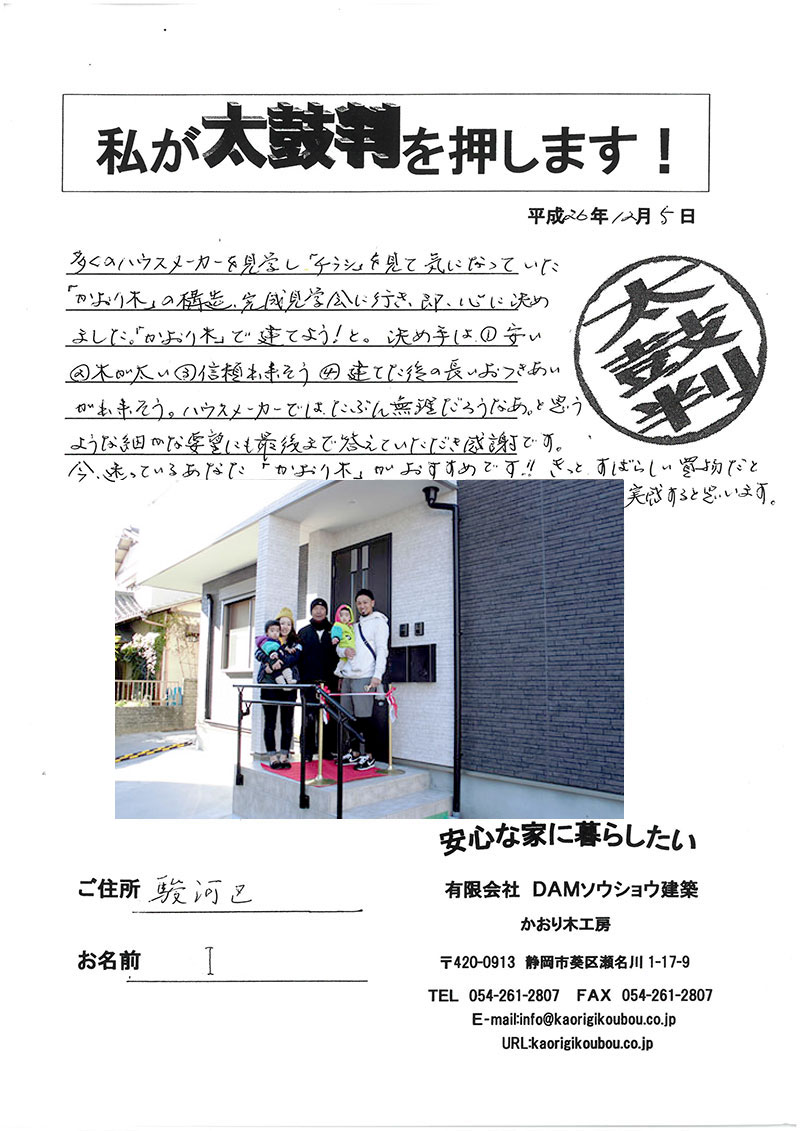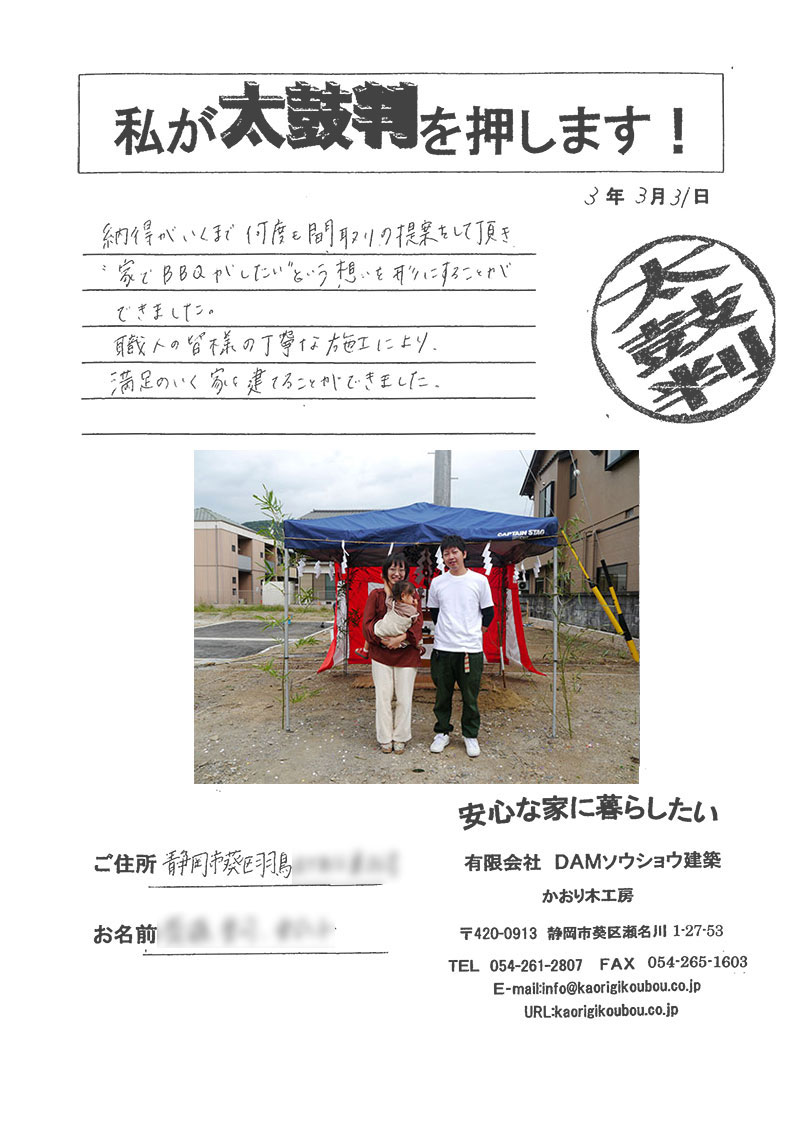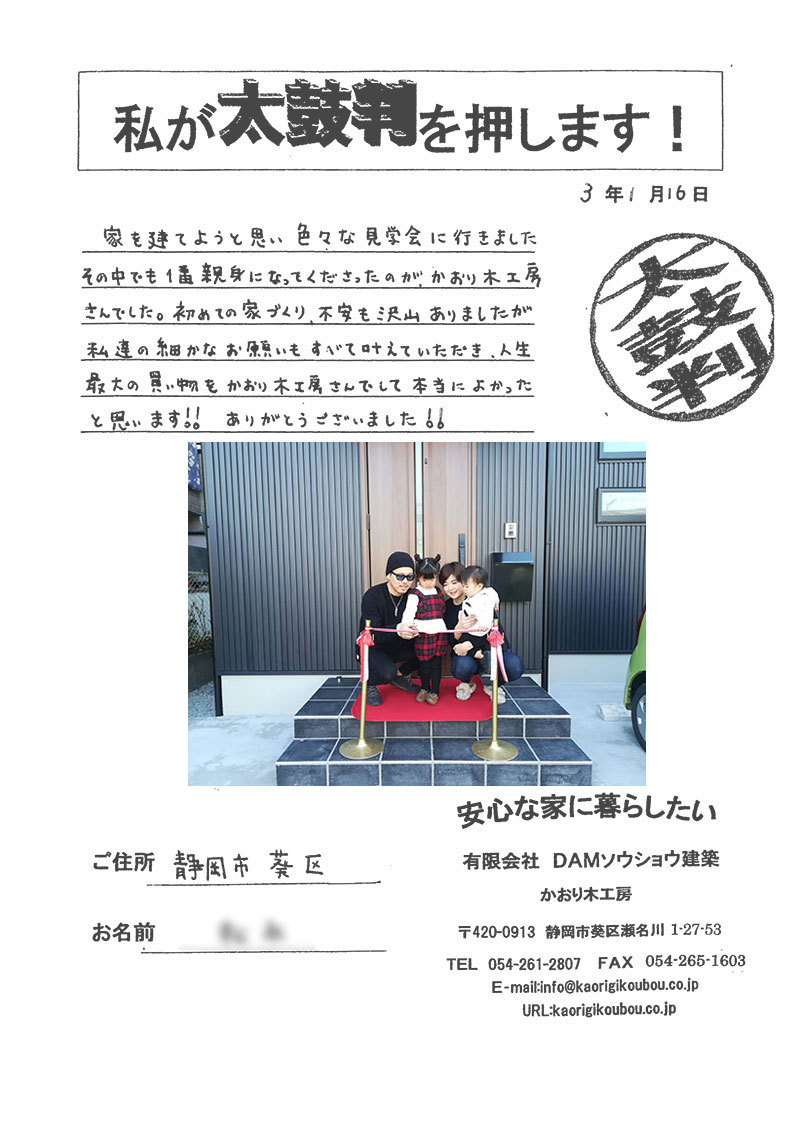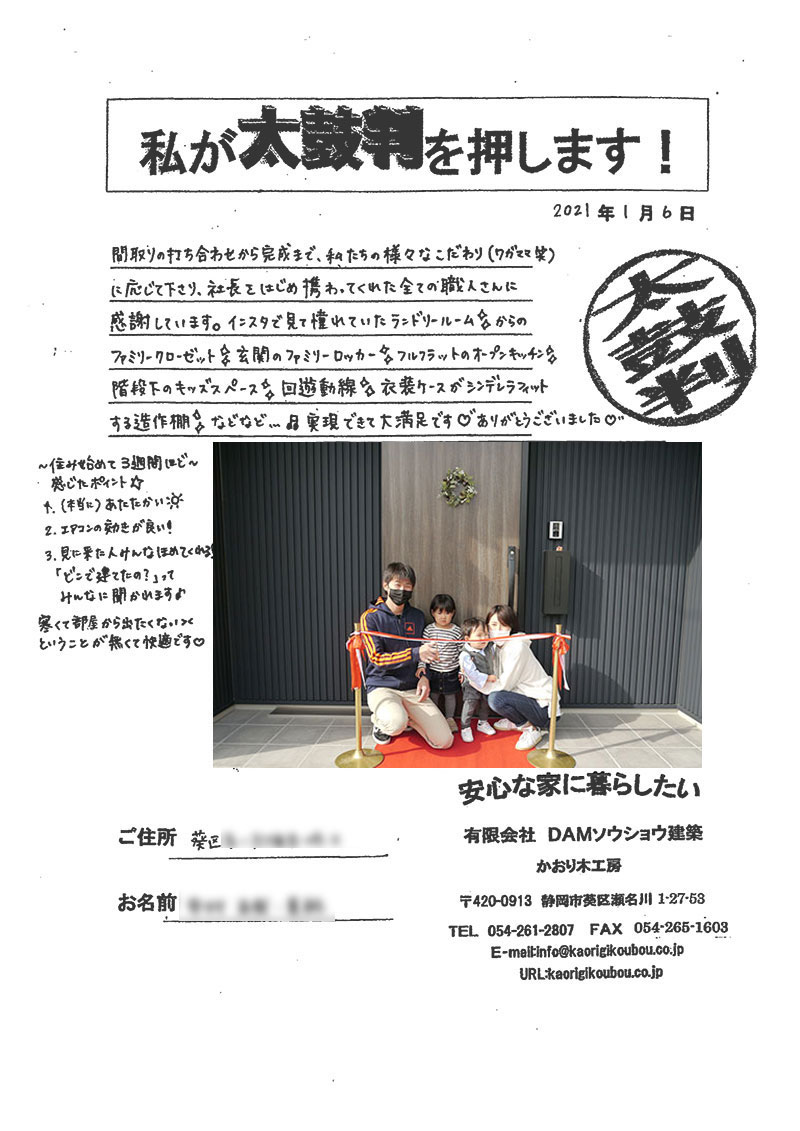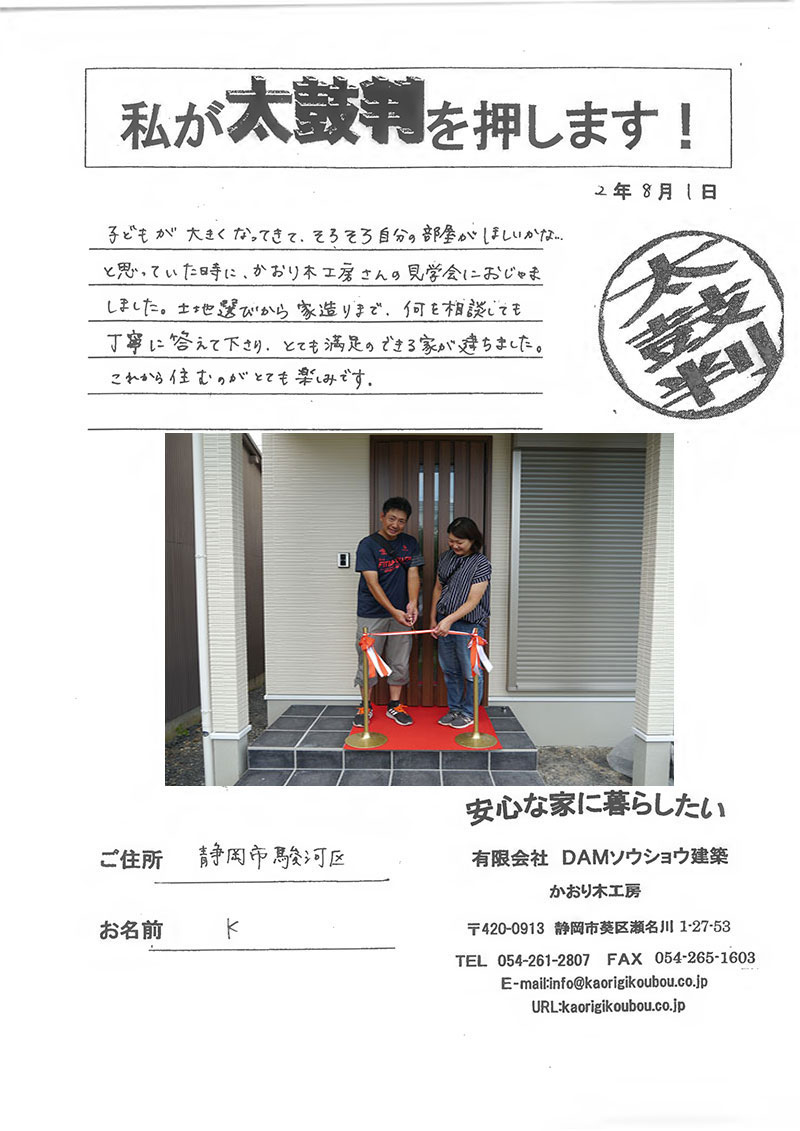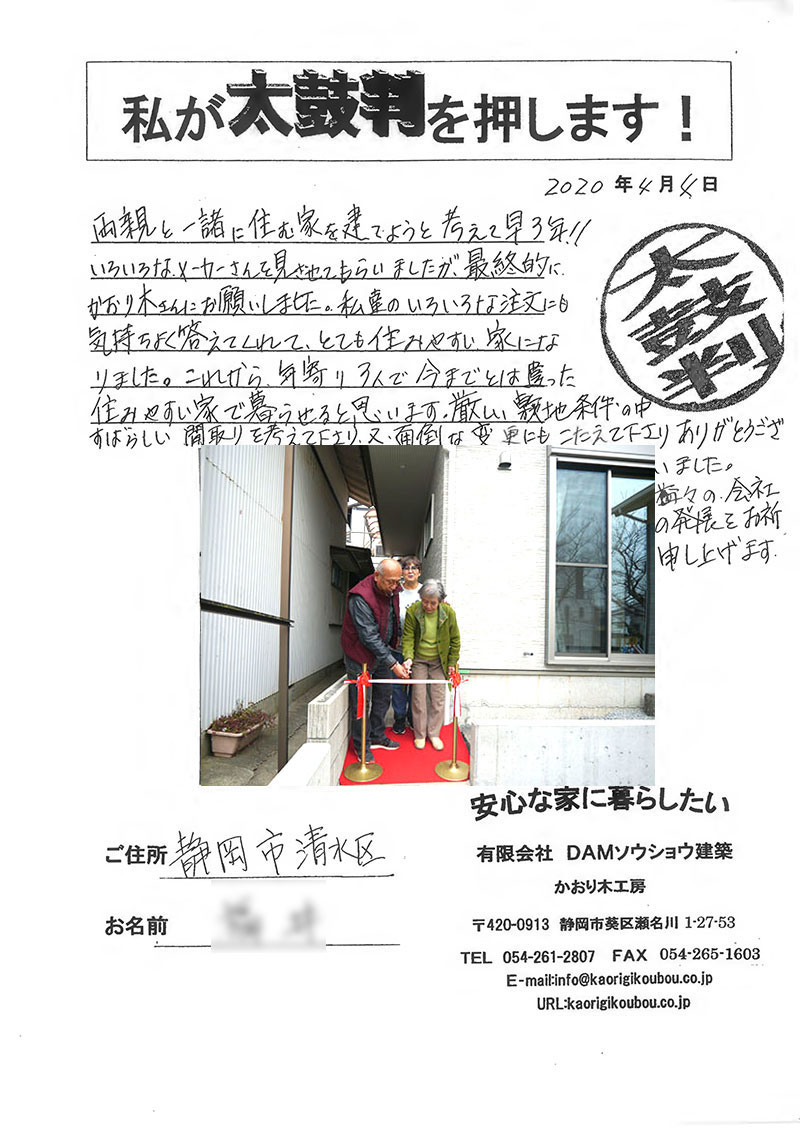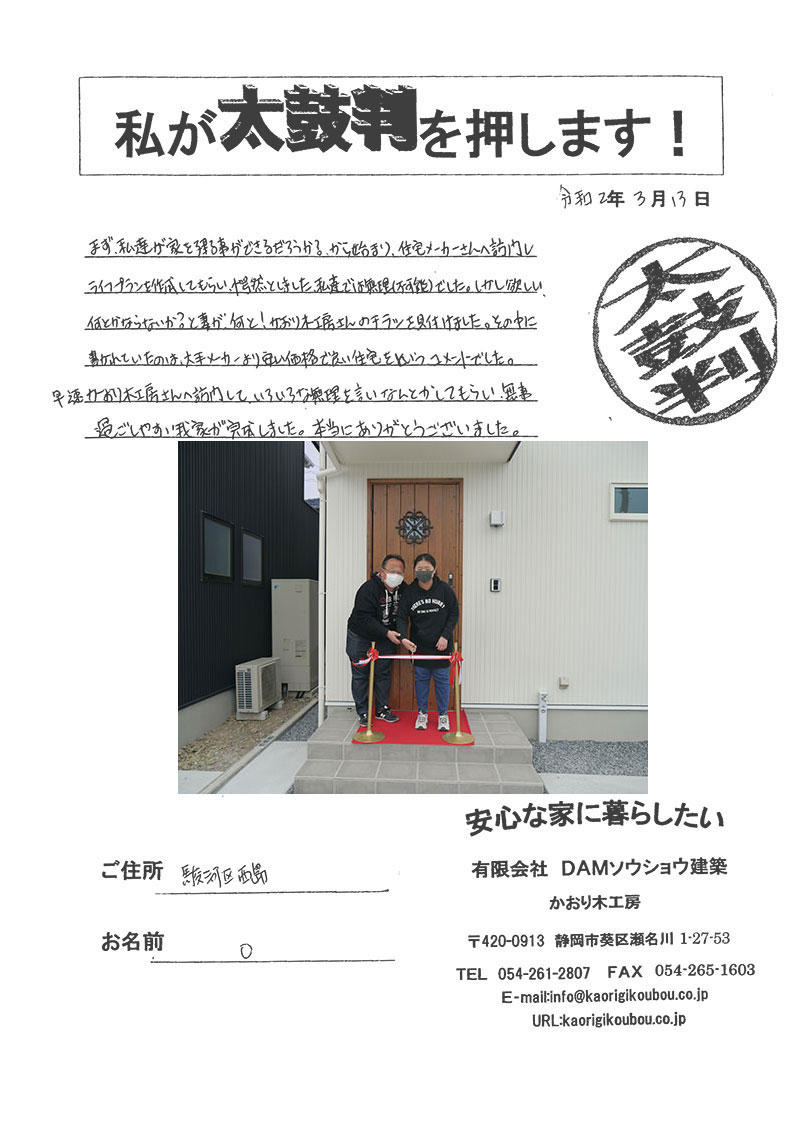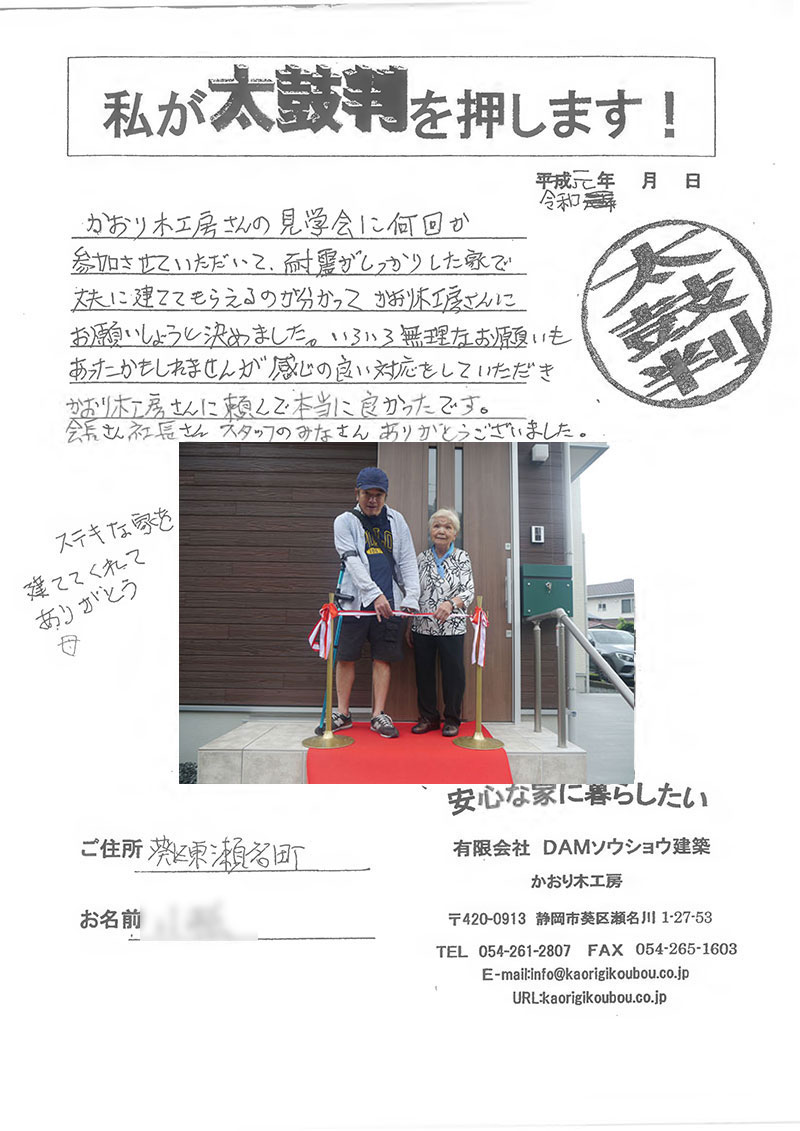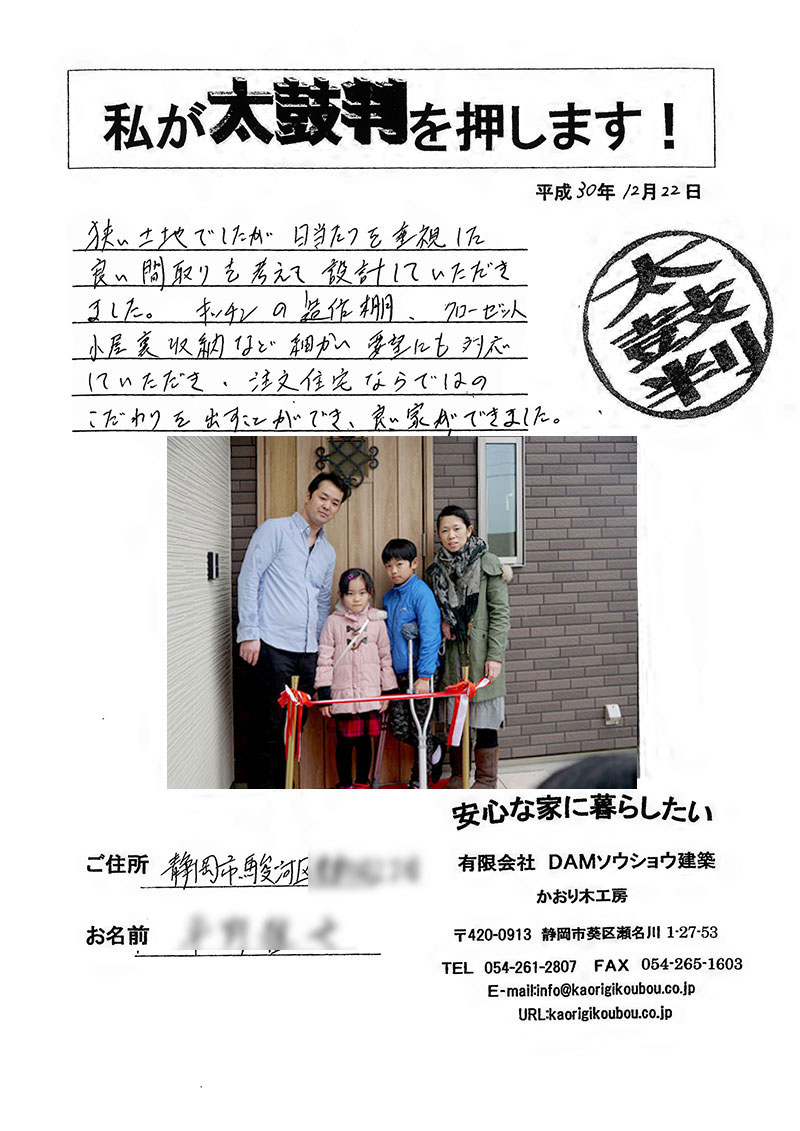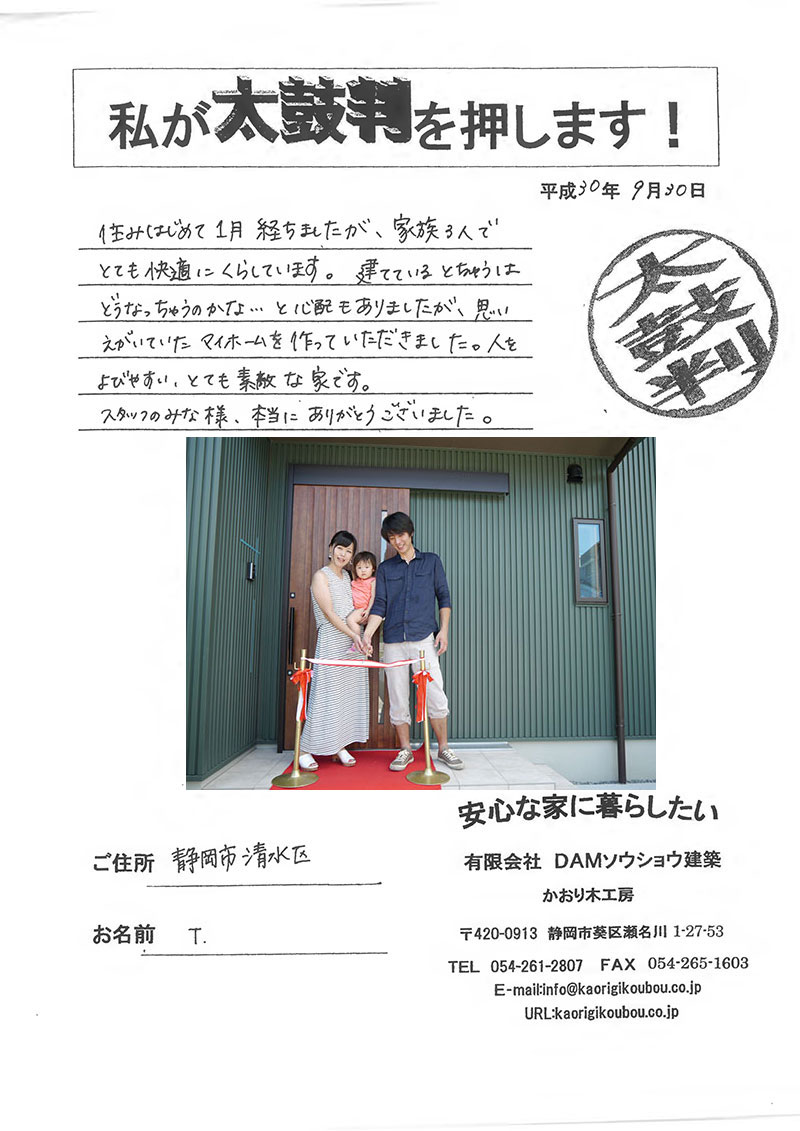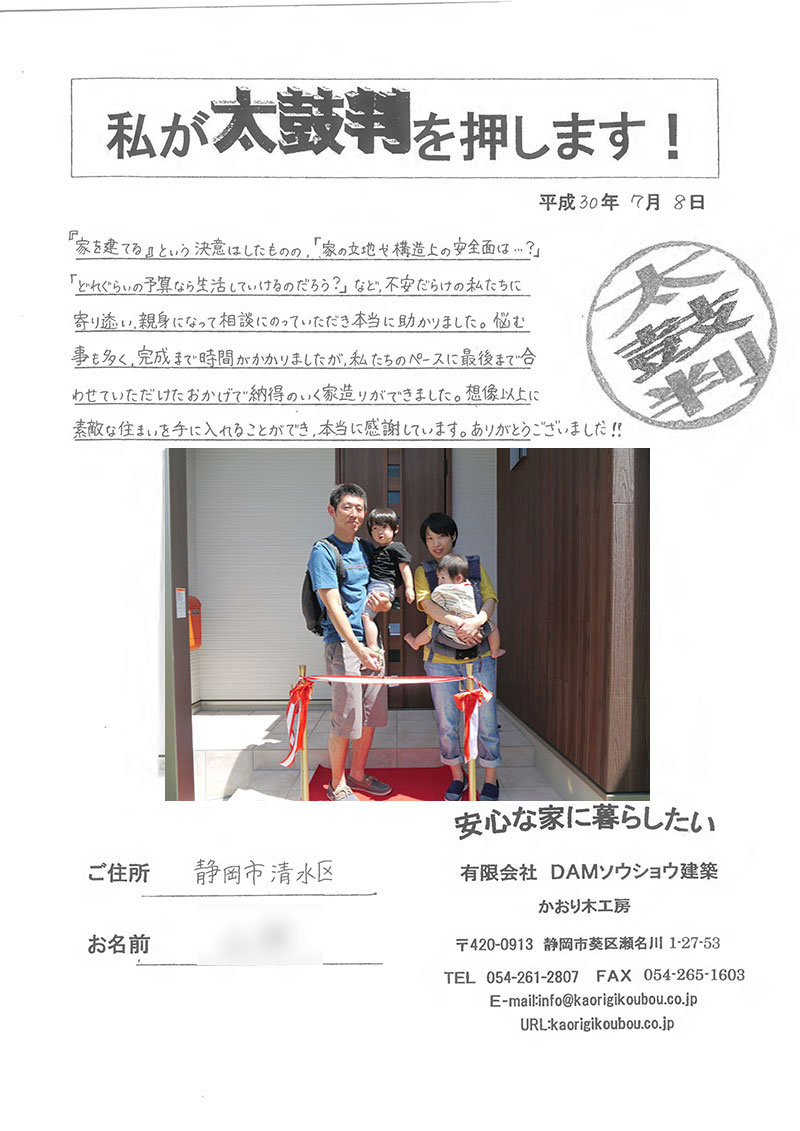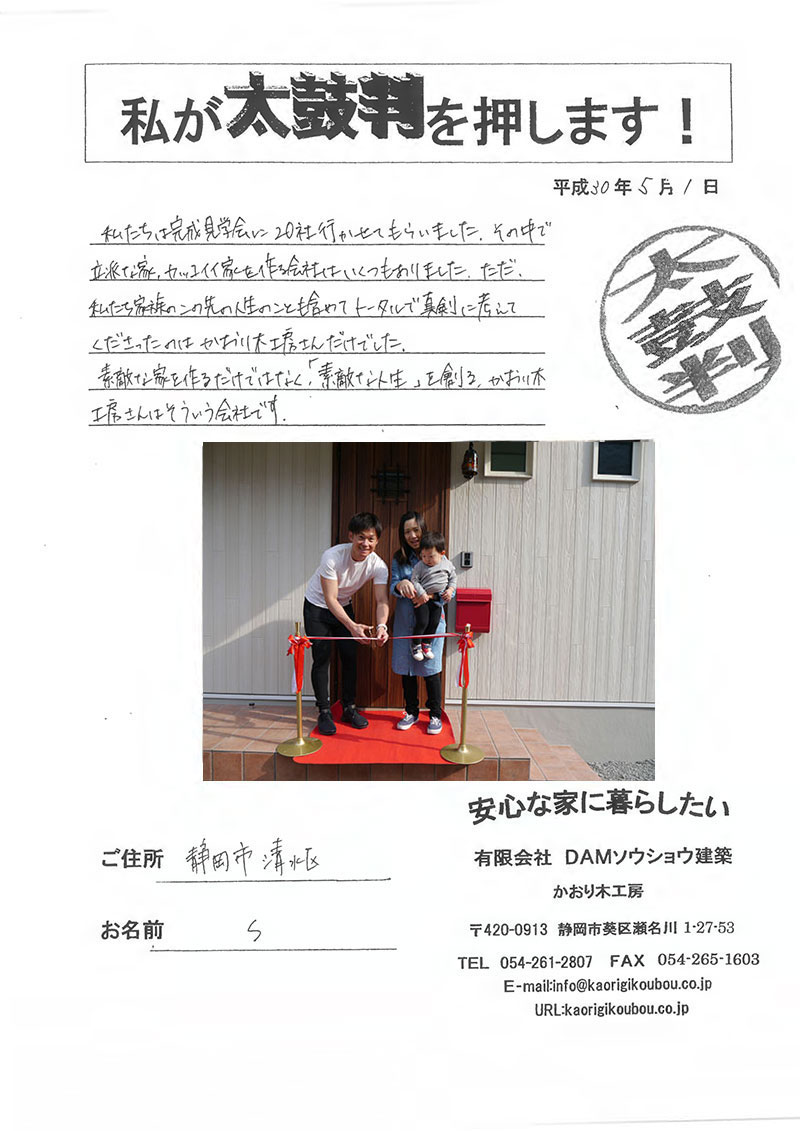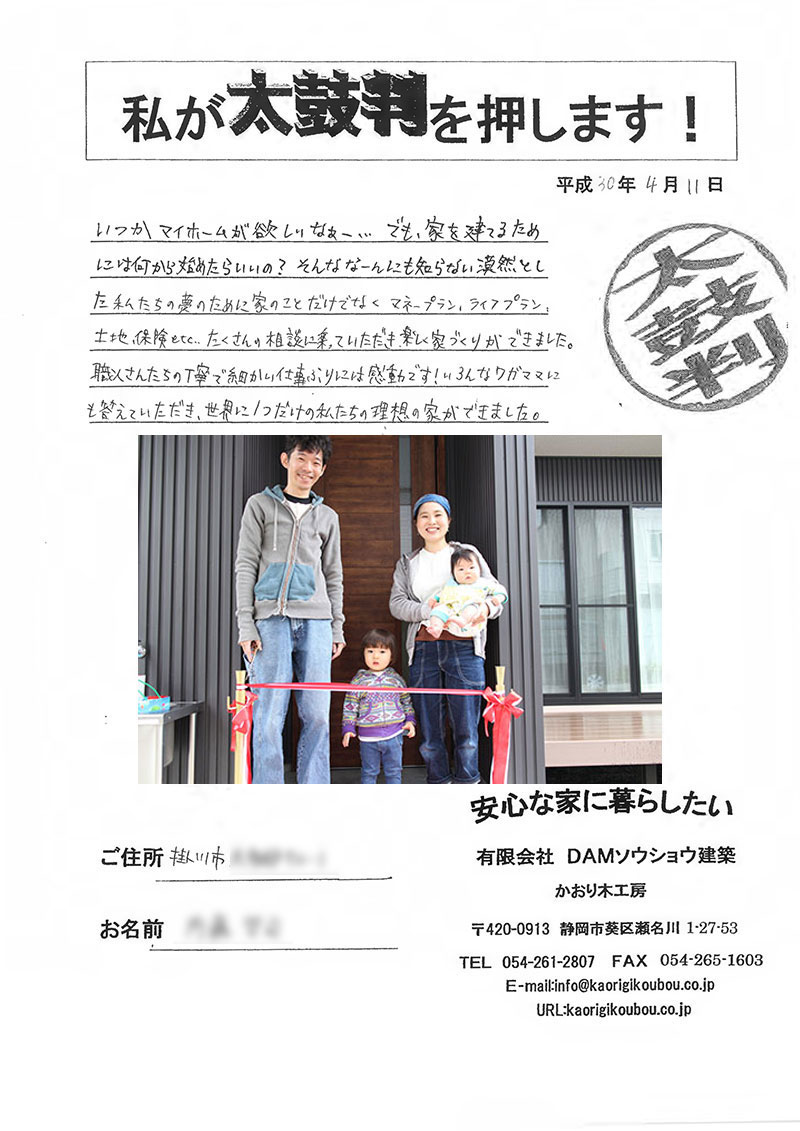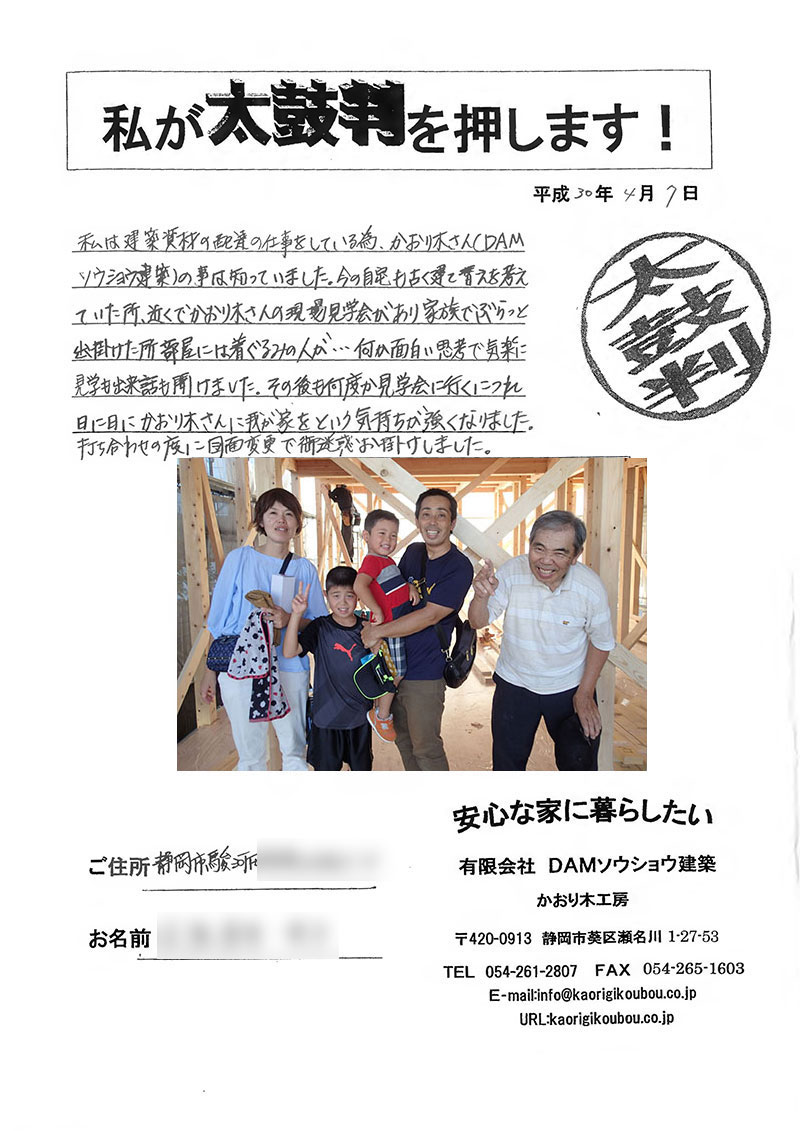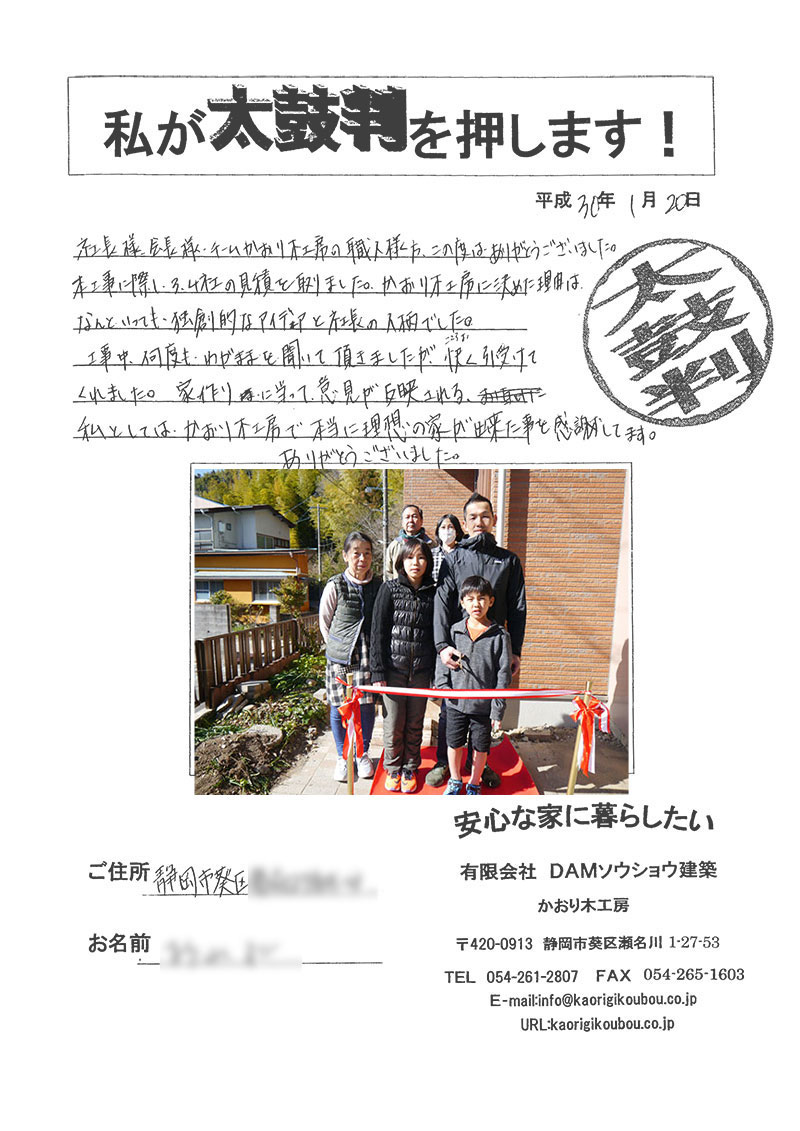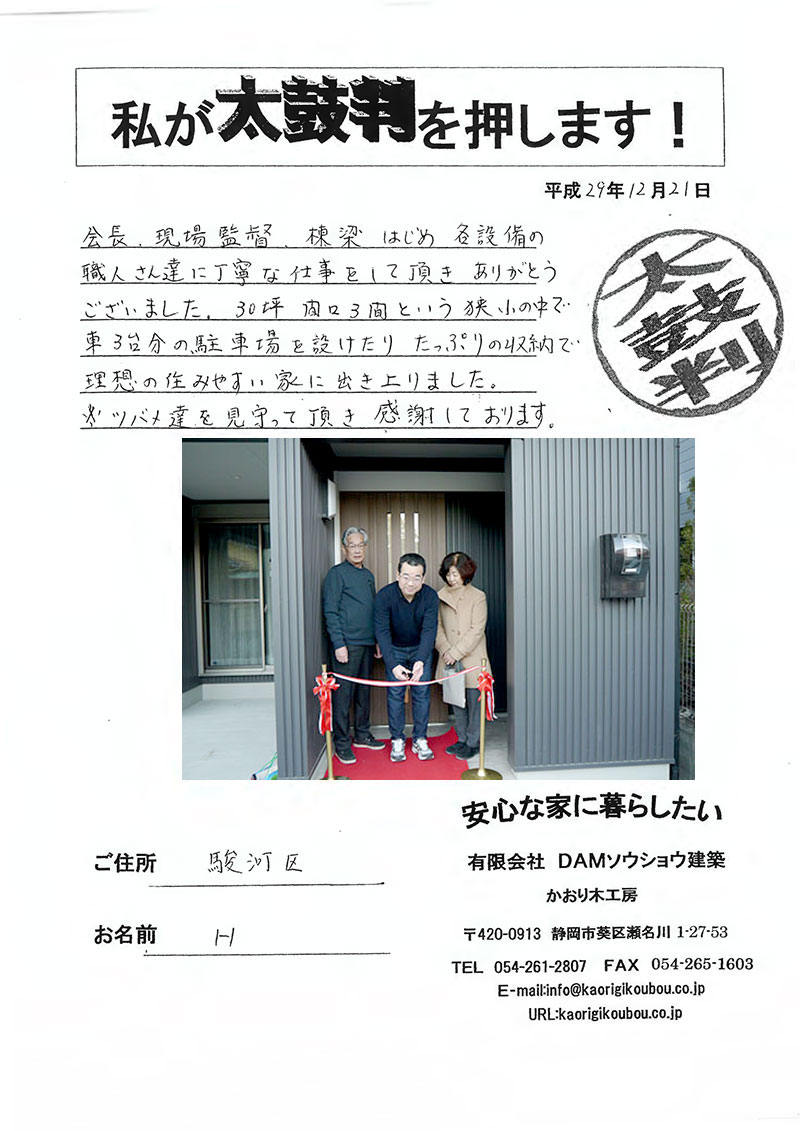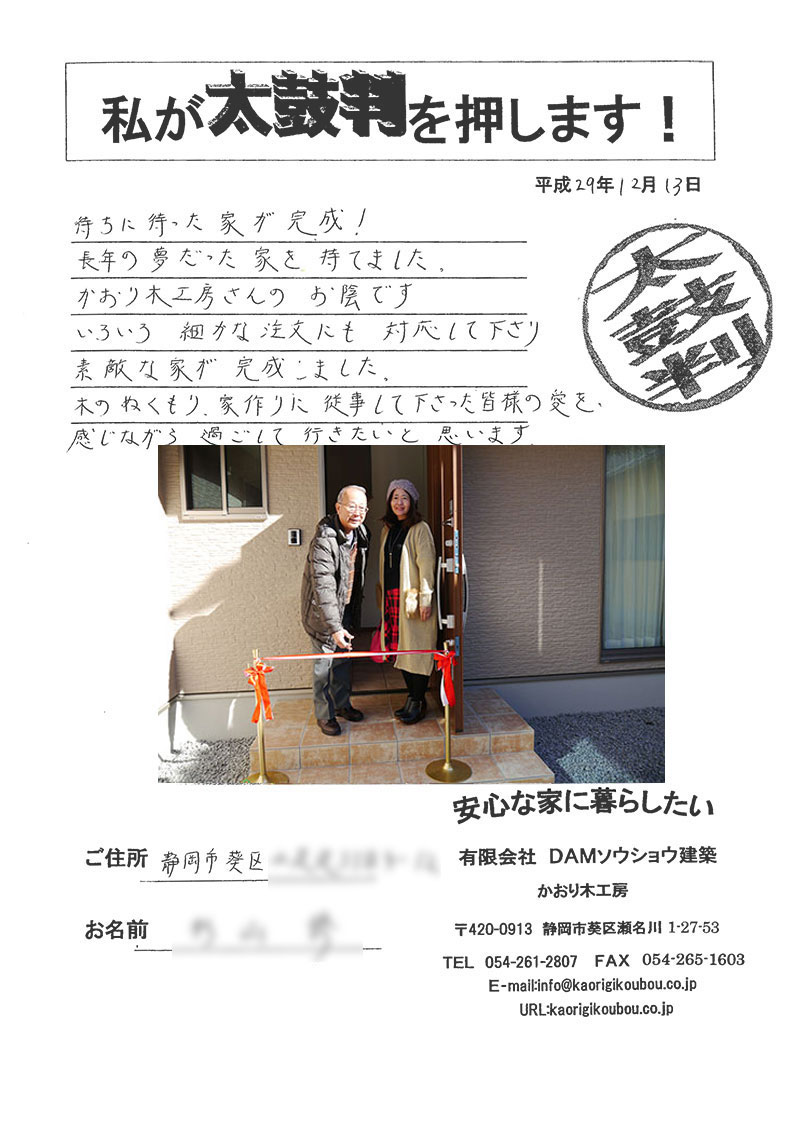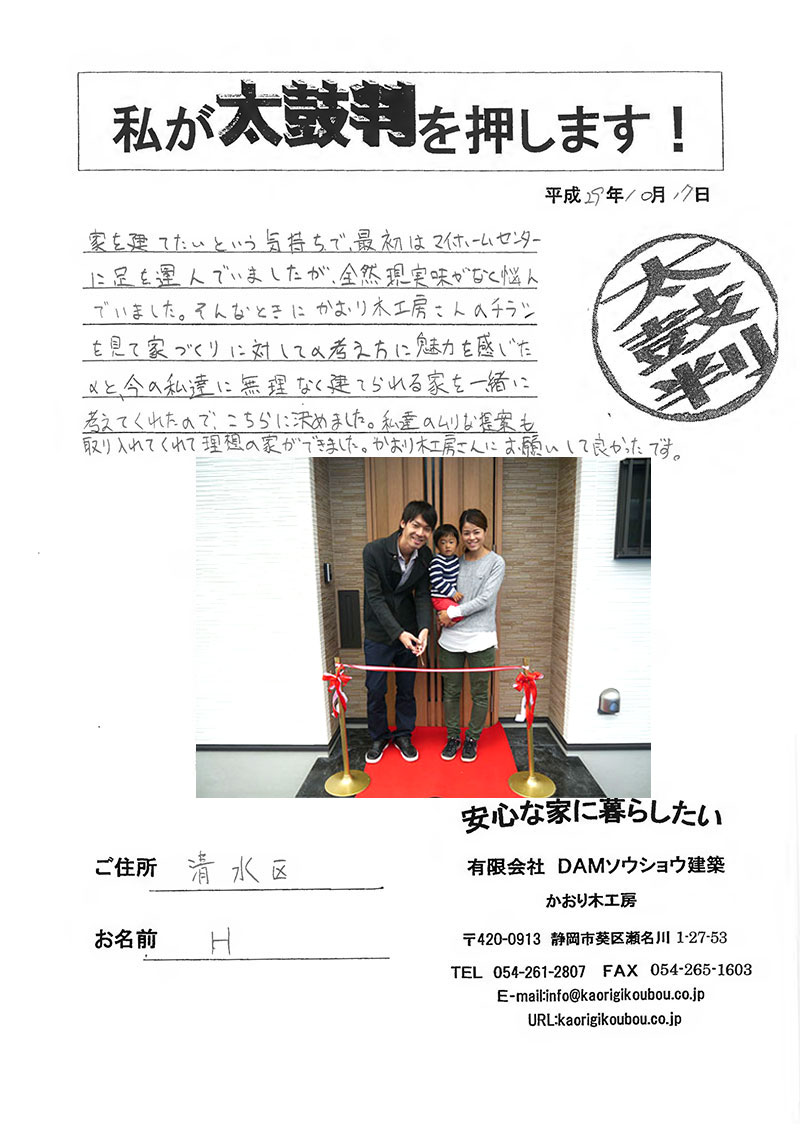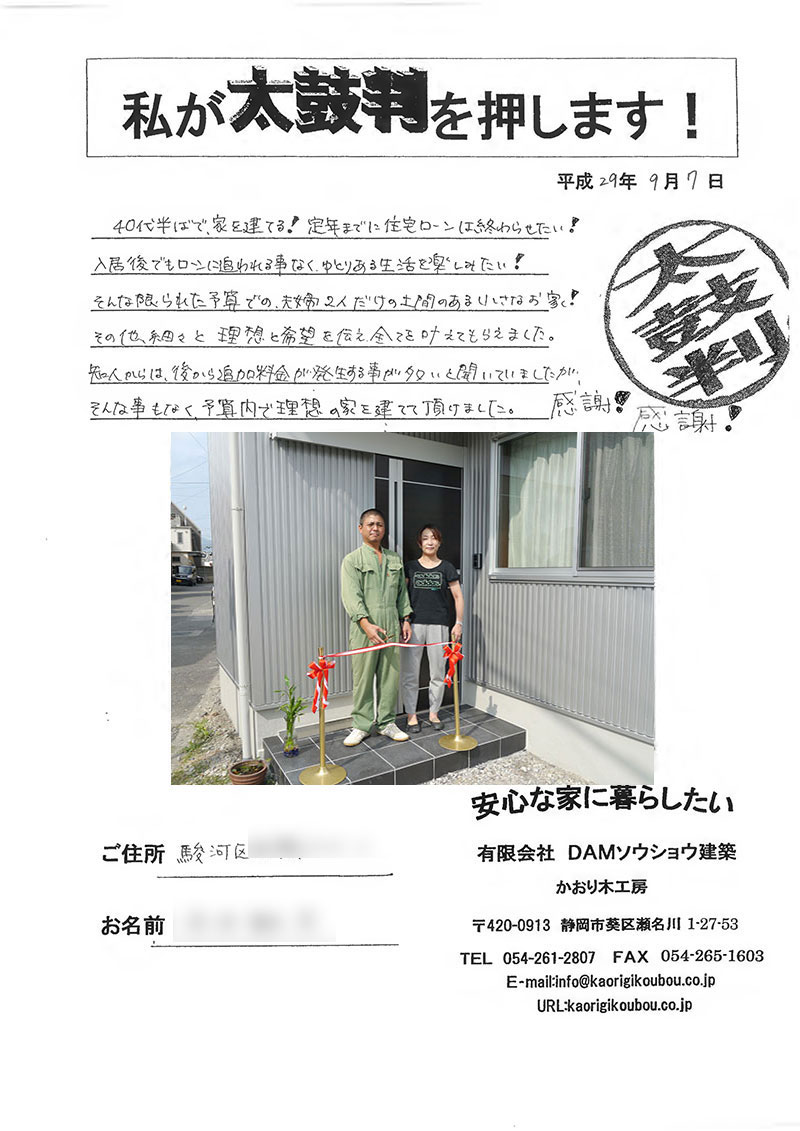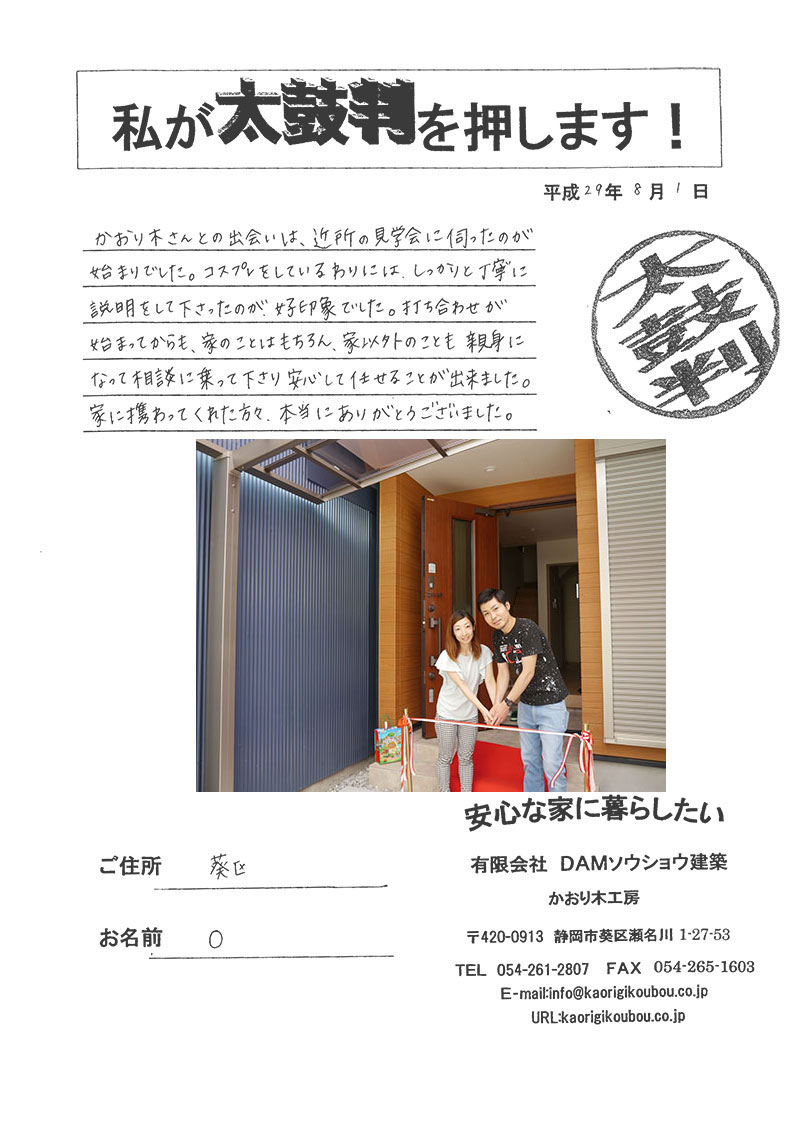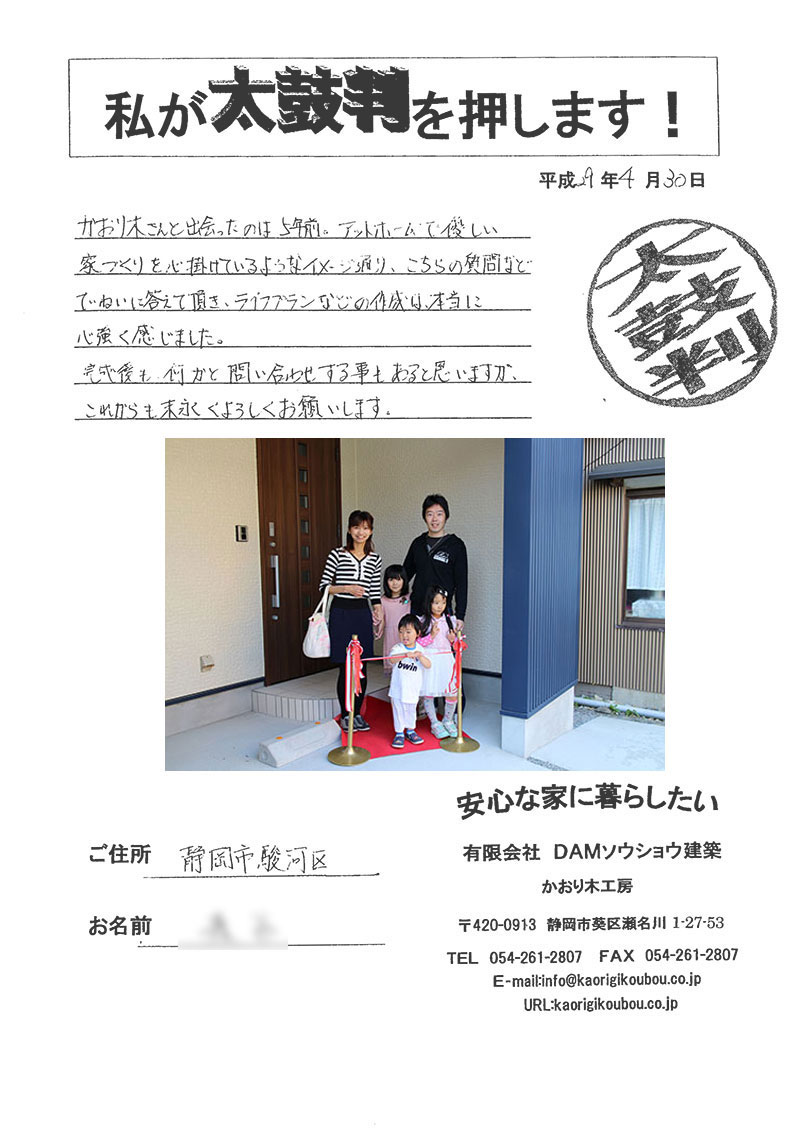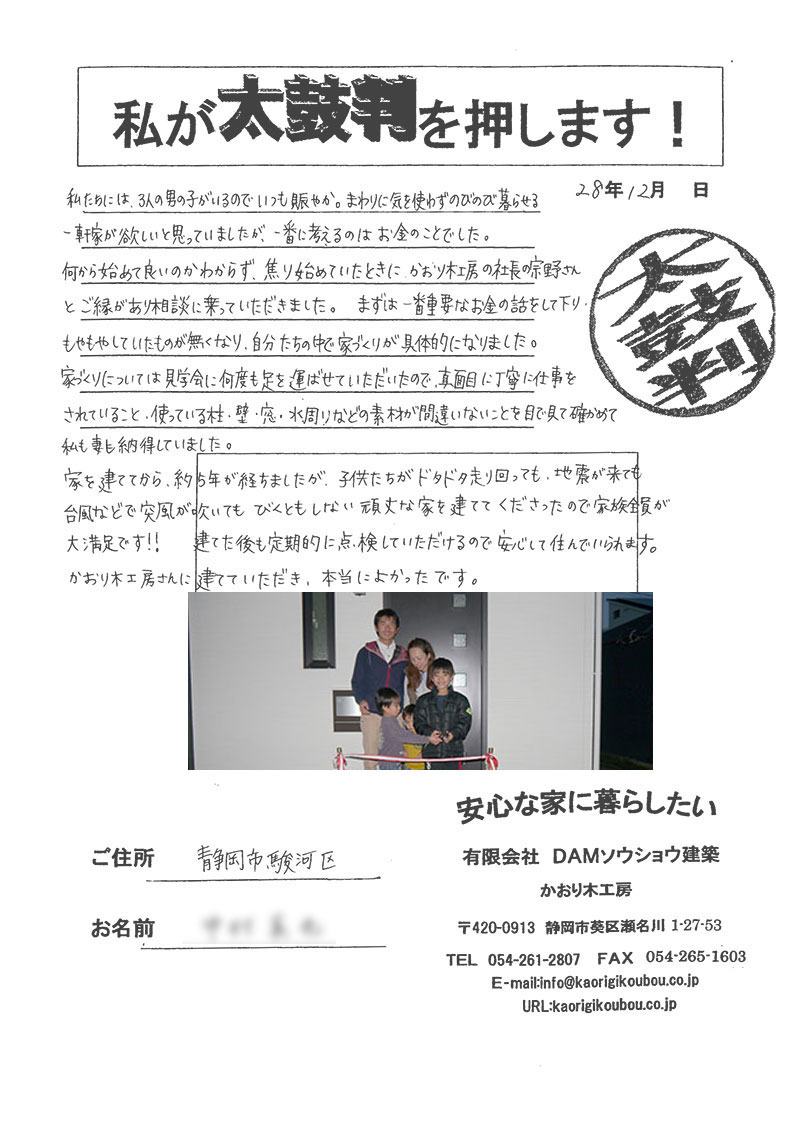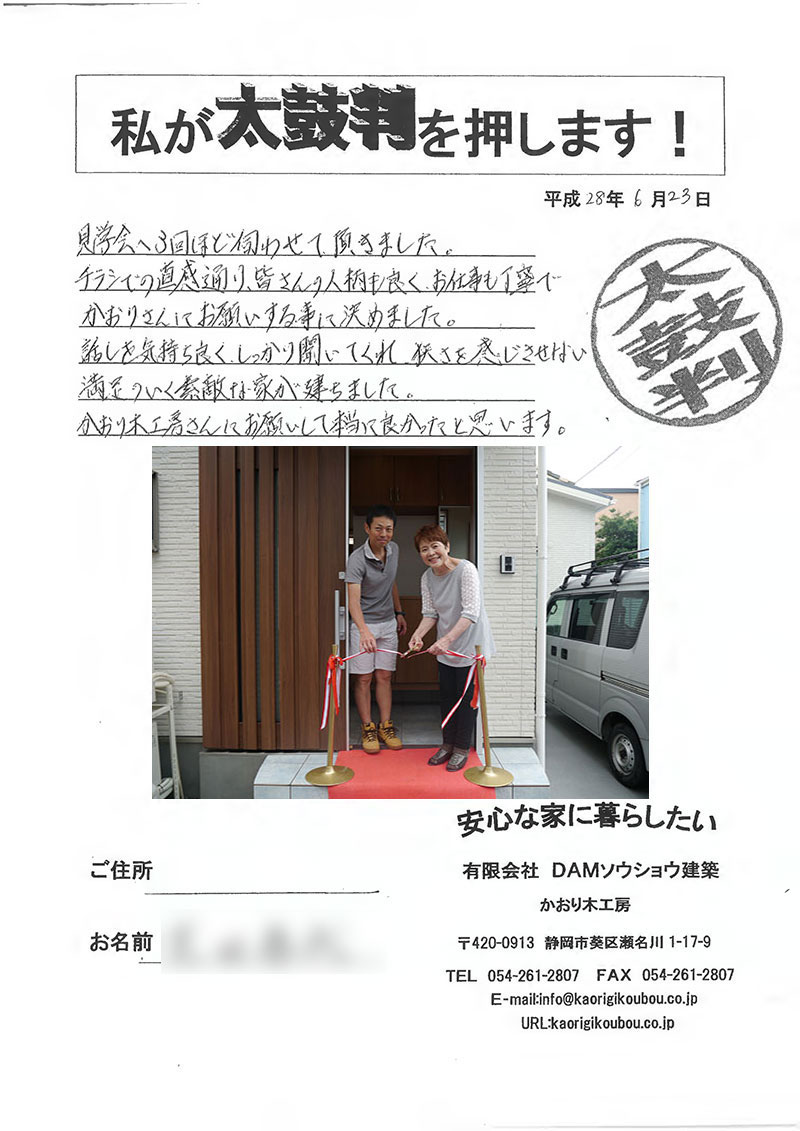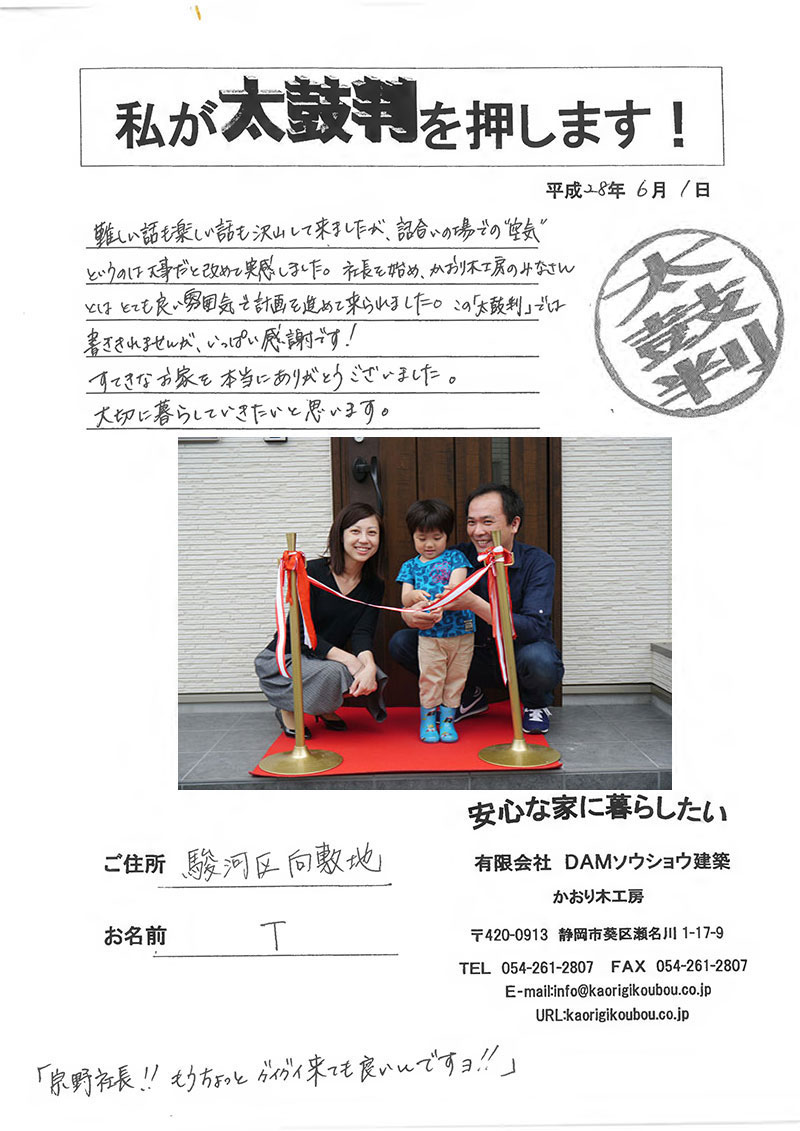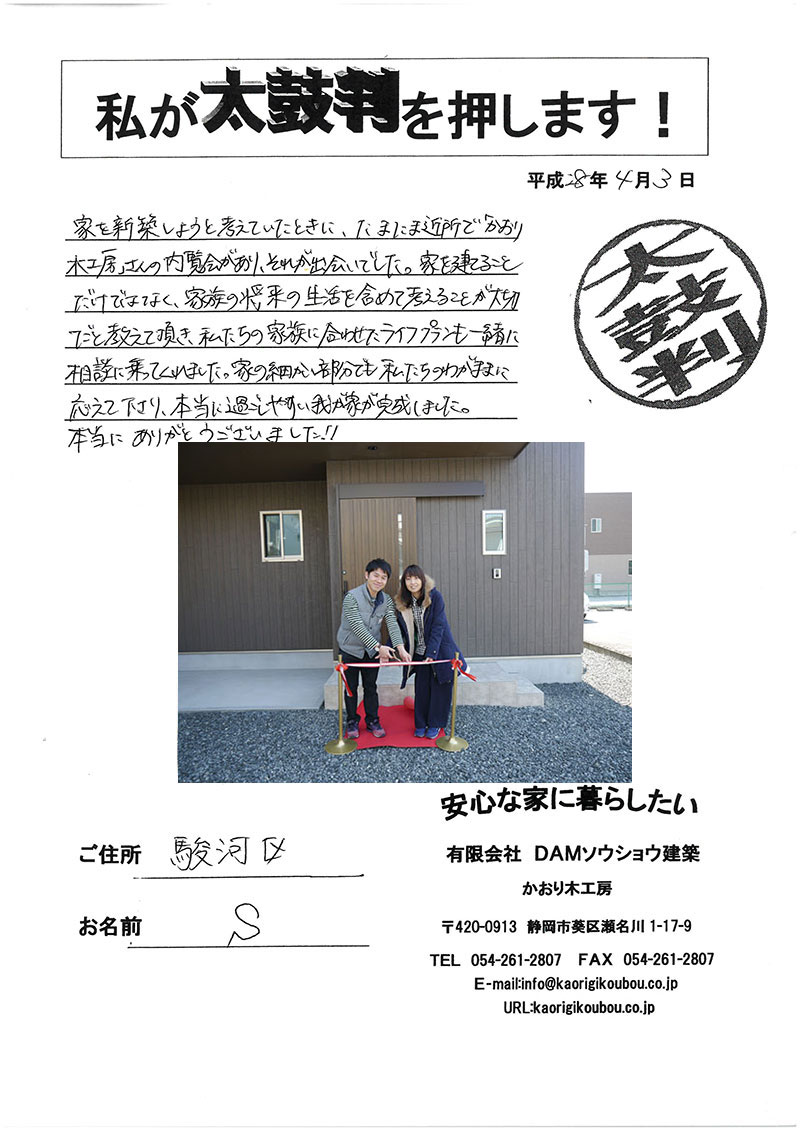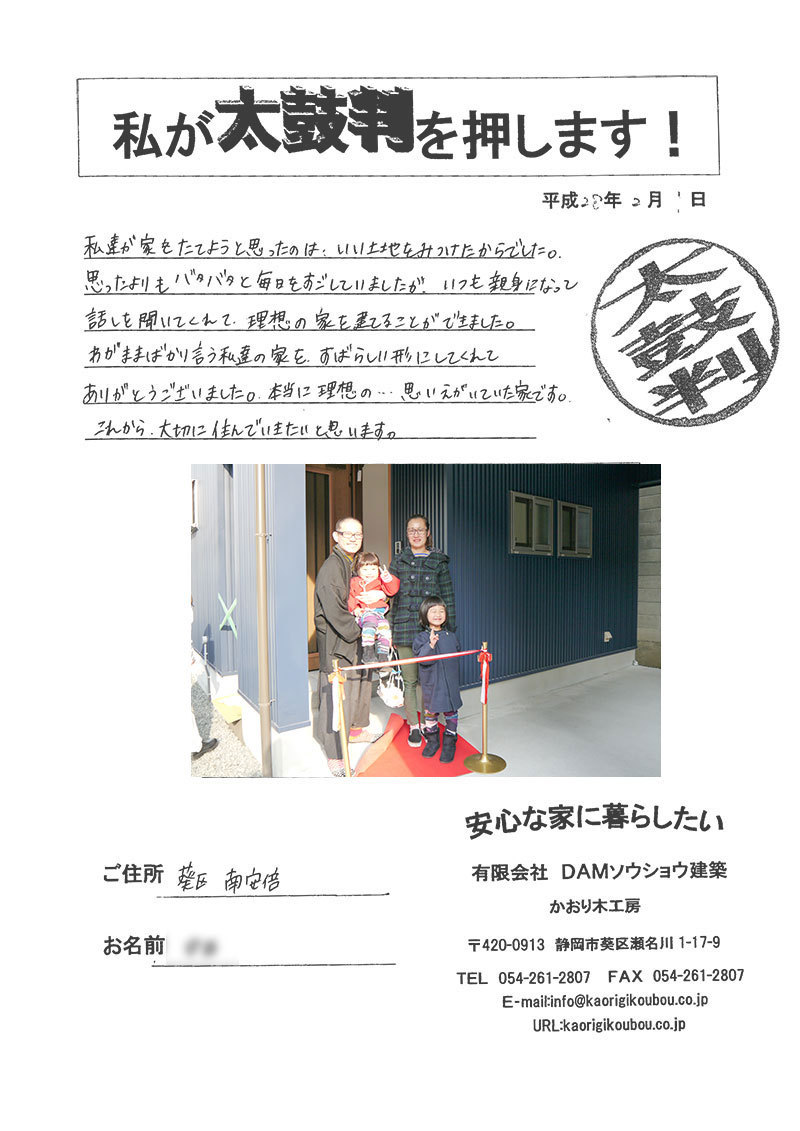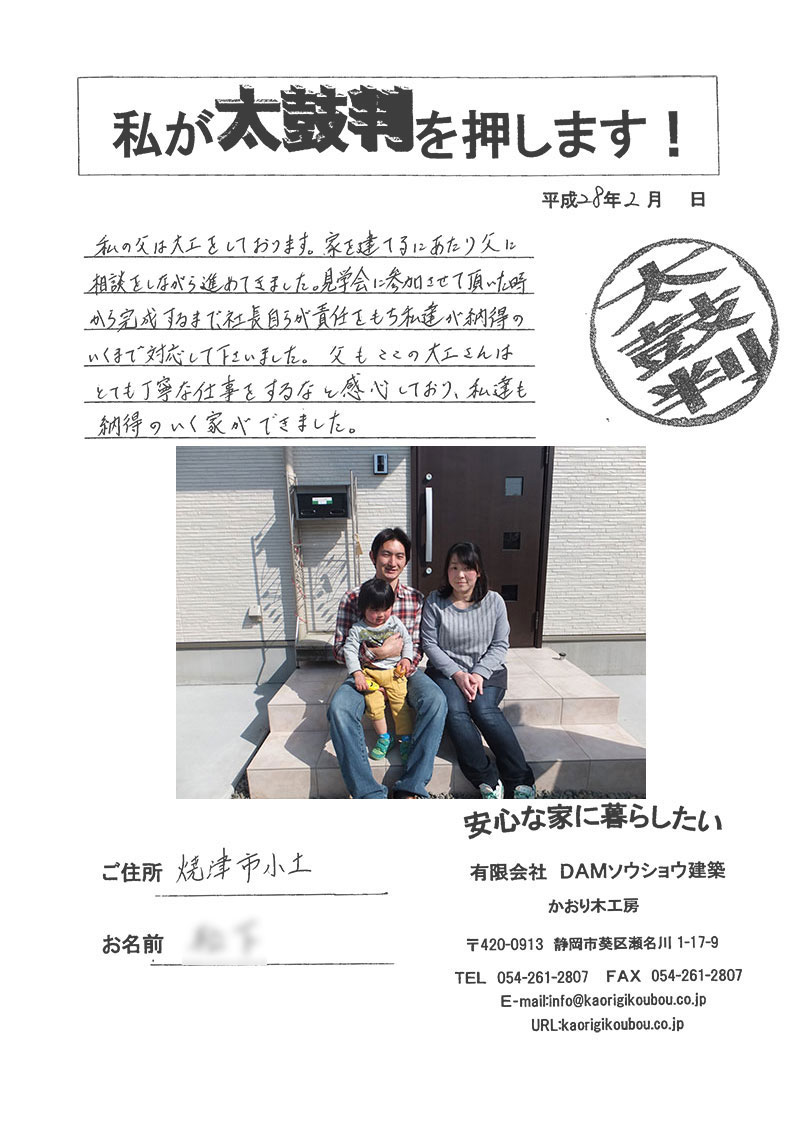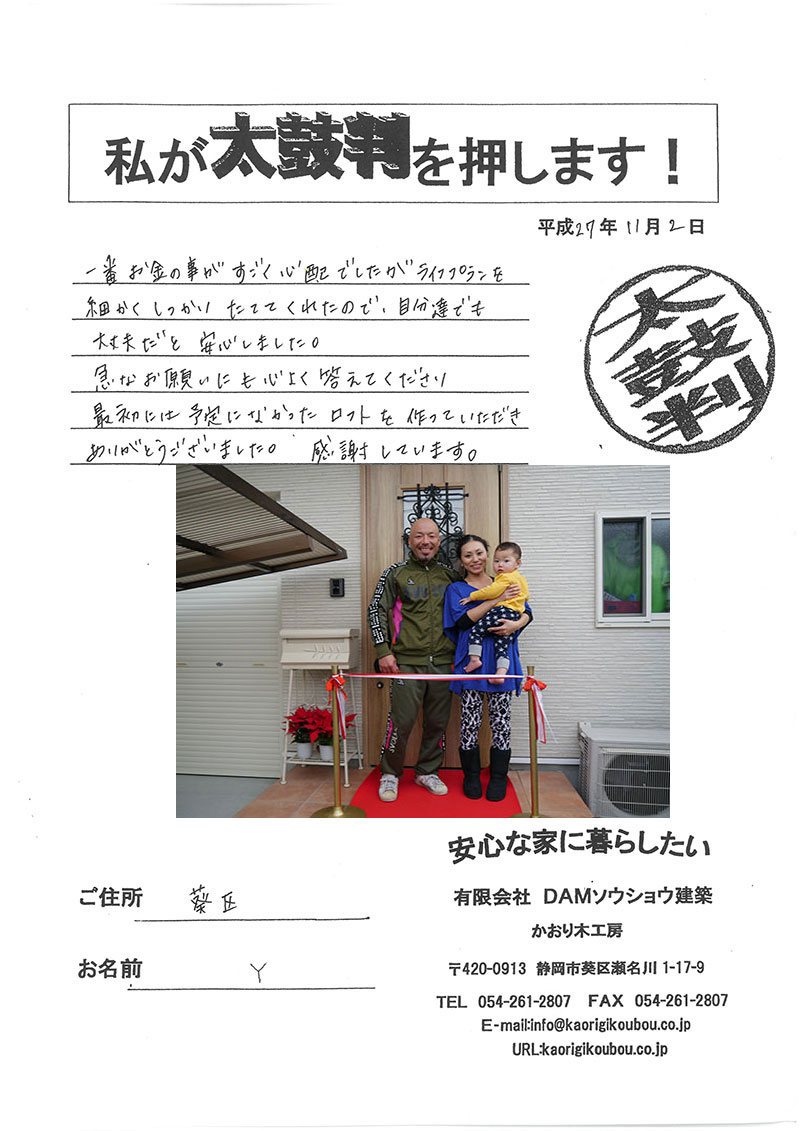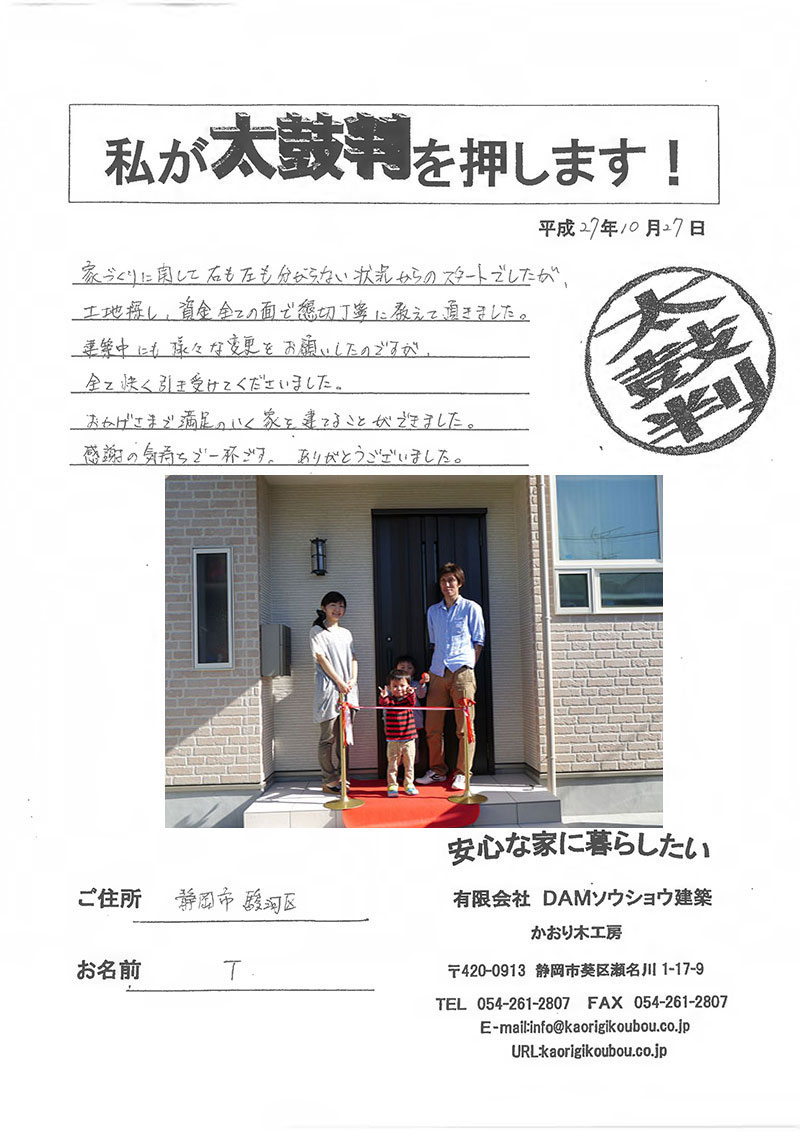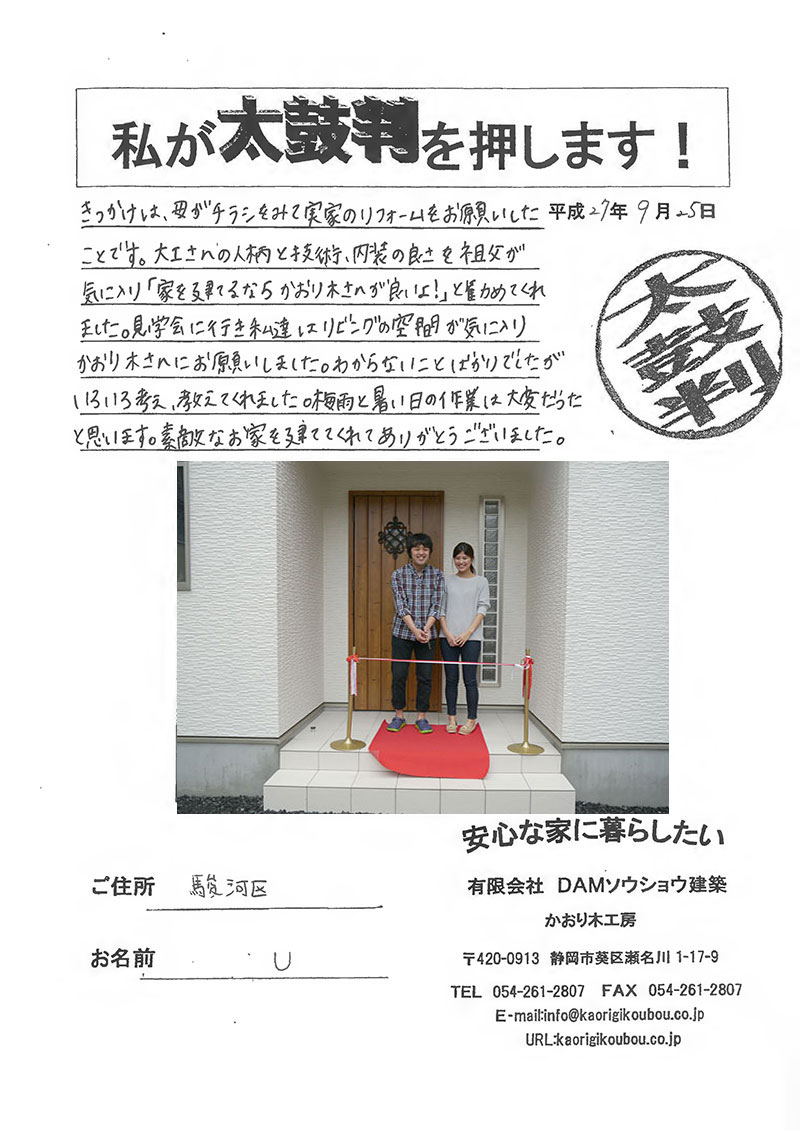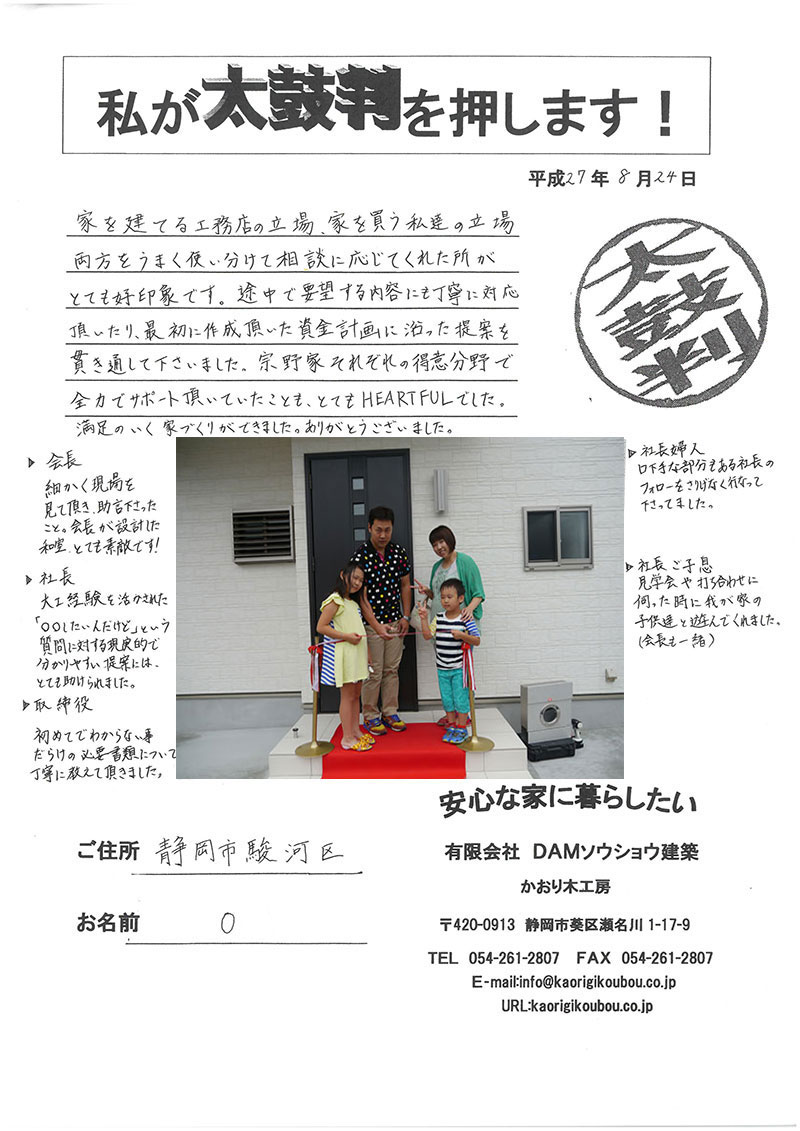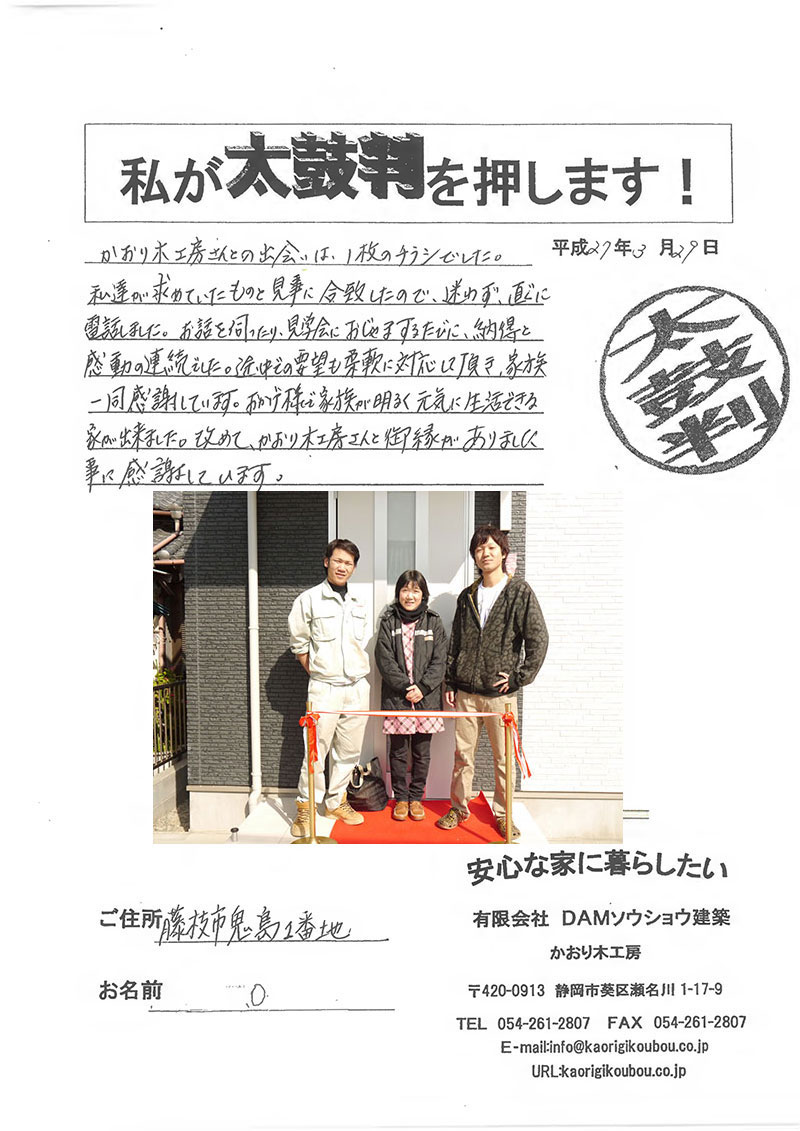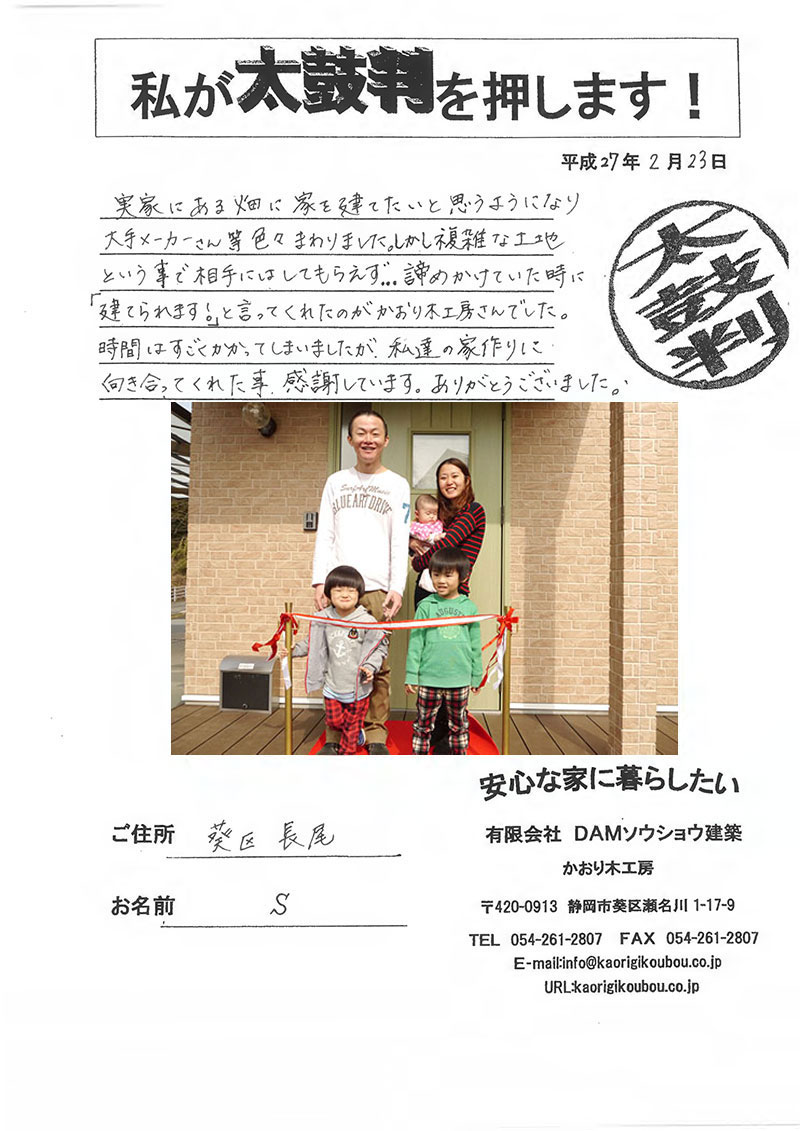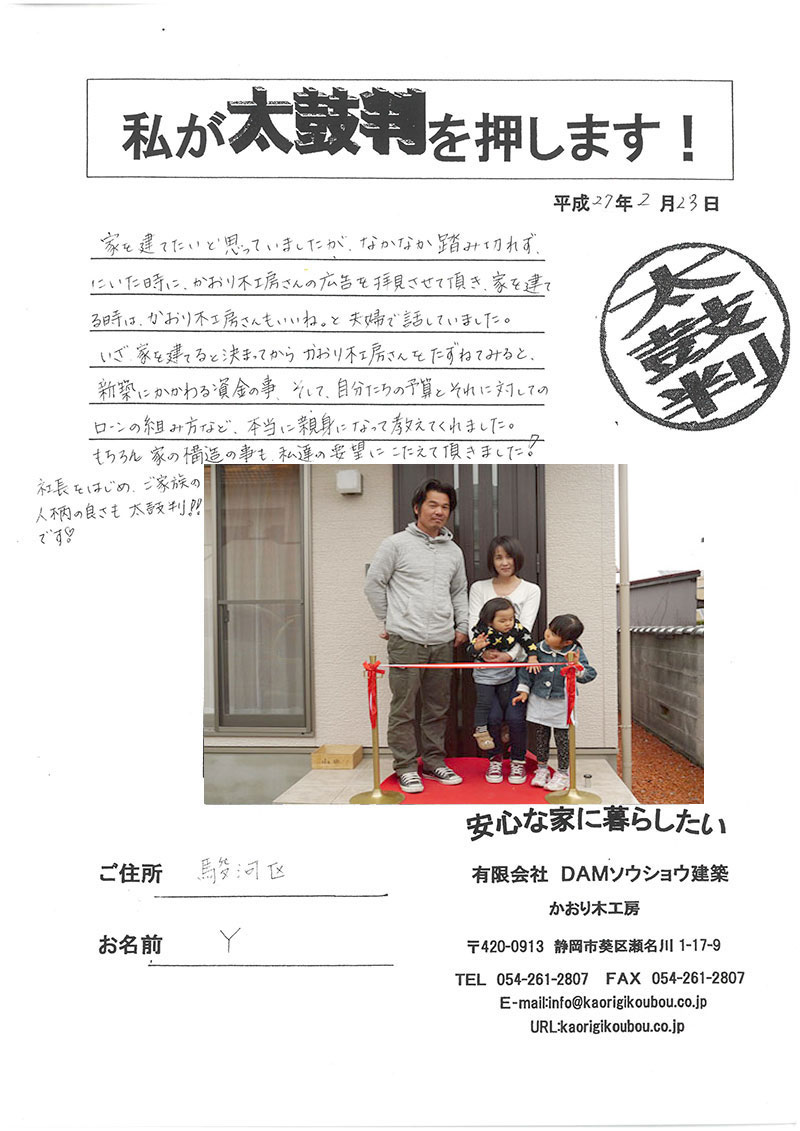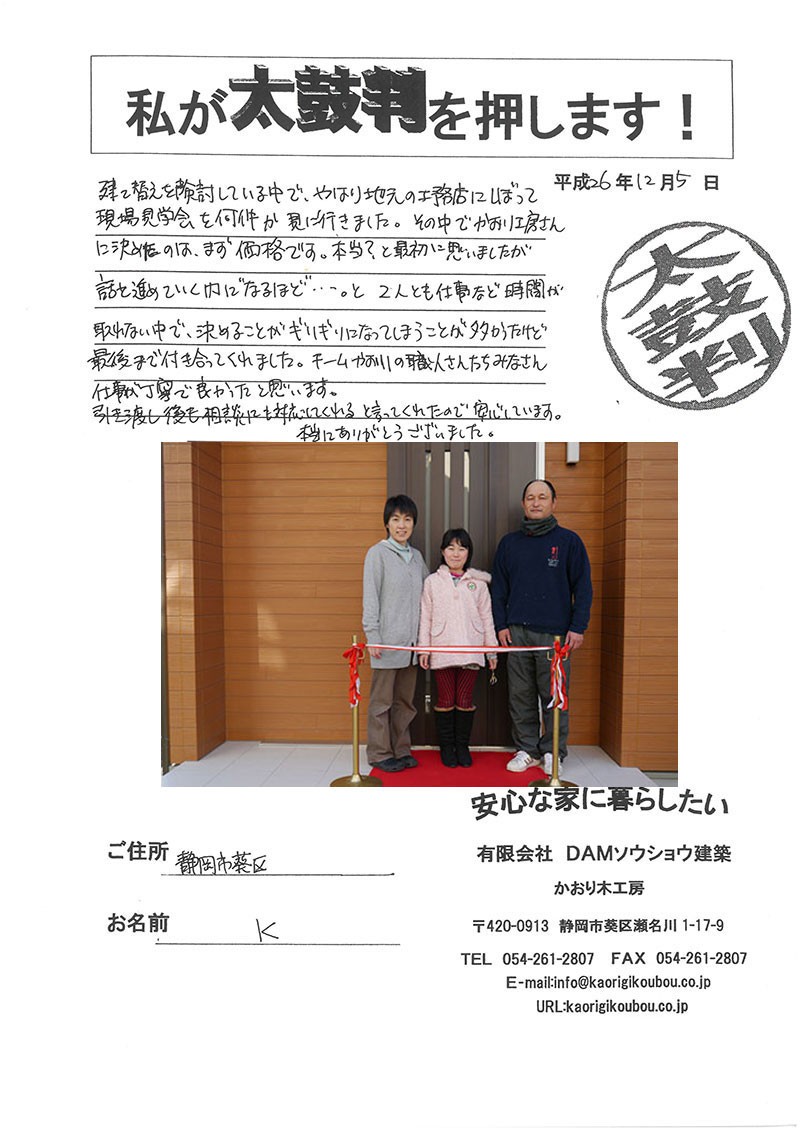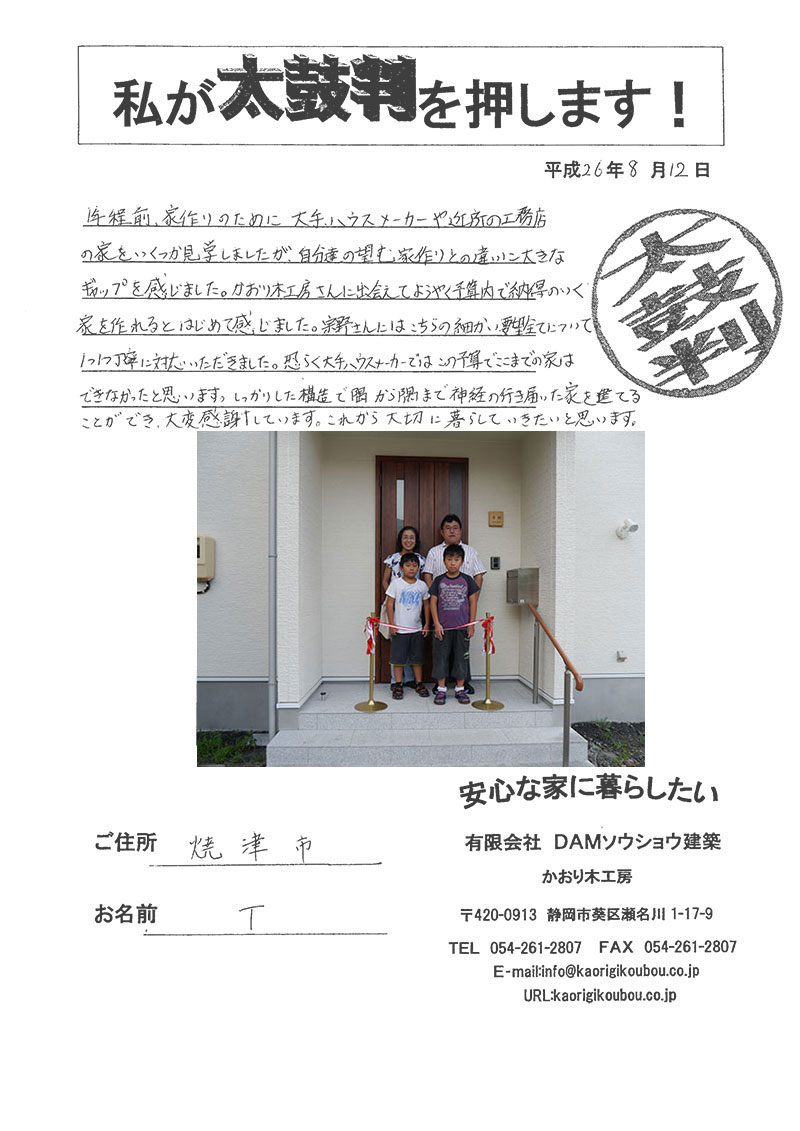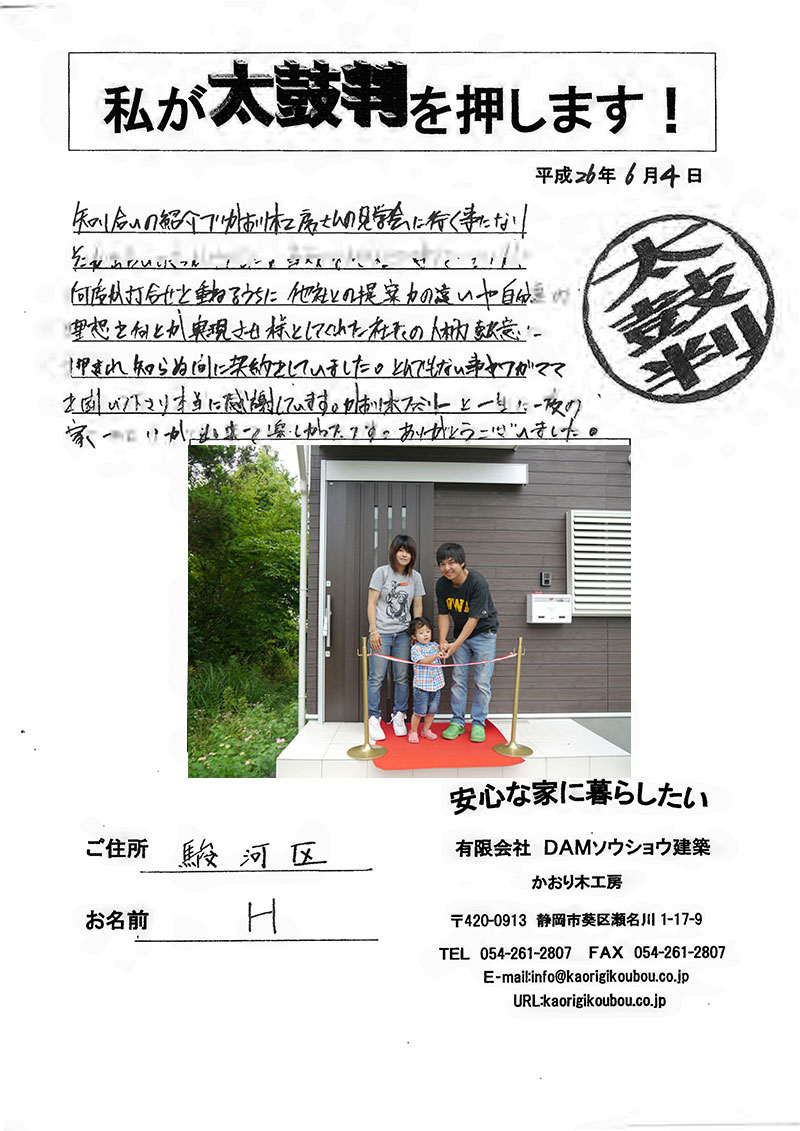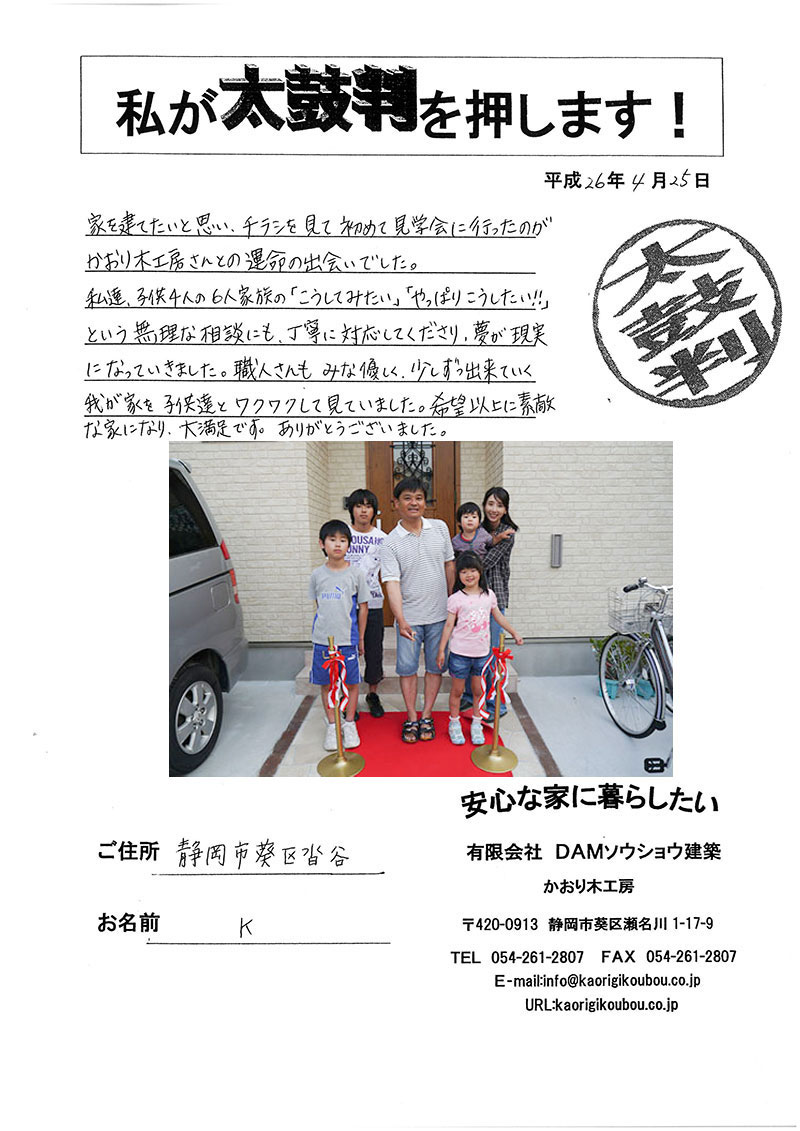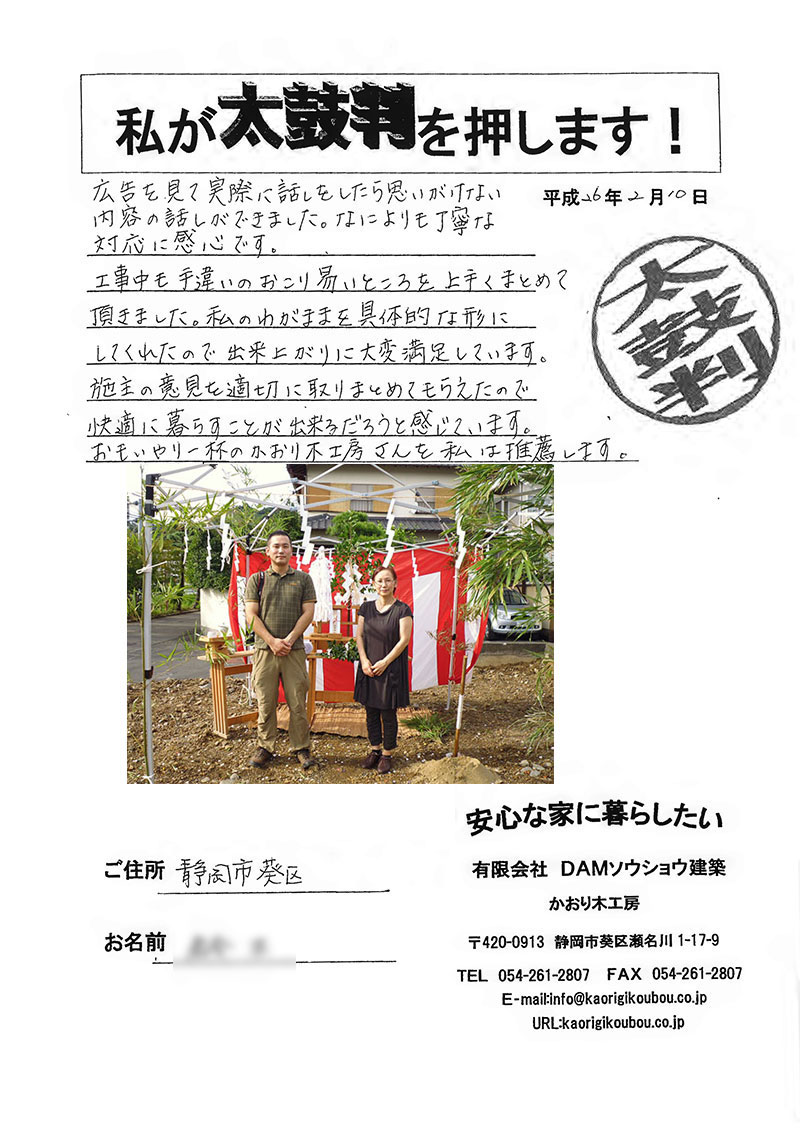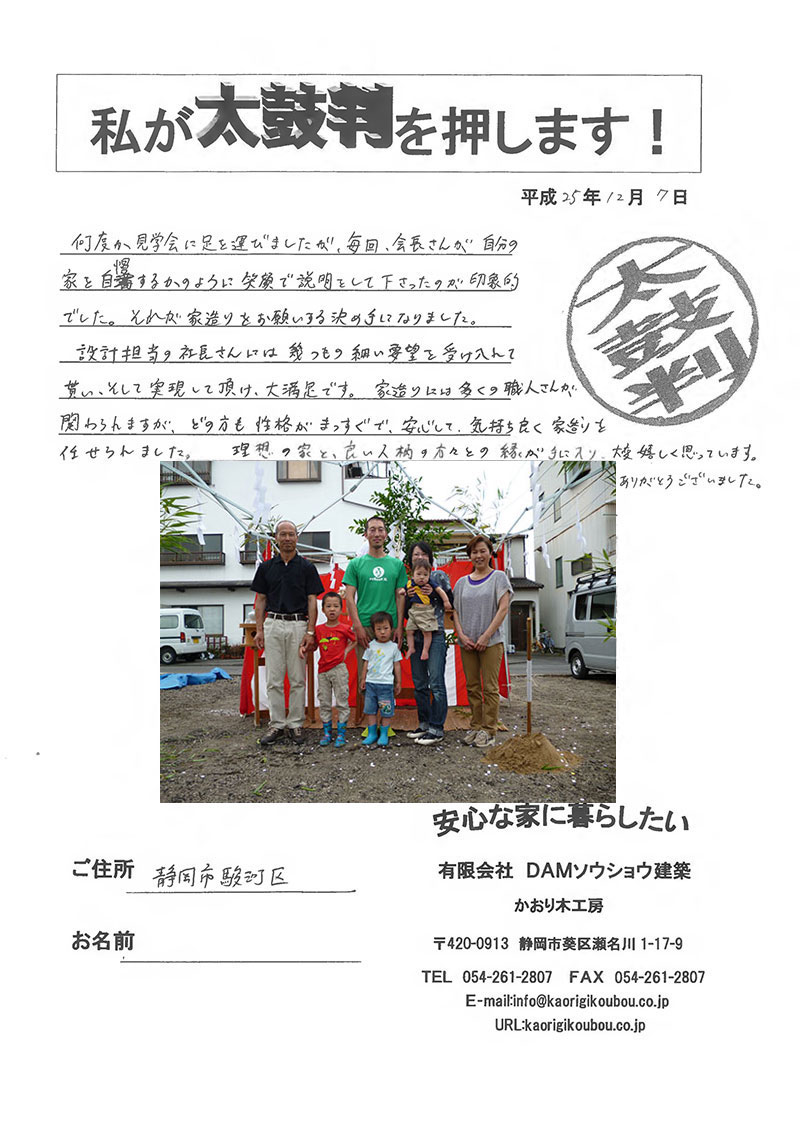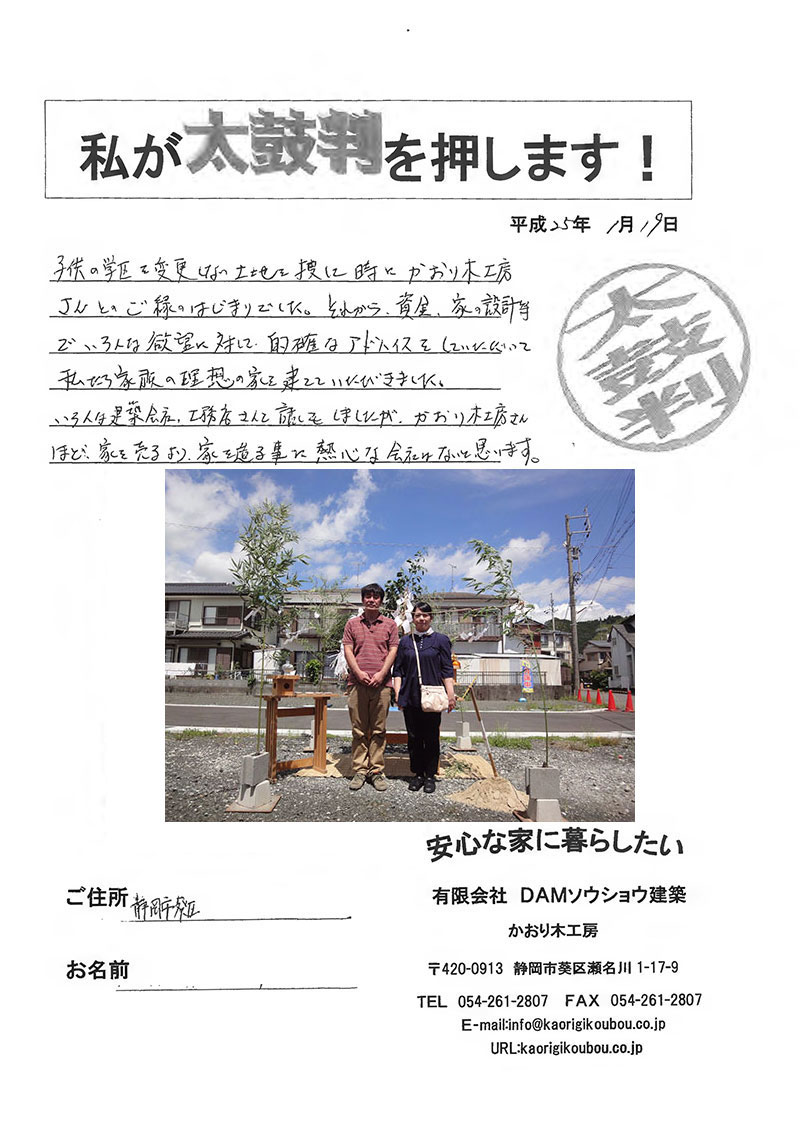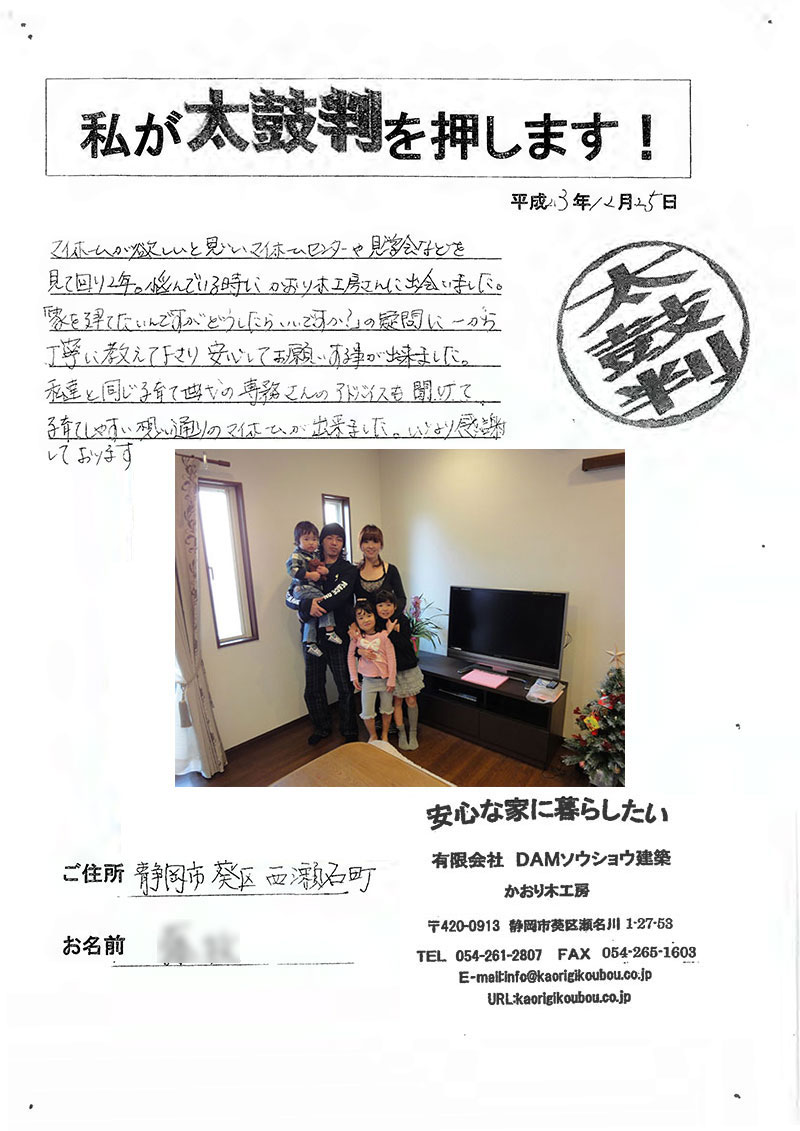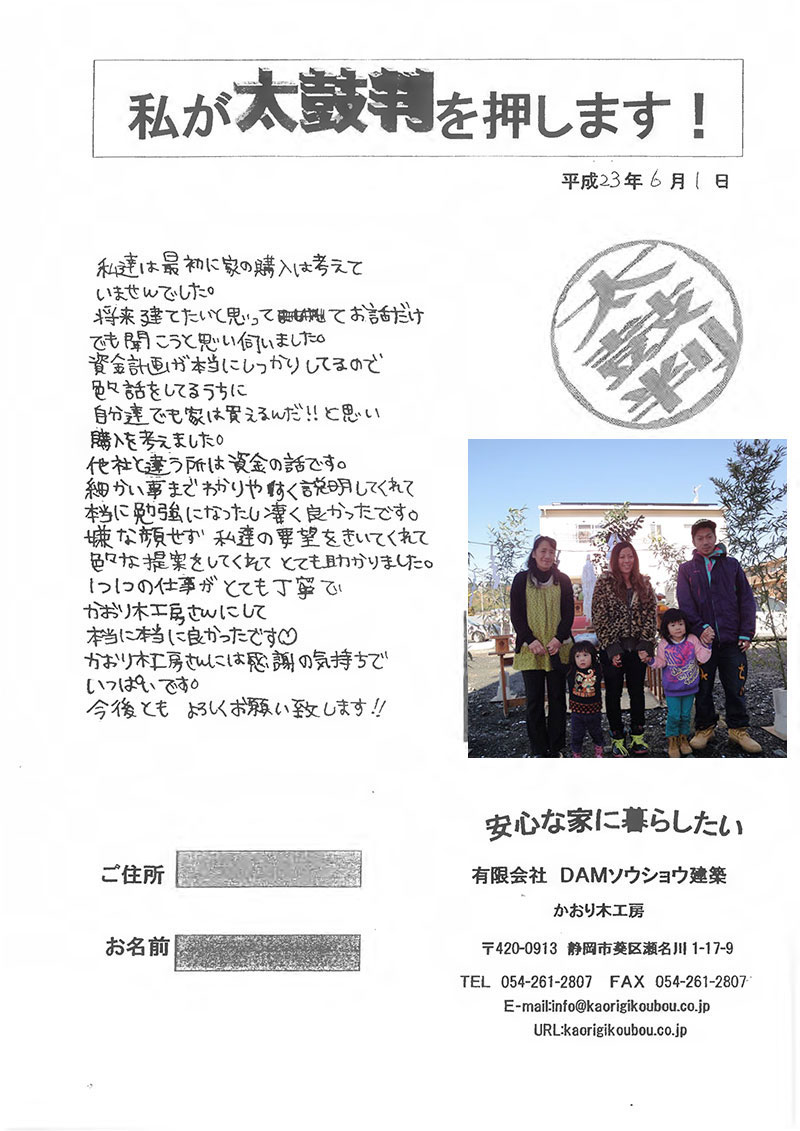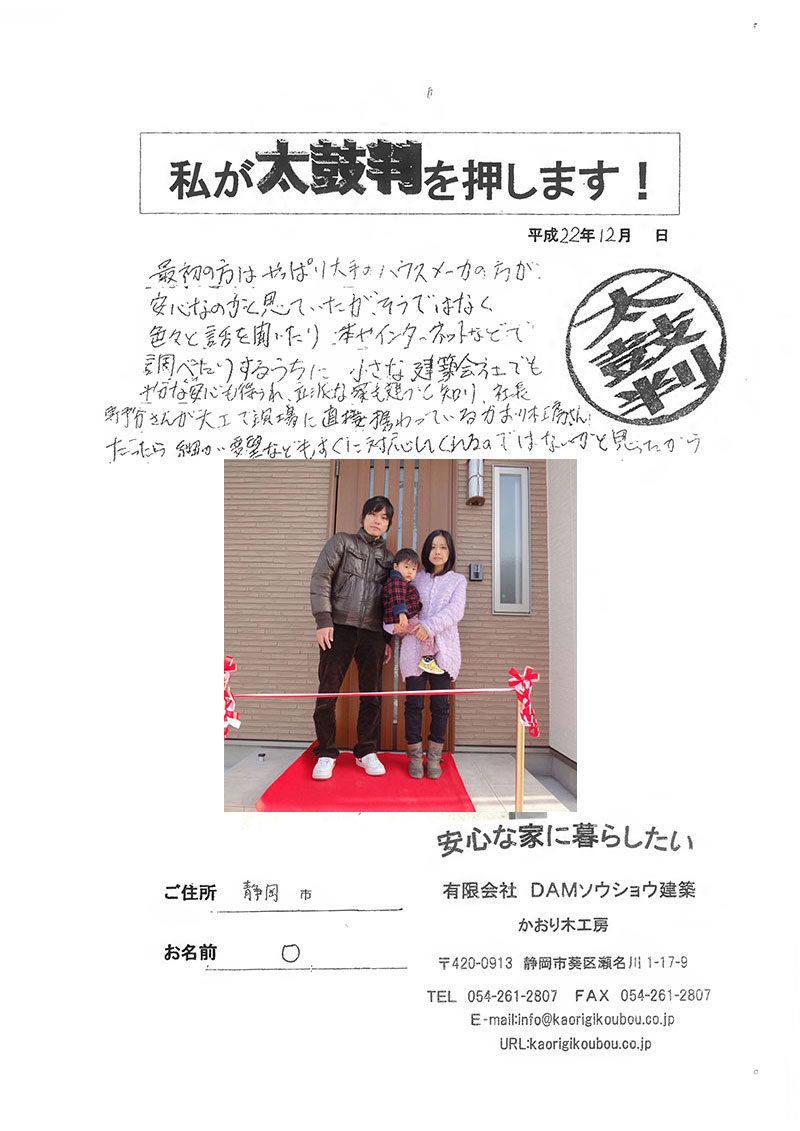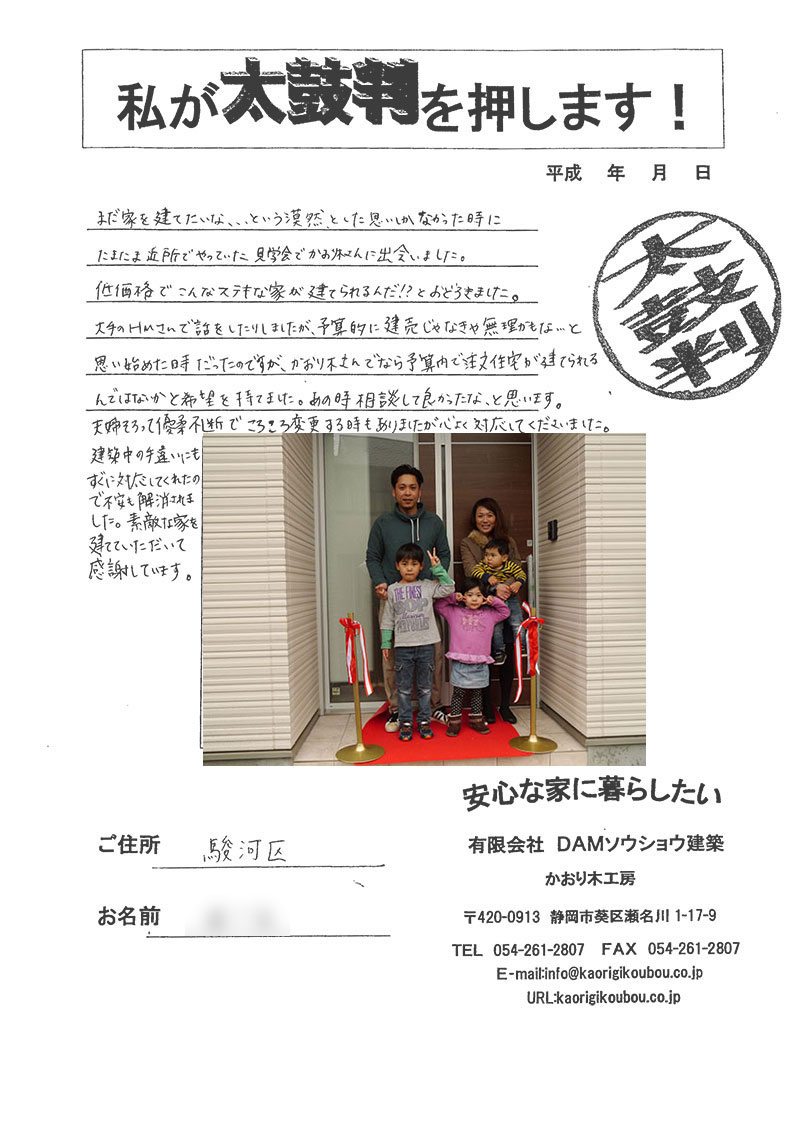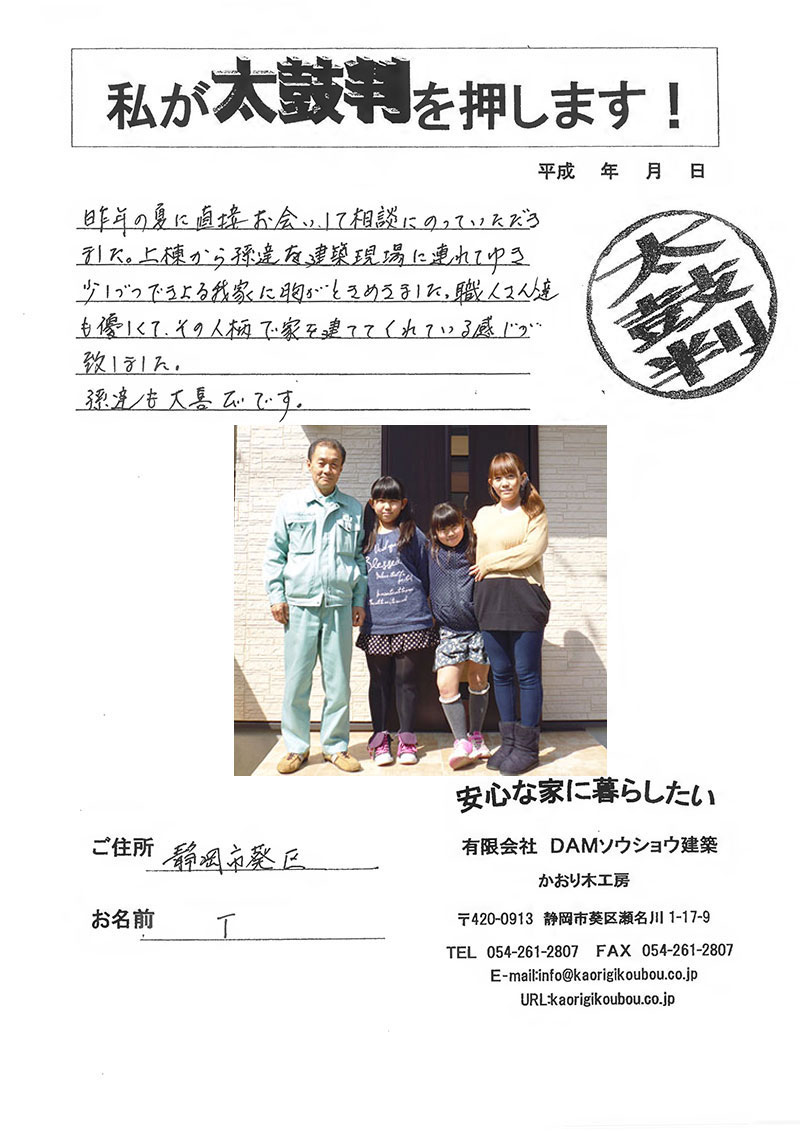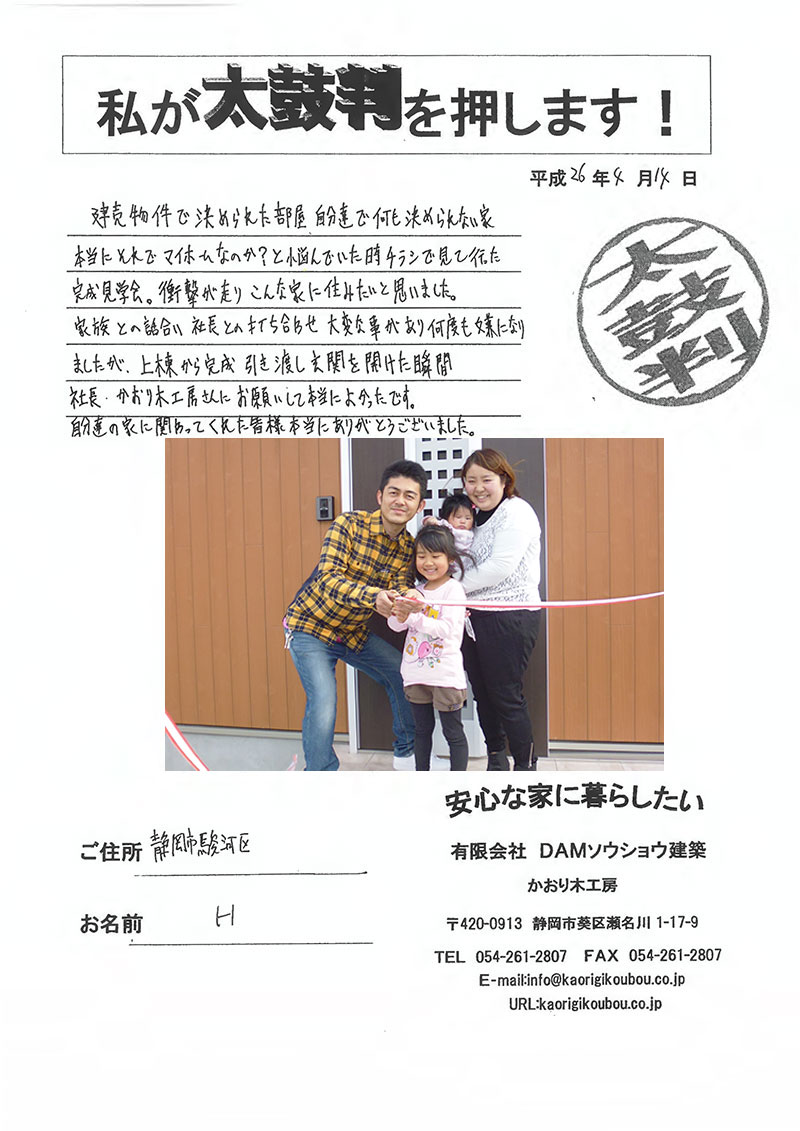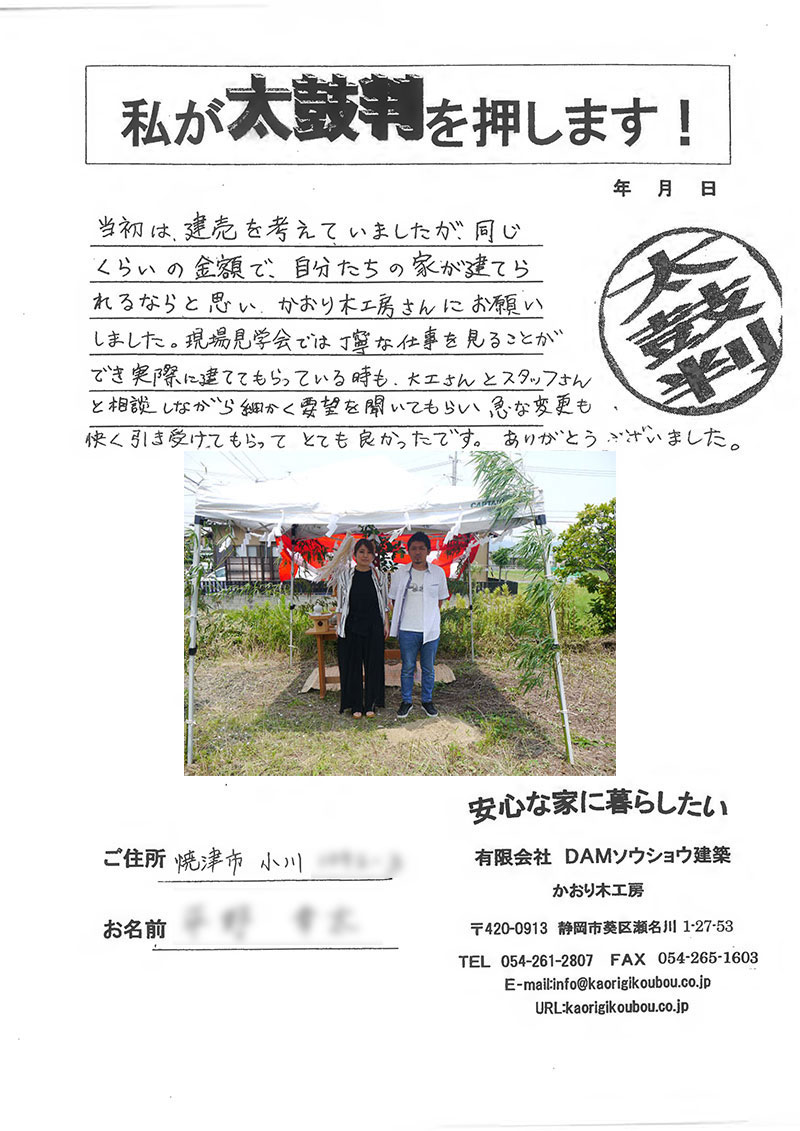【断熱材だけでは防げない】壁内結露を科学的に防ぐための正しい設計とは
こんばんは、かおり木工房の宗野です。
夏の湿気が気になるこの季節、お客様からよくいただく質問の一つにこんなものがあります。
「高性能な断熱材を使っているから結露の心配はないですよね?」
残念ながら、これは大きな誤解です。
本当の結露対策には、「断熱材」だけではなく、「湿気の動線をコントロールする設計」が不可欠なのです。
今回は、ノボパン+コーチパネルという高耐震構造を例に取りながら、構造的に正しい壁内結露対策について解説します。
- 断熱材だけでは結露を防げない理由
高性能グラスウールや吹付ウレタンといった断熱材は、確かに断熱性能は優れています。
しかし、湿気に対する“出口”がない場合、内部に湿気が溜まって結露の原因となります。
建築学会の知見でも、壁内結露の発生要因は断熱性能ではなく、「湿気の出入りの設計ミス」とされています。
- 湿気は「内から外へ」一方向に抜ける設計が基本
湿気対策の原則はシンプルです。
・内側から出た湿気は、外へ逃がす
・外側から入る湿気や雨は、完全に遮断する
つまり、湿気は「通さないことが正義」ではなく、「通す方向と場所を意図的に設計すること」が正解なのです。
- ノボパン+コーチパネル構成の長所と注意点
かおり木工房では、耐震性に優れた「ノボパン+コーチパネル構成」を採用しています。
・ノボパン:高い壁倍率と寸法安定性。ただし透湿抵抗は高く、湿気を通しにくい
・コーチパネル:断熱と構造を一体化した高性能パネル。気密性は高いが、透湿性は低い
この構成は、正しく設計されれば「湿気を通しにくい=外部からの湿気を遮断」できる強みがありますが、設計を間違えると内部湿気が抜けなくなるリスクもあります。
- 可変透湿シートが“湿気の出口”をコントロールする
その出口の役割を果たすのが、調湿型の可変透湿気密シートです。
・冬:室内の湿気が壁に入らないよう“湿気を通しにくく”
・夏:壁内に溜まった湿気を“外へ逃がしやすく”
この“賢い膜”が、季節によって呼吸するように壁内環境を整えてくれます。
- 外部通気層の役割──“逃げ道”があるかどうか
湿気が外に出るには、もうひとつの条件が必要です。
それが、外装材の裏に設ける「通気層」です。
・通気層によって壁の裏で空気が流れ、湿気が自然に排出される
・湿気が抜ける“出口”として働く
かおり木工房では、すべての住宅にこの通気層を設けており、壁内の空気が“滞らない構造”を実現しています。
- 材質選びは「通すかどうか」よりも「流れの設計」が重要
透湿性のある素材を使えば良いという話ではありません。
大事なのは、
・湿気がどこから入るのか?
・どこへ抜ける設計なのか?
・妨げとなる材が途中にないか?
という「湿気の流れ」を建物全体で制御しているかどうかです。
- かおり木工房の壁構成(湿気対策仕様)
構成要素:室内側
採用材・方法:調湿可変透湿シート
機能:室内湿気を制御
構成要素:断熱材
採用材・方法:高性能グラスウール20K
機能:吸放湿性と断熱性
構成要素:構造壁
採用材・方法:ノボパン+コーチパネル
機能:耐震性+気密性(湿気は通さない)
構成要素:外装裏面
採用材・方法:通気胴縁
機能:湿気を逃がす通気構造
構成要素:換気
採用材・方法:松尾式全館空調+第1種換気
機能:室内湿度を快適に管理
このように、内部からの湿気は外へ一方向で抜け、外部からの湿気は入らない構造が実現しています。
- 結論:「断熱材+設計思想」で結露ゼロを実現
結露は“目に見えない敵”ですが、住宅性能にとって致命的なリスクです。
断熱材だけで判断せず、
湿気の動線を建築物理に基づいて設計することが、真の「結露ゼロ住宅」につながります。
見えないところにこそ、本物のこだわりを。
それが、私たちかおり木工房の家づくりです。
それでは、また。
かおり木工房SNSでは、為になる情報を発信していますので、ぜひ見てみてください。
LINE、Instagram、TikTok、YouTube、友達追加、フォローお願いします!
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCV2CLl-P_j80GPTuVRLMXpQ
Instagram:
https://www.instagram.com/kaorigikoubou/