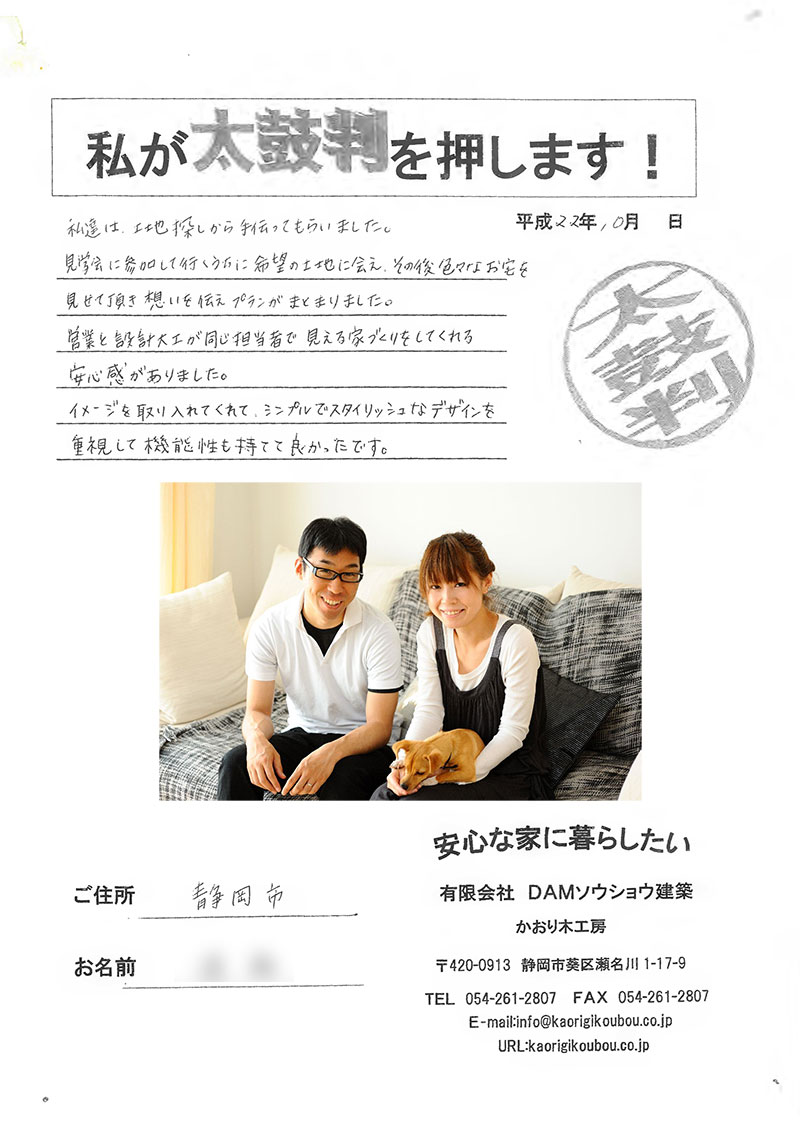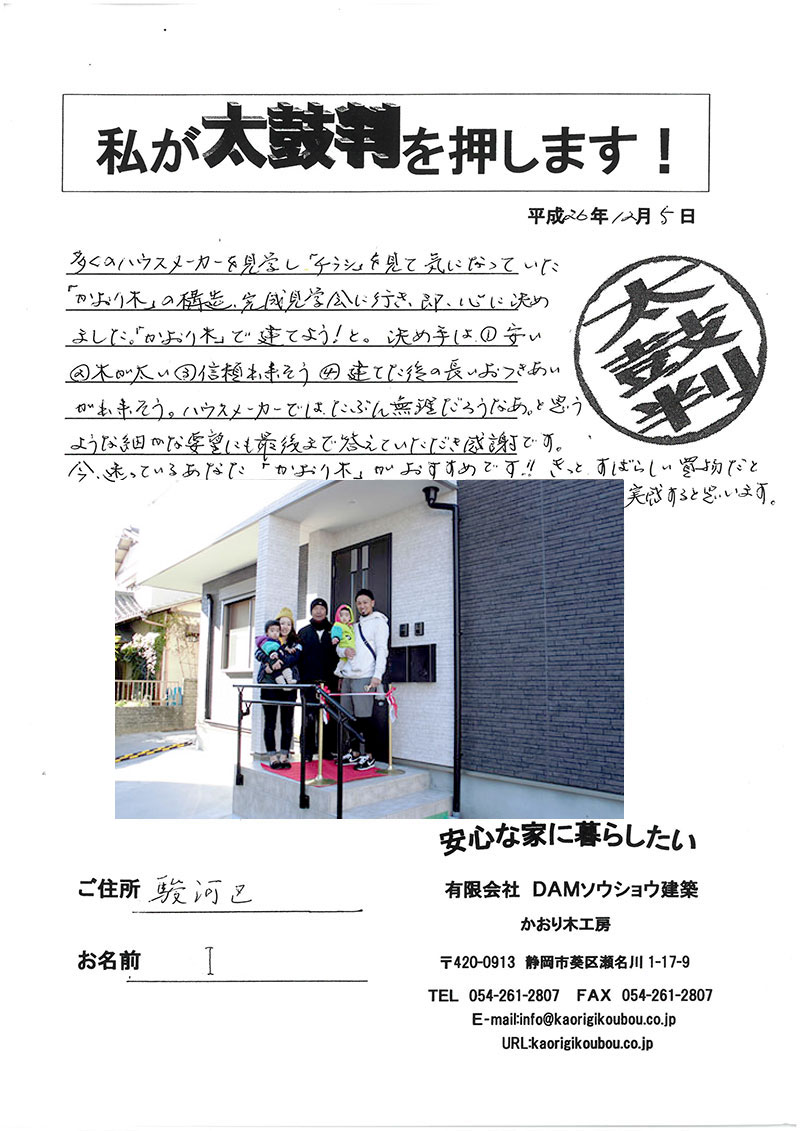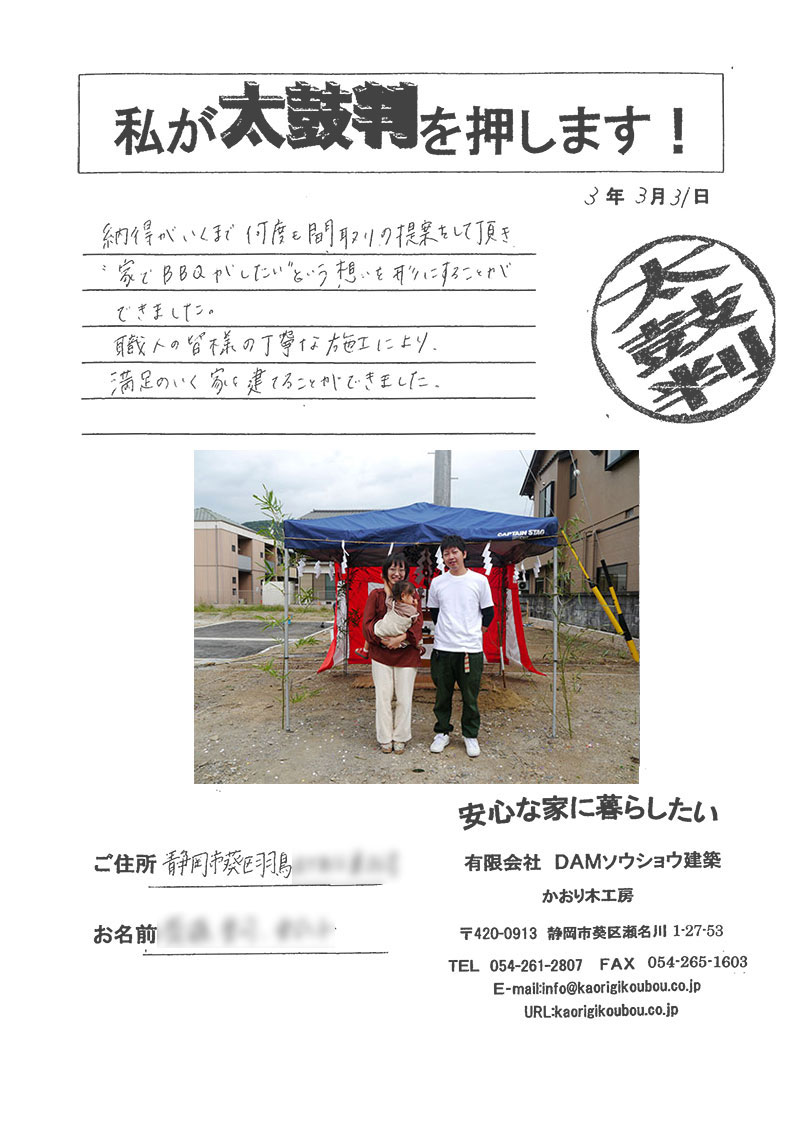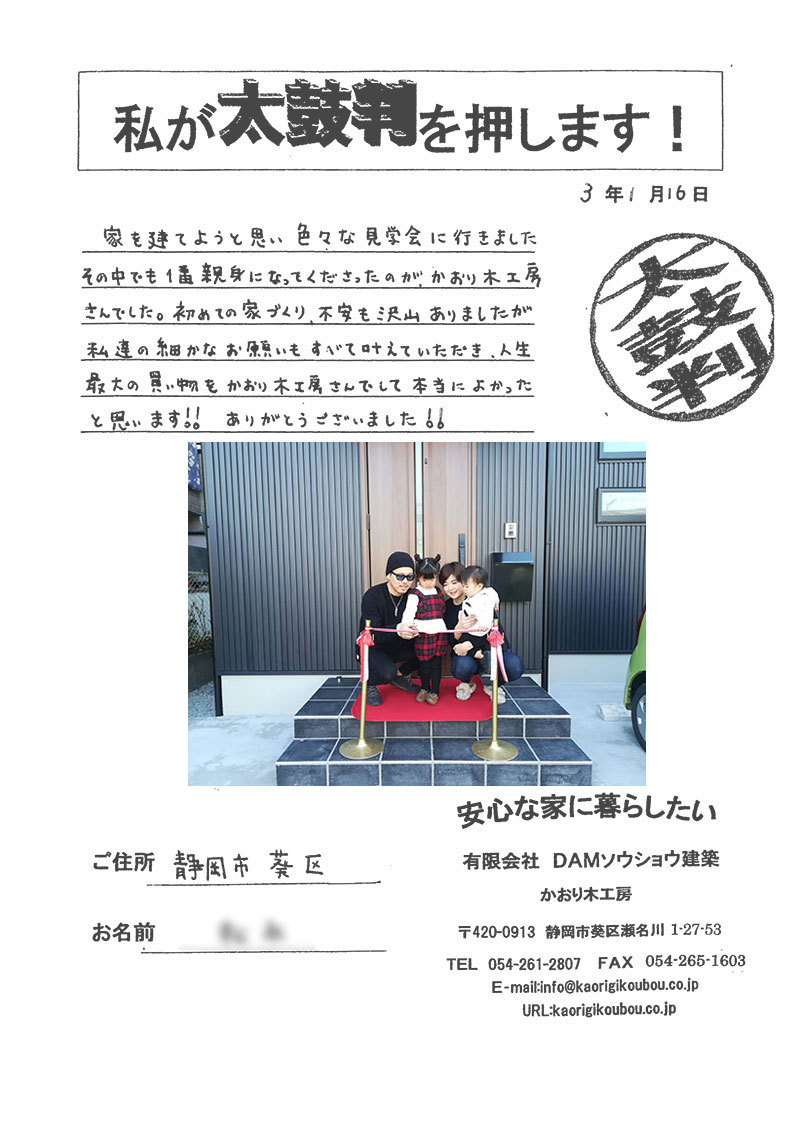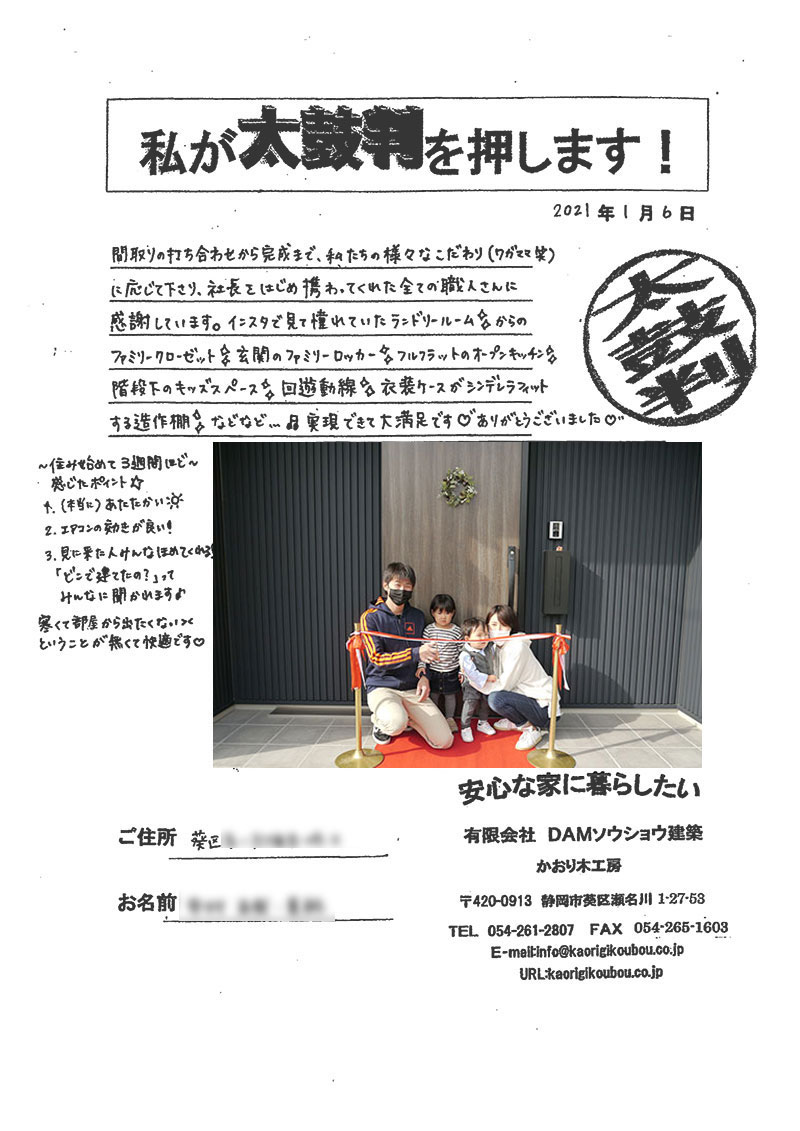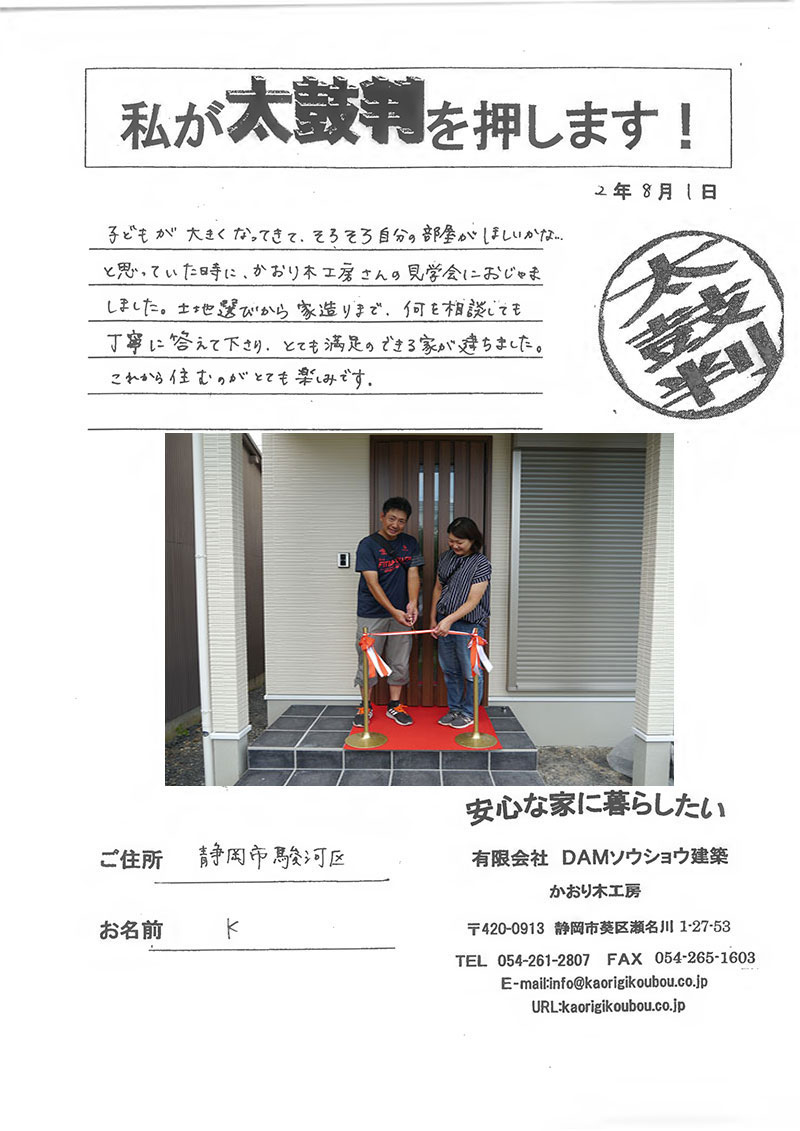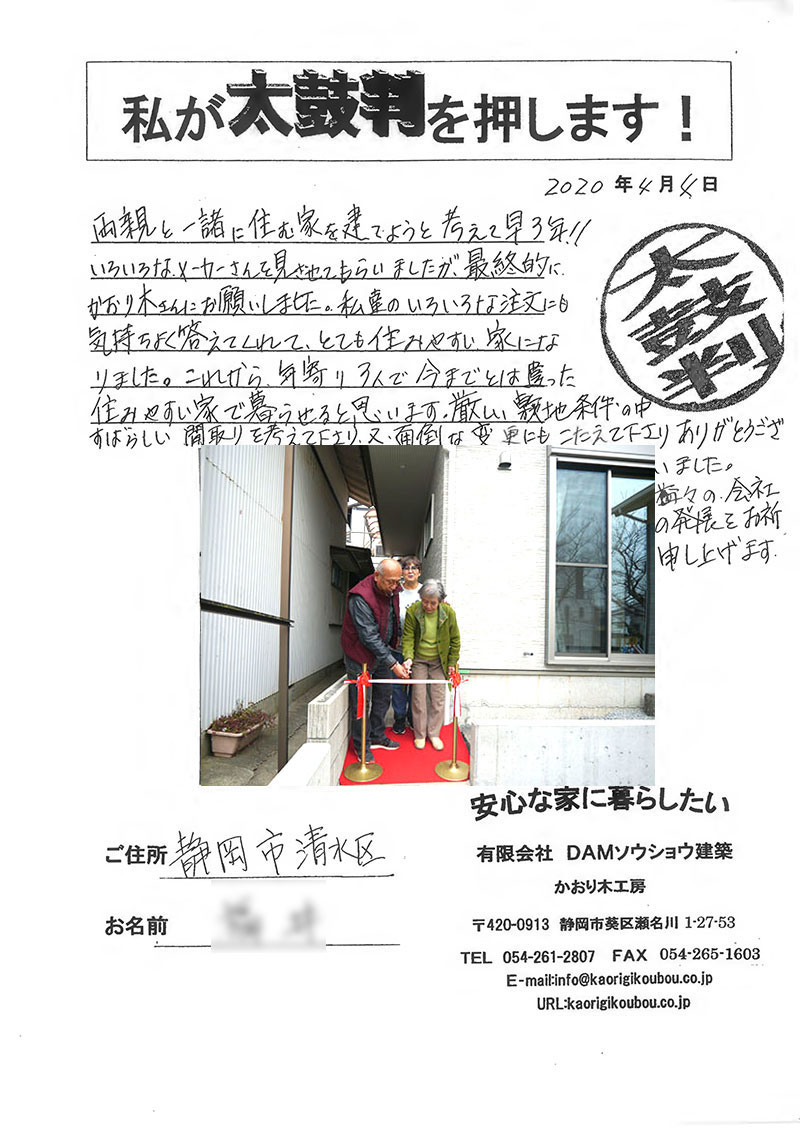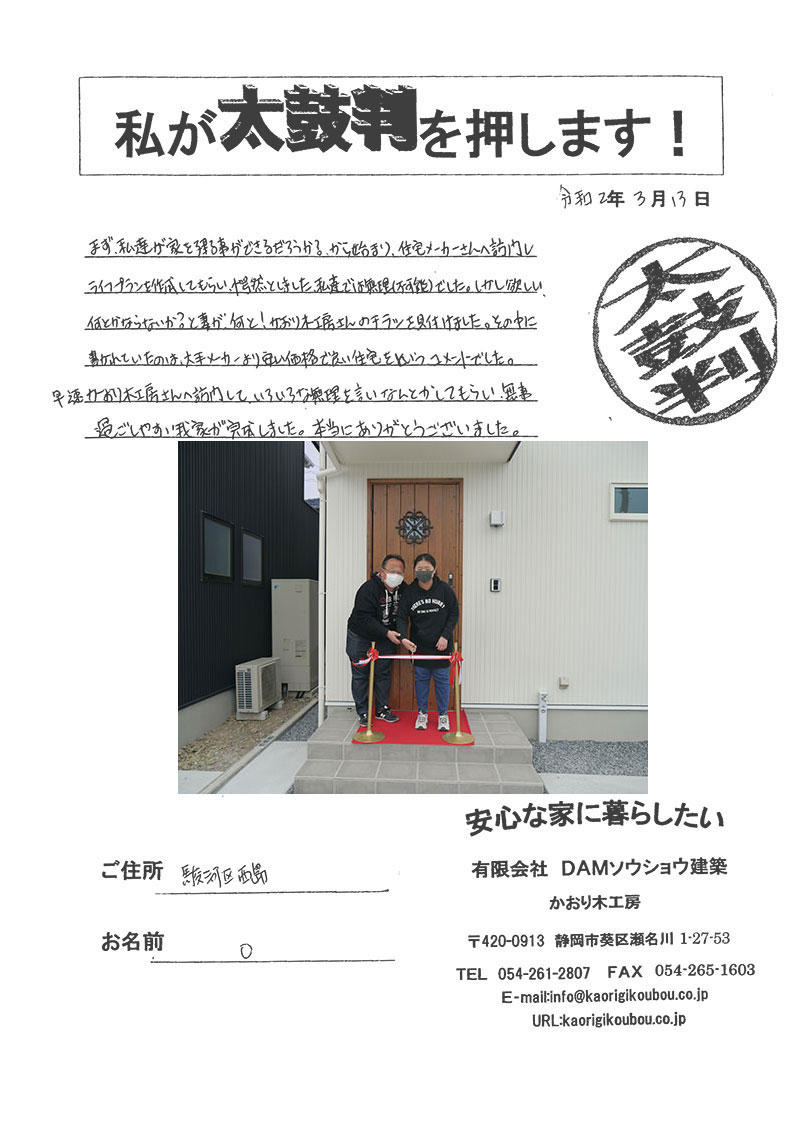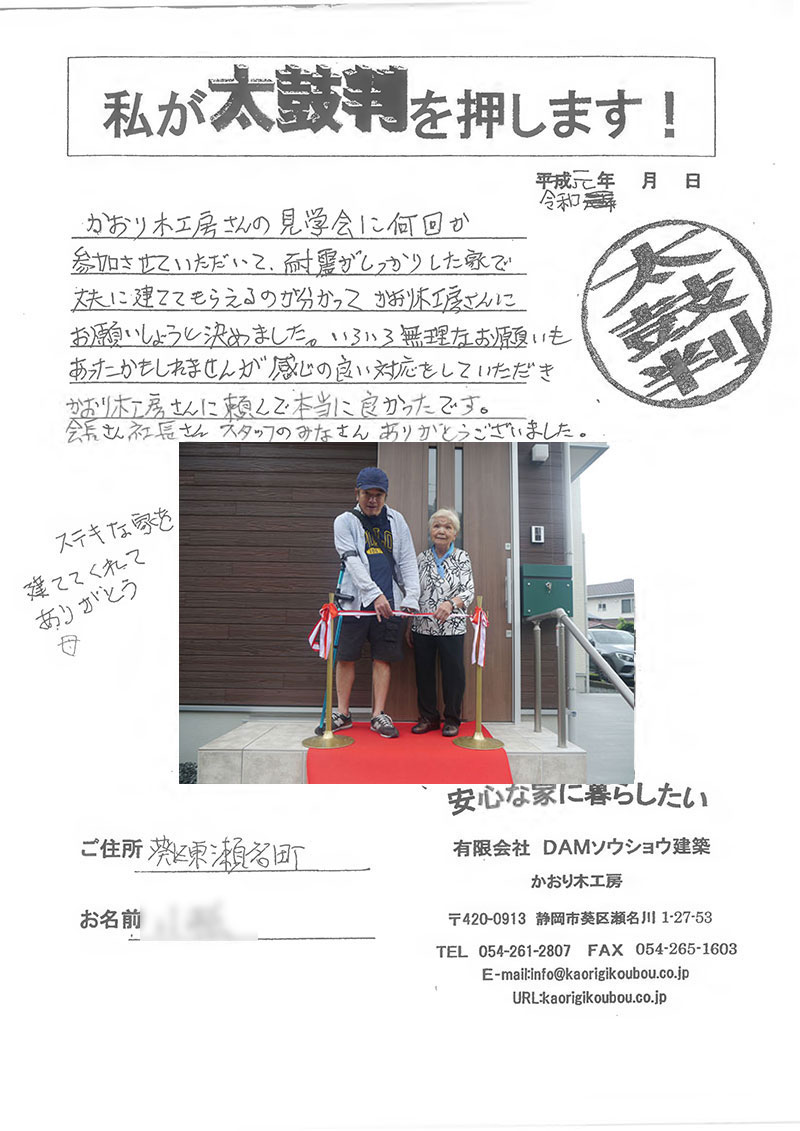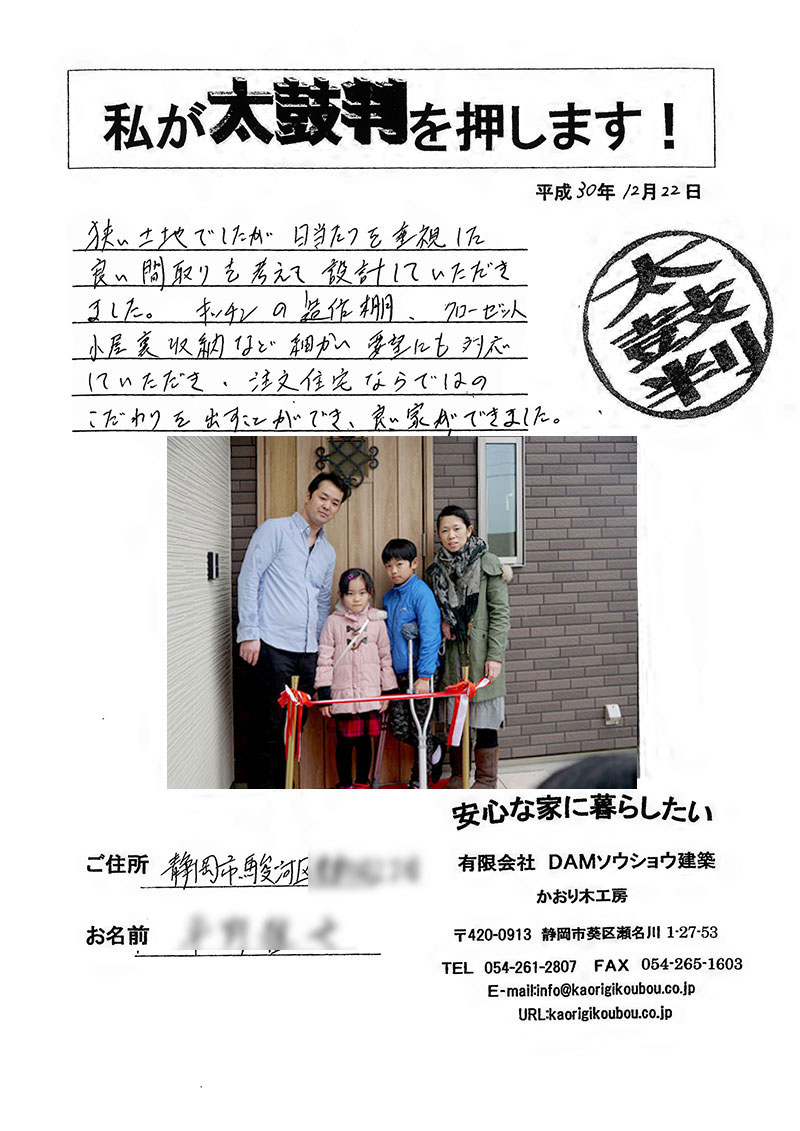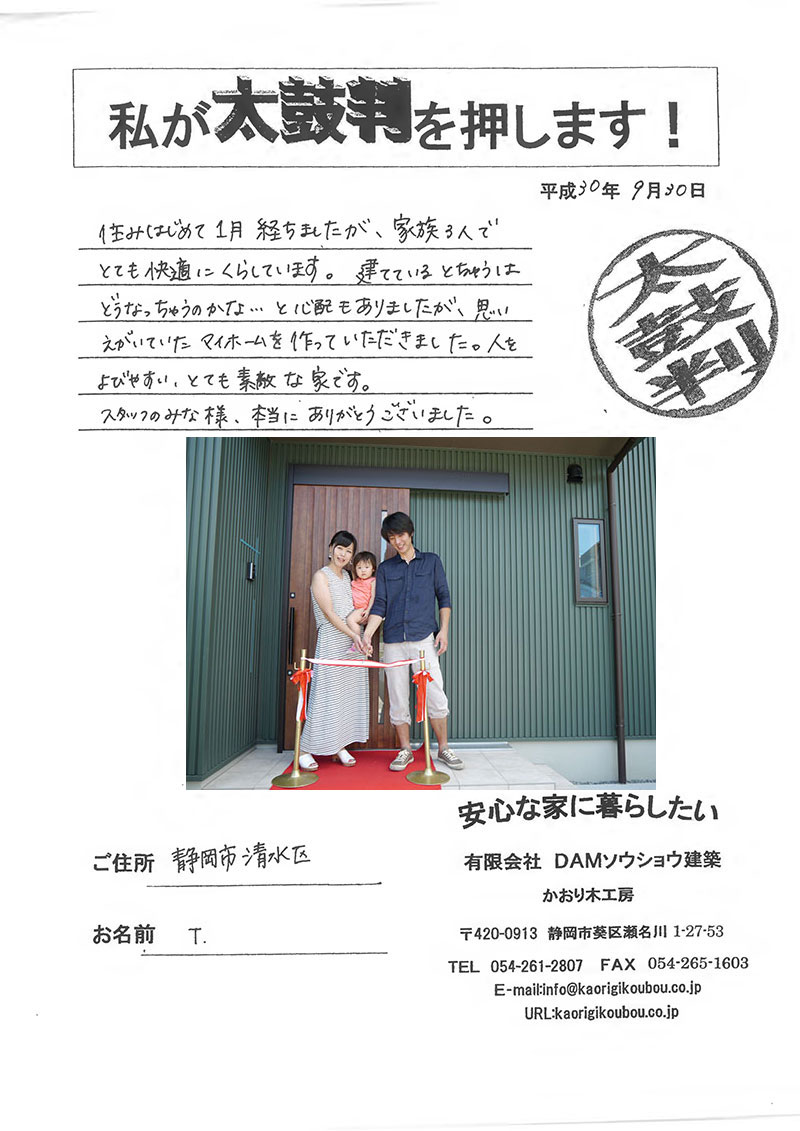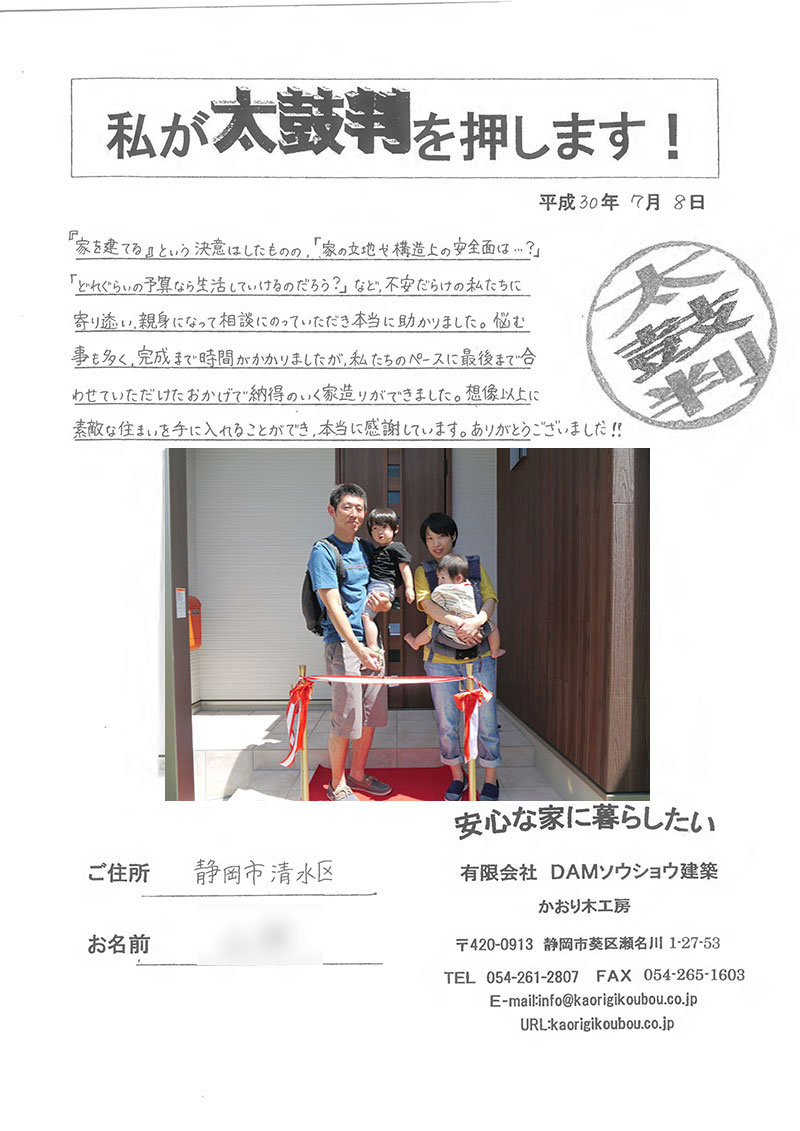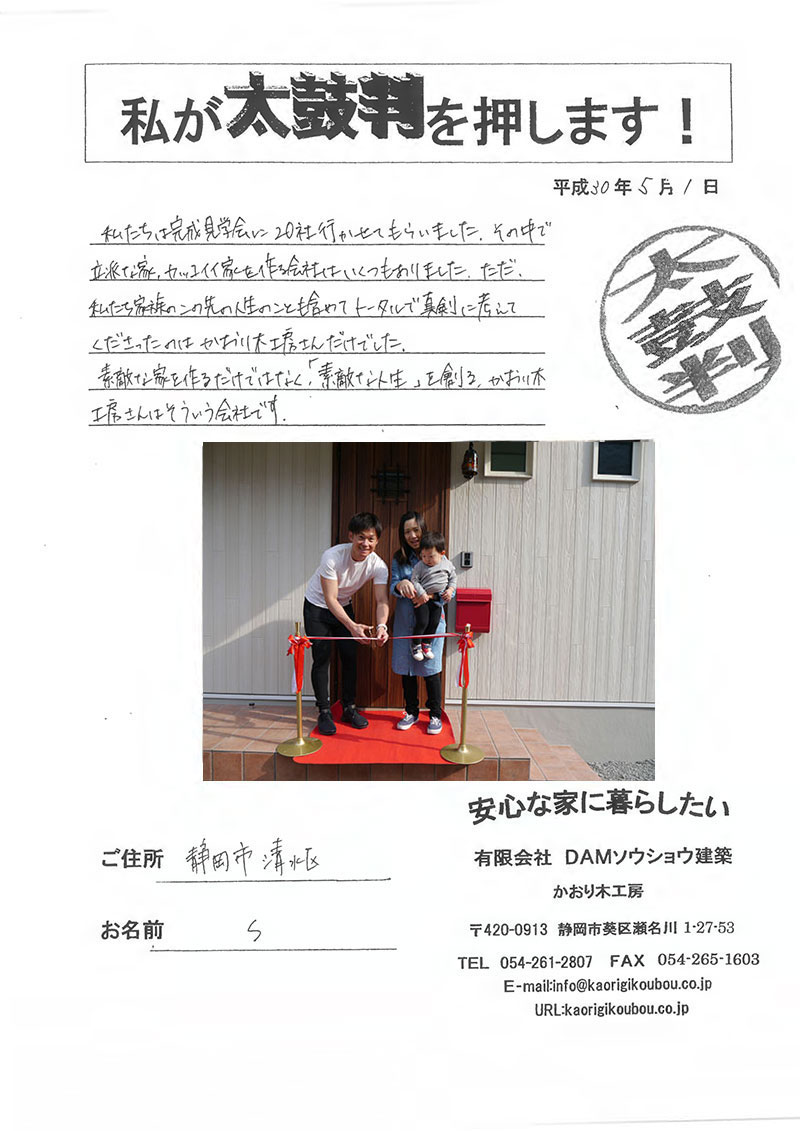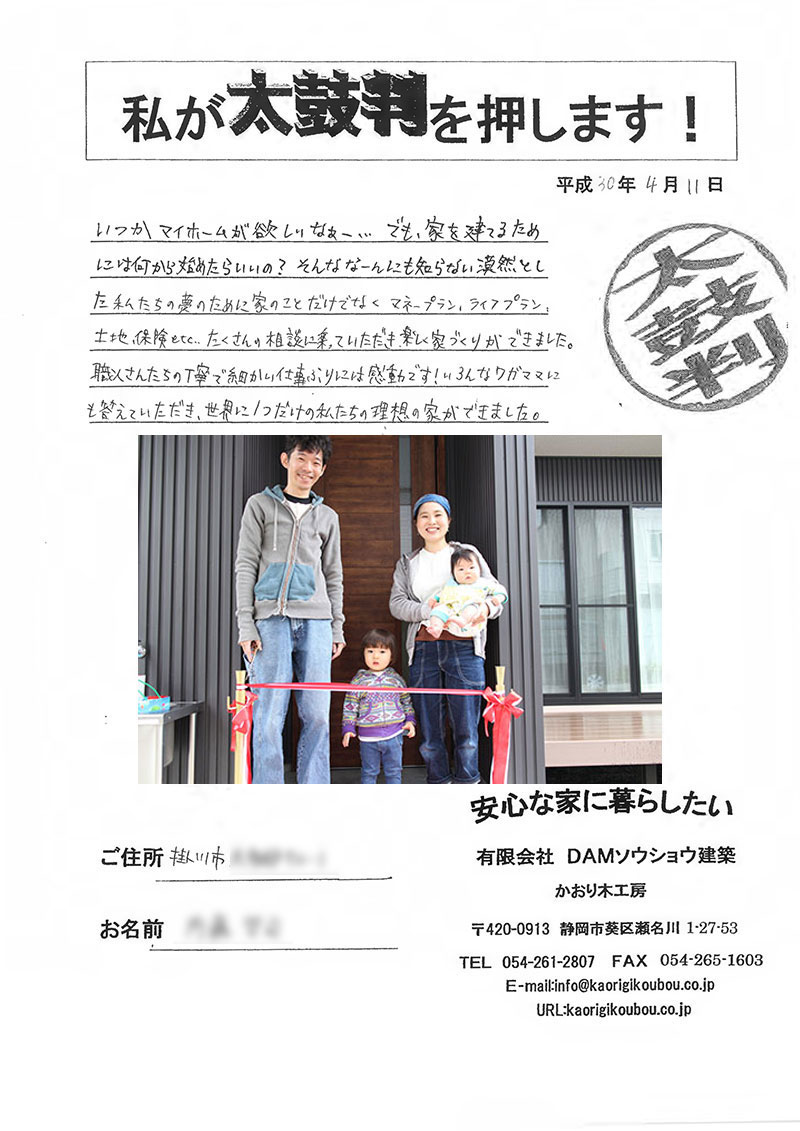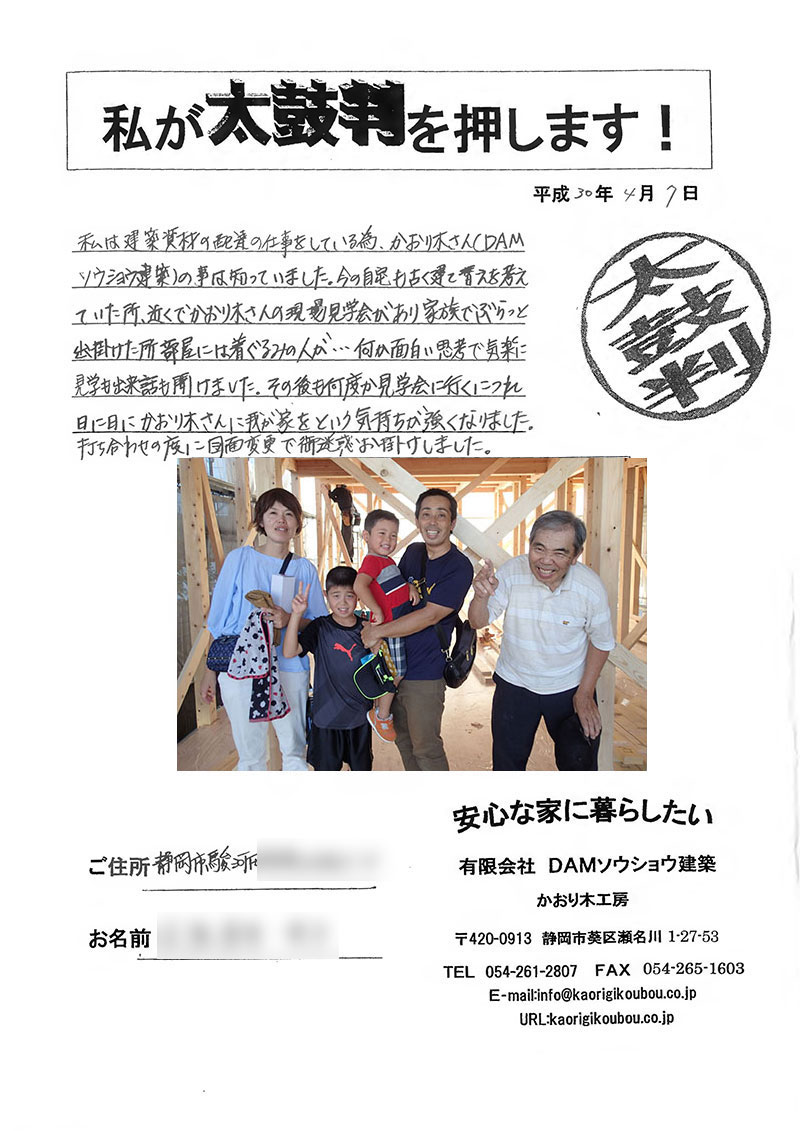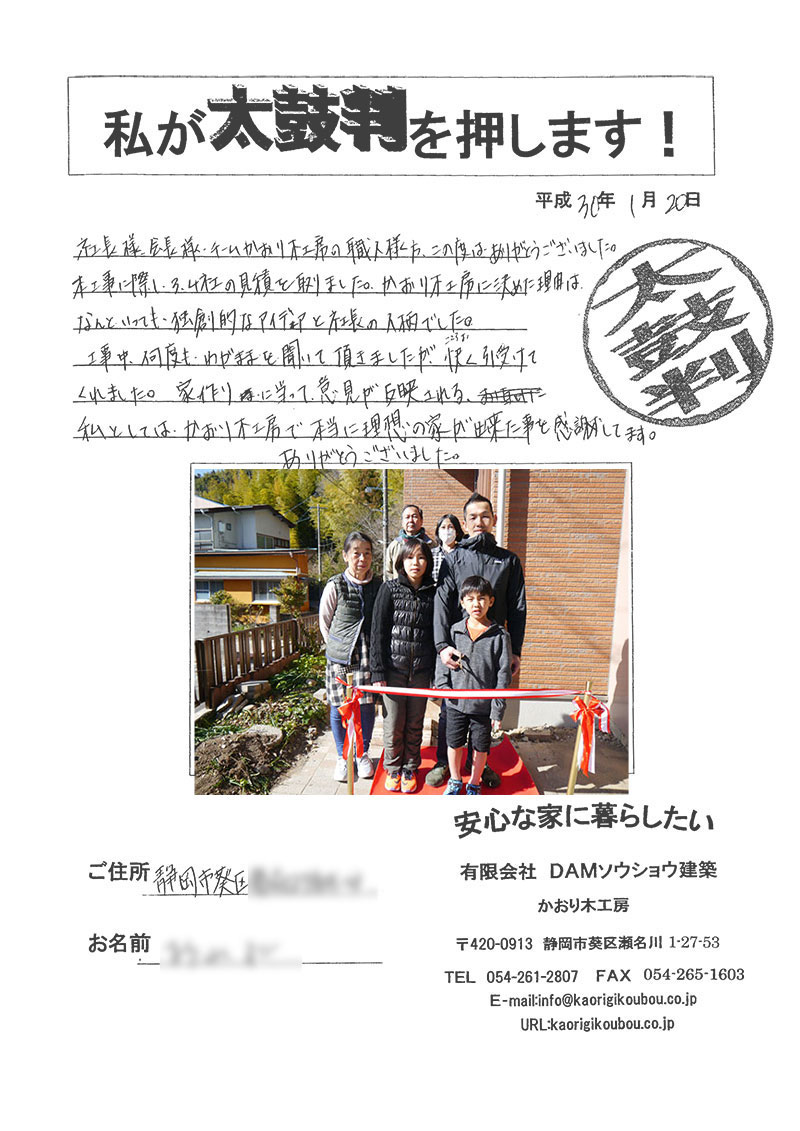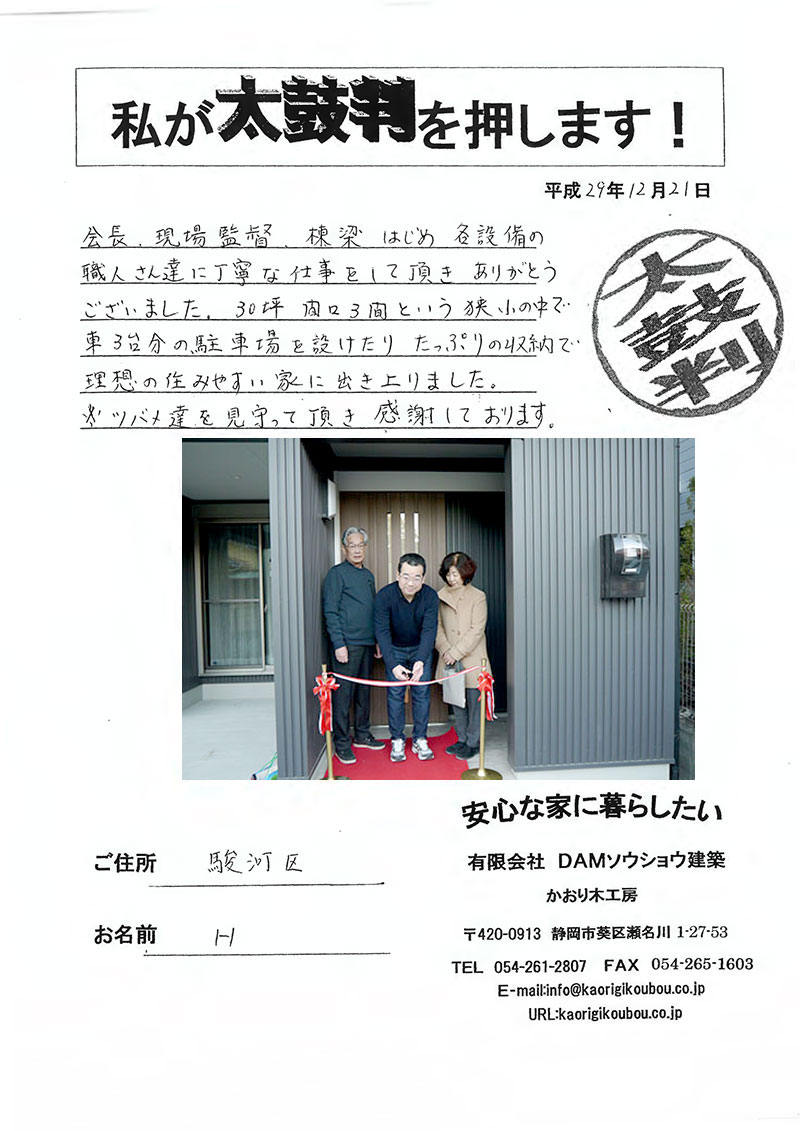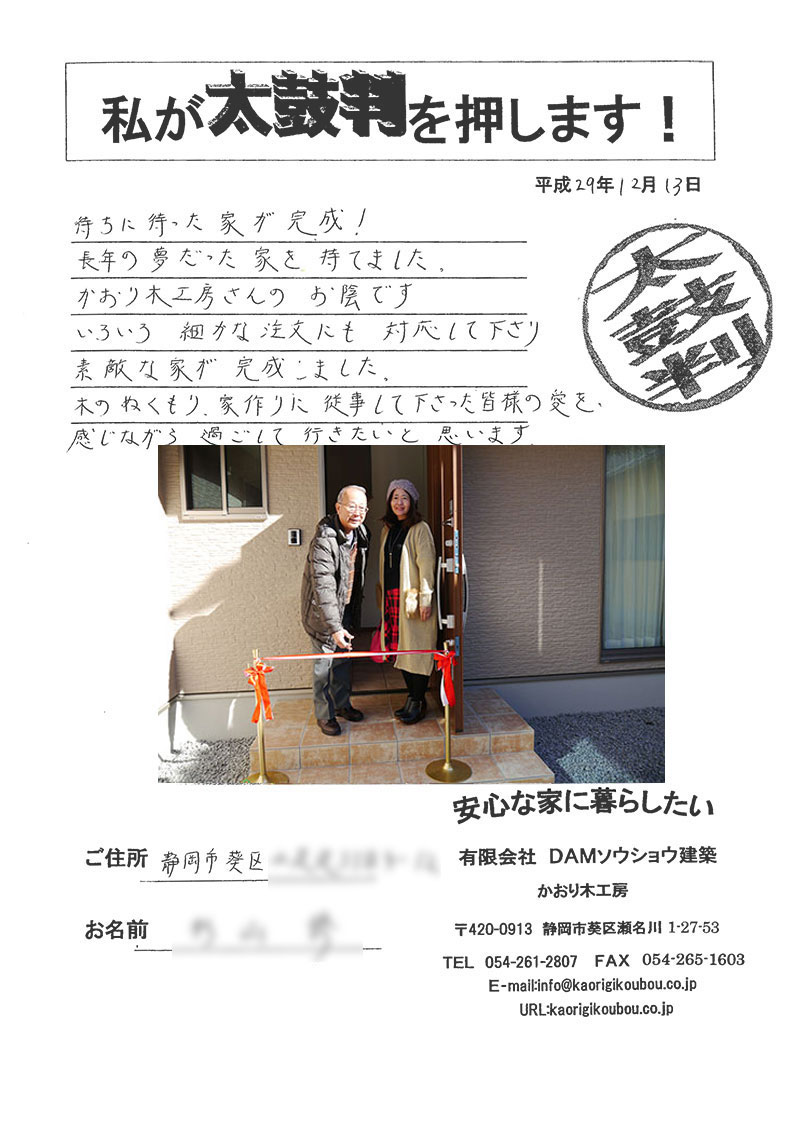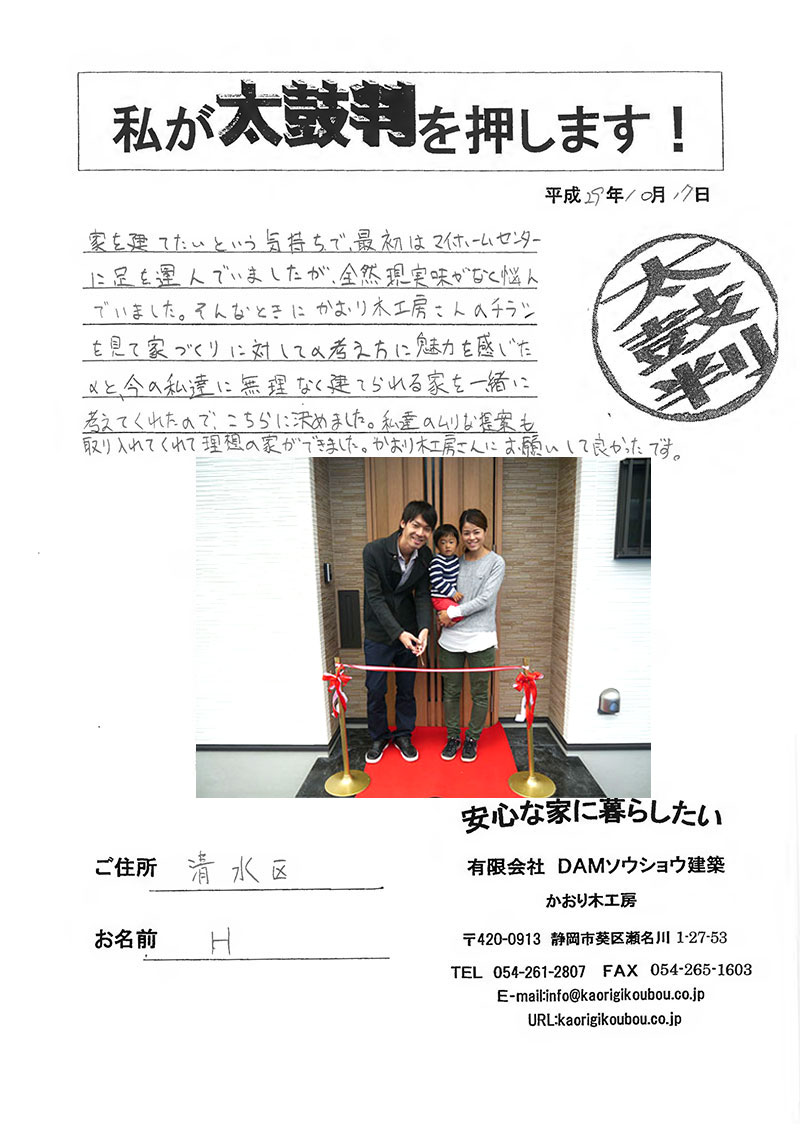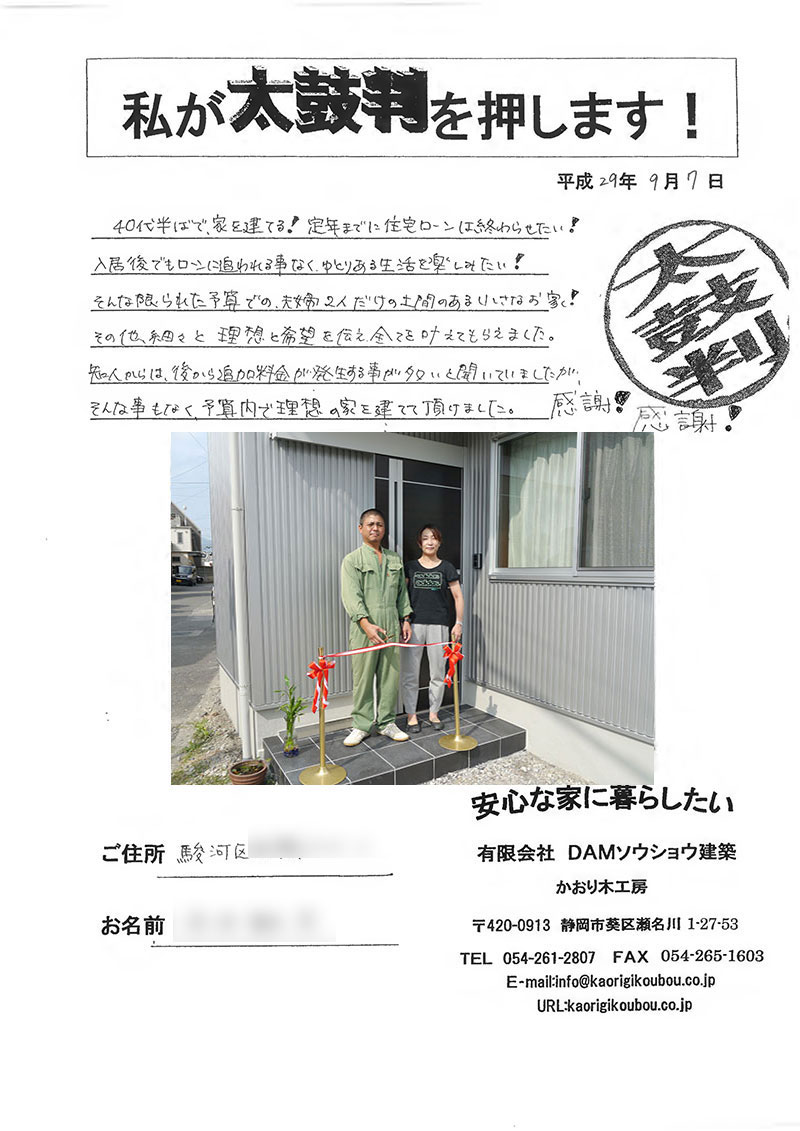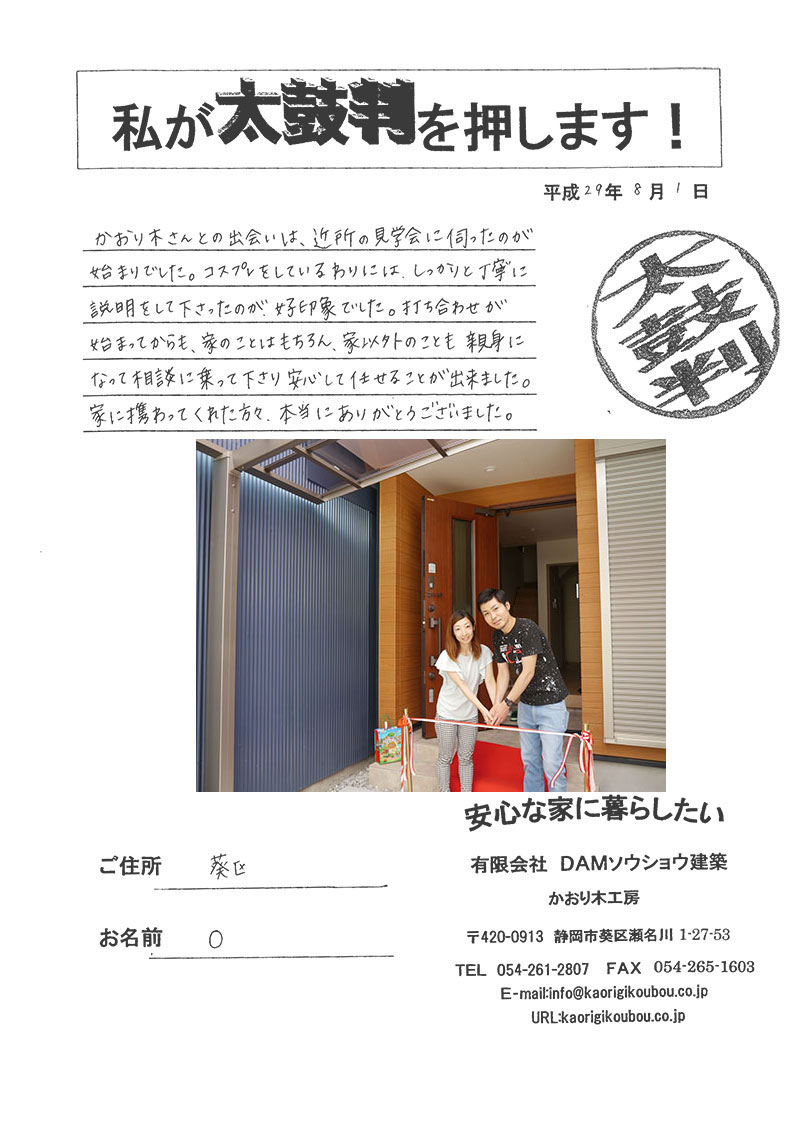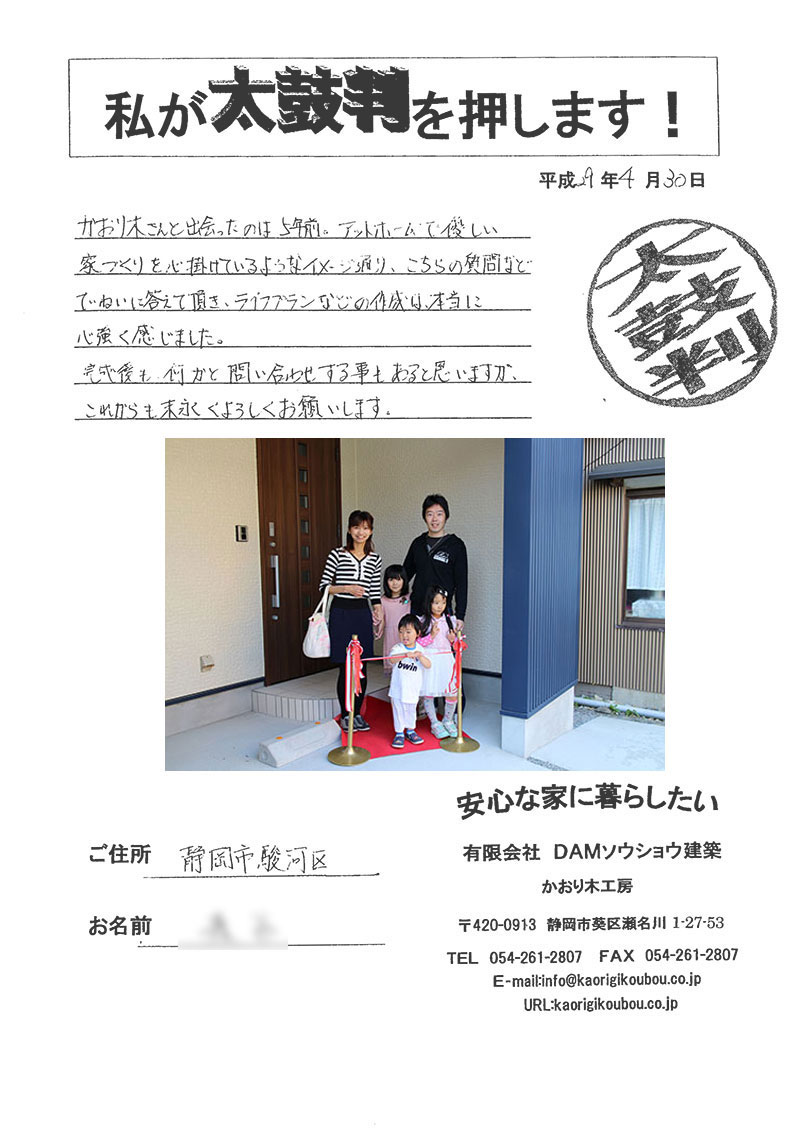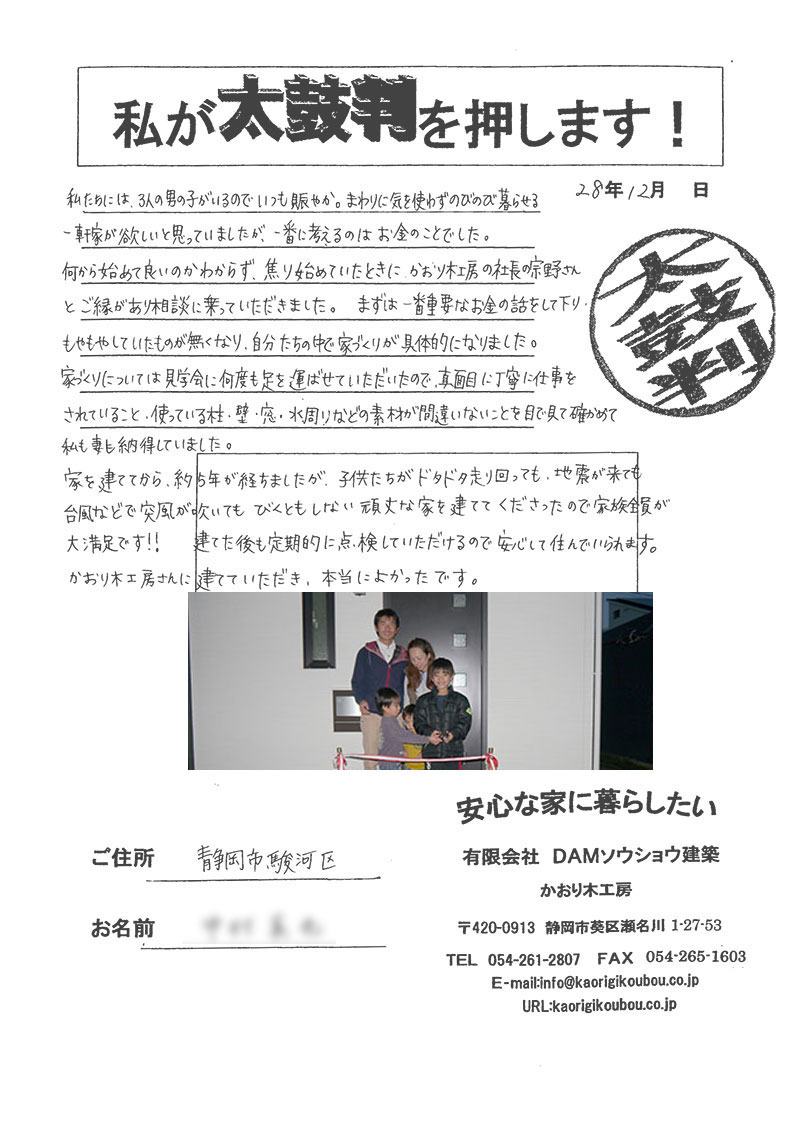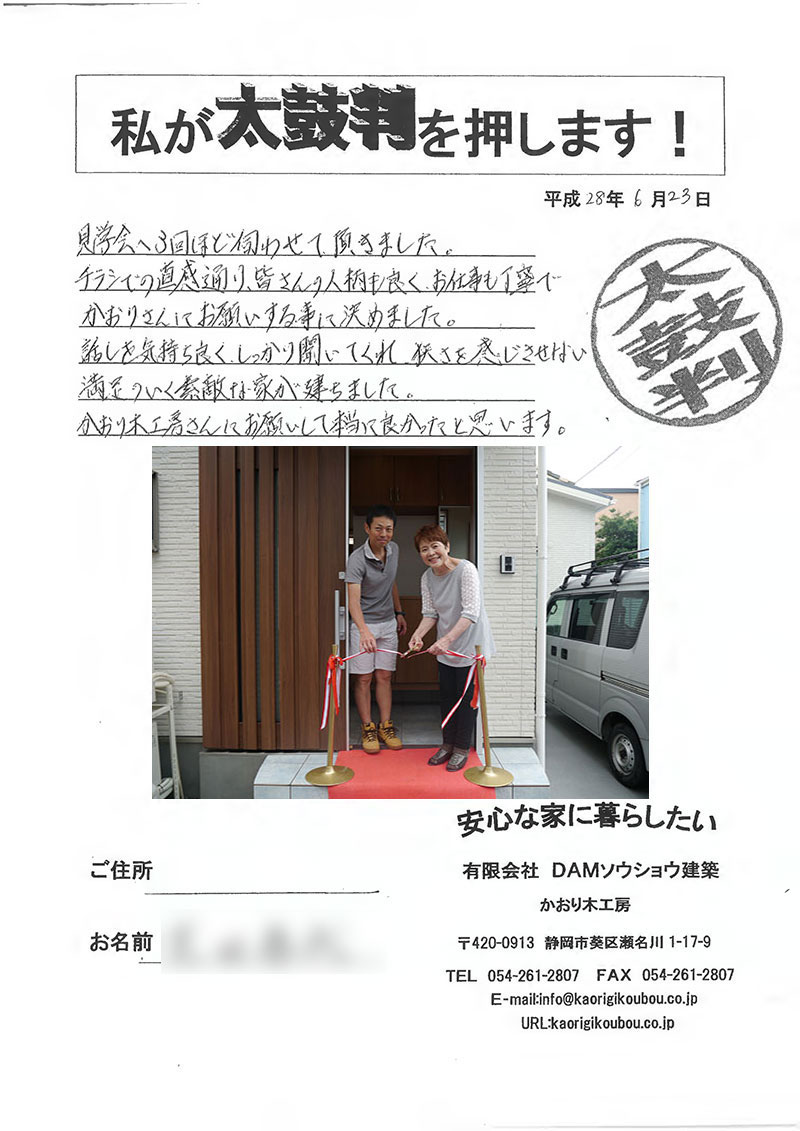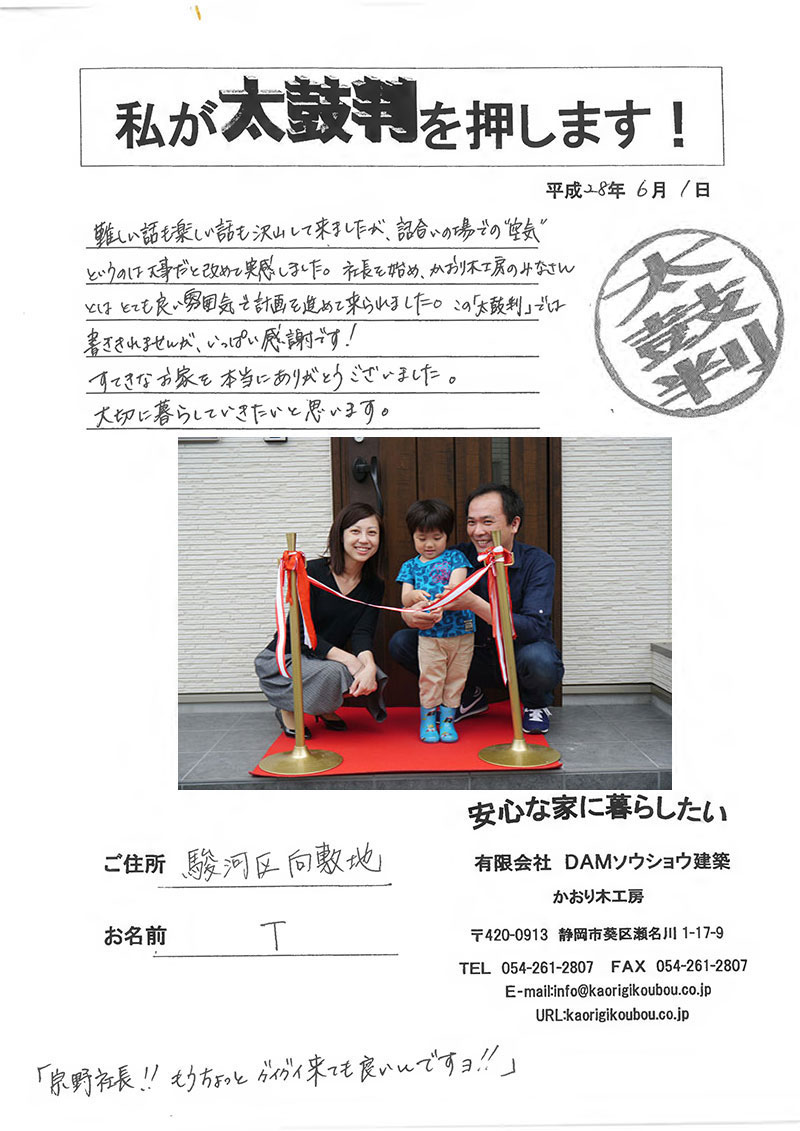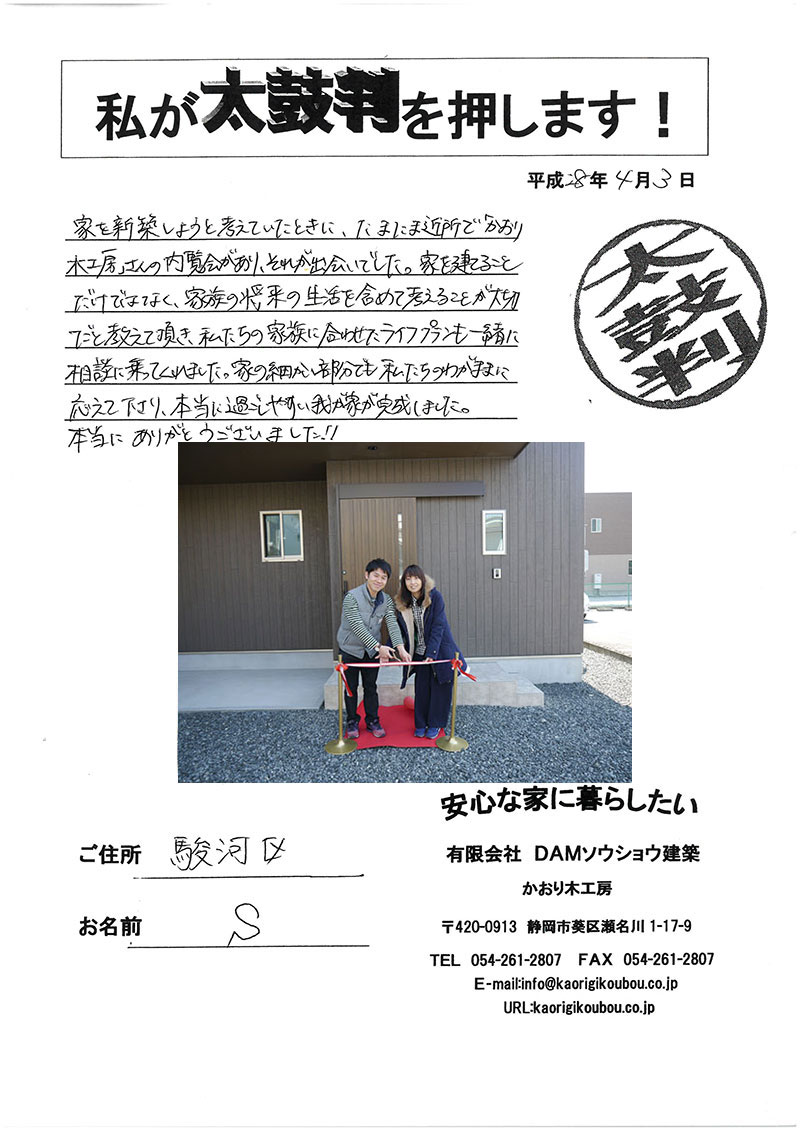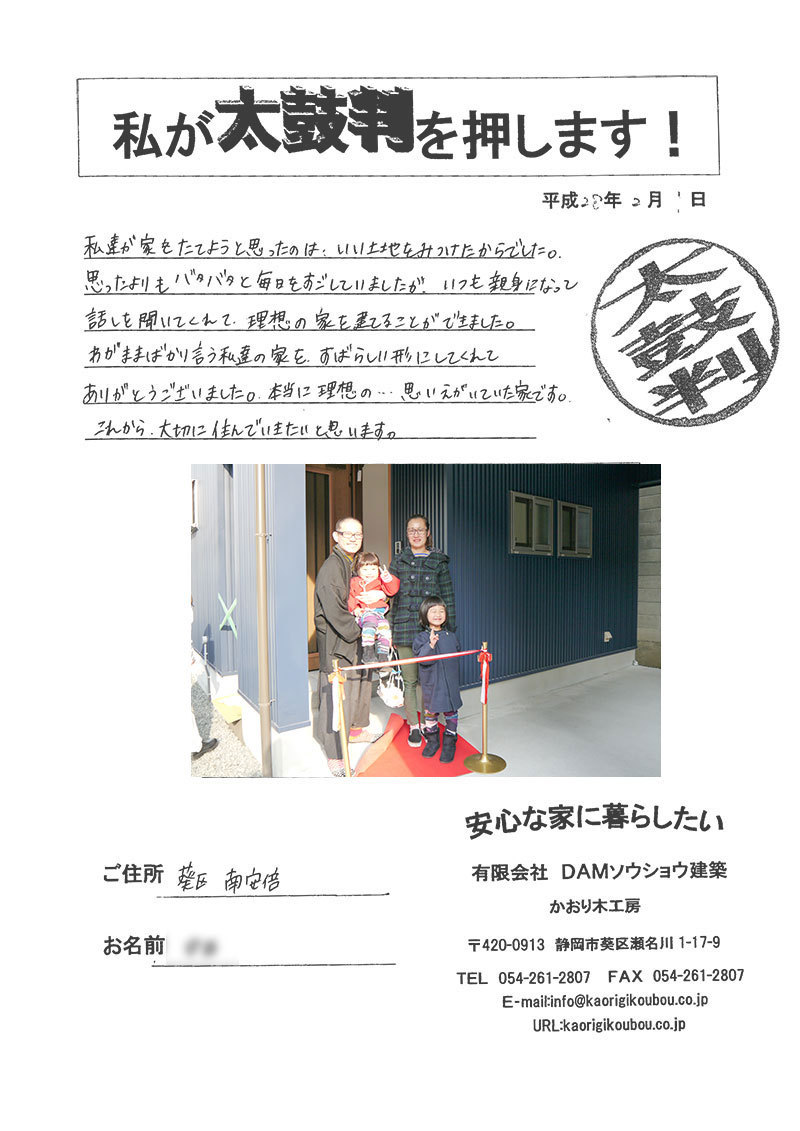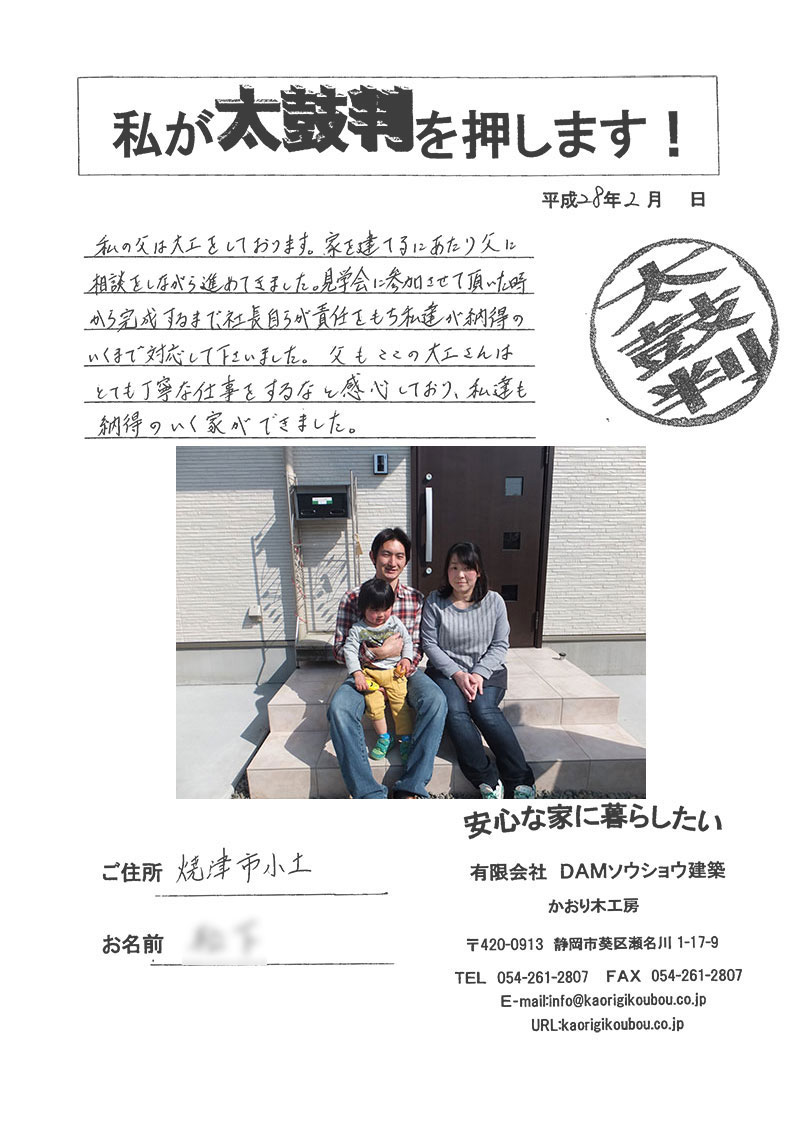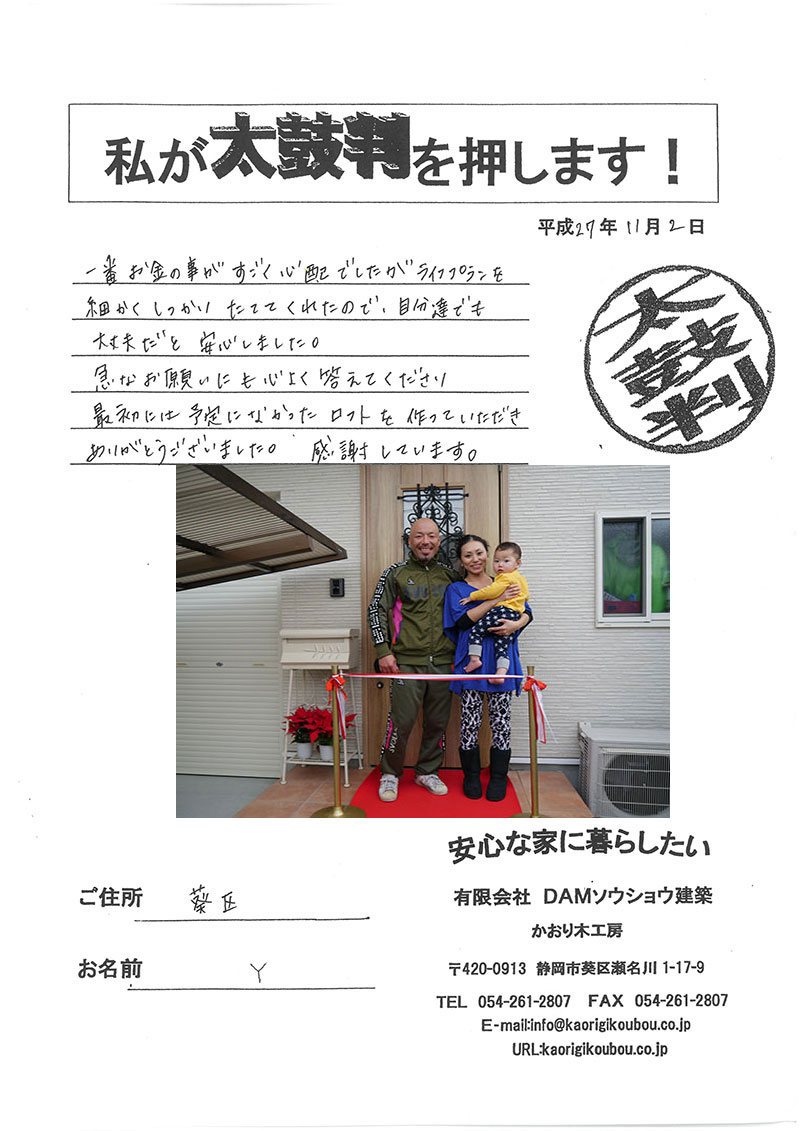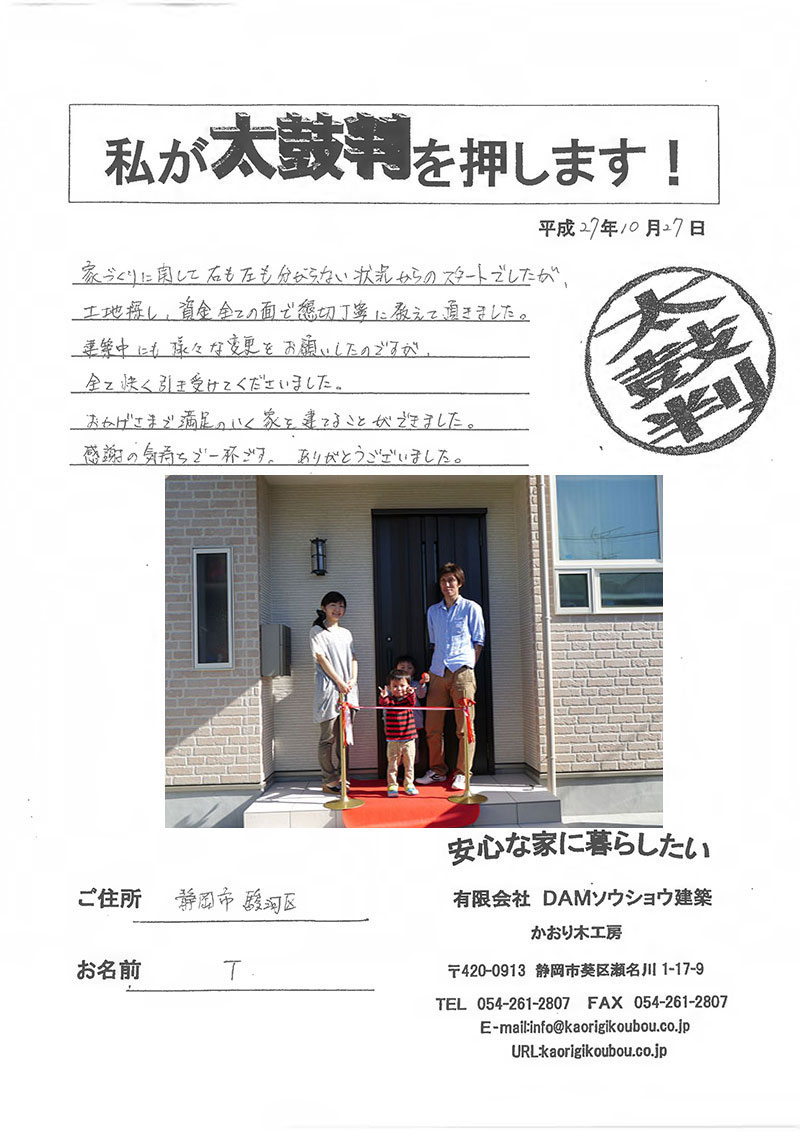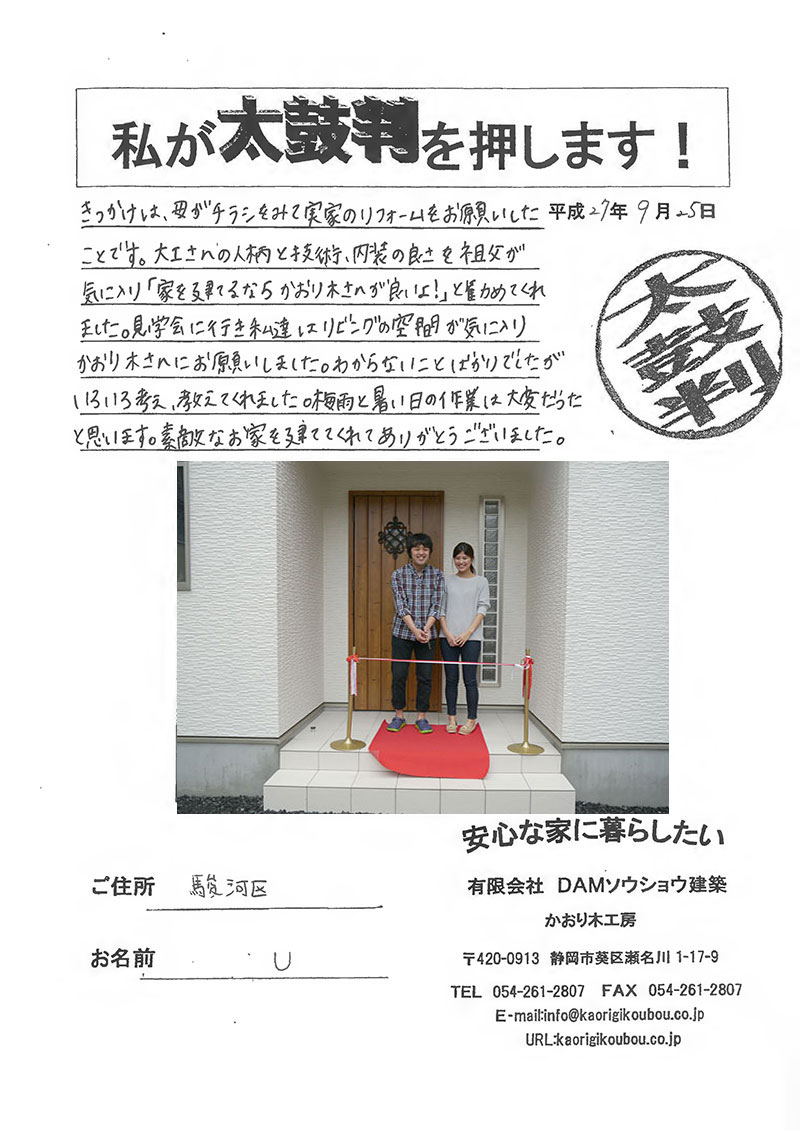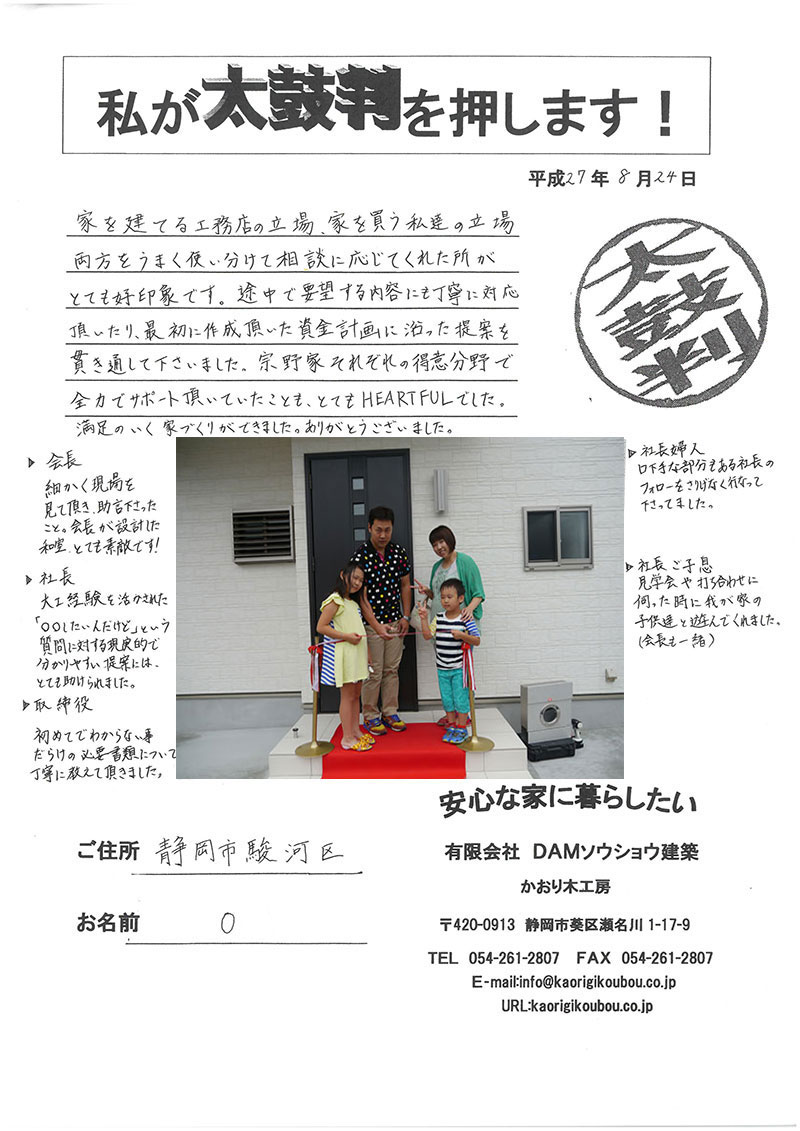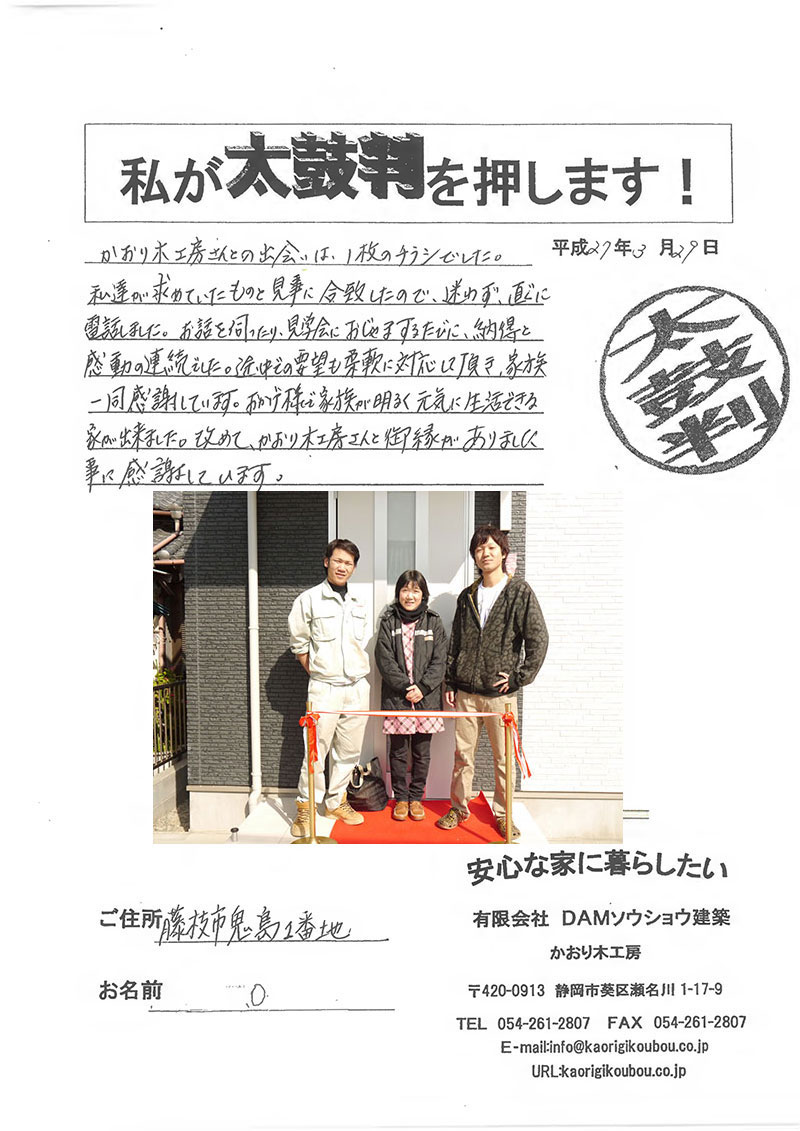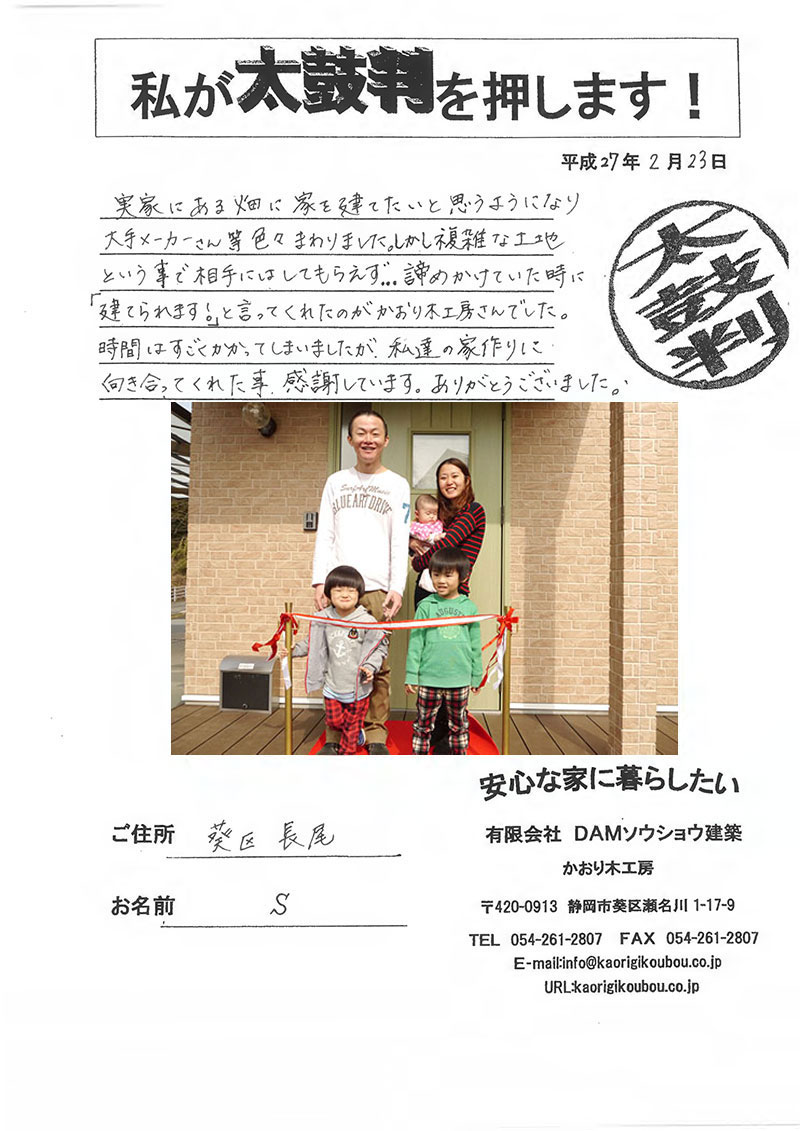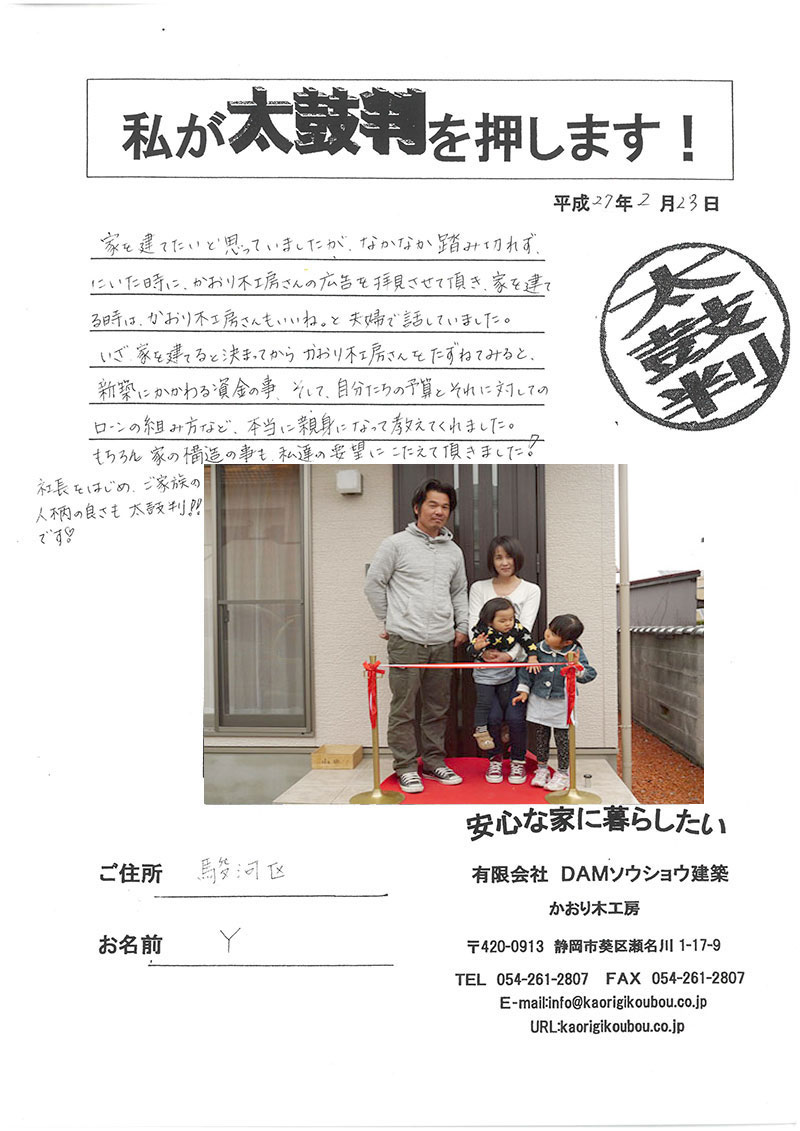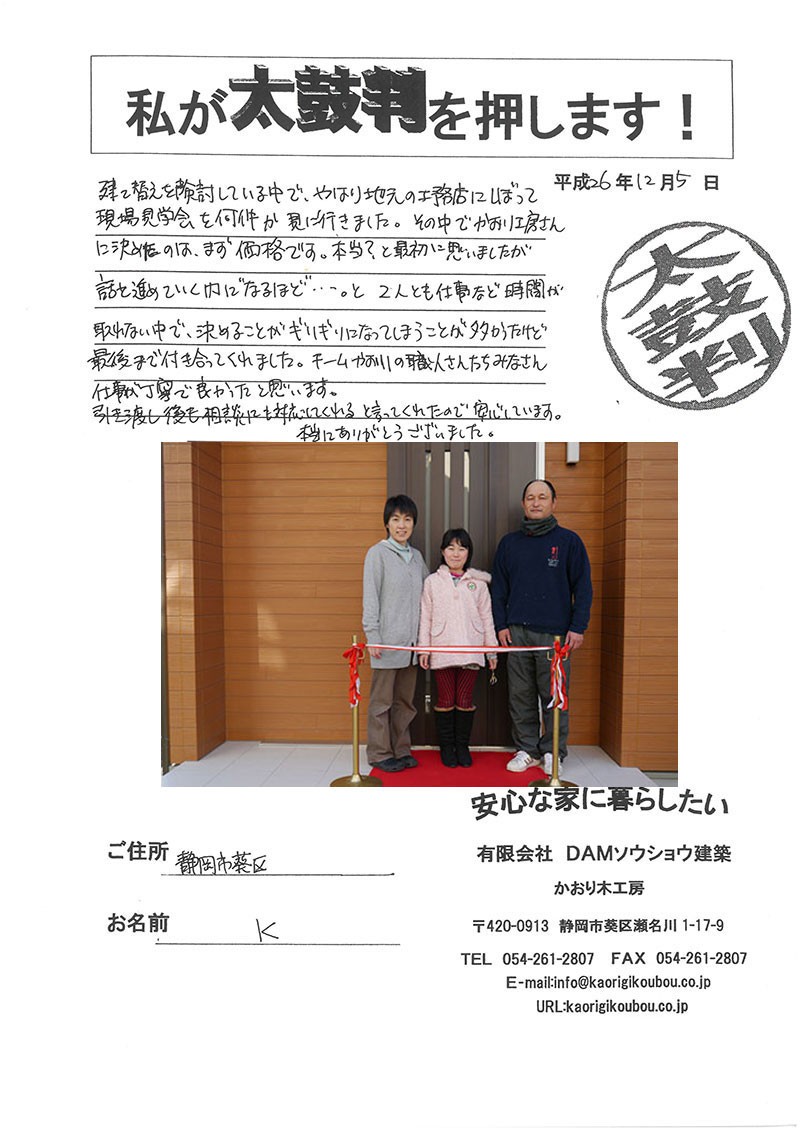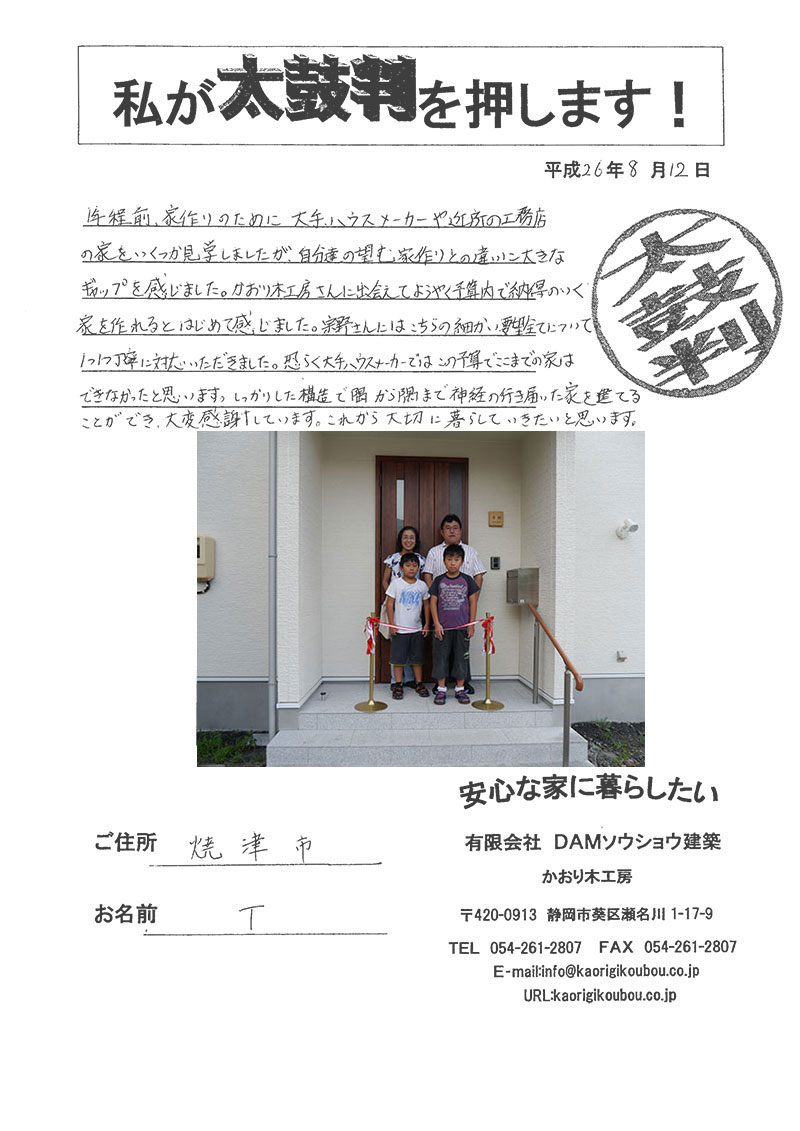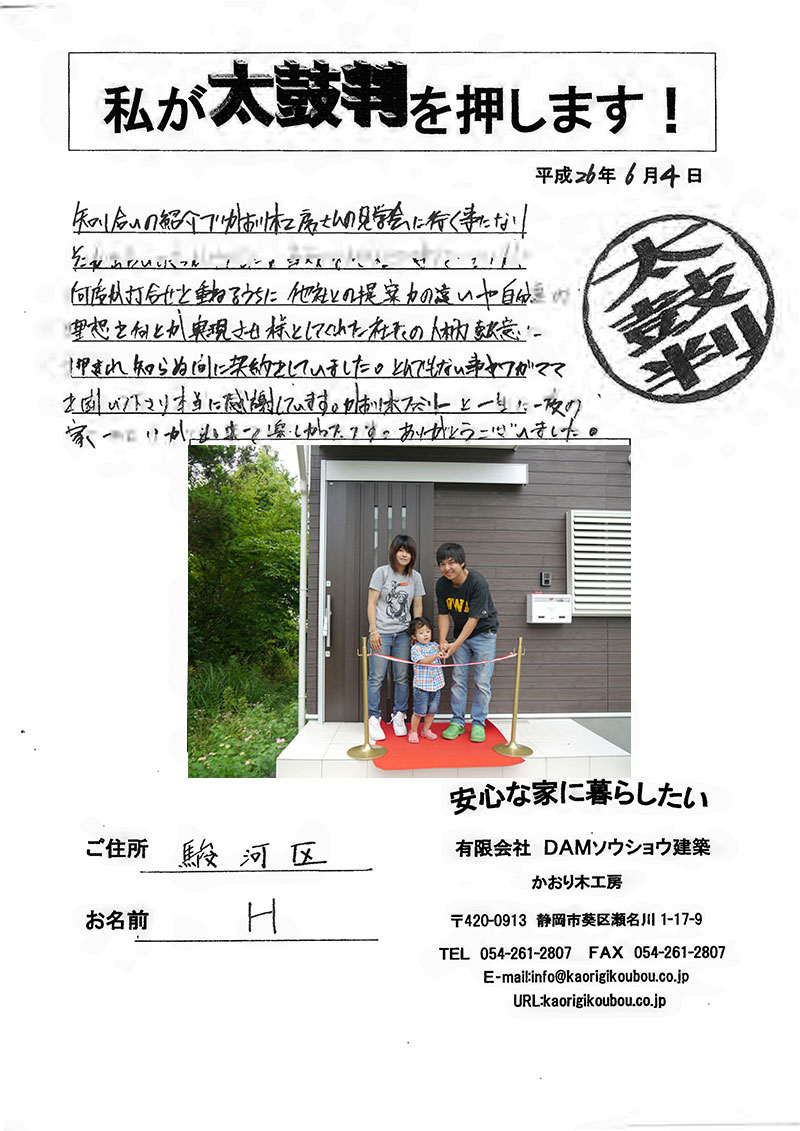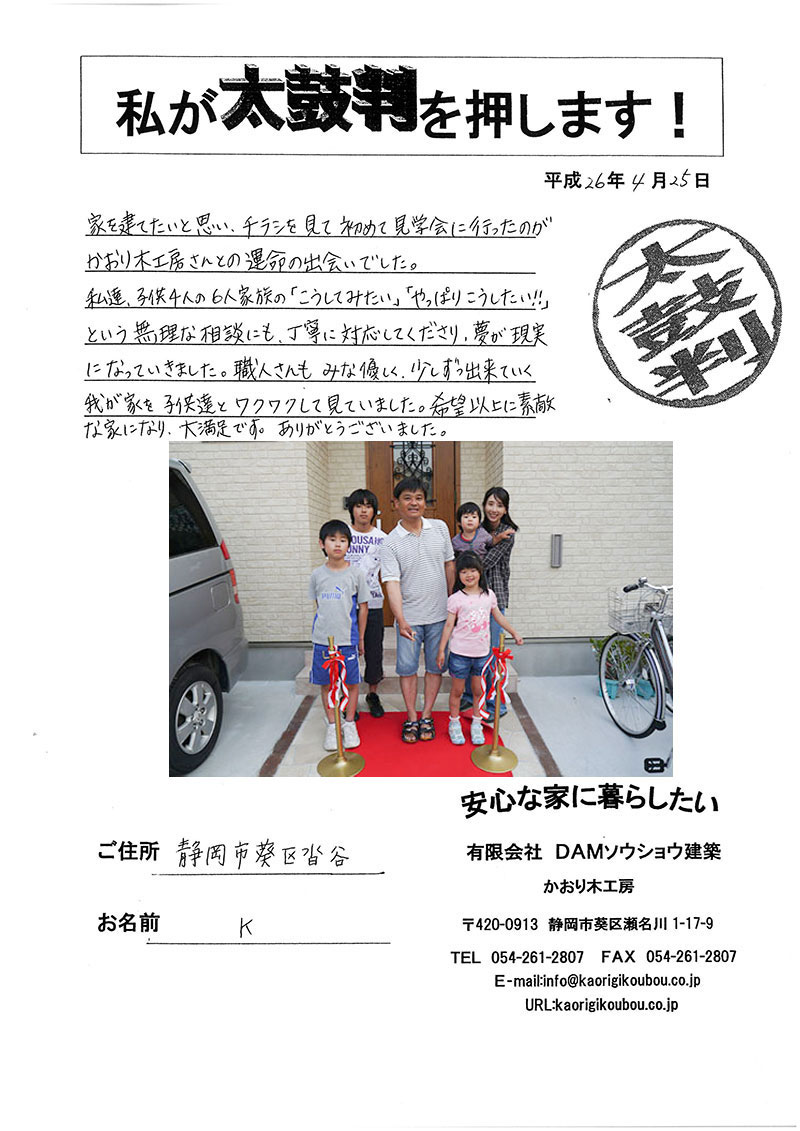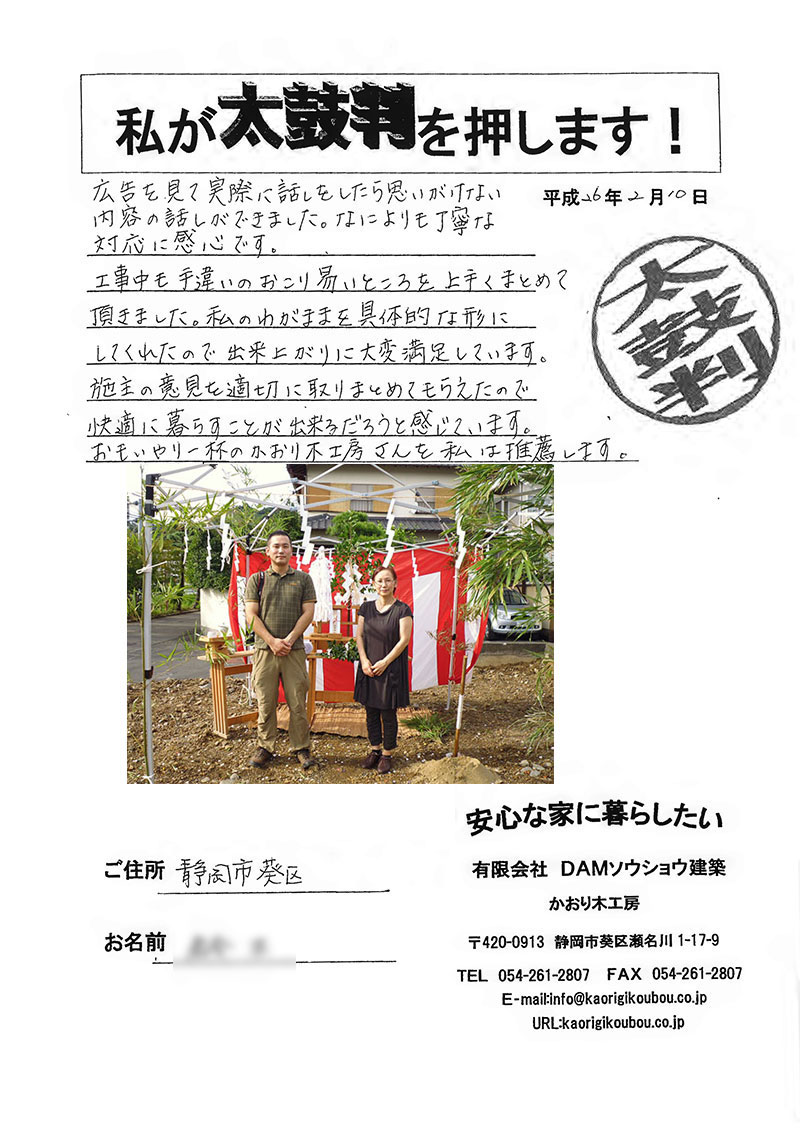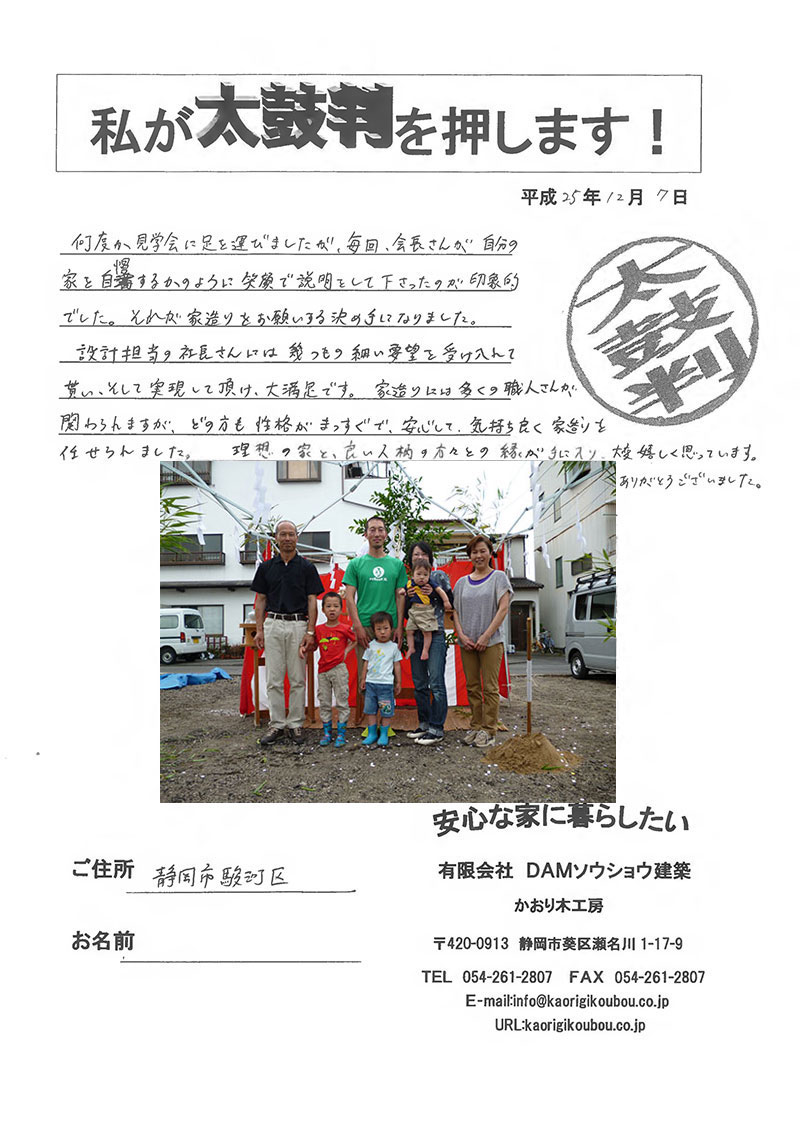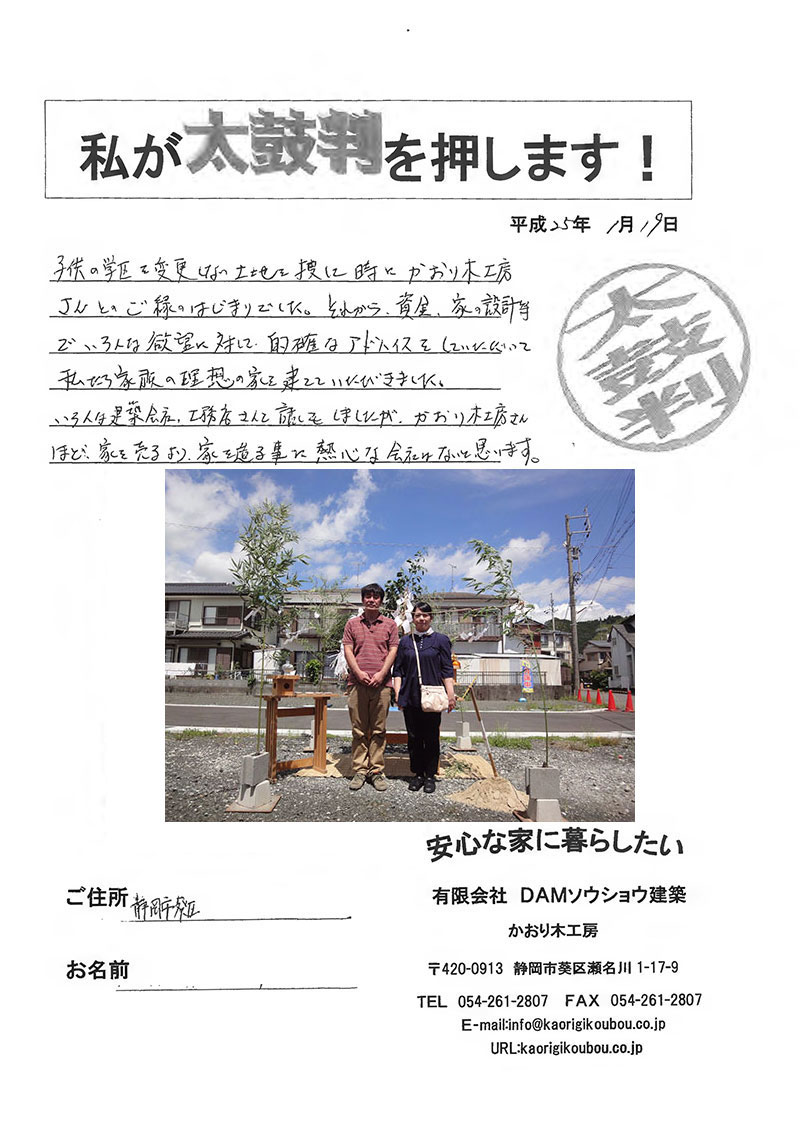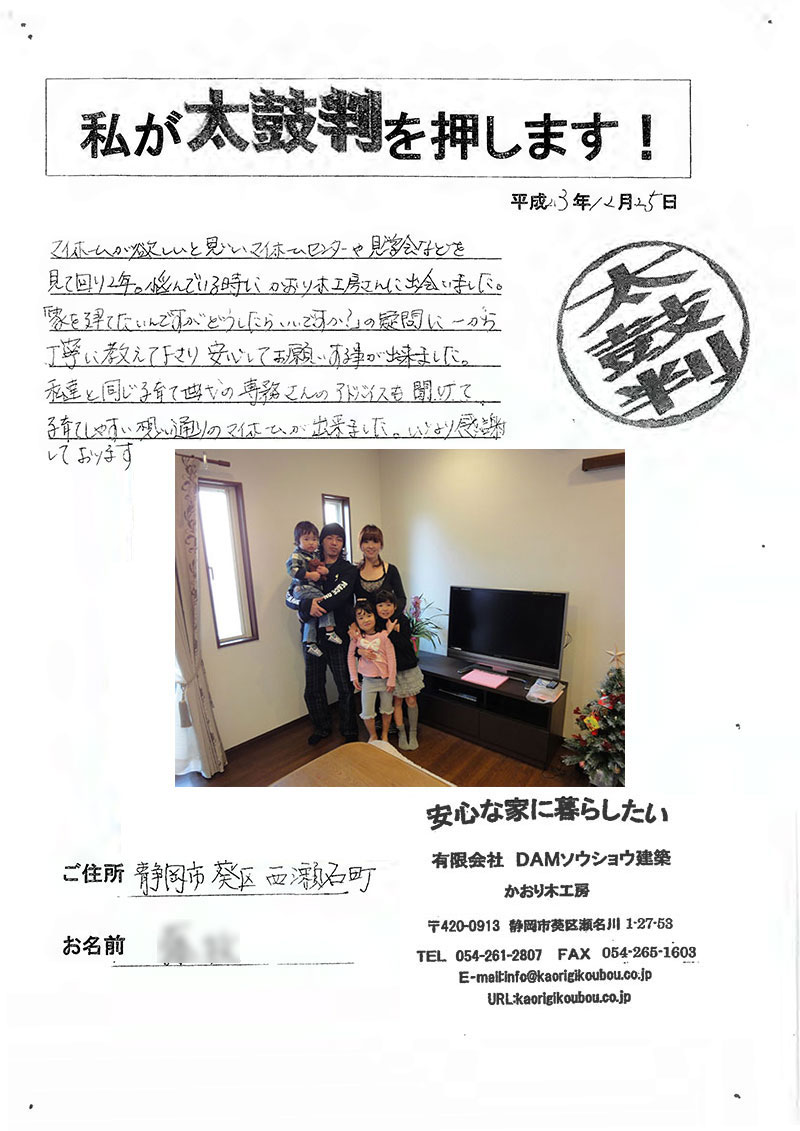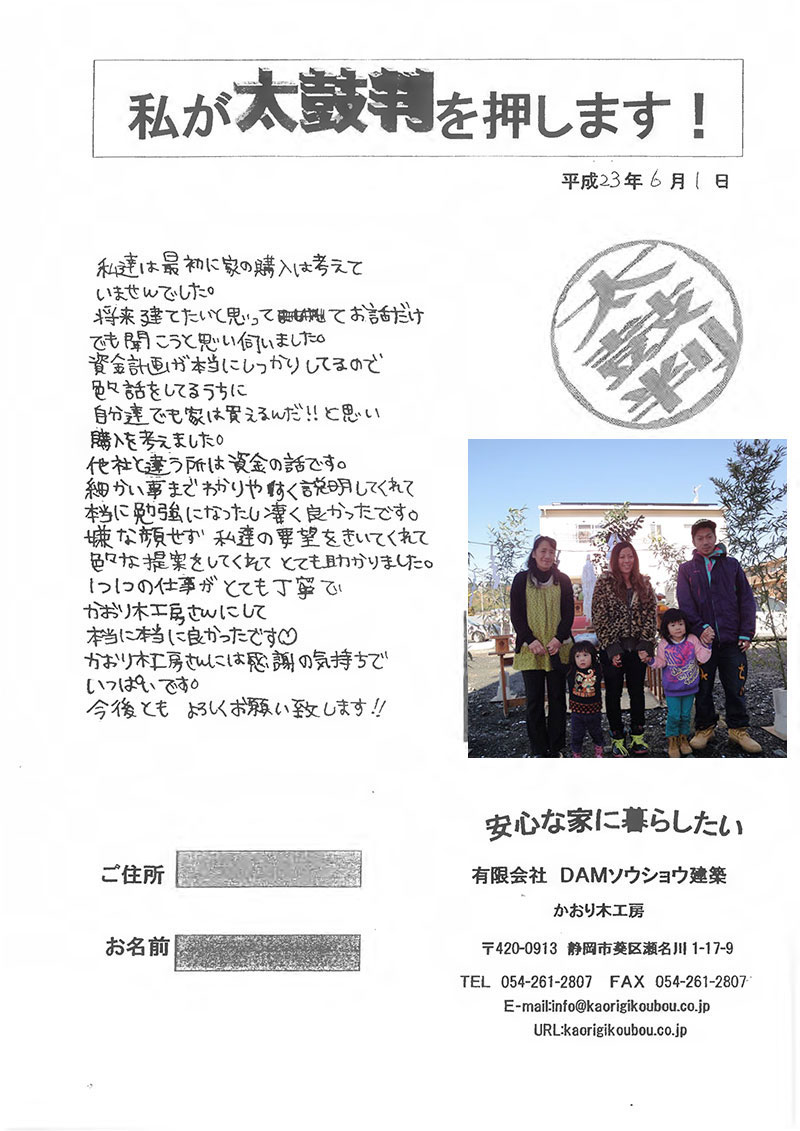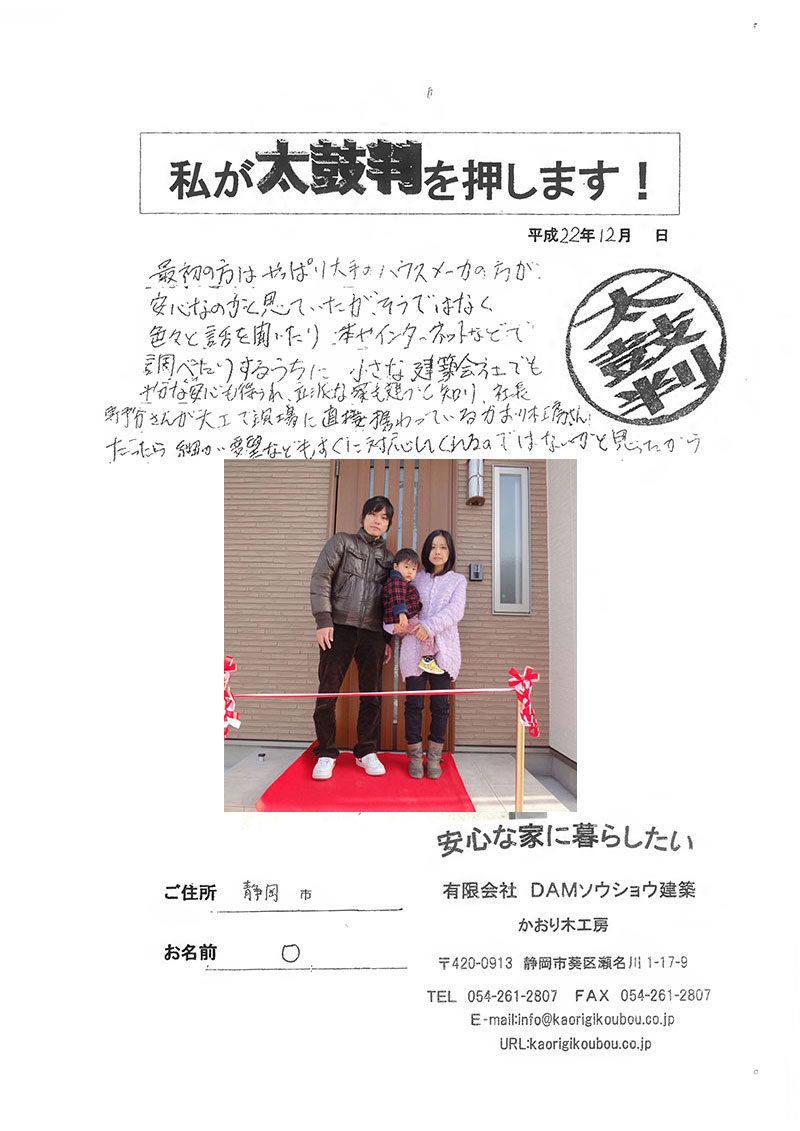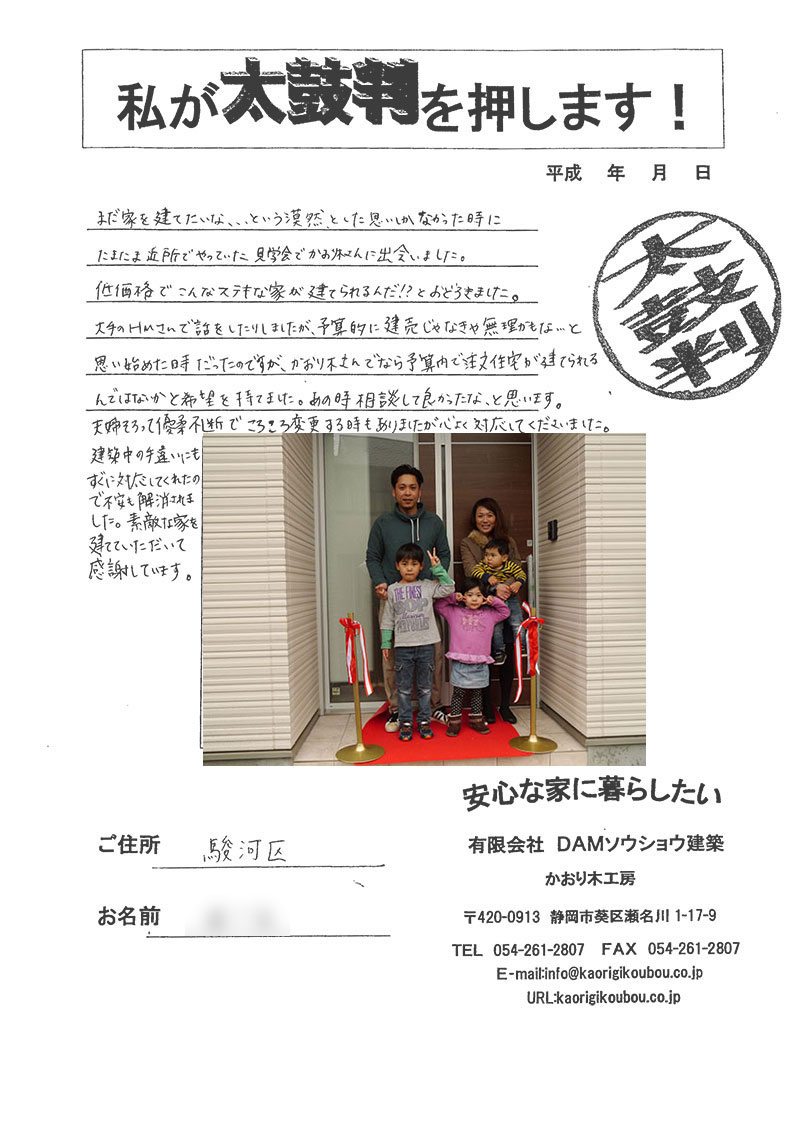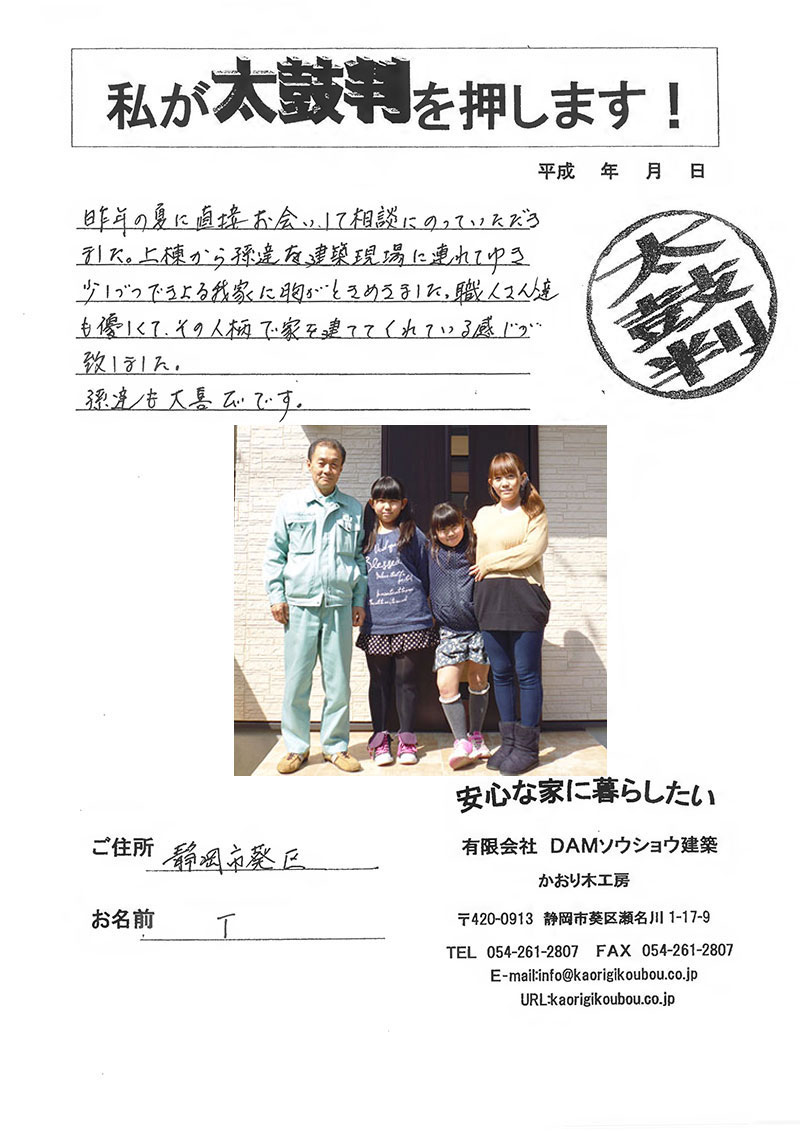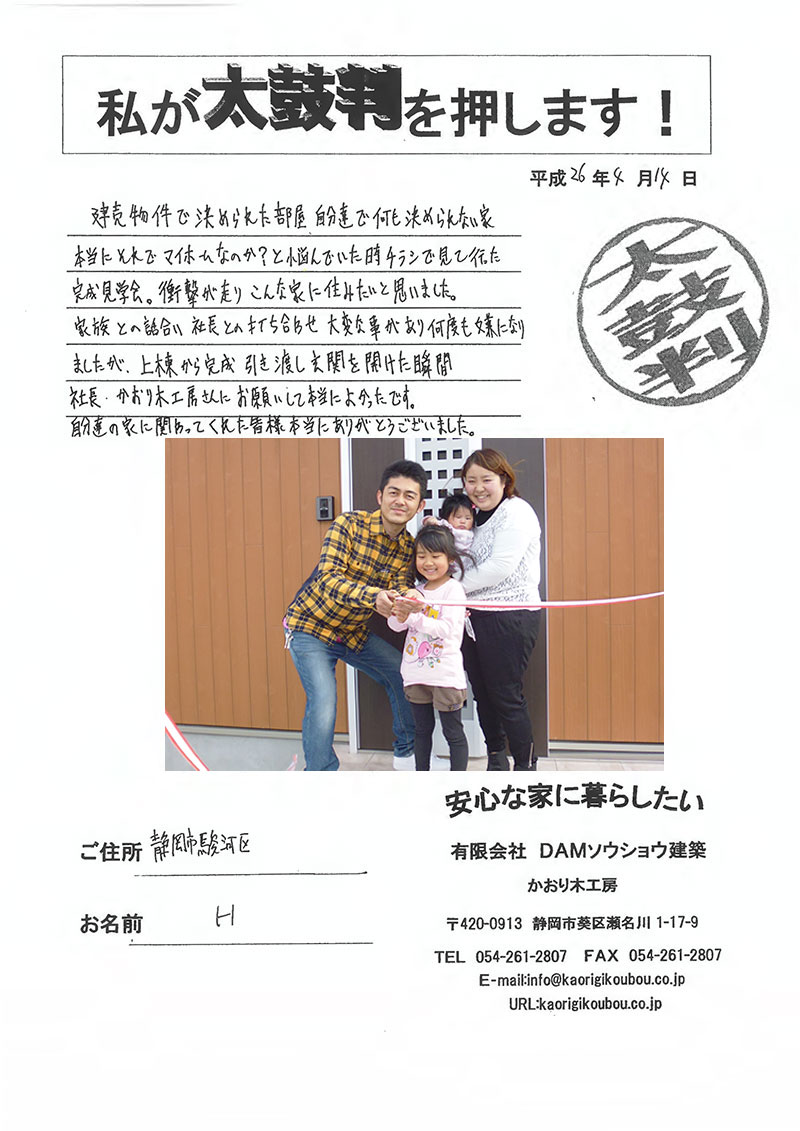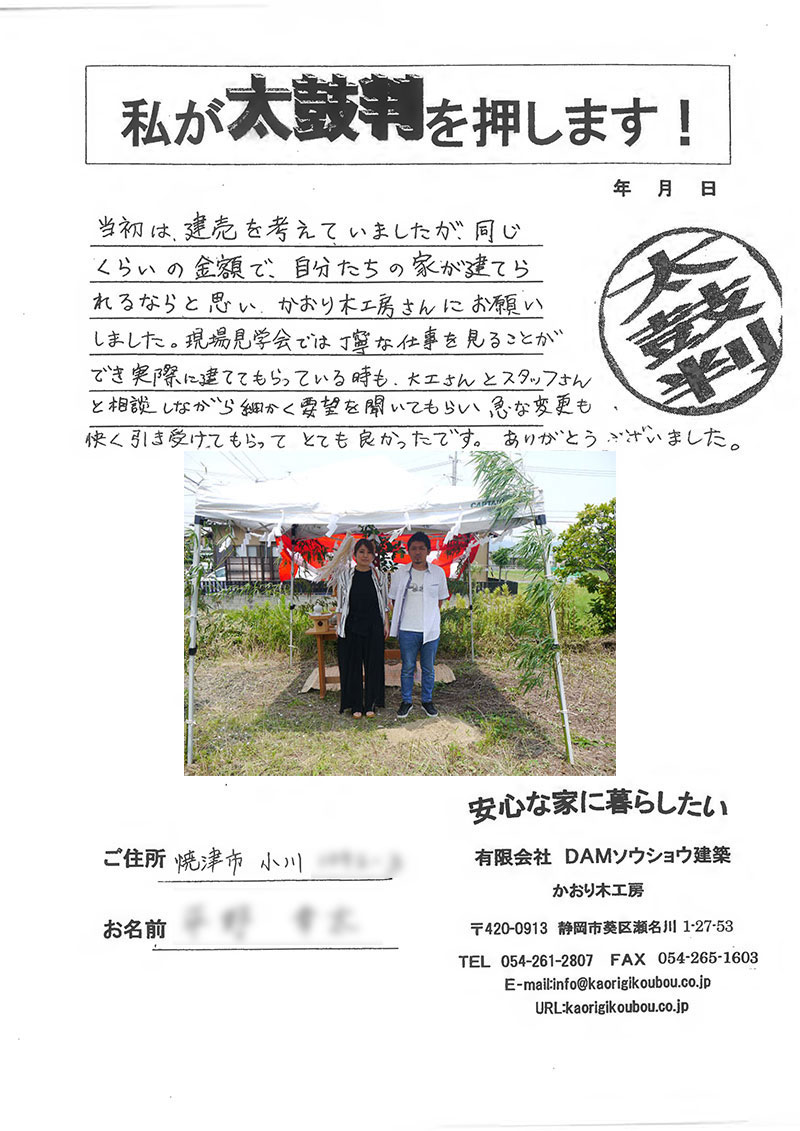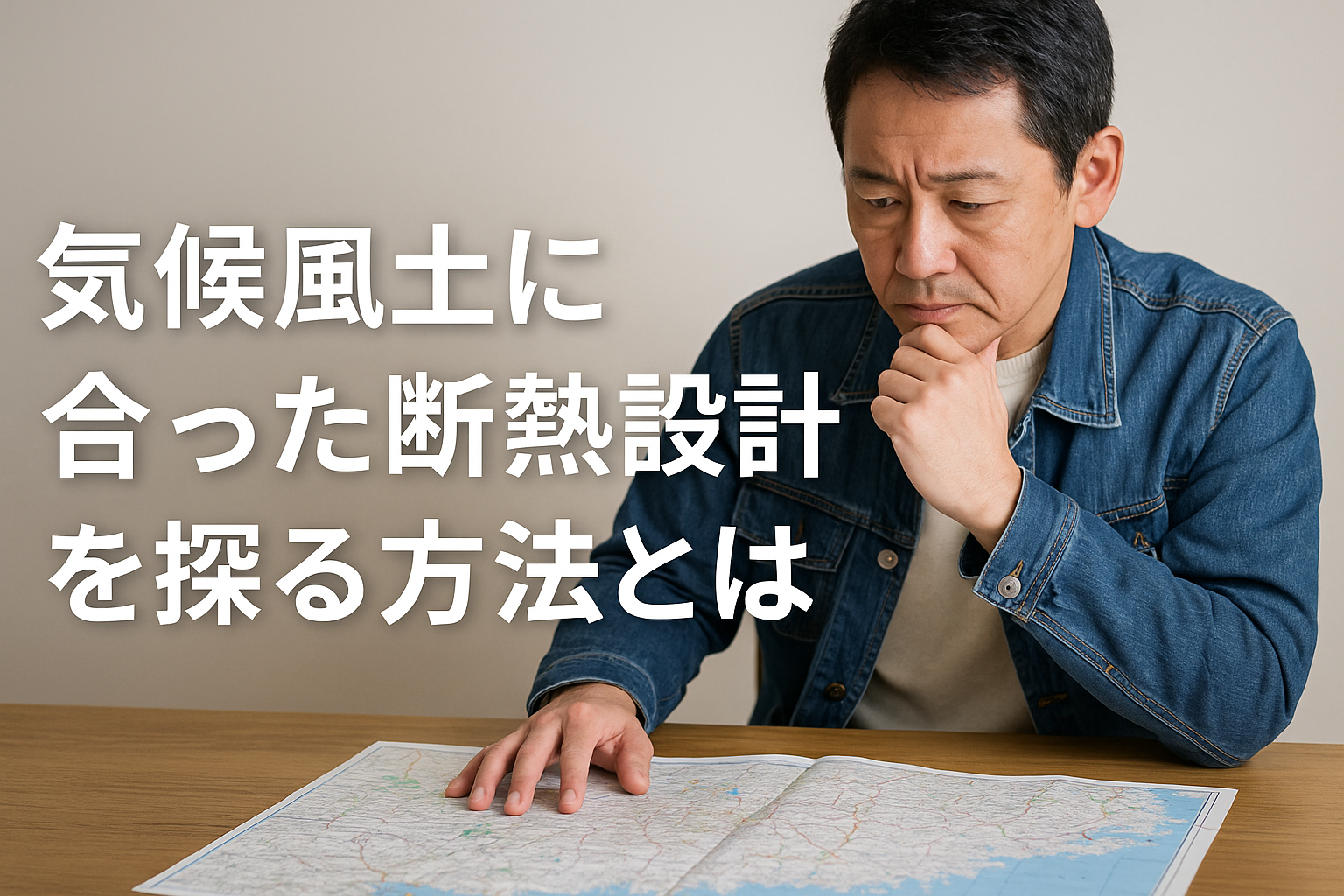
気候風土に合った断熱設計を探る方法とは
“その土地らしさ”を活かす断熱の設計手法
断熱は“地域性”で変わる
断熱設計は、単に断熱材を厚くすればいい、というわけではありません。
その地域の気温変動、湿度、風の流れ、日射量などの「気候風土」を読み解き、それに合った仕様・施工を選ぶことが、住まいの快適性・省エネ性を最大化する鍵です。
とくに静岡のように、冬はほどほど寒く、夏は強い日差しと湿気に悩まされる地域では、断熱+遮熱+通風設計を一体で考えることが不可欠です。
本記事では、地域特性を意識した断熱設計の方向性、静岡を例にした考え方、具体的な設計ポイントをオリジナルの視点でご紹介します。
地域特性を意識した断熱設計の方向性
以下のような地域特性を押さえると、断熱設計の方向性が見えてきます。
1. 冬期の夜間冷えと朝の冷気侵入
冬は、夜から早朝にかけて地面・外気が冷え、建物の外皮(壁・窓・床基礎)から熱が逃げやすくなります。特に床下・地面に接する部分、窓ガラス・窓枠の熱伝導性は注意が必要です。
2. 夏期の日射・紫外線強さと熱侵入
夏の日中、屋根・外壁・南・西の窓面などが直射日光に晒され、高温化します。そこから家の内部に熱が伝わりやすい構造部を断熱・遮熱で制御する設計が求められます。
3. 湿度・気候湿潤環境の影響
湿気が高くなる地域では、結露・カビ・腐朽のリスクが上がります。断熱設計と湿気コントロール(防湿・換気)を一体で考えることが重要です。
4. 通風と気流の利用
風が通りやすい風向き・風道を読み取り、夏季には通風を活かす窓配置と風の抜け道設計を断熱計画と絡めて行うことが、快適性を高めるポイントとなります。
静岡地区を想定した設計例の方向性
静岡のような地域で考える断熱設計の方向性を、例として整理するとこうなります。
- 南面窓は採光と日射取得を活かす仕様 → 冬の日差しを取り入れる窓設計
- 西面・北面は遮熱・断熱強化重視 → 窓面積を抑え、断熱性能を重視
- 屋根断熱+通気層確保 → 高温期の屋根熱が室内に伝わりにくくする
- 壁断熱・基礎断熱の併用 → 足元・壁体・屋根ラインを包み込む断熱ネットワーク
- 換気計画・通風設計を前提に → 熱をこもらせず湿気を逃がす設計
こうした方向性をベースに、具体的な仕様と工法を設計に落とし込むのが理想です。
設計で意識すべき具体ポイント
以下は、地域に合わせた断熱設計を行う際に特に重視したいポイントです。
窓と外壁の取り合い設計
- 南面には大きめの窓を配置しつつ、庇・日除けを設けて夏の日射を調整
- 東西面・北面は窓を抑え、高性能仕様(Low‑E複層ガラス・トリプルガラス・高断熱サッシ)を採用
- 窓まわりのシーリング・気密施工を丁寧に取り扱うこと
屋根・天井断熱と遮熱設計
- 屋根断熱を強化しつつ、通気層・棟換気を設けて屋根裏の熱溜まりを防ぐ
- 断熱材選定時に断熱性能・耐火性・耐湿性を兼ね備えた材料を選ぶ
- 天井・屋根の取り合い部や開口部(天窓など)に注意
床・基礎断熱を軽視しない
- 床下または基礎断熱を導入して、床面から伝わる冷気を抑える
- 土間床や床スラブと断熱の接続を断熱ネットワークで一体化
- シロアリ対策・湿気処理を組み込むことも忘れずに
気密性と換気設計
- 隙間をできるだけ減らす気密処理(配線・配管まわり、取り合い部等)
- 熱交換型換気や適切な換気経路設計で湿気排出を確保
- 換気風量・給気・排気配置をプラン段階で決定
ゾーニング/断熱強化優先箇所
- リビング・寝室・水まわりなど、使用頻度の高い領域を優先的に断熱強化
- 廊下・階段など間接的空間の断熱も無視せず、温度ムラを抑える設計
- 天井高・吹抜けの扱い方を慎重に
まとめ:地域性を取り入れた断熱設計で、ちょうどいい住まいを
断熱設計は単なる材料選びではなく、その土地の気候風土を味方にする設計が本質です。
静岡のような地域では、日射・湿度・風向きといった要素を断熱設計に組み込み、バランスの取れた設計を行うことで、快適・省エネ・長寿命を実現できます。
次回以降もこの流れで、住まいづくりに役立つテーマをオリジナルでお届けします。
次回予告
次回は 「梅雨期の湿気対策として断熱+換気をどう組み合わせるか」 をテーマに、湿気の影響を抑える設計技術と施工方法を解説します。
資料請求・お問い合わせ
資料請求はこちらから
賢い夫婦がやっぱり選んだ注文住宅専門工務店 かおり木工房
住所:静岡市葵区瀬名川1‑27‑53
電話:054‑261‑2807(受付 10時〜17時)
社長直通:090‑6587‑4713(「HP見た」とお伝えください)
施工エリア:静岡市・焼津市・藤枝市