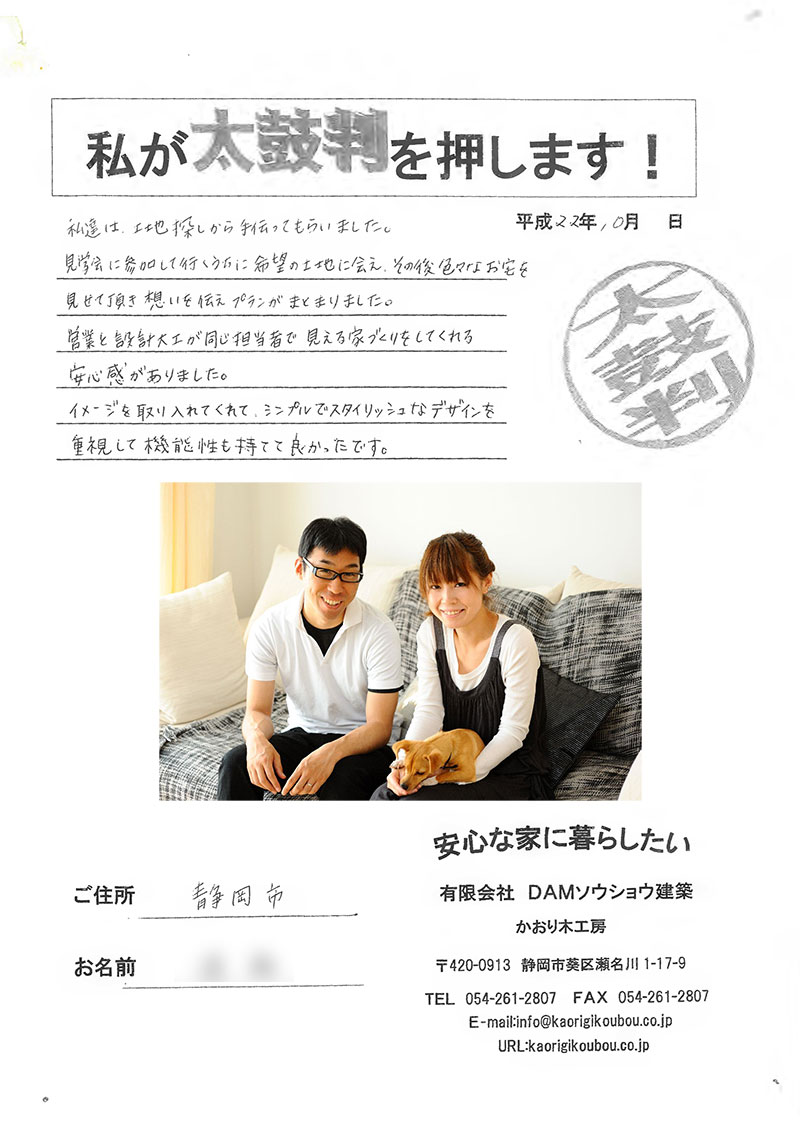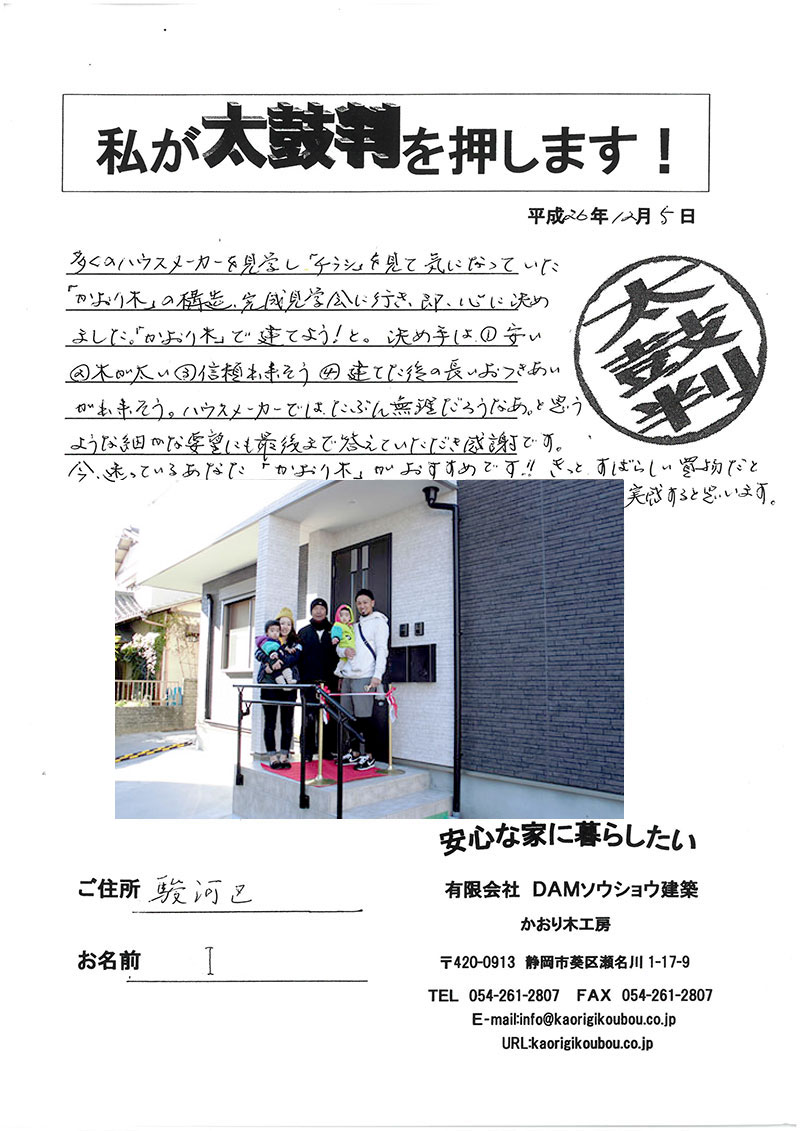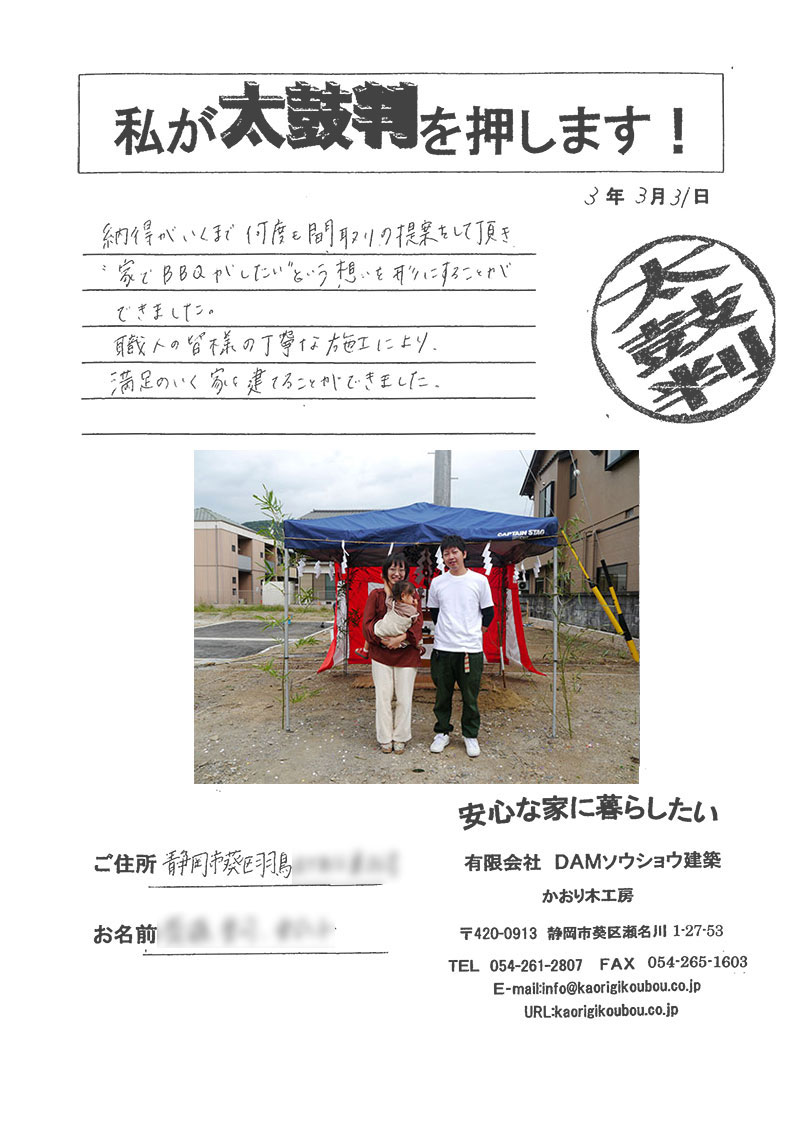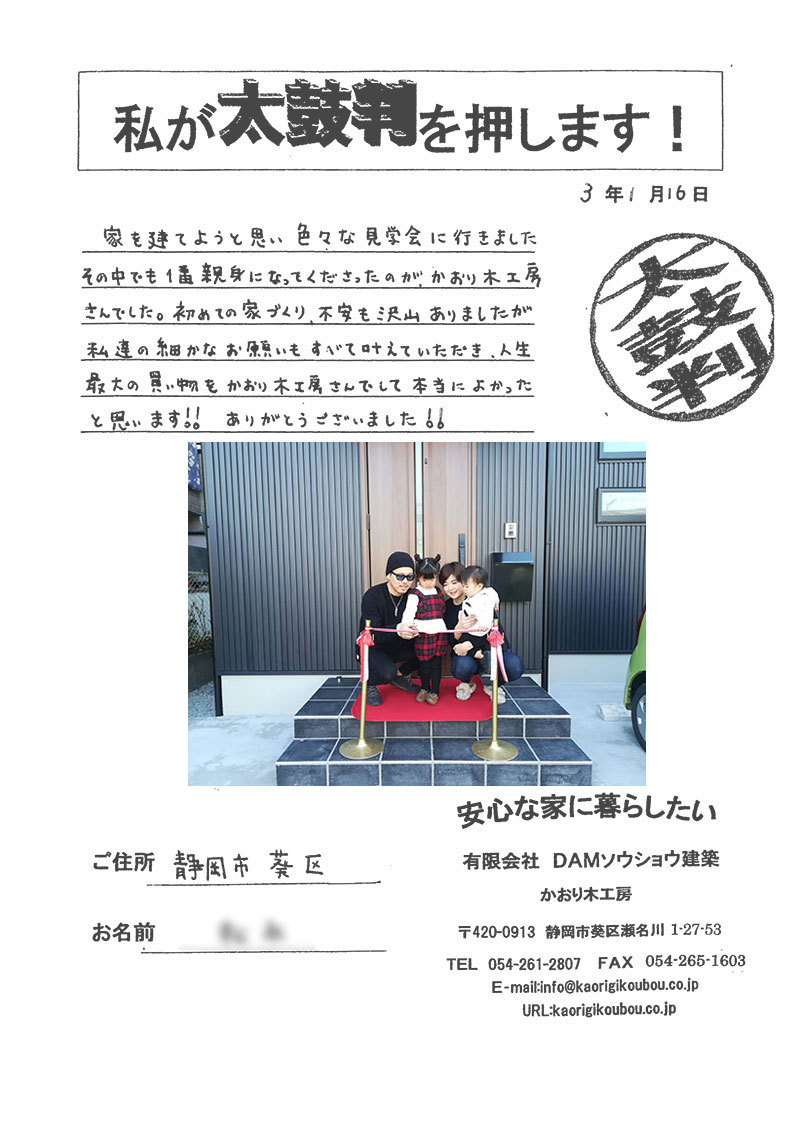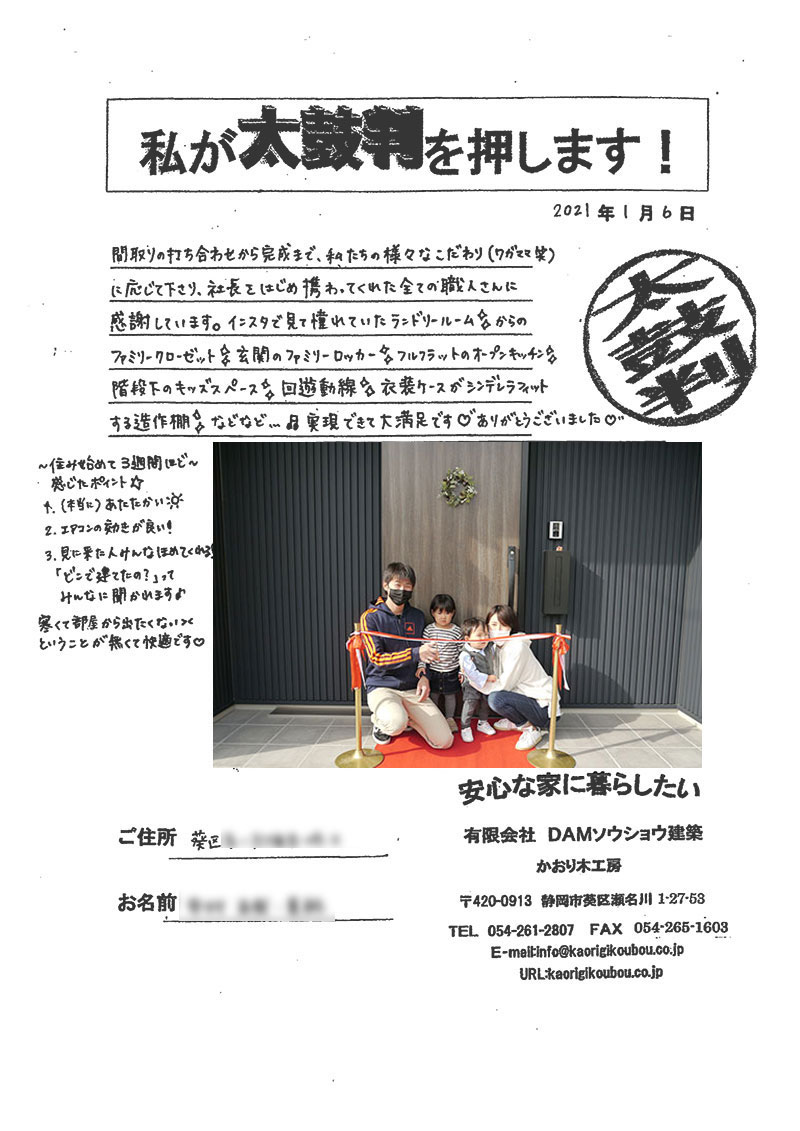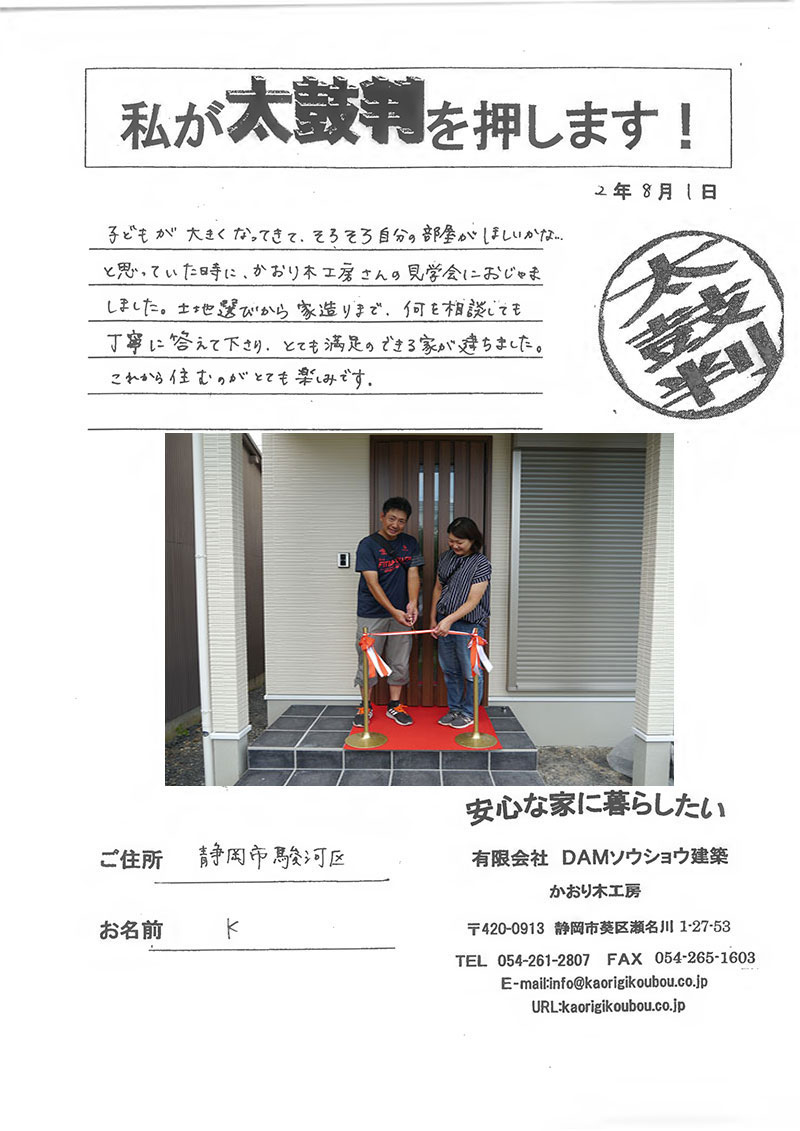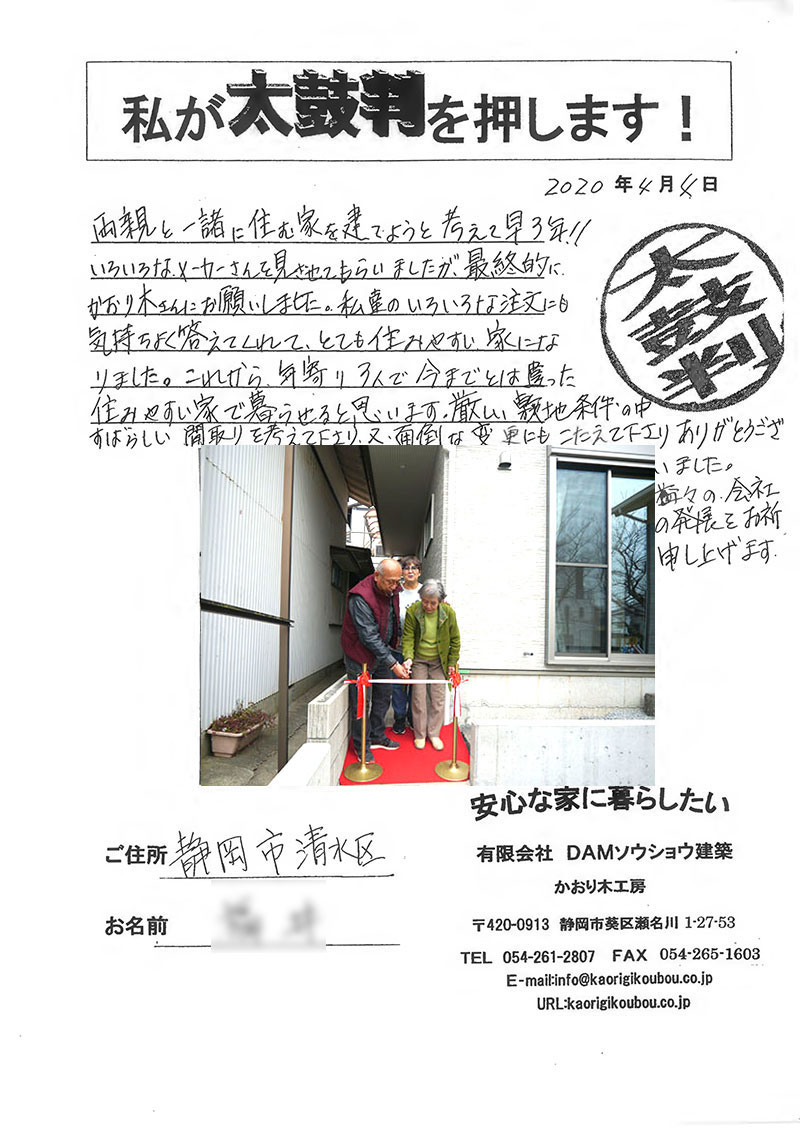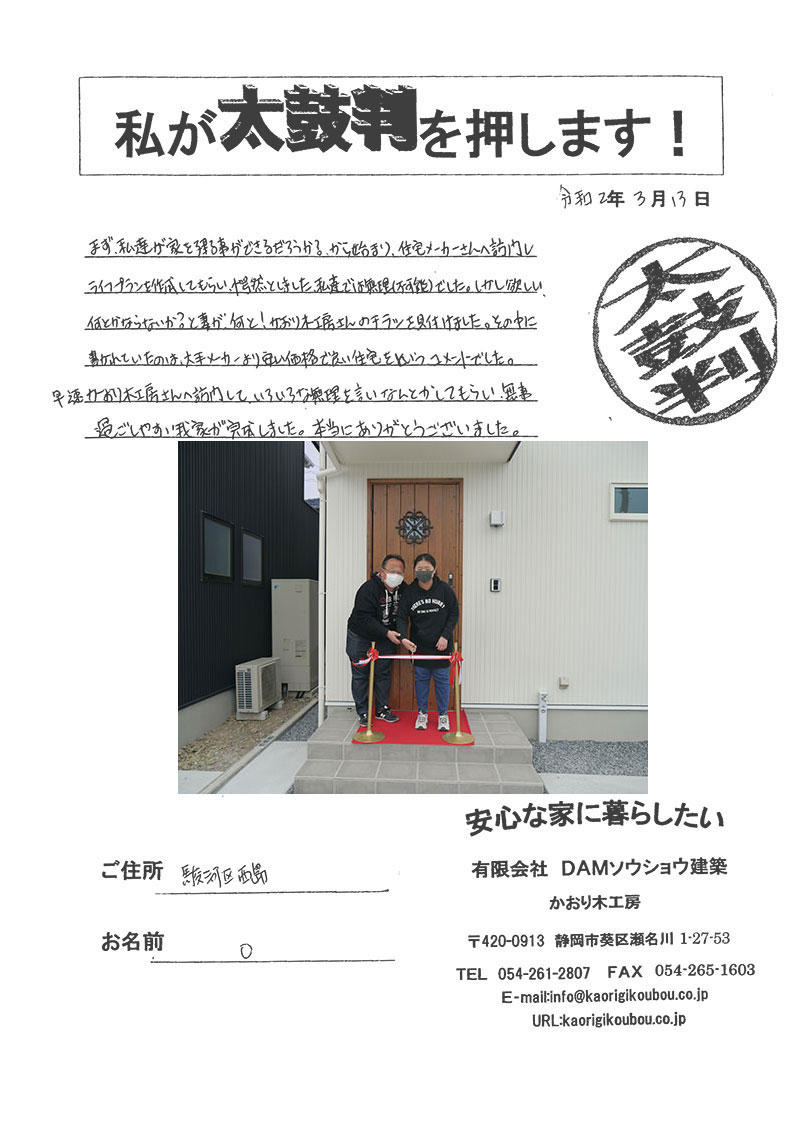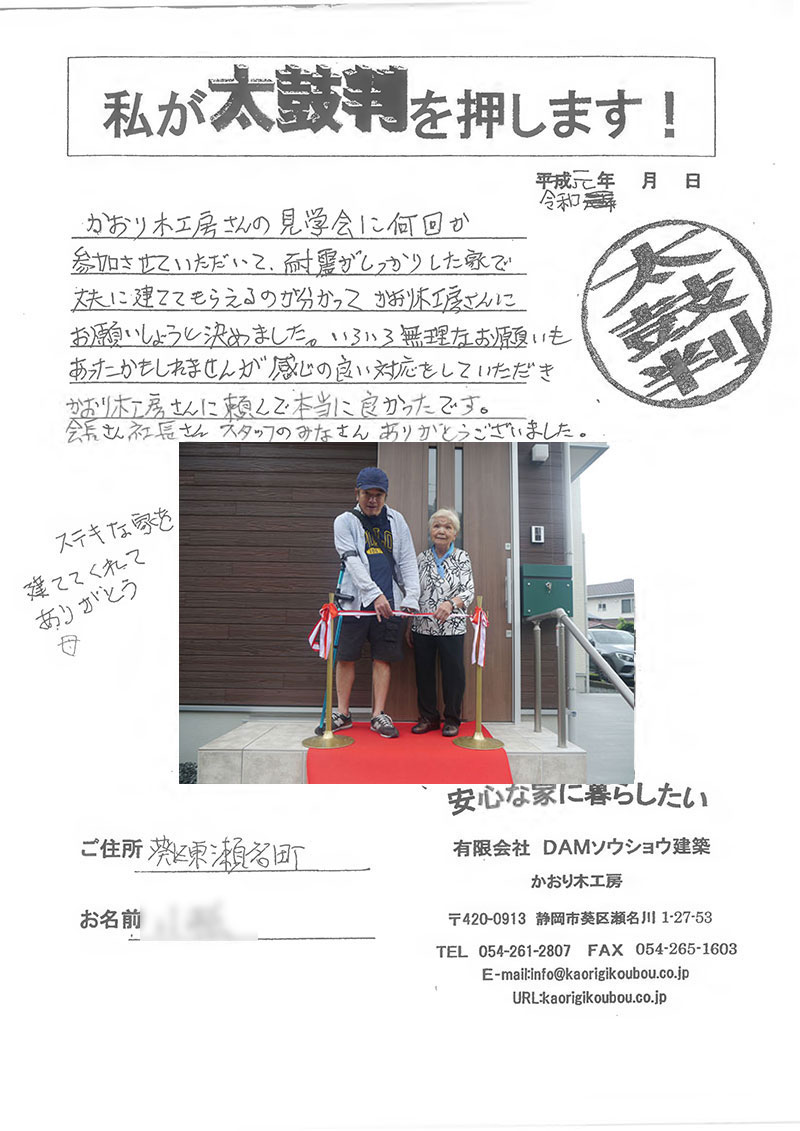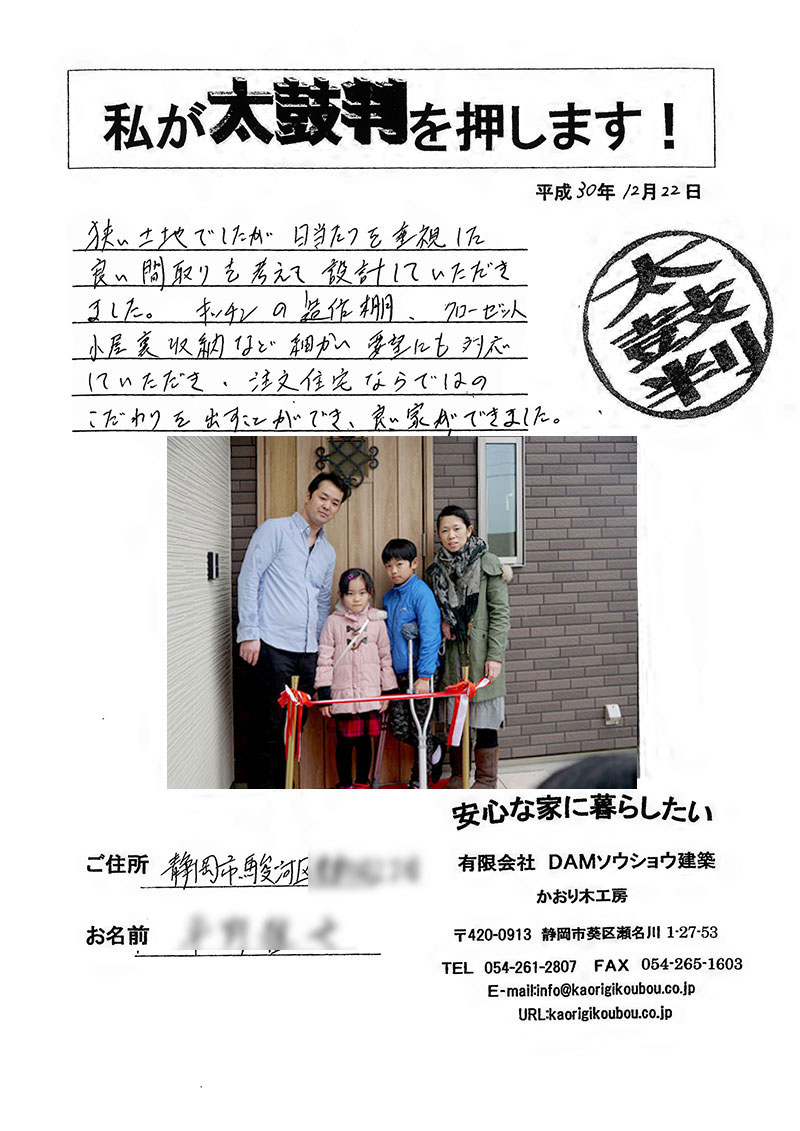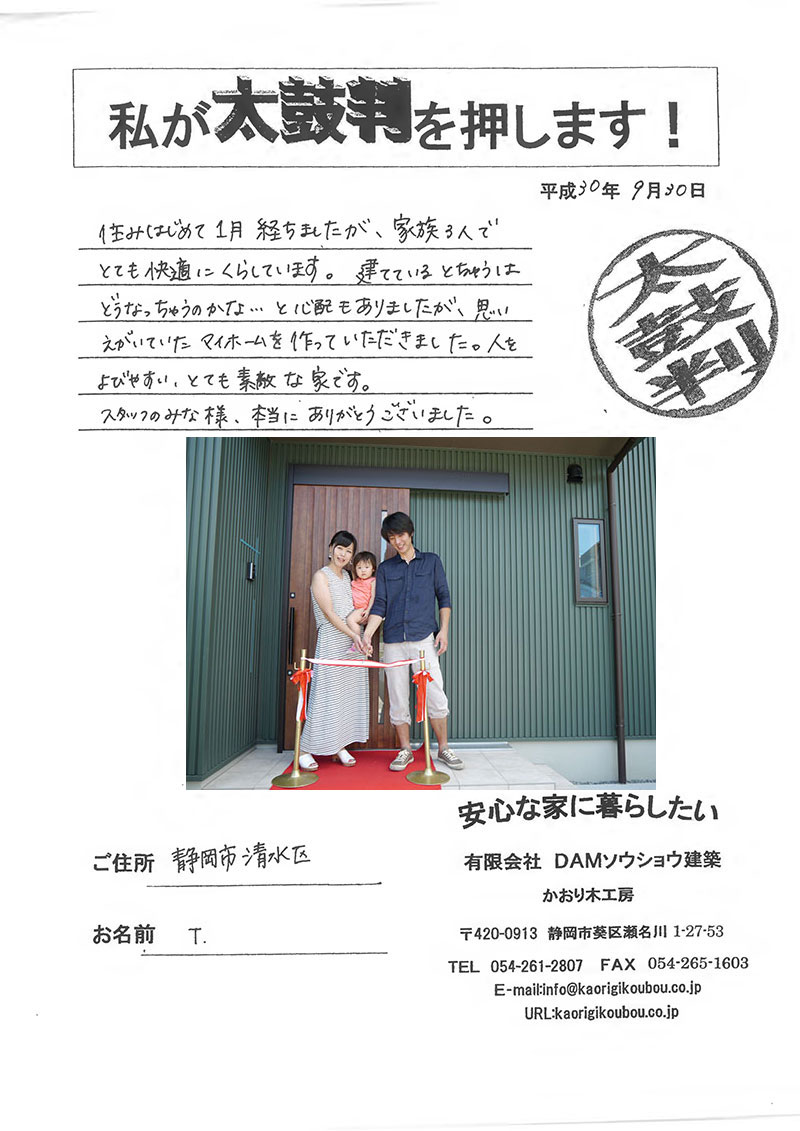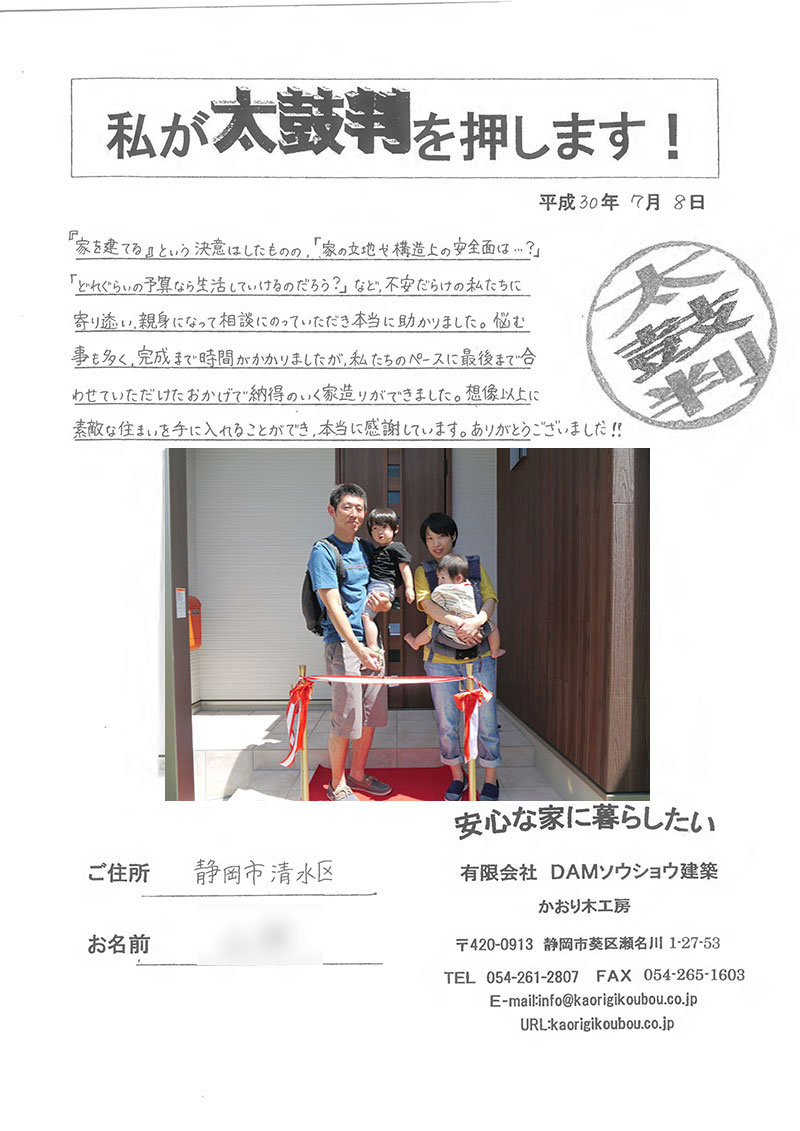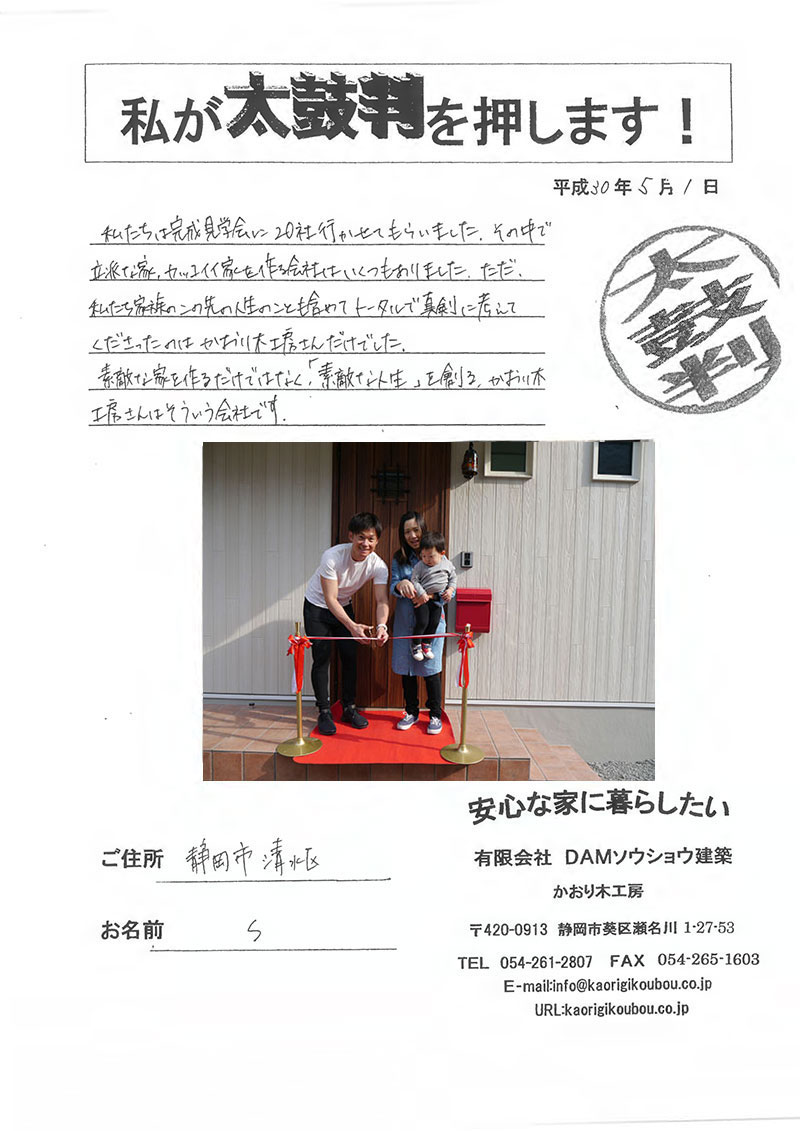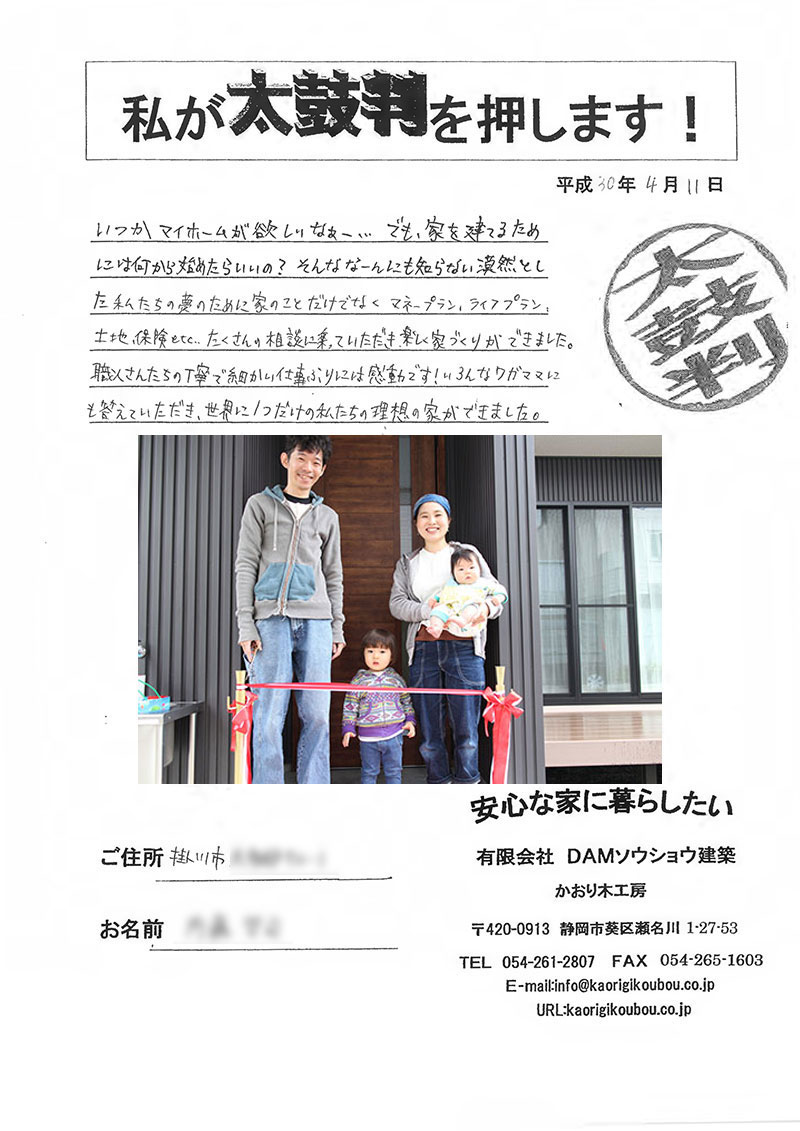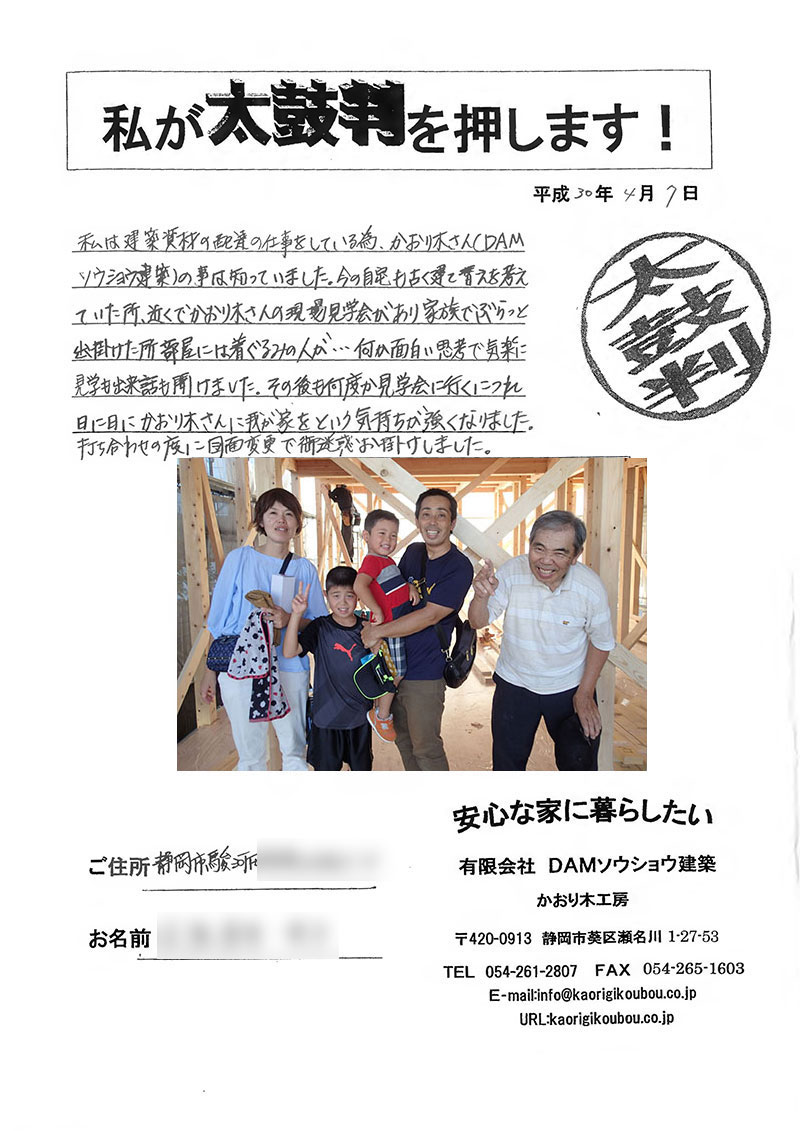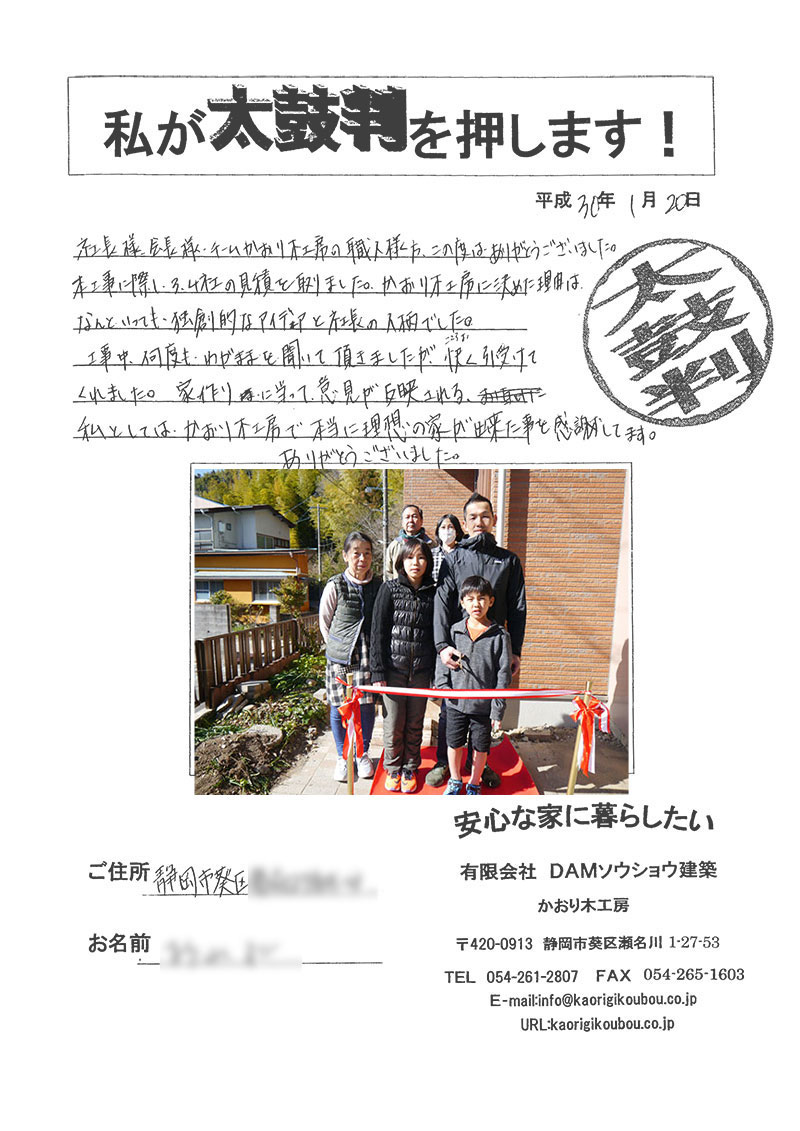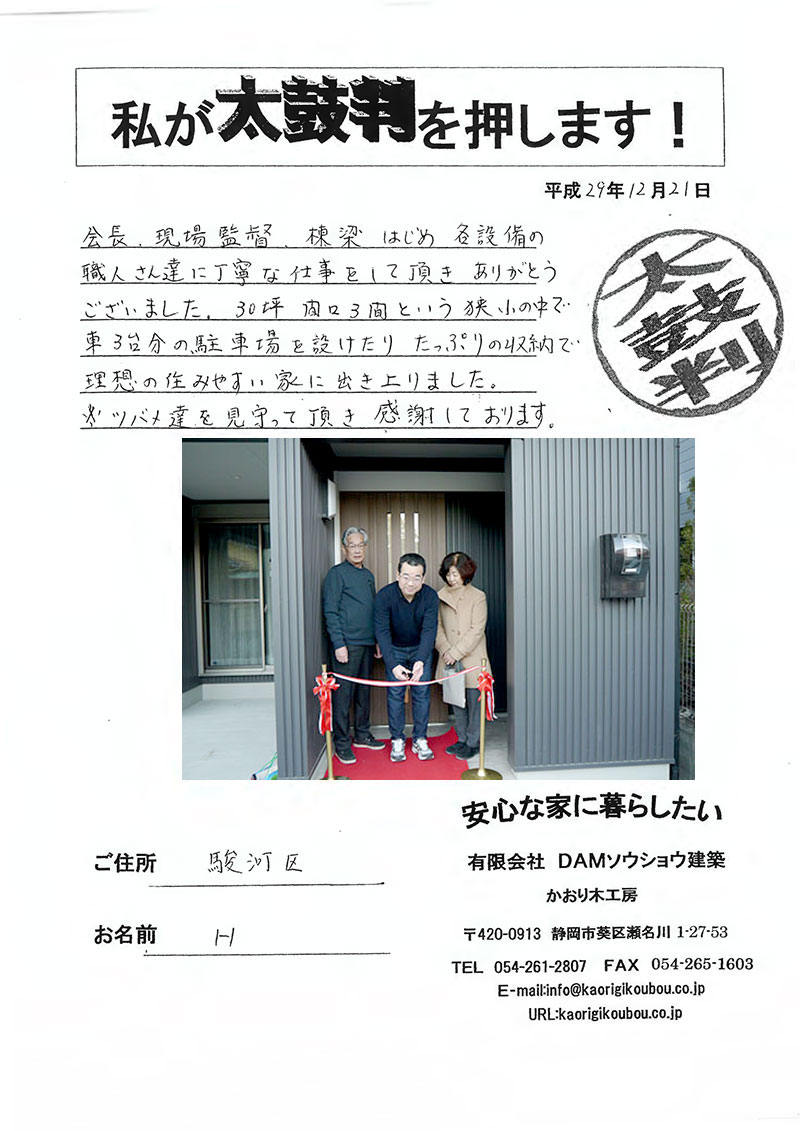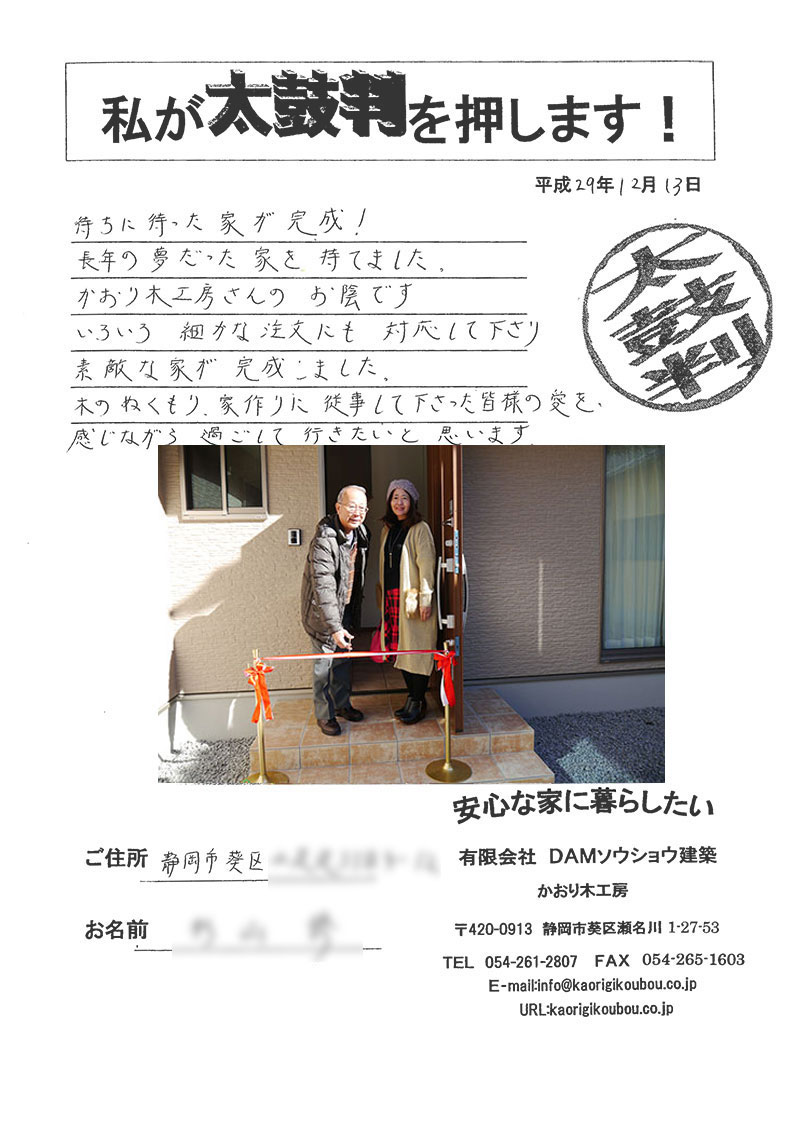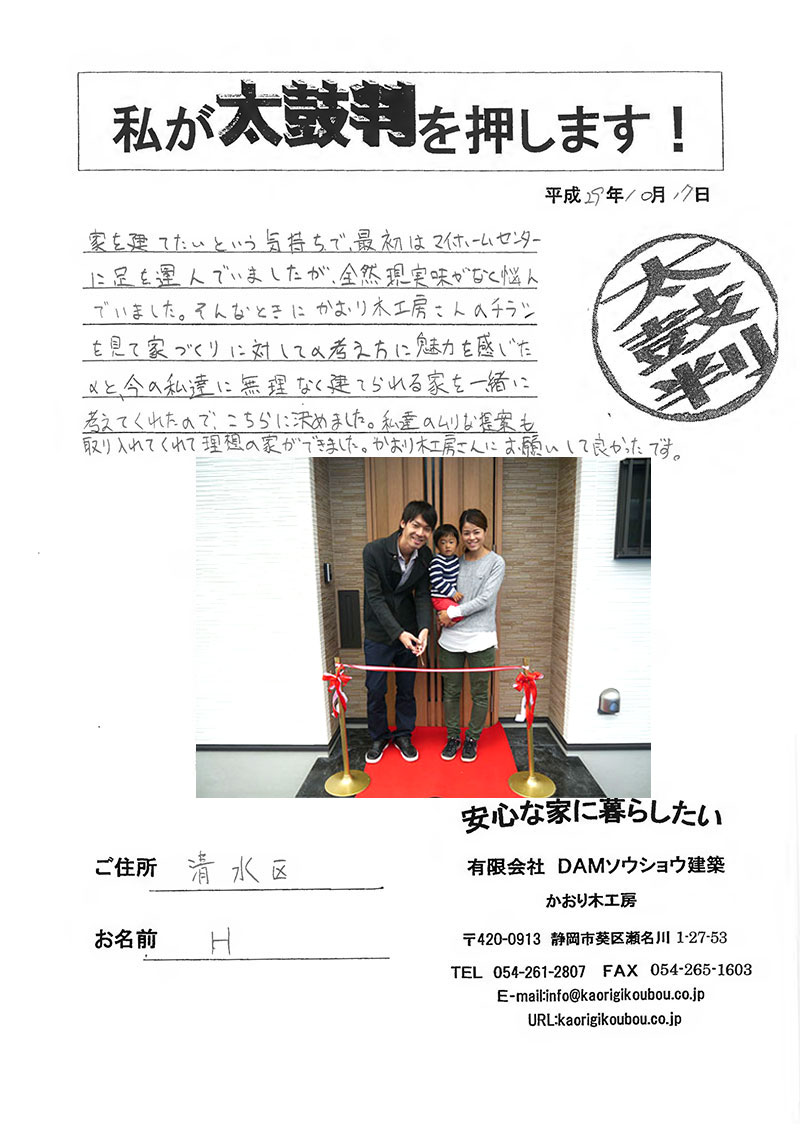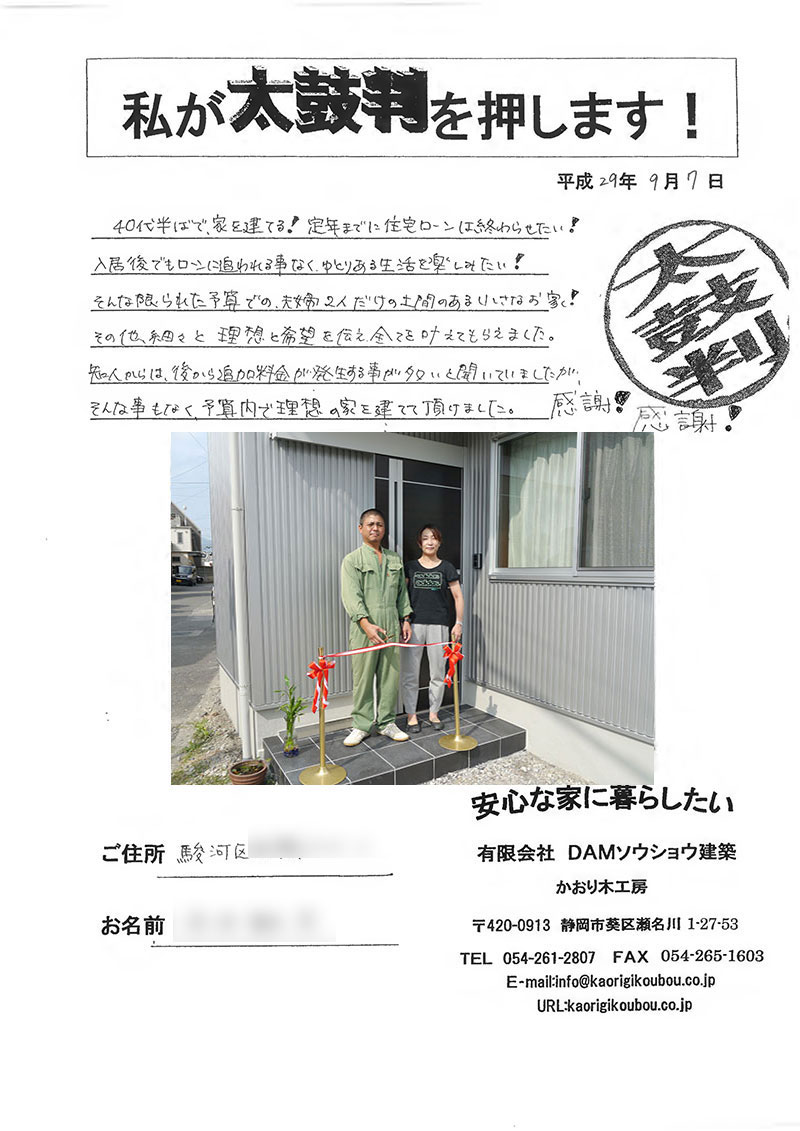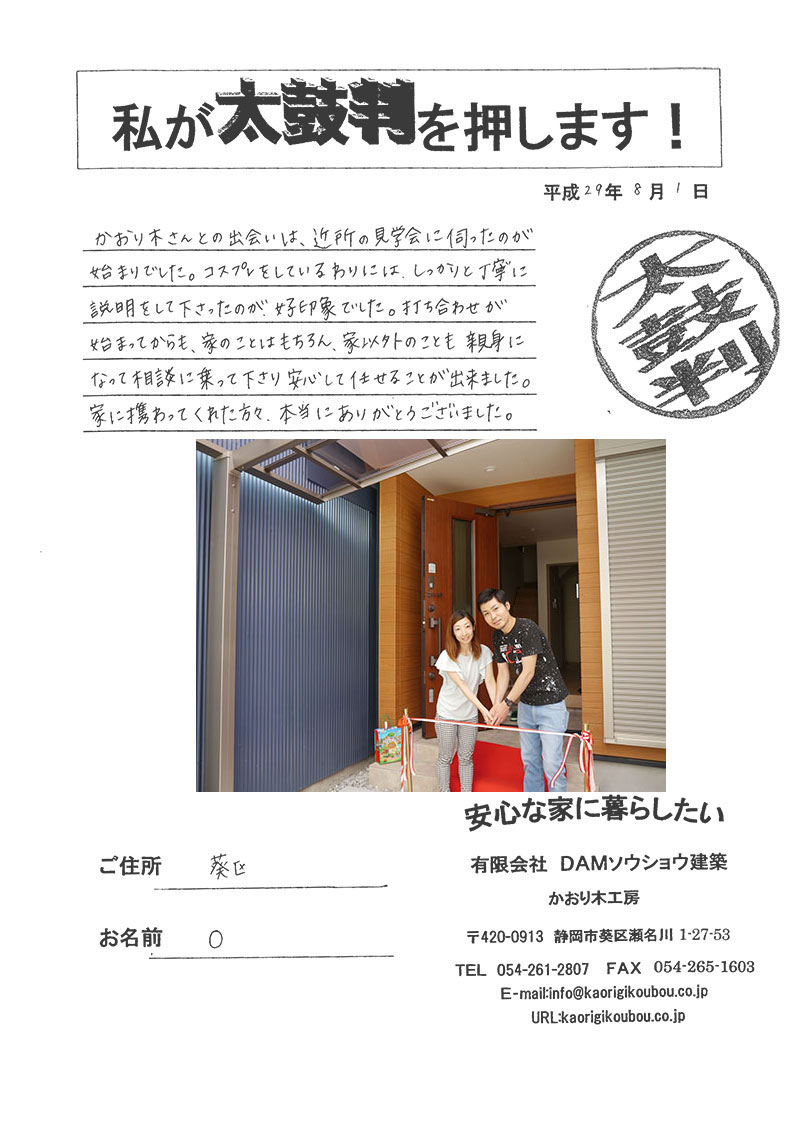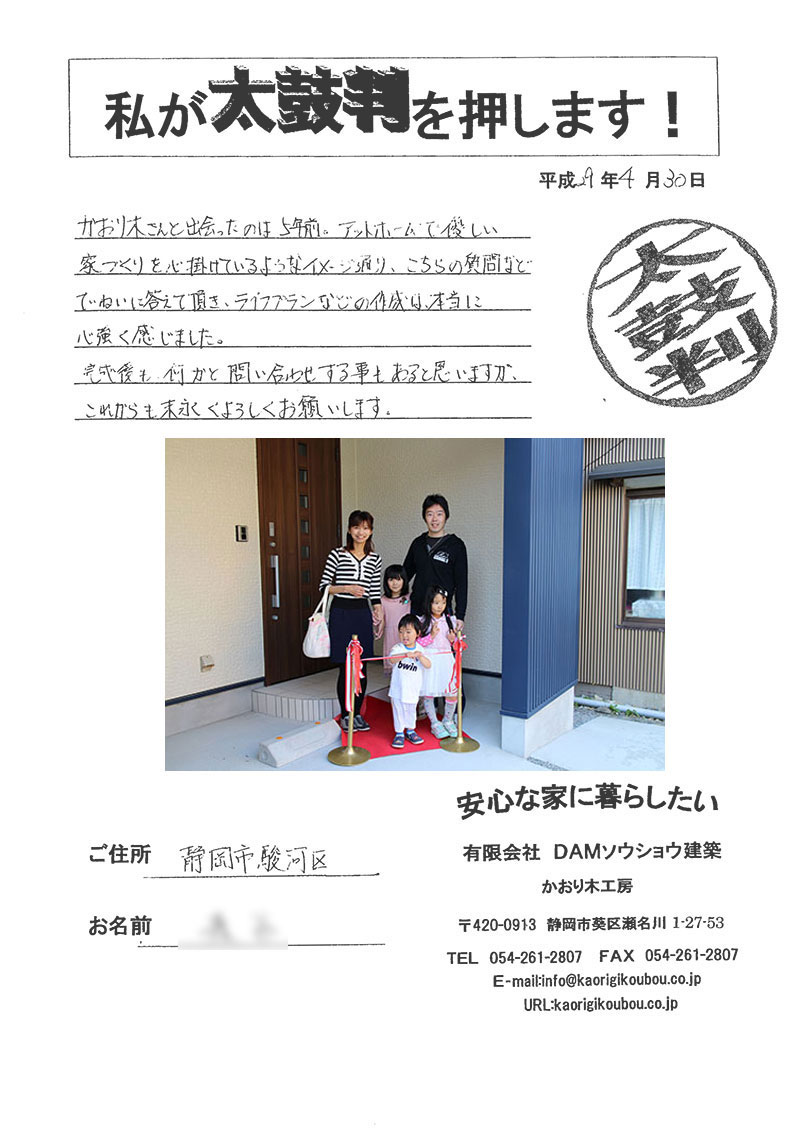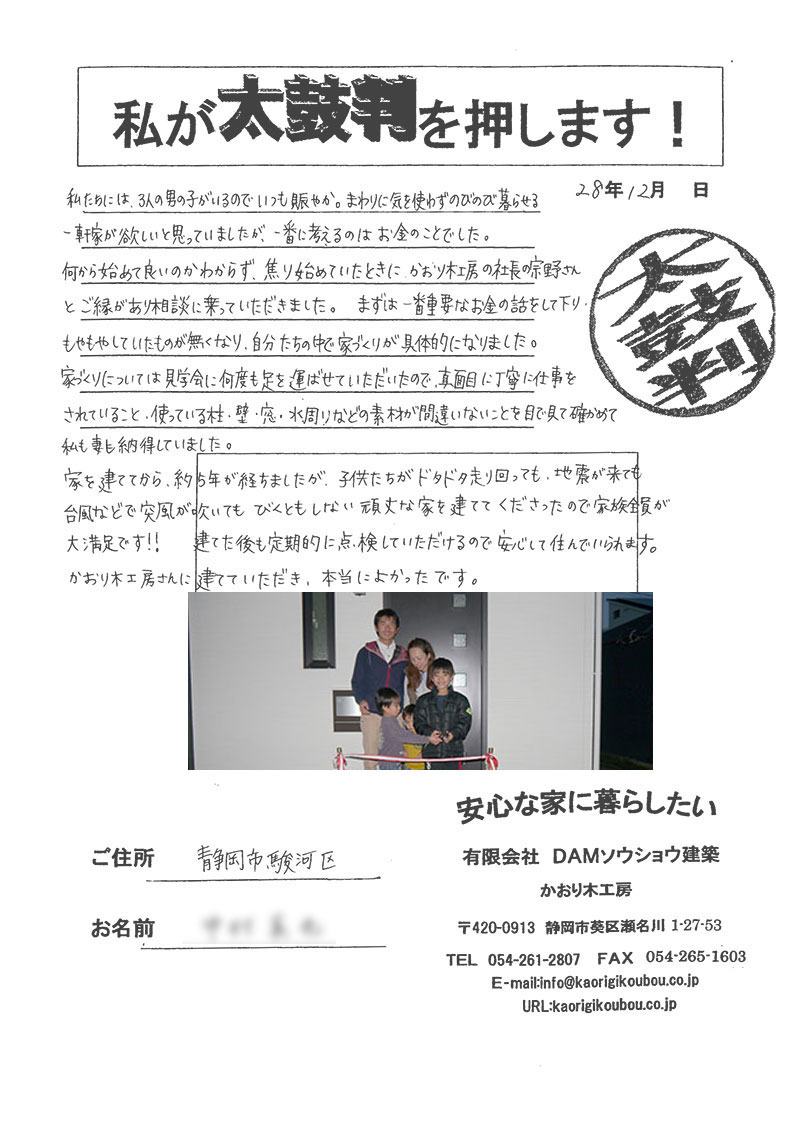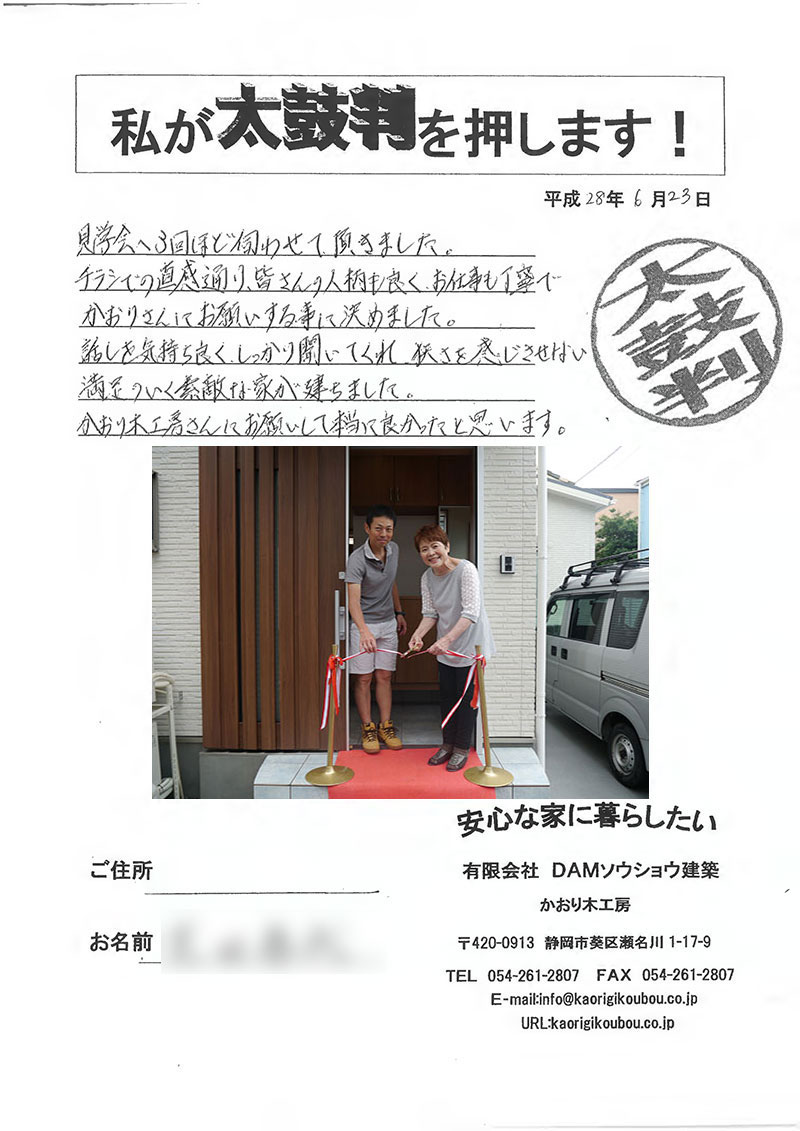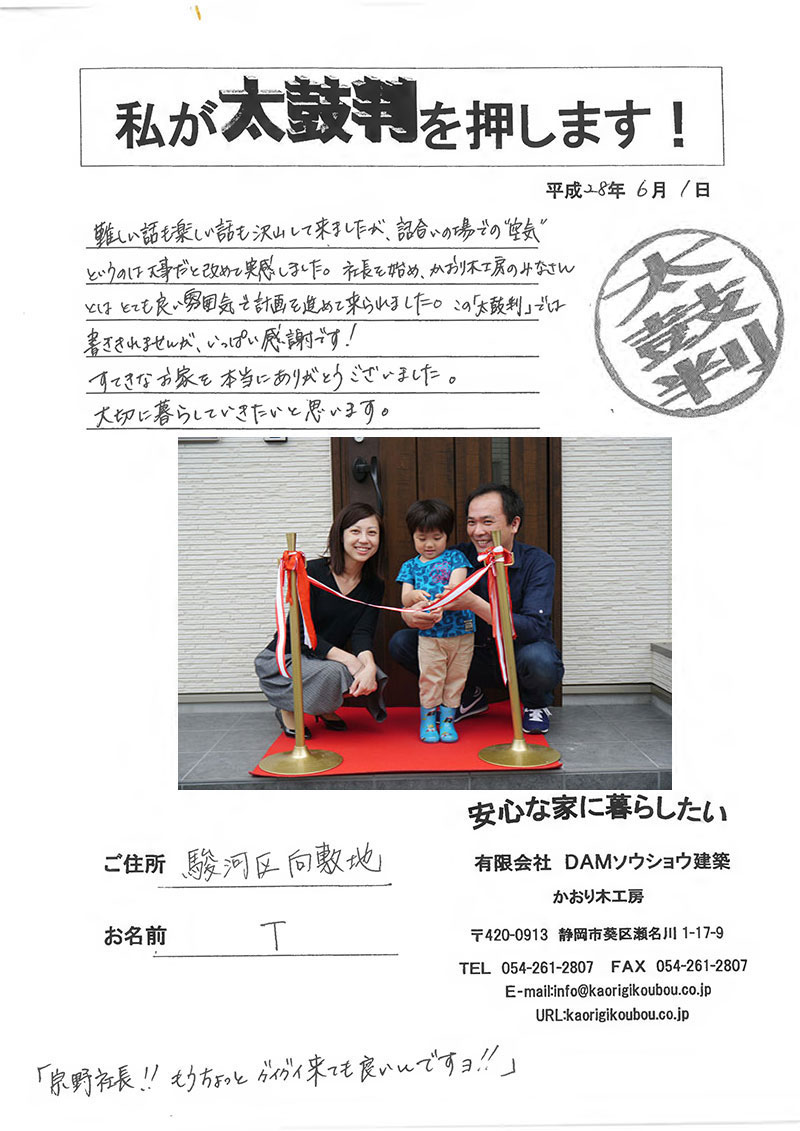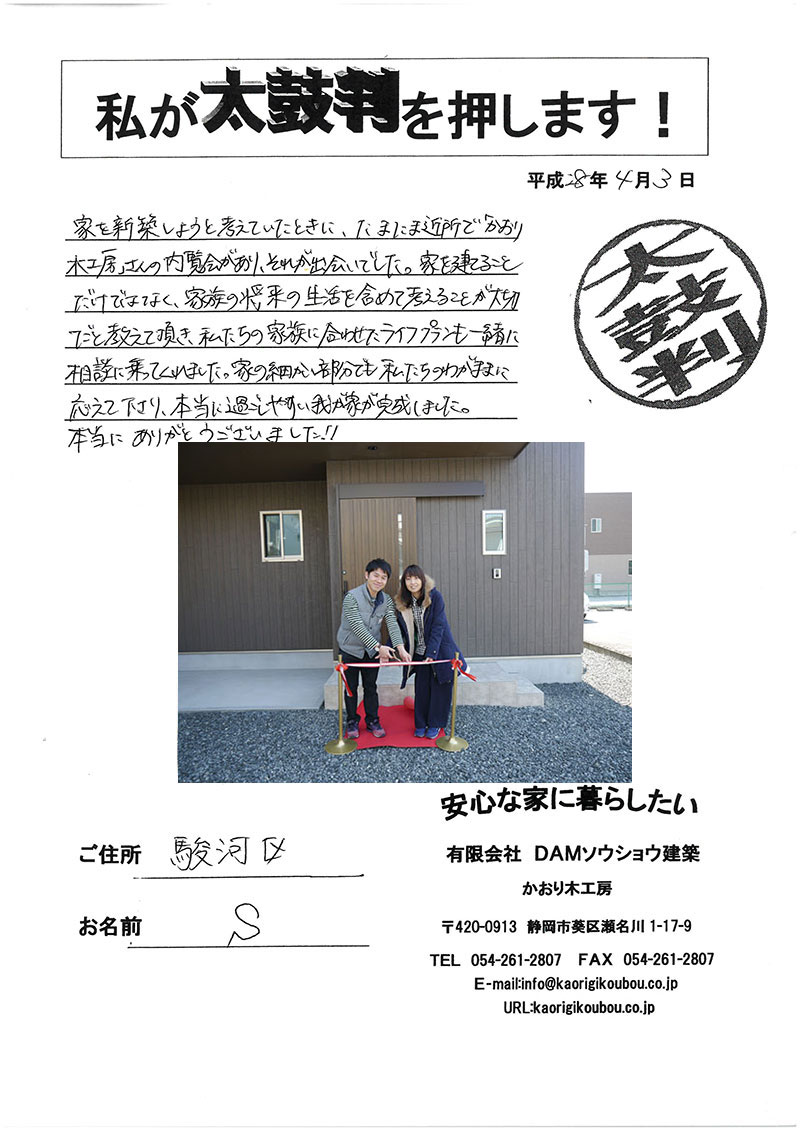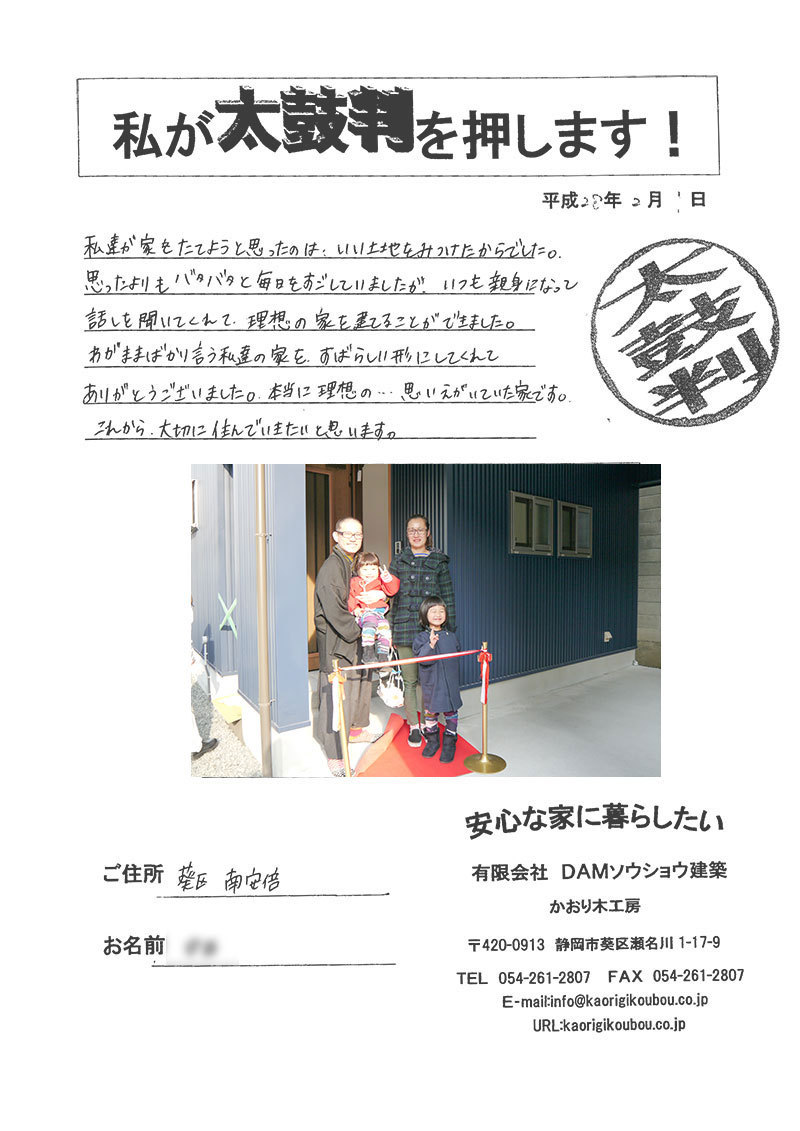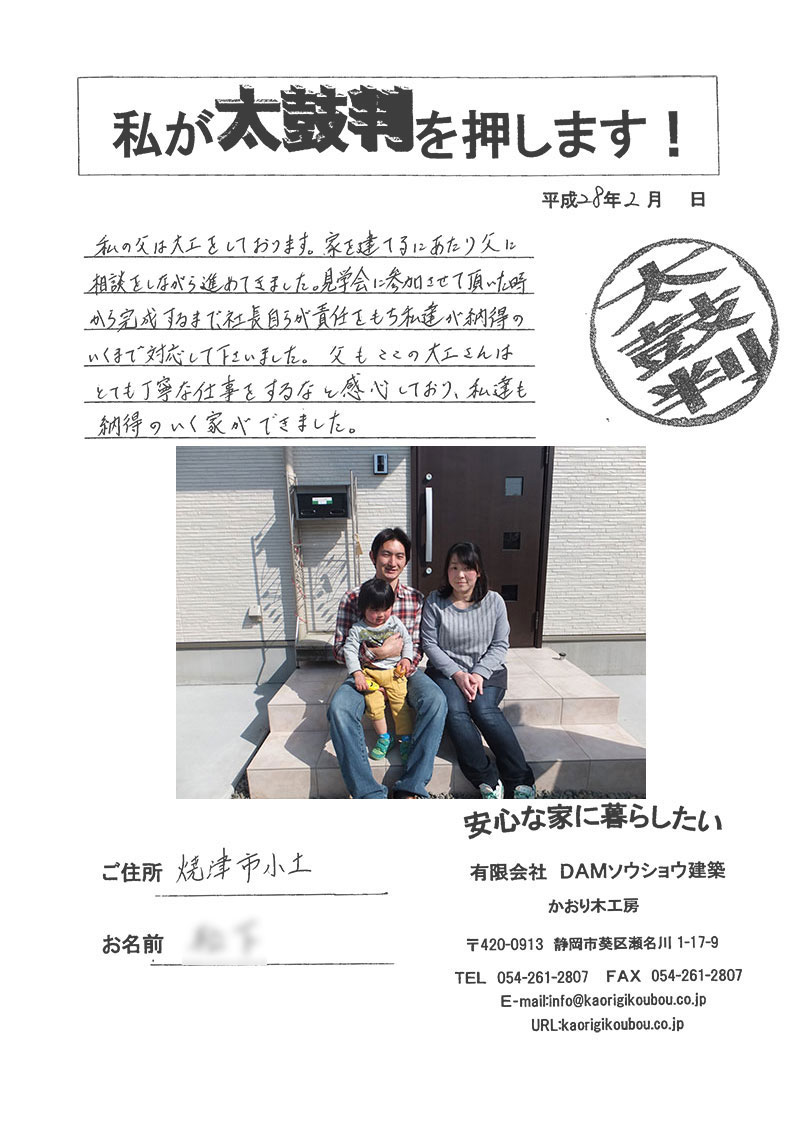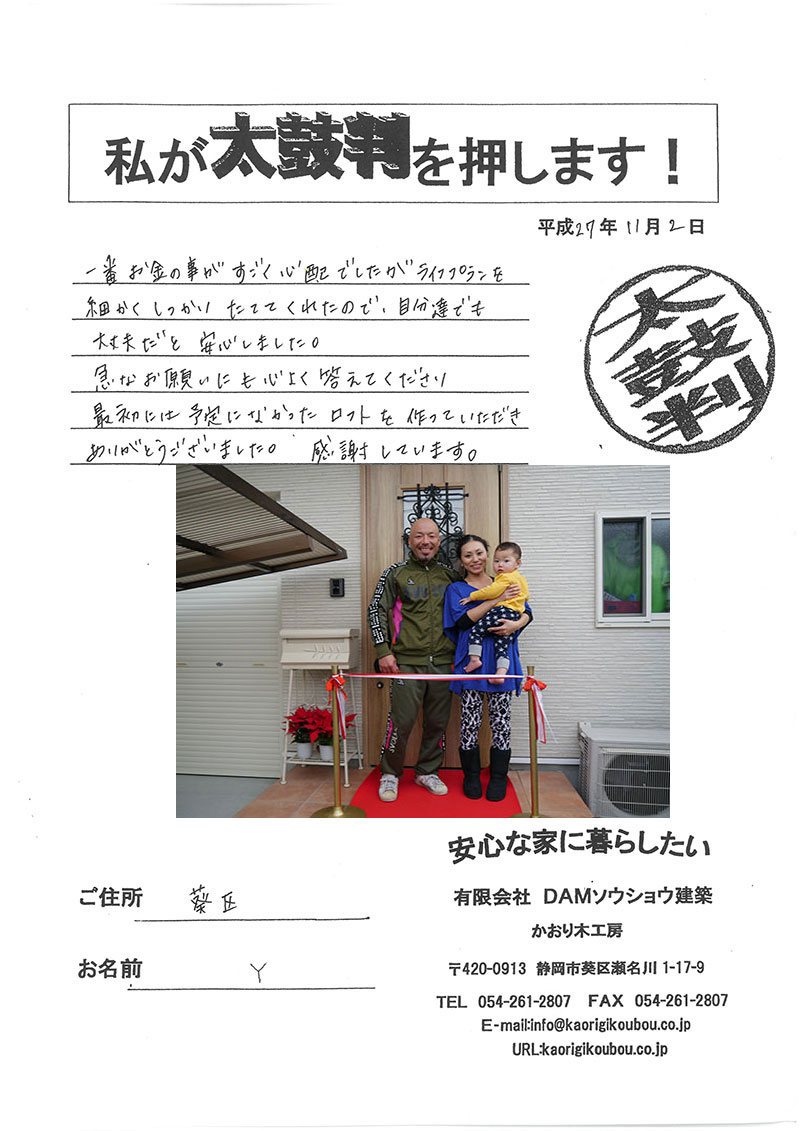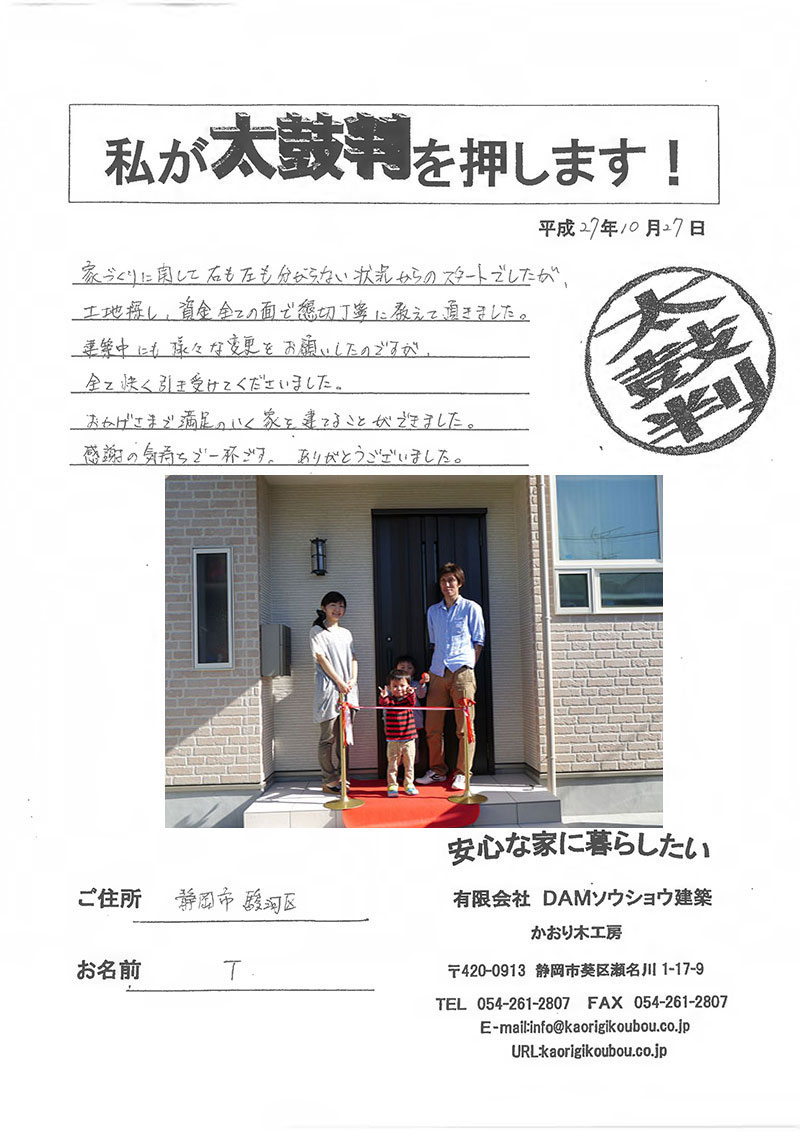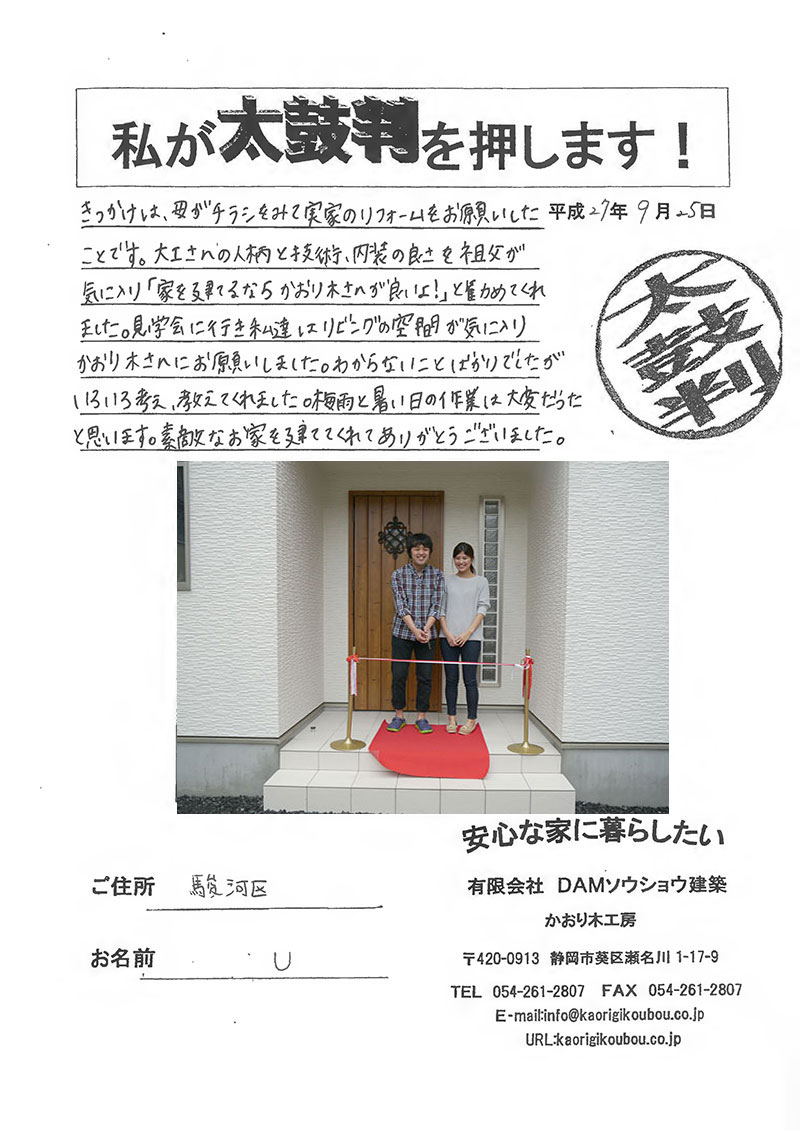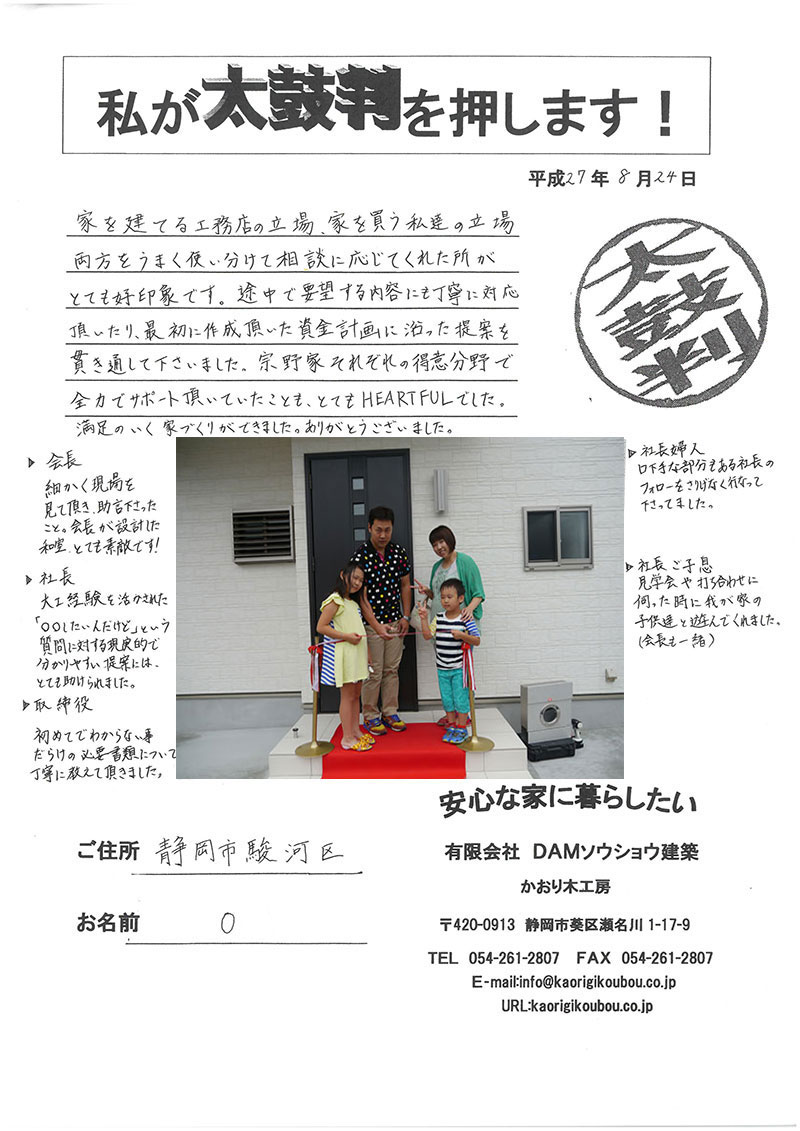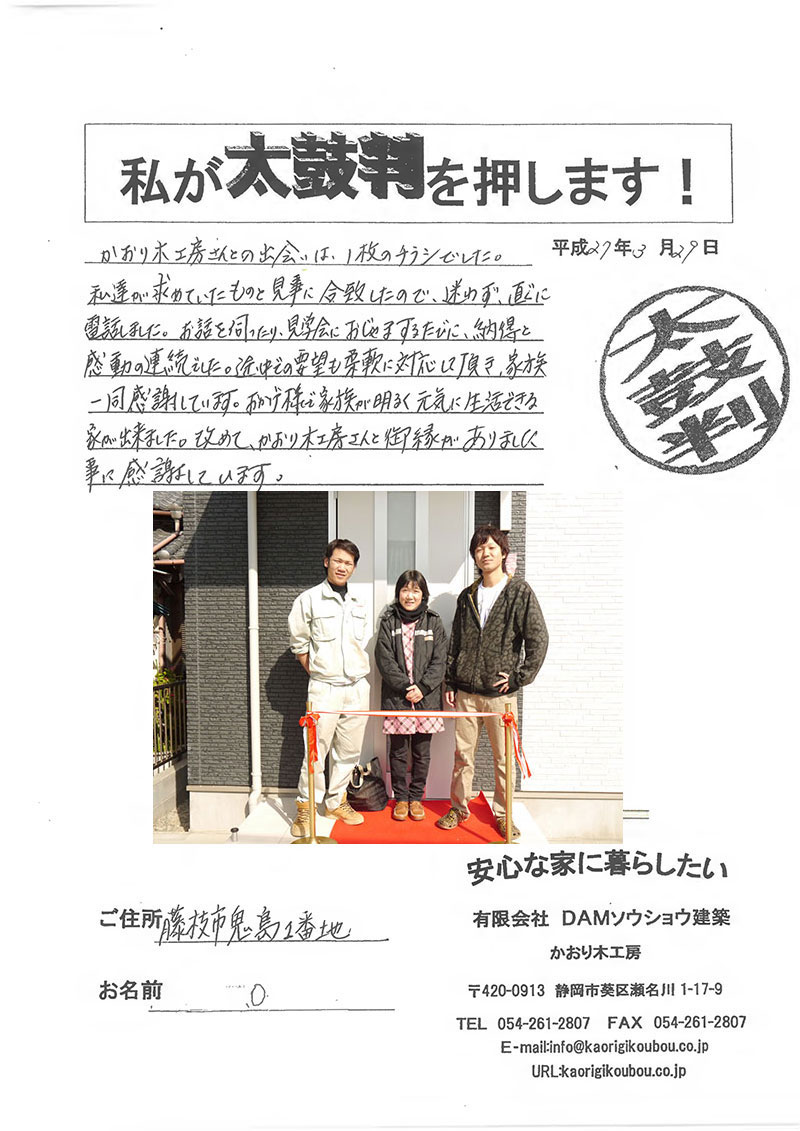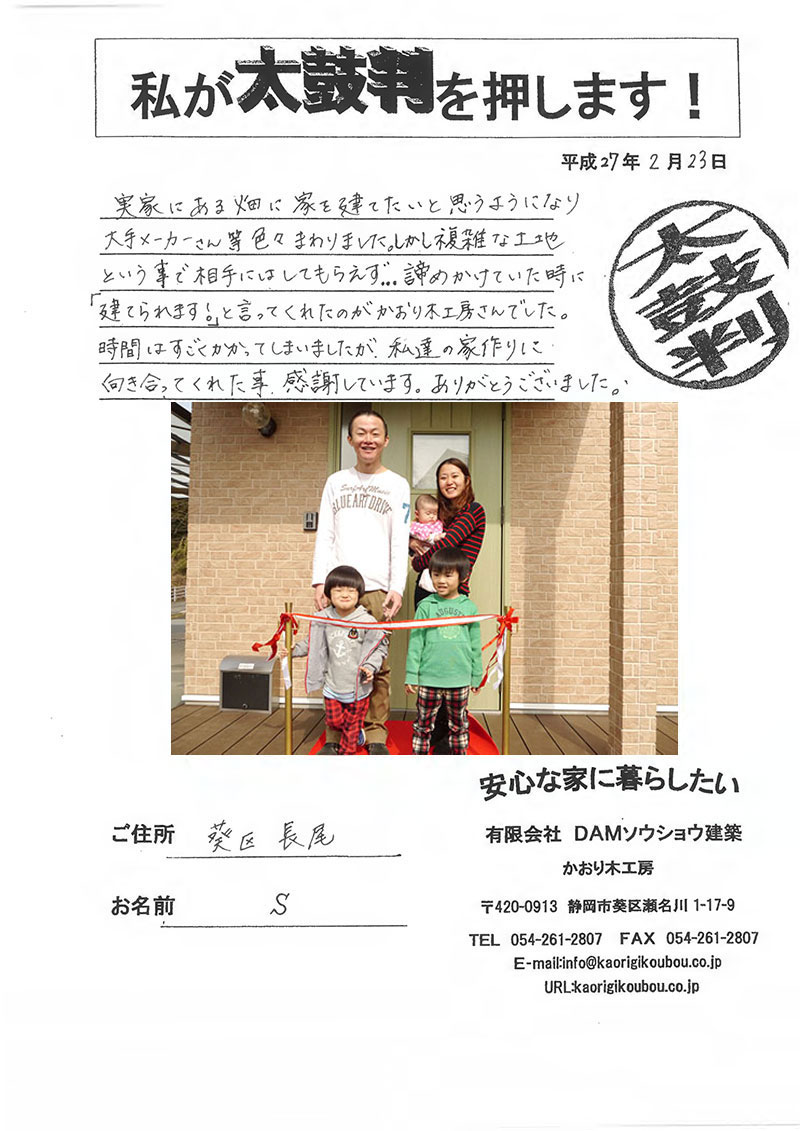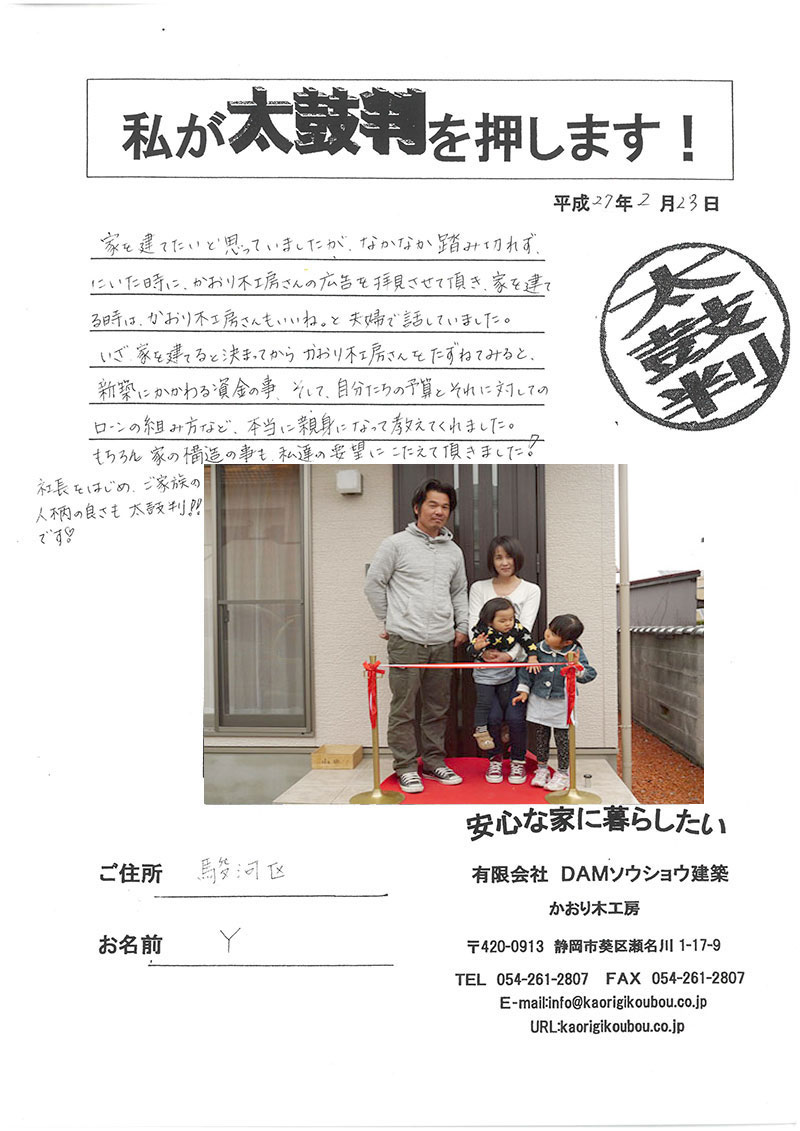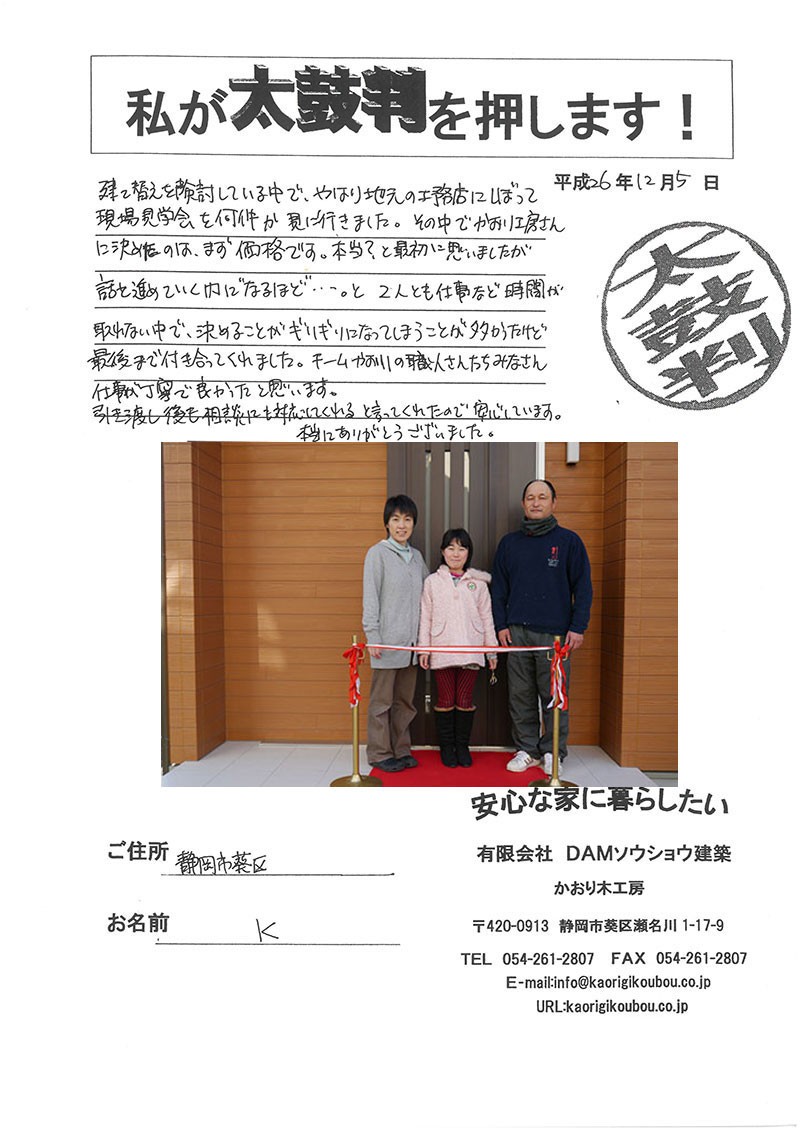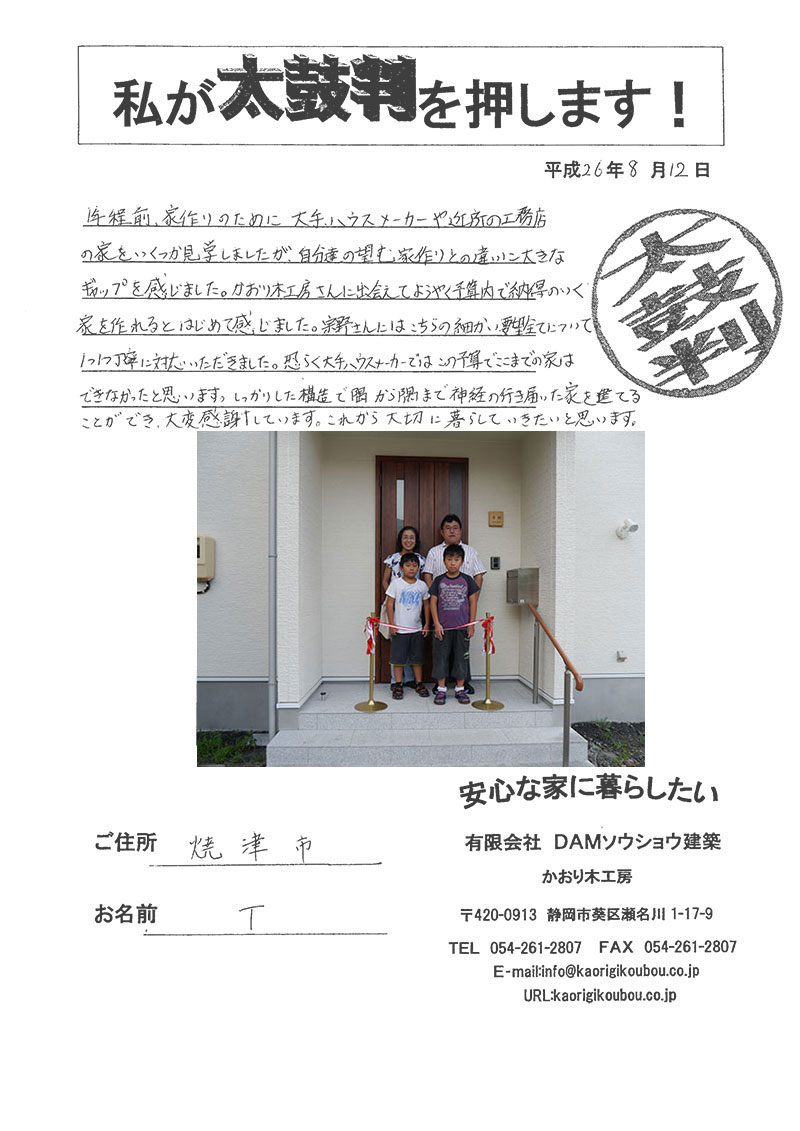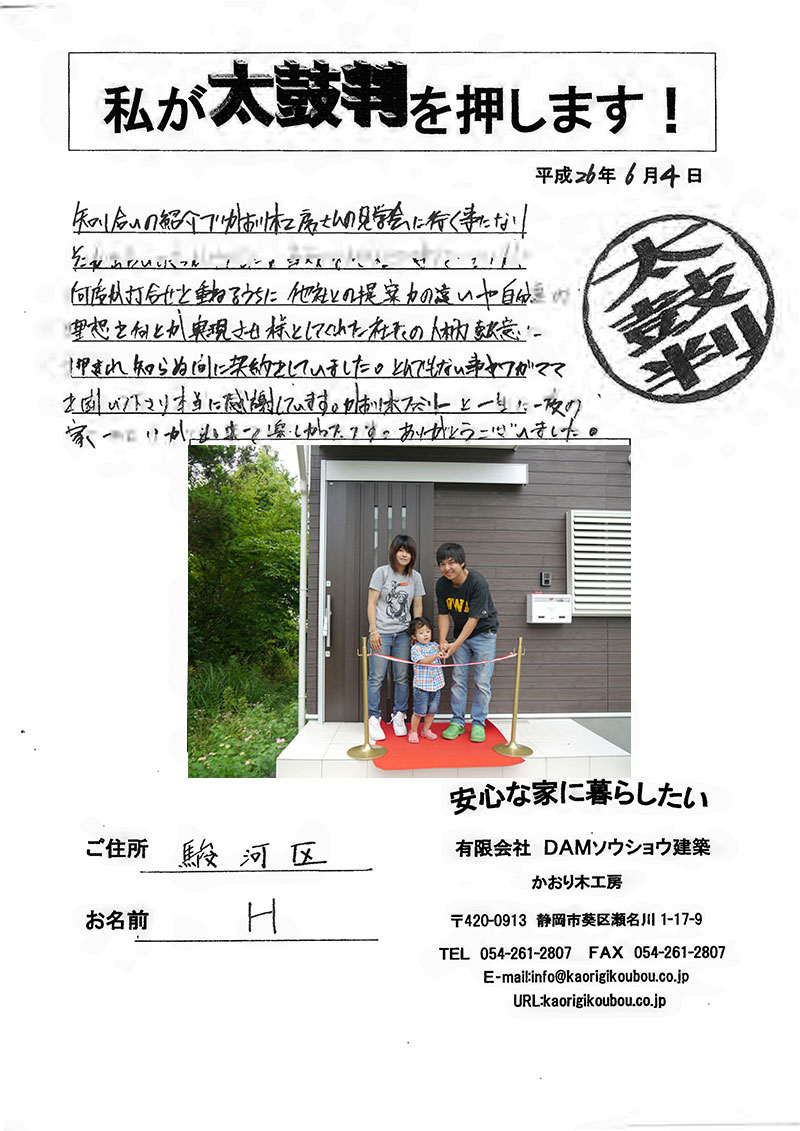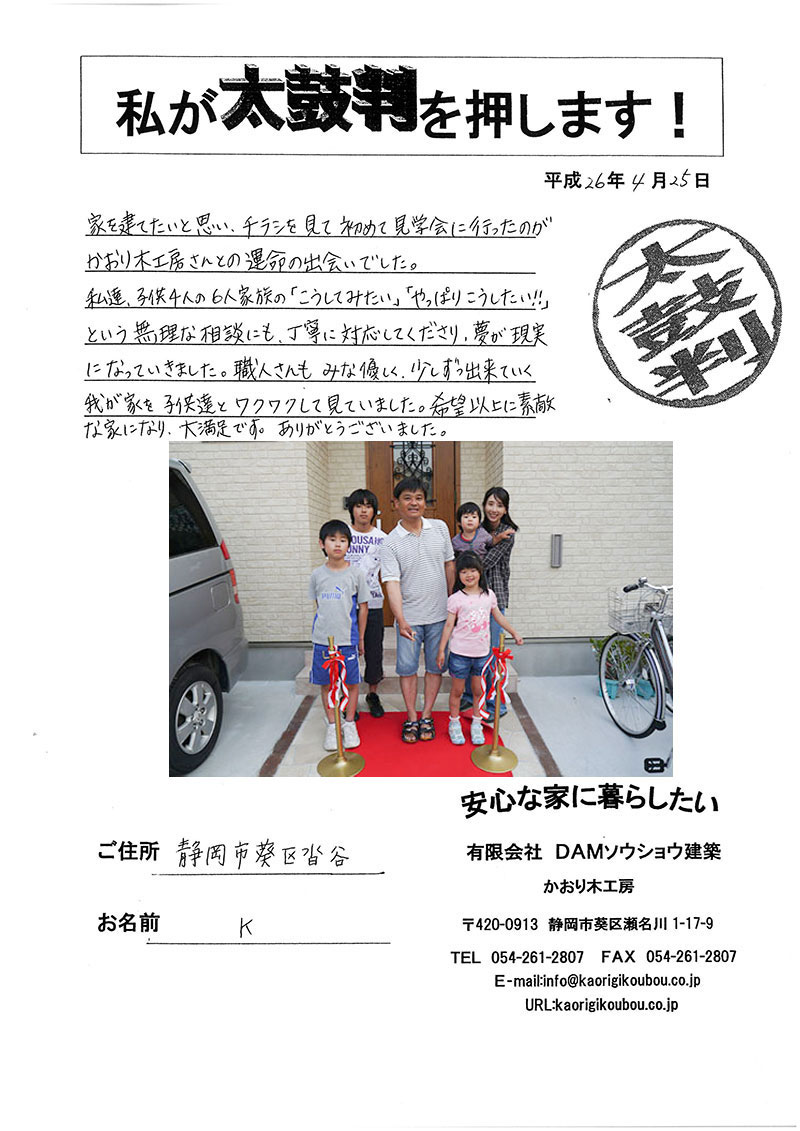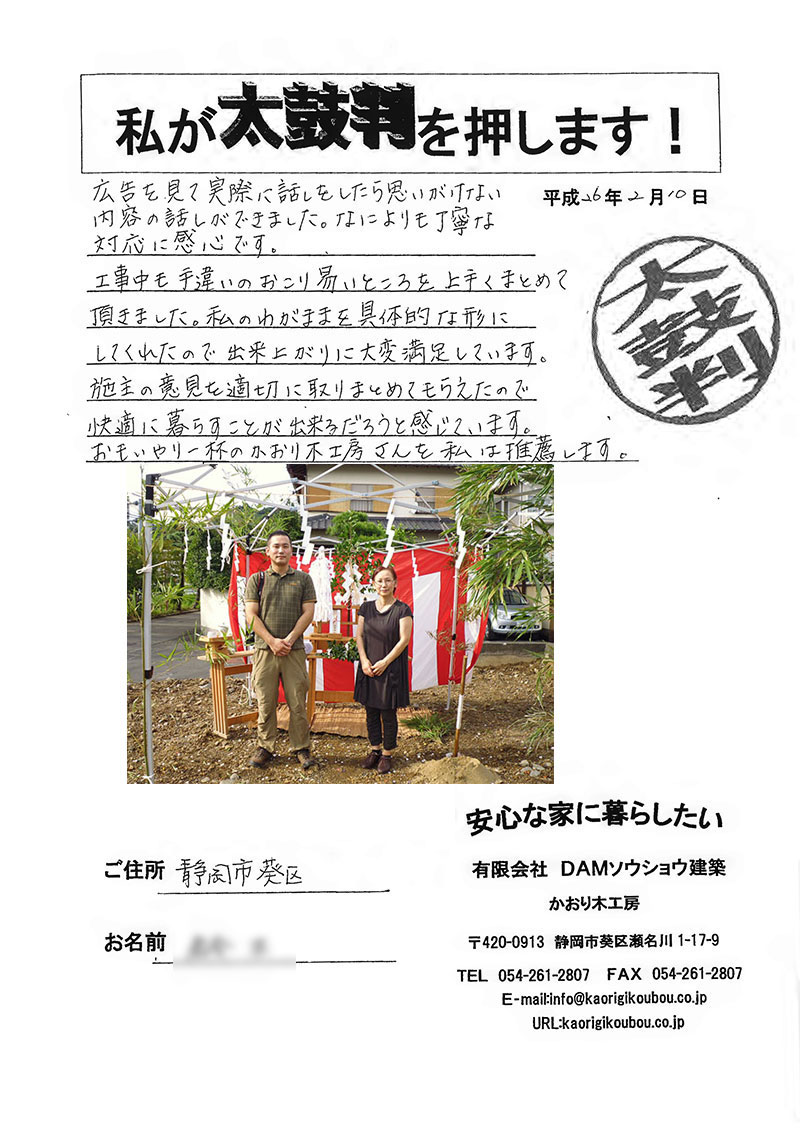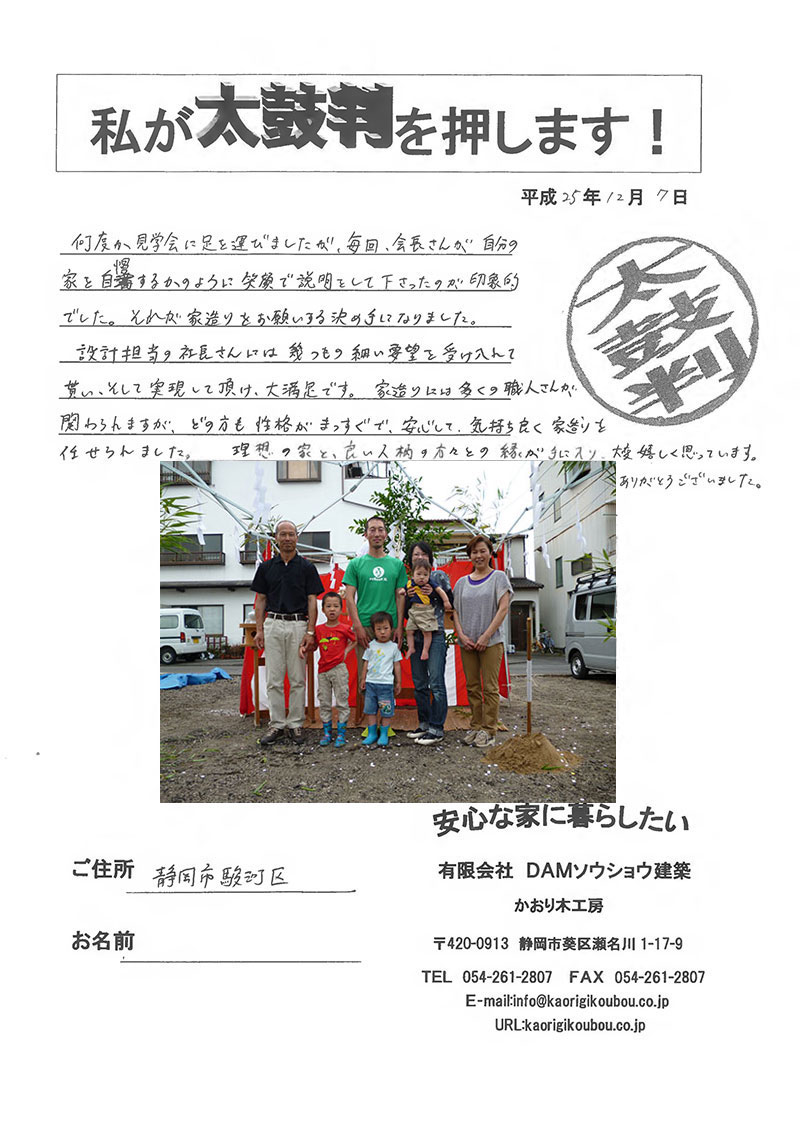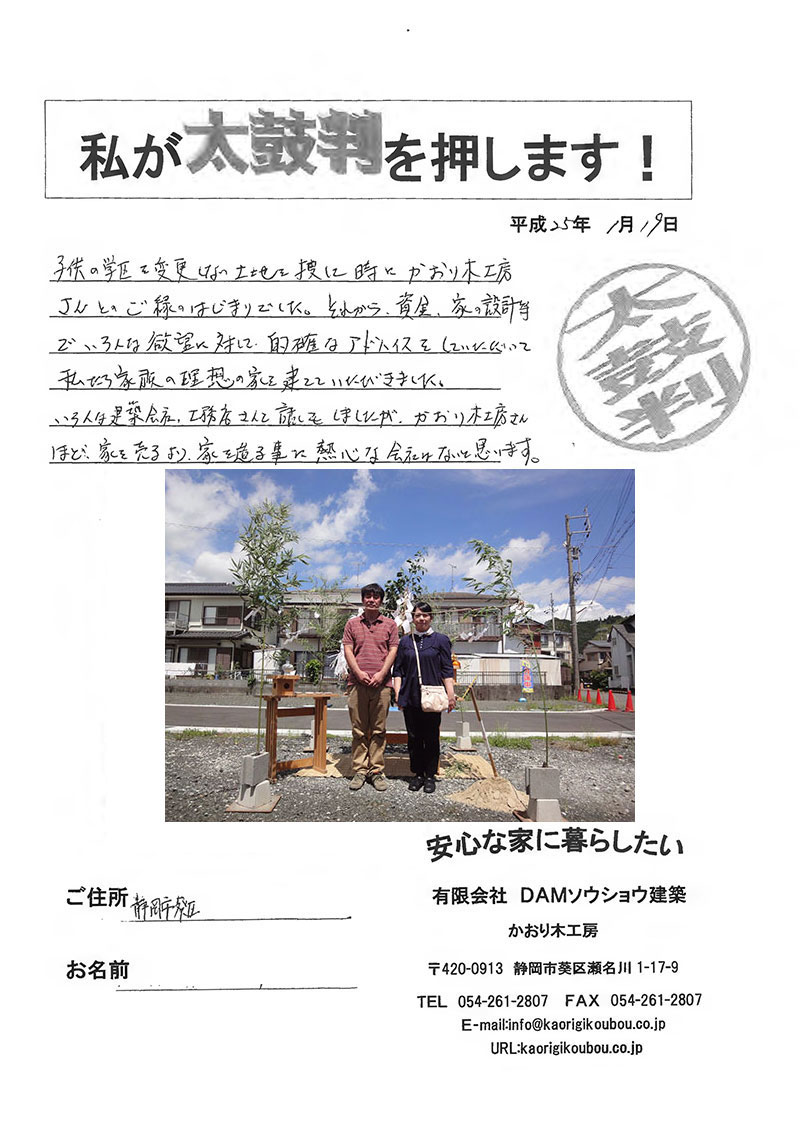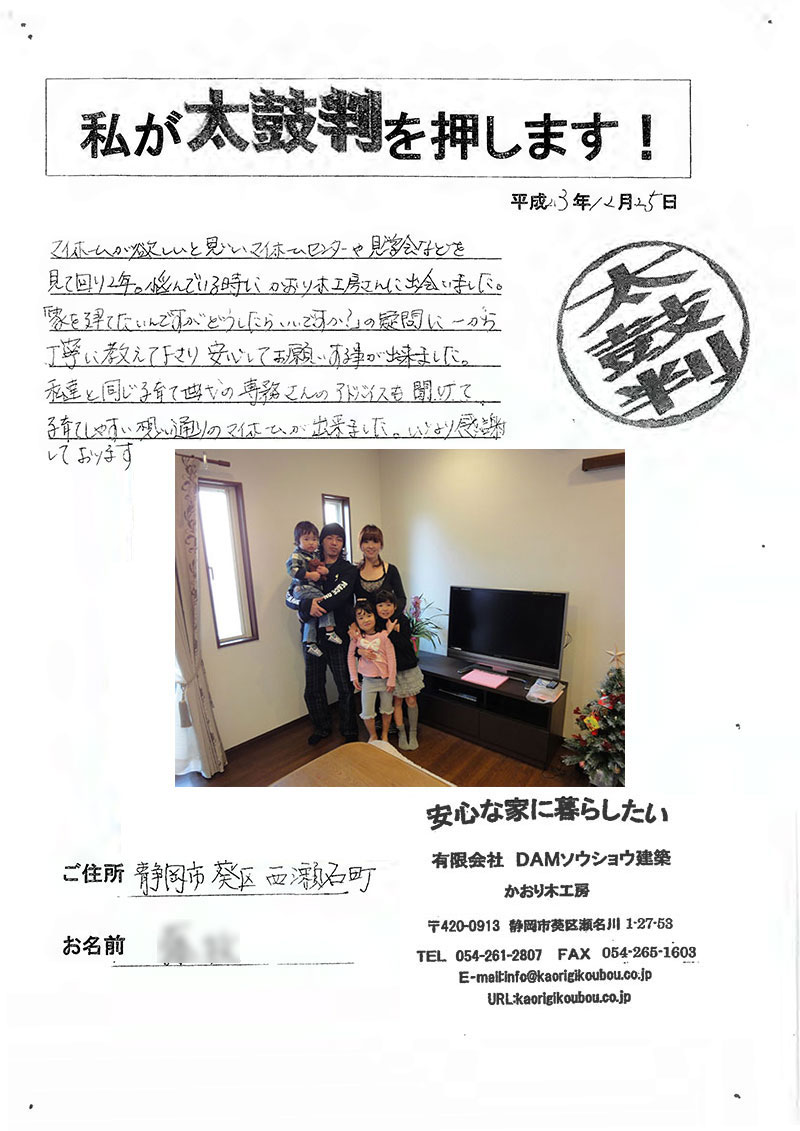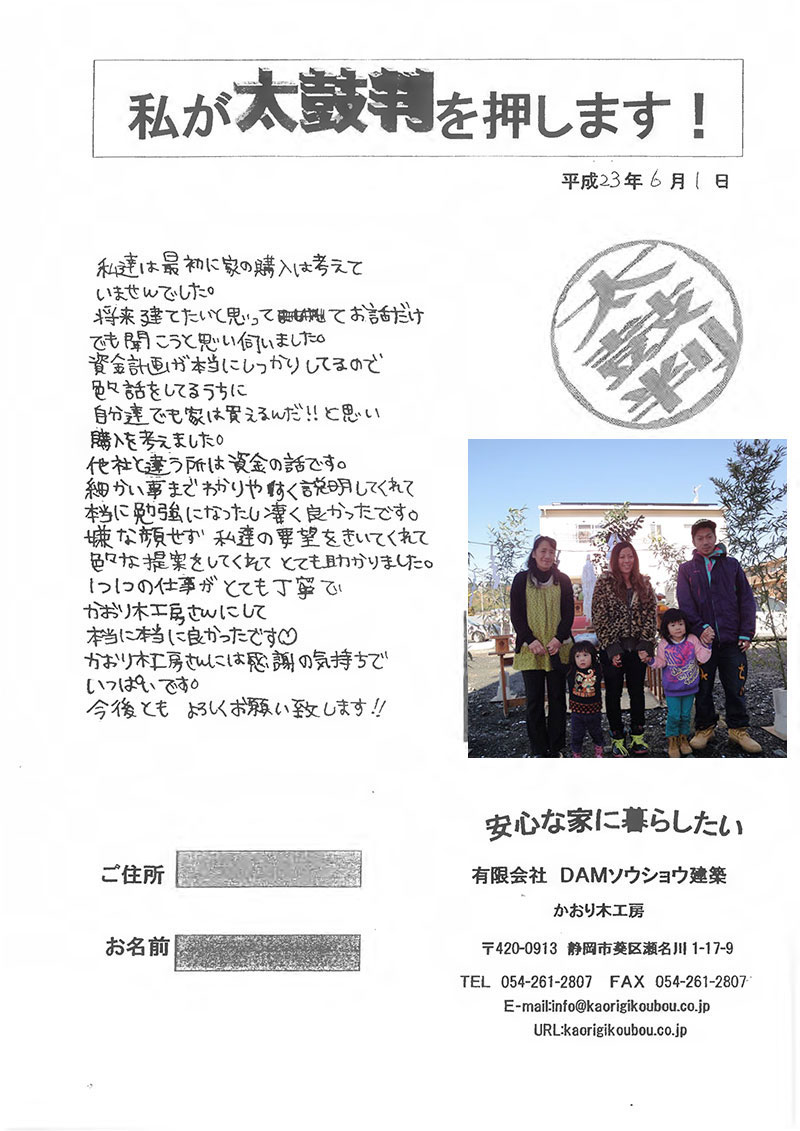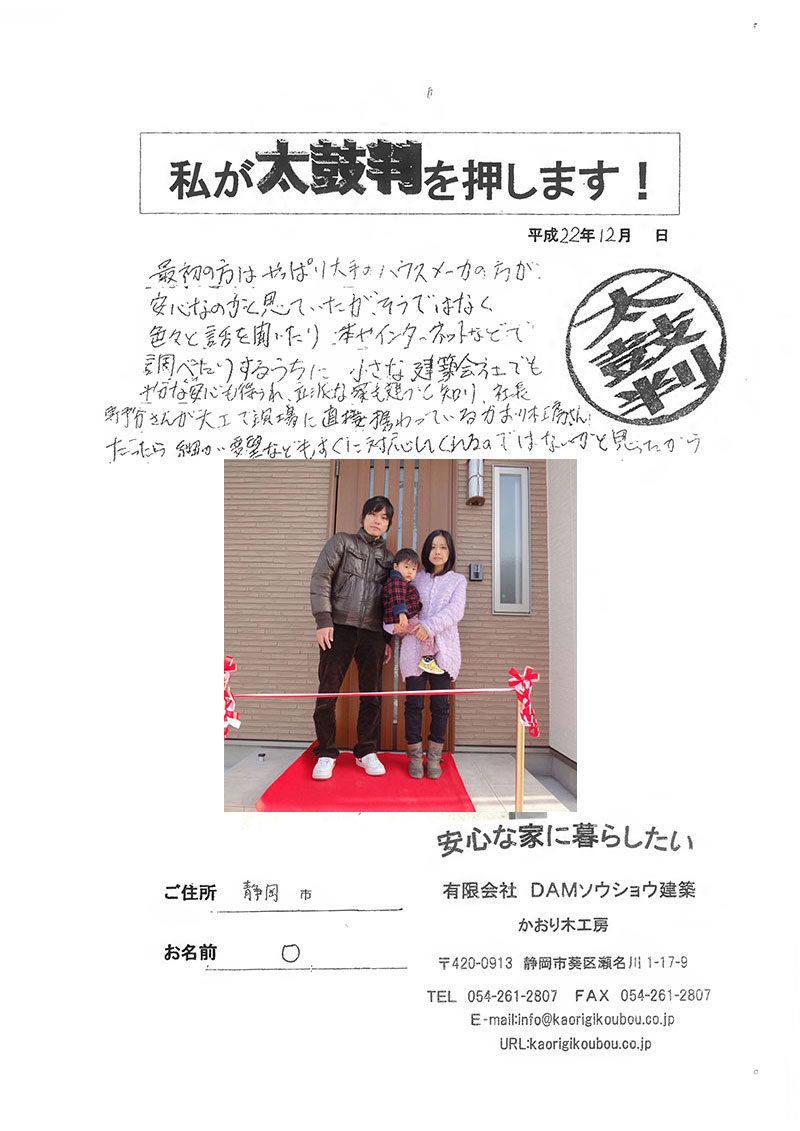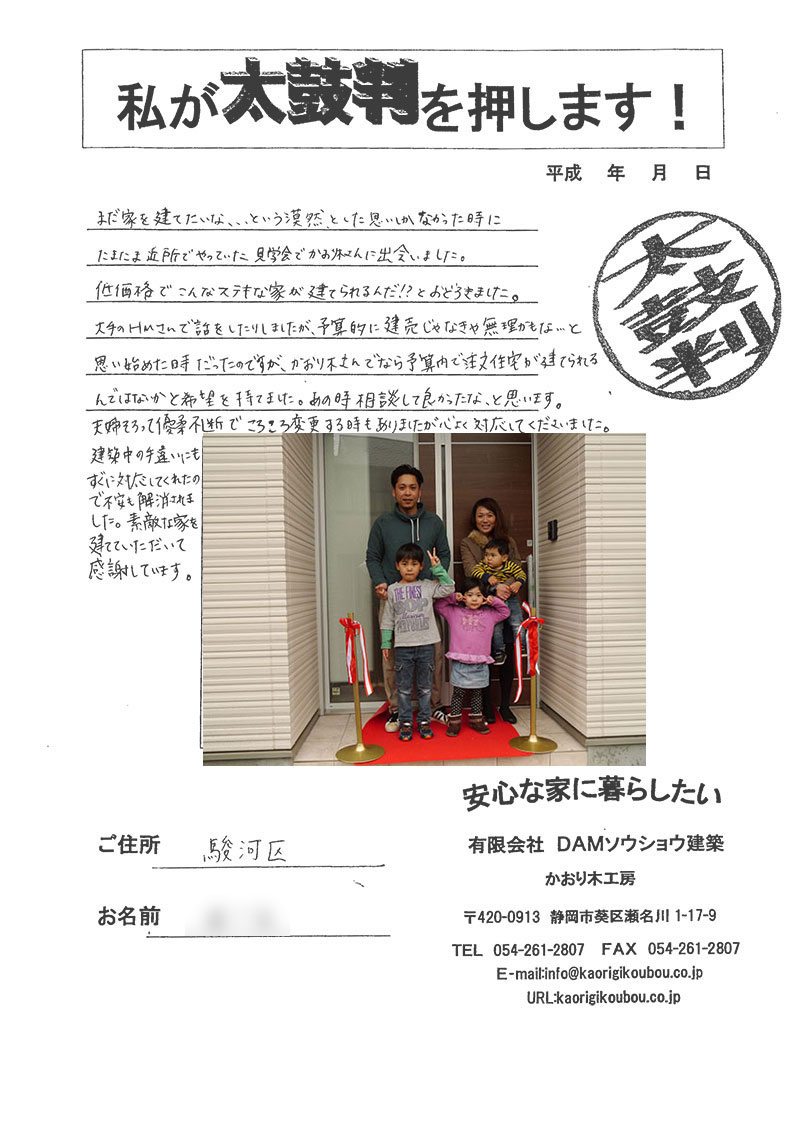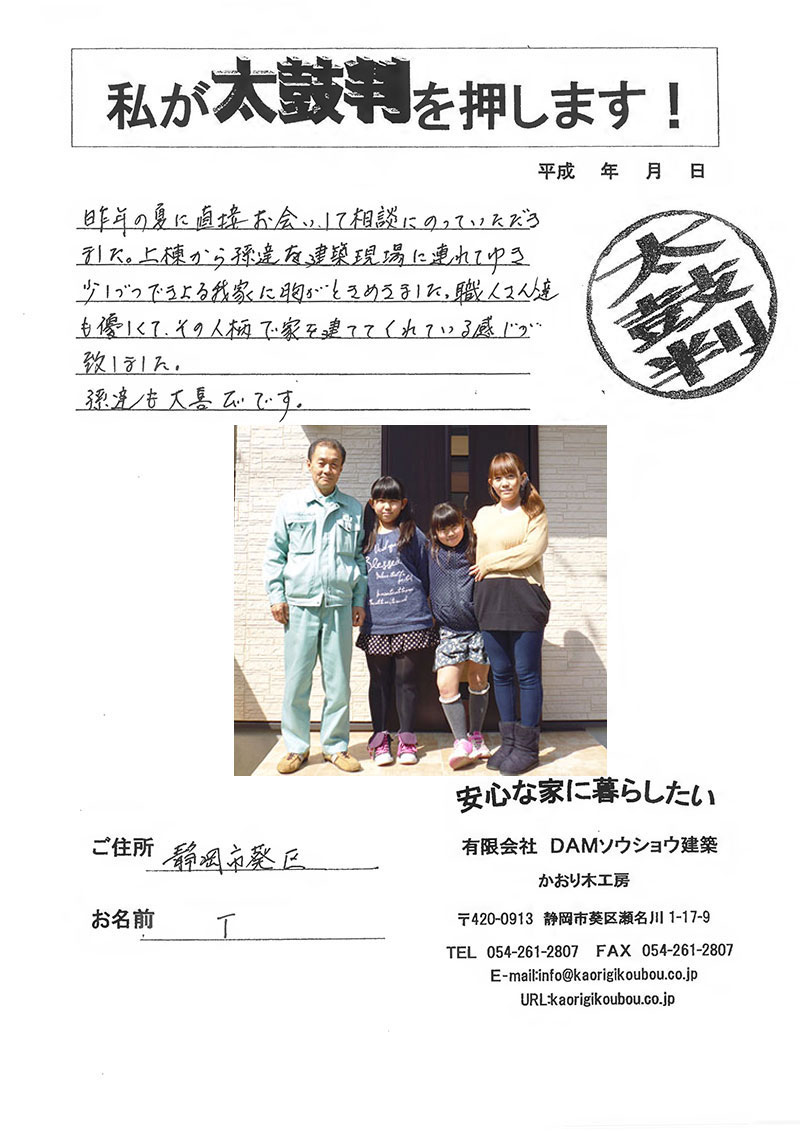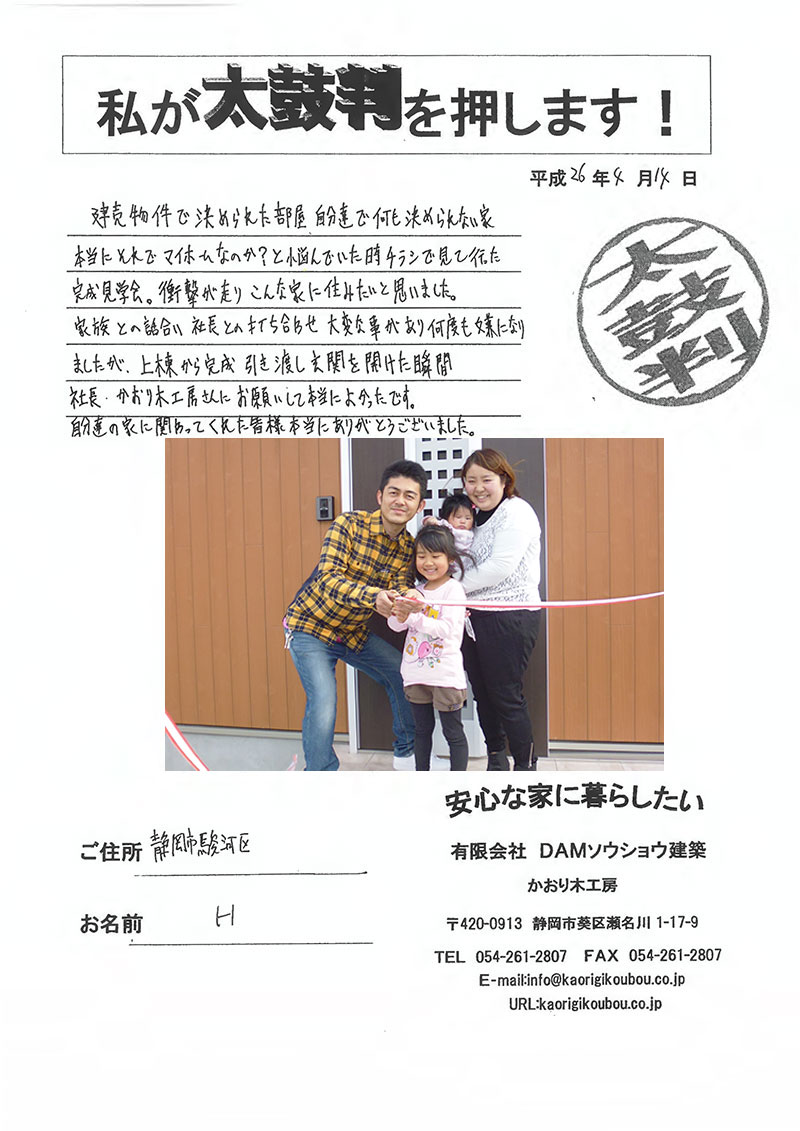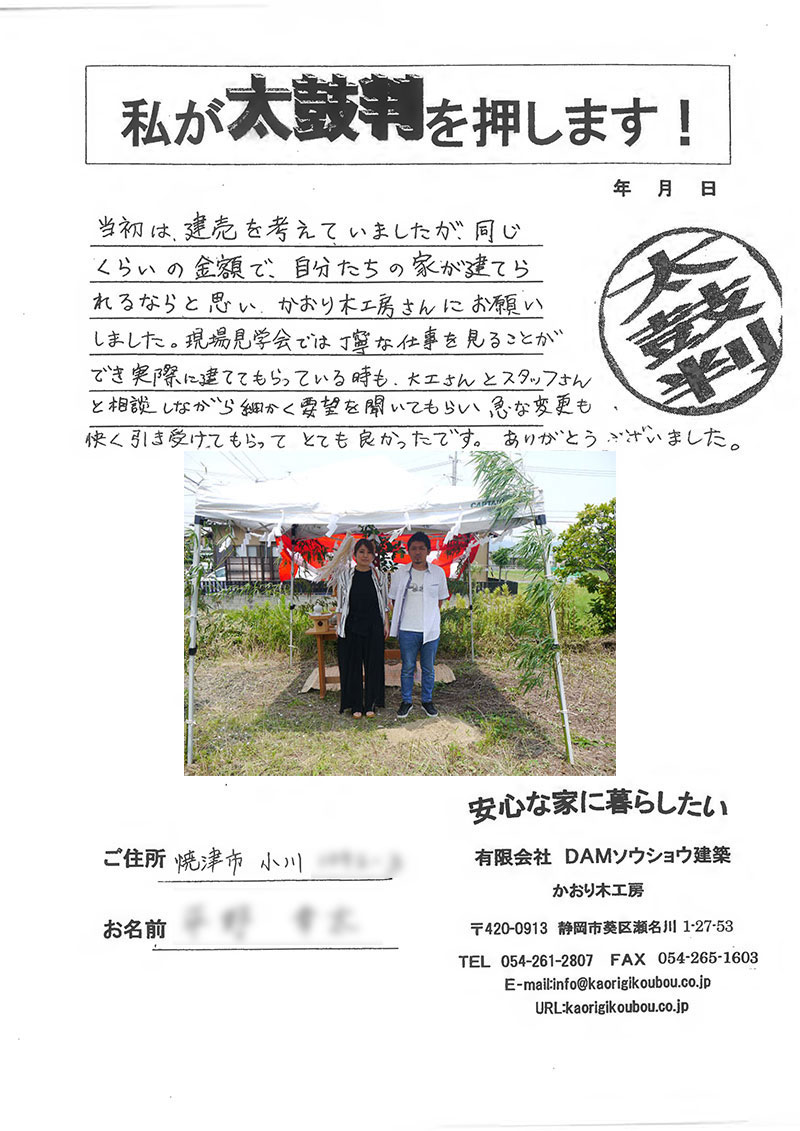“吹き抜けは寒い”はもう古い、温度ムラゼロで暮らす吹き抜け設計の新常識
こんばんは、かおり木工房のそうのです。
11月も後半に入り、静岡市は一気に冬らしい空気が濃くなってきました。
朝晩は手がかじかむようなひんやりした空気でも、
日が差すとポカポカしてきて、
冬と秋が混じり合うような季節。
朝の冷え込みが強くなると、
家づくりの相談では決まってこういう話題が増えます。
「吹き抜けって、寒くなりませんか?」
「友達の家は吹き抜けで後悔したと言っていました」
「暖房費が高くなるんですよね?」
吹き抜けは、
家づくりで後悔トップ10に必ず入るテーマ。
でも私は、断言できます。
“吹き抜けが寒い”は、昔の家の話でしかない。
今の高性能住宅では、むしろ吹き抜けは“あった方が快適”。
そして、
吹き抜けが寒くなる家は“理由が決まっている”。
今日は、
静岡の気候 × 高性能住宅 × 松尾式空調
という、かおり木工房ならではの視点で
「吹き抜けは寒くならない家」の仕組み
を、超わかりやすく解説します。
吹き抜けが寒いのではなく、
吹き抜けの“設計が悪い”だけ。
実際に寒くなる吹き抜けには共通点があります。
・窓の大きさのミス
・吹き抜けの“形”のミス
・暖気・冷気の移動を読んでいない
・階段のつながり方が悪い
・空気の出口がない
・空調の位置が悪い
・周囲の建物の影を読んでいない
つまり、吹き抜けそのものが悪いのではなく、
“空気の動線を理解していない会社の設計”が悪い。
逆に、空気・熱・風・反射・陰影まで読み切った吹き抜けは
驚くほど快適で、開放感と明るさが圧倒的。
かおり木工房の家を見学した方がよく
「吹き抜けなのにどこにも寒さがない」
「1階も2階も体感温度が同じ」
と言ってくださる理由はそこにあります。
なぜ“昔の吹き抜け”は寒かったのか?
あなたも一度は経験したことがあるかもしれませんが、
以前の家で吹き抜けを採用すると、
「冷気が下に降りてきて寒い」
「2階ばかり暖まって1階が寒い」
といった現象が当たり前に起きていました。
その理由は3つ。
① 断熱性能が圧倒的に低かった
昔の家は UA値0.8〜1.5程度。
窓はアルミサッシ。
隙間だらけ(C値7〜10)。
この状態で吹き抜けは “冷気の滑り台”。
② 空気の逃げ道を作っていなかった
冷たい空気は重く、暖かい空気は軽い。
これを考慮しない吹き抜けは
上だけ暖まり、下が冷える構造になってしまいます。
③ 窓が大きすぎた
大きい窓は光より“熱の穴”になりやすい。
昔の吹き抜け窓はこれが多く、
夏暑く、冬寒い
最悪な条件を作り出していました。
では、なぜ“かおり木工房の吹き抜け”は寒くならないのか?
それは、吹き抜けを
「空気と熱の動きを整える装置」
として設計しているから。
吹き抜けは“ただの空間”ではありません。
1階と2階の空気を混ぜる、巨大な“空気のエンジン”
なのです。
① 松尾式全館空調が“吹き抜け向き”
松尾式は
・床下で暖気を作り
・小屋裏で冷気を作る
・空気を循環させ
・温度ムラを消す
という構造。
吹き抜けはこの循環を助け、
家全体の空気を自然にまわす役割を果たします。
だから
・1階と2階の温度差がなく
・階段方向に熱が逃げず
・吹き抜けが空調効率をむしろ上げる
これが高性能住宅の吹き抜けの姿です。
② 窓の大きさではなく“働き”で配置する
吹き抜けの失敗は
「でかい窓つけすぎ」がほとんど。
かおり木工房は違います。
風の道・光の反射・隣家の影を読み、
吹き抜け窓はすべて“働き”から逆算します。
✔ 明るさの調整
✔ 景色ではなく“光の質”
✔ 夏の反射
✔ 冬の散乱光
✔ 隣家の壁の反射光利用
窓は“光のレースをデザインする道具”。
吹き抜け=大きい窓、という常識はもう古い。
③ 空気の入り口と出口を吹き抜けに仕込む
吹き抜けに必要なのは
・空気の入口
・空気の出口
・動かす道
この3つ。
特に“出口”を設計しないと空気は動かない。
✔ 高さの違う窓の組み合わせ
✔ 隅に設けた小窓
✔ 視線を切りながら風を通す窓
✔ 室内扉の位置
✔ 空調の吹出口の向き
これらを精密に組み合わせることで、
吹き抜けは“家の空気を整える装置”に変わります。
④ 2階の廊下の形が肝心
吹き抜けの寒さの原因は、
「2階の廊下が空気を止めてしまう」こと。
気流が停滞すると
・冷気が落ちる
・暖気が上がりすぎる
・ムラが生まれる
かおり木工房は、
吹き抜けと廊下の関係を“空気の道”で考えます。
廊下は“空気の川”です。
その川をせき止めない設計が吹き抜け成功の鍵です。
吹き抜けの“寒い・暑い”は
形によって100%決まる
吹き抜けには3種類あります。
① 縦長の“吹き抜け縦穴型”
空気が混ざりにくく、寒い失敗が多い。
② 横に広がる“ホール型吹き抜け”
空気が動きやすく成功しやすい。
③ L字・三角・変形吹き抜け
空気が滞留しやすく、プロでも難易度が高い。
かおり木工房では
吹き抜けは“形”から決める
という独自の考えを採用しています。
形が間違っている吹き抜けはいくら性能が高くても快適になりません。
静岡の気候だからこそ吹き抜けは“相性がいい”
静岡市は
✔ 冬は昼間暖かい
✔ 朝晩だけ少し冷える
✔ 夏は湿気が多く、風が入りにくい
という地域。
つまり、
冬は太陽を味方につけて吹き抜けで光を回し、
夏は空気を上下で循環させるのが最適解。
吹き抜けは、
静岡のためにあるような装置なのです。
実例:吹き抜けのお客様からよくいただく声
実際に吹き抜け採用のご家族からは
「どこにいても温度が同じ」
「冬でもヒーターを使わなくなった」
「夏が前より涼しい」
「風が自然に動いて空気が軽い」
「吹き抜けがあるのに電気代が安い」
「子どもの気配が分かるのが安心」
「明るすぎない柔らかい光が良い」
という声をよくいただきます。
特に
“明るさ”より“光の質”が良い
と言われることが多い。
これは、
隣家の壁の反射光を計算して窓を配置しているからです。
「吹き抜けは寒い」は、もう過去の話
本当は“吹き抜けほど快適な空間はない”
昔の吹き抜けは寒かった。
これは事実です。
しかし現代の高性能住宅では、
✔ 全館空調
✔ C値0.3以下
✔ 断熱等級6以上
✔ 温度差ゼロ設計
✔ 窓の働きを見た配置
✔ 建物の影と反射を読む
この条件が揃えば、
吹き抜けはむしろ“最も快適で明るい空間”になります。
そして何より、
吹き抜けは家族をつなぐ装置でもある。
・気配が分かる
・光を共有する
・空気が流れる
・温度が整う
・コミュニケーションが増える
これを体験したご家族は、
「吹き抜けにして本当によかった」
と必ず言います。
✔ 吹き抜けは寒くない。設計が悪いだけ
✔ 高性能住宅×吹き抜け=最強の組み合わせ
✔ 吹き抜けは“空気のエンジン”
✔ 松尾式全館空調との相性が最高
✔ 光を“量”ではなく“質”で採る
✔ 窓の大きさではなく“働き”で決める
✔ 静岡市の気候に吹き抜けはぴったり
✔ 家族の気配がつながる、心に優しい空間
吹き抜けは、
「寒い」という過去のイメージで判断すると後悔します。
大事なのは
“今の家の性能”と“本当の吹き抜け設計”を知ること。
あなたの家づくりが、
光と空気が調和した気持ちの良い空間になりますように。
かおり木工房SNSでは、家づくりに役立つ情報を発信しています。ぜひご覧ください。
賢い夫婦がやっぱり選んだ注文住宅専門工務店「かおり木工房」
住所:静岡市葵区瀬名川1-27-53
電話:054-261-2807(10時〜17時)
社長直通:090-6587-4713(「HP見た」とお伝えください)
施工エリア:静岡市・焼津市・藤枝市
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCV2CLl-P_j80GPTuVRLMXpQ
Instagram:https://www.instagram.com/kaorigikoubou/
LINE:https://page.line.me/107aufgi?openQrModal=true
TikTok:https://www.tiktok.com/@kaorigikoubou